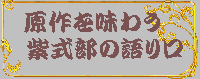
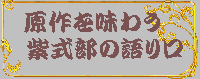
原文 口語訳
[第一段 源氏、須磨退去を決意]
世の中、いとわづらはしく、はしたなきことのみまされば、「せめて知らず顔にあり経ても、これよりまさること もや」と思しなりぬ。
「かの須磨は、昔こそ人の住みかなどもありけれ、今は、いと里離れ心すごくて、海人の家だにまれに」など聞き たまへど、「人しげく、ひたたけたらむ住まひは、いと本意なかるべし。さりとて、都を遠ざからむも、故郷おぼつ かなかるべきを」、人悪くぞ思し乱るる。
よろづのこと、来し方行く末、思ひ続けたまふに、悲しきこといとさまざまなり。憂きものと思ひ捨てつる世も、 今はと住み離れなむことを思すには、いと捨てがたきこと多かるなかにも、姫君の、明け暮れにそへては、思ひ嘆き たまへるさまの、心苦しうあはれなるを、「行きめぐりても、また逢ひ見むことをかならず」と、思さむにてだに、 なほ一、二日のほど、よそよそに明かし暮らす折々だに、おぼつかなきものにおぼえ、女君も心細うのみ思ひたまへ るを、「幾年そのほどと限りある道にもあらず、逢ふを限りに隔たりゆかむも、定めなき世に、やがて別るべき門出 にもや」と、いみじうおぼえたまへば、「忍びてもろともにもや」と、思し寄る折あれど、さる心細からむ海づらの 、波風よりほかに立ちまじる人もなからむに、かくらうたき御さまにて、引き具したまへらむも、いとつきなく、わ が心にも、「なかなか、もの思ひのつまなるべきを」など思し返すを、女君は、「いみじからむ道にも、後れきこえ ずだにあらば」と、おもむけて、恨めしげに思いたり。
かの花散里にも、おはし通ふことこそまれなれ、心細くあはれなる御ありさまを、この御蔭に隠れてものしたまへ ば、思し嘆きたるさまも、いとことわりなり。なほざりにても、ほのかに見たてまつり通ひたまひし所々、人知れぬ 心をくだきたまふ人ぞ多かりける。
入道の宮よりも、「ものの聞こえや、またいかがとりなさむ」と、わが御ためつつましけれど、忍びつつ御とぶら ひ常にあり。「昔、かやうに相思し、あはれをも見せたまはましかば」と、うち思ひ出でたまふにも、「さも、さま ざまに、心をのみ尽くすべかりける人の御契りかな」と、つらく思ひきこえたまふ。
[第一段 源氏、須磨退去を決意]
世の中、まことに厄介で、体裁の悪いことばかり増えていくので、「無理にそ知らぬふりをして過ごしていても、 これより厄介なことが増えていくのでは」とお思いになった。
「あの須磨は、昔こそ人の住居などもあったが、今では、とても人里から離れ物寂しくて、漁師の家さえまれで」 などとお聞きになるが、「人が多く、ごみごみした住まいは、いかにも本旨にかなわないであろう。そうといって、 都から遠く離れるのも、家のことがきっと気がかりに思われるであろう」と、人目にもみっともなくお悩みになる。
すべてのこと、今までのこと将来のこと、お思い続けなさると、悲しいことさまざまである。嫌な世だとお捨てに なった世の中も、今は最後と住み離れるようなことお思いになると、まことに捨てがたいことが多いなかでも、 姫君が、明け暮れ日の経つにつれて、思い悲しんでいられる様子が、気の毒で悲しいので、「別れ別れになても、 再び逢えることは必ず」と、お思いになる場合でも、やはり一、二日の間、別々にお過ごしになった時でさえ、 気がかりに思われ、女君も心細いばかりに思っていらっしゃるのを、「何年間と期限のある旅路でもなく、再び逢え るまであてどもなく漂って行くのも、無常の世に、このまま別れ別れになってしまう旅立ちにでもなりはしまいか」 と、たいそう悲しく思われなさるので、「こっそりと一緒にでは」と、お思いよりになる時もあるが、そのような 心細いような海辺の、波風より他に訪れる人もないような所に、このようないじらしいご様子で、お連れなさるのも、 まことに不似合いで、自分の心にも、「かえって、物思いの種になるにちがいなかろう」などとお考え直しになる が、女君は、「どんなにつらい旅路でも、ご一緒申し上げることができたら」と、それとなくほのめかして、 恨めしそうに思っていらっしゃった。
あの花散里にも、お通いになることはまれであるが、心細く気の毒なご様子を、この君のご庇護のもとに過ごして いらっしゃるので、お嘆きになる様子も、いかにもごもっともである。かりそめであっても、わずかにお逢い申しお 通いにった所々では、人知れず心をお痛めになる方々が多かったのである。
入道の宮からも、「世間の噂は、またどのように取り沙汰されるだろうか」と、ご自身にとっても用心されるが、 人目に立たないよう立たないようにしてお見舞いが始終ある。「昔、このように互いに思ってくださり、情愛をも お見せくださったのであったならば」と、ふとお思い出しになるにつけても、「そのようにも、あれやこれやと、 心の限りを尽くさなければならない宿縁のお方であった」と、辛くお思い申し上げなさる。
源氏、悩んだ末、須磨退去を決意
原文 口語訳
[第二段 左大臣邸に離京の挨拶]
三月二十日あまりのほどになむ、都を離れたまひける。人にいつとしも知らせたまはず、ただいと近う仕うまつり 馴れたる限り、七、八人ばかり御供にて、いとかすかに出で立ちたまふ。さるべき所々に、御文ばかりうち忍びたま ひしにも、あはれと忍ばるばかり尽くいたまへるは、見どころもありぬべかりしかど、その折の、心地の紛れに、は かばかしうも聞き置かずなりにけり。
二、三日かねて、夜に隠れて、大殿に渡りたまへり。網代車のうちやつれたるにて、女車のやうにて隠ろへ入りた まふも、いとあはれに、夢とのみ見ゆ。御方、いと寂しげにうち荒れたる心地して、若君の御乳母ども、昔さぶらひ し人のなかに、まかで散らぬ限り、かく渡りたまへるをめづらしがりきこえて、参う上り集ひて見たてまつるにつけ ても、ことにもの深からぬ若き人びとさへ、世の常なさ思ひ知られて、涙にくれたり。
若君はいとうつくしうて、され走りおはしたり。 「久しきほどに、忘れぬこそ、あはれなれ」 とて、膝に据ゑたまへる御けしき、忍びがたげなり。
大臣、こなたに渡りたまひて、対面したまへり。 「つれづれに籠もらせたまへらむほど、何とはべらぬ昔物語も、参りて、聞こえさせむと思うたまへれど、身の病 重きにより、朝廷にも仕うまつらず、位をも返したてまつりてはべるに、私ざまには腰のべてなむと、ものの聞こえ ひがひがしかるべきを、今は世の中憚るべき身にもはべらねど、いちはやき世のいと恐ろしうはべるなり。かかる御 ことを見たまふるにつけて、命長きは心憂く思うたまへらるる世の末にもはべるかな。天の下をさかさまになしても 、思うたまへ寄らざりし御ありさまを見たまふれば、よろづいとあぢきなくなむ」 と聞こえたまひて、いたうしほたれたまふ。
「とあることも、かかることも、前の世の報いにこそはべるなれば、言ひもてゆけば、ただ、みづからのおこたり になむはべる。さして、かく、官爵を取られず、あさはかなることにかかづらひてだに、朝廷のかしこまりなる人の 、うつしざまにて世の中にあり経るは、咎重きわざに人の国にもしはべるなるを、遠く放ちつかはすべき定めなども はべるなるは、さま異なる罪に当たるべきにこそはべるなれ。濁りなき心にまかせて、つれなく過ぐしはべらむも、 いと憚り多く、これより大きなる恥にのぞまぬさきに、世を逃れなむと思うたまへ立ちぬる」 など、こまやかに聞こえたまふ。
昔の御物語、院の御こと、思しのたまはせし御心ばへなど聞こえ出でたまひて、御直衣の袖もえ引き放ちたまはぬに、 君も、え心強くもてなしたまはず。若君の何心なく紛れありきて、これかれに馴れきこえたまふを、いみじと思いた り。
[第二段 左大臣邸に離京の挨拶] 三月二十日過ぎのころに、都をお離れになった。誰にもいつとはお知らせなさらず、わずかにごく親しくお仕え 申し馴れている者だけ、七、八人ほどをお供として、たいそうひっそりとご出発になる。
しかるべき所々には、お手紙だけをそっと差し上げなさったが、しみじみと偲ばれるほど言葉をお尽くしになった のは、きっと素晴らしいものであっただろうが、その時の、気の動転で、はっきりと聞いて置かないままになって しまったのであった。
二、三日前に、夜の闇に隠れて、大殿にお渡りになった。網代車の粗末なので、女車のようにひっそりとお入り になるのも、実にしみじみと、夢かとばかり思われる。お部屋は、とても寂しそうに荒れたような感じがして、 若君の御乳母どもや、生前から仕えていた女房の中で、お暇を取らずにいた人は皆、このようにお越しになったのを 珍しくお思い申して、参集して拝し上げるにつけても、たいして思慮深くない若い女房でさえ、世の中の無常が思 い知られて、涙にくれた。
若君はとてもかわいらしく、はしゃいで走っていらっしゃった。 「長い間逢わないのに、忘れていないのが、感心なことだ」 と言って、膝の上にお乗せになったご様子、堪えきれなさそうである。
大臣、こちらにお越しになって、お会いになった。 「所在なくお引き籠もりになっていらっしゃる間、何ということもない昔話でも、参上して、お話し申し上げよう と存じておりましたが、わが身の病気が重い理由で、朝廷にもお仕え申さず、官職までもお返し申し上げております のに、私事には腰を伸ばして勝手にと、世間の風評も悪く取り沙汰されるにちがいないので、今では世間に遠慮しな ければならない身の上ではございませんが、厳しく性急な世の中がとても恐ろしいのでございます。このようなご悲 運を拝見するにつけても、長生きは厭わしく存じられる末世でございますね。天地を逆様にしても、存じよりません でしたご境遇を拝見しますと、万事がまことにおもしろくなく存じられます」 とお申し上げになって、ひどく涙にくれていらっしゃる。
「このようなことも、あのようなことも、前世からの因果だということでございますから、せんじつめれば、ただ 、わたくしの宿運のつたなさゆえでございます。これと言った理由で、このように、官位を剥奪されず、ちょっと した科に関係しただけでも、朝廷のお咎めを受けた者が、普段と変わらない様子で世の中に生活をしているのは、 罪の重いことに唐土でも致しておるということですが、遠流に処すべきだという決定などもございますというのは、 容易ならぬ罪科に当たることになっているのでしょう。潔白な心のままで、素知らぬ顔で過ごしていますのも、 まことに憚りが多く、これ以上大きな辱めを受ける前に、都を離れようと決意致した次第です」 などと、詳しくお話し申し上げなさる。
昔のお話、院の御事、御遺言あそばされた御趣旨などをお申し上げなさって、お直衣の袖もお引き放しになれないので 、君も、気丈夫に我慢がおできになれない。若君が無邪気に走り回って、二人にお甘え申していらっしゃるのを、 悲しくお思いになる。
源氏、ひそかに左大臣邸を訪れ、別れの挨拶
原文 口語訳
[第三段 二条院の人々との離別]
殿におはしたれば、わが御方の人びとも、まどろまざりけるけしきにて、所々に群れゐて、あさましとのみ世を思 へるけしきなり。侍には、親しう仕まつる限りは、御供に参るべき心まうけして、私の別れ惜しむほどにや、人もな し。さらぬ人は、とぶらひ参るも重き咎めあり、わづらはしきことまされば、所狭く集ひし馬、車の方もなく、寂し きに、「世は憂きものなりけり」と、思し知らる。 台盤なども、かたへは塵ばみて、畳、所々引き返したり。「見るほどだにかかり。ましていかに荒れゆかむ」と思 す。
西の対に渡りたまへれば、御格子も参らで、眺め明かしたまひければ、簀子などに、若き童女、所々に臥して、今 ぞ起き騒ぐ。宿直姿どもをかしうてゐるを見たまふにも、心細う、「年月経ば、かかる人びとも、えしもあり果てで や、行き散らむ」など、さしもあるまじきことさへ、御目のみとまりけり。
「昨夜は、しかしかして夜更けにしかばなむ。例の思はずなるさまにや思しなしつる。かくてはべるほどだに御目 離れずと思ふを、かく世を離るる際には、心苦しきことのおのづから多かりける、ひたやごもりにてやは。常なき世 に、人にも情けなきものと心おかれ果てむと、いとほしうてなむ」 と聞こえたまへば、 「かかる世を見るよりほかに、思はずなることは、何ごとにか」 とばかりのたまひて、いみじと思し入れたるさま、人よりことなるを、ことわりぞかし、
父親王、いとおろかにも とより思しつきにけるに、まして、世の聞こえをわづらはしがりて、訪れきこえたまはず、御とぶらひにだに渡りた まはぬを、人の見るらむことも恥づかしく、なかなか知られたてまつらでやみなましを、継母の北の方などの、 「にはかなりし幸ひのあわたたしさ。あな、ゆゆしや。思ふ人、方々につけて別れたまふ人かな」 とのたまひけるを、さる便りありて漏り聞きたまふにも、いみじう心憂ければ、これよりも絶えて訪れきこえたま はず。また頼もしき人もなく、げにぞ、あはれなる御ありさまなる。
「なほ世に許されがたうて、年月を経ば、巌の中にも迎へたてまつらむ。ただ今は、人聞きのいとつきなかるべき なり。朝廷にかしこまりきこゆる人は、明らかなる月日の影をだに見ず、安らかに身を振る舞ふことも、いと罪重か なり。過ちなけれど、さるべきにこそかかることもあらめと思ふに、まして思ふ人具するは、例なきことなるを、ひ たおもむきにものぐるほしき世にて、立ちまさることもありなむ」 など聞こえ知らせたまふ。 日たくるまで大殿籠もれり。
帥宮、三位中将などおはしたり。対面したまはむとて、御直衣などたてまつる。 「位なき人は」 とて、無紋の直衣、なかなか、いとなつかしきを着たまひて、うちやつれたまへる、いとめでたし。御鬢かきたま ふとて、鏡台に寄りたまへるに、面痩せたまへる影の、我ながらいとあてにきよらなれば、 「こよなうこそ、衰へにけれ。この影のやうにや痩せてはべる。あはれなるわざかな」 とのたまへば、女君、涙一目うけて、見おこせたまへる、いと忍びがたし。
親王は、あはれなる御物語聞こえたまひて、暮るるほどに帰りたまひぬ。
[第三段 二条院の人々との離別]
殿にお帰りになると、ご自分方の女房たちも、眠らなかった様子で、あちこちにかたまっていて、驚くばかりだ とご境遇の変化を思っている様子である。侍所では、親しくお仕えしている者だけは、お供に参るつもりをして、 個人的な別れを惜しんでいるころなのであろうか、人影も見えない。その他の人は、お見舞いに参上するにも重い 処罰があり、厄介な事が増えるので、所狭しと集まっていた馬、車が跡形もなく、寂しい気がするので、 「世の中とは嫌なものだ」と、お悟りになる。 台盤所なども、半分は塵が積もって、畳も所々裏返ししてある。「見ているうちでさえこんなである。まして どんなに荒れてゆくのだろう」とお思いになる。
西の対にお渡りになると、御格子もお下ろしにならないで、物思いに沈んで夜を明かしていられたので、簀子など に、若い童女が、あちこちに臥せっていて、急に起き出し騒ぐ。宿直姿がかわいらしく座っているのを御覧になるに つけても、心細く、「歳月が重なったら、このような子たちも、最後まで辛抱しきれないで、散りじりに辞めていく のではなかろうか」などと、何でもないことまで、お目が止まるのであった。
「昨夜は、これこれの事情で夜を明かしてしまいました。いつものように心外なふうに邪推でもなさっていたので は。せめてこうしている間だけでも離れないようにと思うのが、このように京を離れる際には、気にかかることが 自然と多かったので、籠もってばかりいるわけにも行きましょうか。無常の世に、人からも薄情な者だとすっかり 疎まれてしまうのも、辛いのです」 とお申し上げになると、
「このような悲しい目を見るより他に、もっと心外な事とは、どのような事でしょうか」 とだけおっしゃって、悲しいと思い込んでいらっしゃる様子、人一倍であるのは、もっともなことで、父親王は、 実に疎遠にはじめからお思いになっていたが、まして今は、世間の噂を煩わしく思って、お便りも差し上げなさらず 、お見舞いにさえお越しにならないのを、人の手前も恥ずかしく、かえってお知られ頂かないままであればよ かったのに、継母の北の方などが、 「束の間であった幸せの急がしさ。ああ、縁起でもない。大事な人が、それぞれに別れなさる人だわ」 とおっしゃったのを、ある筋から漏れ聞きなさるにつけても、ひどく情けないので、こちらからも少しもお便り を差し上げなさらない。他に頼りとする人もなく、なるほど、お気の毒なご様子である。
「いつまでたっても赦免されずに、歳月が過ぎるようなら、巌の中でもお迎え申そう。今すぐでは、人聞きがま ことに悪いであろう。朝廷に謹慎申し上げている者は、明るい日月の光をさえ見ず、思いのままに身を振る舞うこ とも、まことに罪の重いことである。過失はないが、前世からの因縁でこのようなことになったのであろうと思うが 、まして愛する人を連れて行くのは、先例のないことなので、一方的で道理を外れた世の中なので、これ以上の災難も きっと起ころう」 などと、お話し申し上げなさる。
日が高くなるまでお寝みになっていた。
帥宮や三位中将などがいらっしゃった。お会いなさろうとして、お直衣などをお召しになる。 「無位無官の者は」 と言って、無紋の直衣、かえって、とても優しい感じなのをお召しになって、地味にしていらっしゃるのが、 たいそう素晴らしい。鬢の毛を掻きなでなさろうとして、鏡台に近寄りなさると、面痩せなさった顔形が、自分 ながらとても気品あって美しいので、 「すっかり、衰えてしまったな。この影のように痩せていますか。ああ、悲しいことだ」 とおっしゃると、女君、涙を目にいっぱい浮かべて、こちらを御覧になるが、とても堪えきれない。 「わが身はこのように流浪しようとも 鏡に映った影はあなたの元を離れずに残っていよう」 と、お申し上げになると、 「お別れしても影だけでもとどまっていてくれるものならば 鏡を見て慰めることもできましょうに」 柱の蔭に隠れて座って、涙を隠していらっしゃる様子、「やはり、おおぜいの妻たちの中で類のない人だ」と、 思わずにはいらっしゃれないご様子の方である。
親王は、心のこもったお話を申し上げなさって、日の暮れるころにお帰りになった。
二条院の人々と別れ、女君の悲しみ。
(「第四段花散る里との別れ」省略)
原文 口語訳
[第五段 旅生活の準備と身辺整理]
よろづのことどもしたためさせたまふ。親しう仕まつり、世になびかぬ限りの人びと、殿の事とり行なふべき上下 、定め置かせたまふ。御供に慕ひきこゆる限りは、また選り出でたまへり。 かの山里の御住みかの具は、えさらずとり使ひたまふべきものども、ことさらよそひもなくことそぎて、さるべき 書ども文集など入りたる箱、さては琴一つぞ持たせたまふ。所狭き御調度、はなやかなる御よそひなど、さらに具し たまはず、あやしの山賤めきてもてなしたまふ。
さぶらふ人びとよりはじめ、よろづのこと、みな西の対に聞こえわたしたまふ。領じたまふ御荘、御牧よりはじめ て、さるべき所々、券など、みなたてまつり置きたまふ。それよりほかの御倉町、納殿などいふことまで、少納言を はかばかしきものに見置きたまへれば、親しき家司ども具して、しろしめすべきさまどものたまひ預く。 わが御方の中務、中将などやうの人びと、つれなき御もてなしながら、見たてまつるほどこそ慰めつれ、「何ご とにつけてか」と思へども、 「命ありてこの世にまた帰るやうもあらむを、待ちつけむと思はむ人は、こなたにさぶらへ」 とのたまひて、上下、皆参う上らせたまふ。
若君の御乳母たち、花散里なども、をかしきさまのはさるものにて、まめまめしき筋に思し寄らぬことなし。
尚侍の御もとに、わりなくして聞こえたまふ。 「問はせたまはぬも、ことわりに思ひたまへながら、今はと、世を思ひ果つるほどの憂さもつらさも、たぐひなき ことにこそはべりけれ。
逢ふ瀬なき涙の河に沈みしや 流るる澪の初めなりけむ
と思ひたまへ出づるのみなむ、罪逃れがたうはべりける」 道のほども危ふければ、こまかには聞こえたまはず。
女、いといみじうおぼえたまひて、忍びたまへど、御袖よりあまるも所狭うなむ。
「涙河浮かぶ水泡も消えぬべし 流れて後の瀬をも待たずて」
泣く泣く乱れ書きたまへる御手、いとをかしげなり。今ひとたび対面なくやと思すは、なほ口惜しけれど、思し返 して、憂しと思しなすゆかり多うて、おぼろけならず忍びたまへば、いとあながちにも聞こえたまはずなりぬ。
[第五段 旅生活の準備と身辺整理] 何から何まで整理をおさせになる。親しくお仕えし、時勢に靡かない家臣たちだけの、邸の事務を執り行うべき 上下の役目、お決め置きになる。お供に随行申し上げる者は皆、別にお選びになった。
あの山里の生活の道具は、どうしてもご必要な品物類を、特に飾りけなく簡素にして、しかるべき漢籍類、 『白氏文集』などの入った箱、その他には琴を一張を持たせなさる。大げさなご調度類や、華やかなお装いなどは、 まったくお持ちにならず、賎しい山里人のような振る舞いをなさる。
お仕えしている女房たちをはじめ、万事、すべて西の対にお頼み申し上げなさる。ご所領の荘園、牧場をはじめ として、しかるべき領地、証文など、すべて差し上げ置きなさる。その他の御倉町、納殿などという事まで、少納言 を頼りになる者と見込んでいらっしゃるので、腹心の家司たちを付けて、取りしきられるように命じて置きなさる。
ご自身方の中務、中将などといった女房たち、何気ないお扱いとはいえ、お身近にお仕えしていた間は慰めること もできたが、「何を期待してか」と思うが、 「生きてこの世に再び帰って来るようなこともあろうから、待っていようと思う者は、こちらに伺候しなさい」 とおっしゃって、上下の女房たち、皆参上させなさる。
若君の乳母たち、花散里などにも、風情のある品物はもちろんのこと、実用品までお気のつかない事がない。
尚侍の君の御許に、困難をおかしてお便りを差し上げなさる。 「お見舞いくださらないのも、ごもっともに存じられますが、今は最後と、この世を諦めた時の嫌で辛い思いも、 何とも言いようがございません。
あなたに逢えないことに涙を流したことが 流浪する身の上となるきっかけだったのでしょうか
と思い出される事だけが、罪も逃れ難い事でございます」
届くかどうか不安なので、詳しくはお書きにならない。
女、大層悲しく思われなさって、堪えていらしたが、お袖から涙がこぼれるのもどうしようもない。
「涙川に浮かんでいる水泡も消えてしまうでしょう 生きながらえて再びお会いできる日を待たないで」
泣く泣く心乱れてお書きになったご筆跡、まことに深い味わいがある。もう一度お逢いできないものかとお思い になるのは、やはり残念に思われるが、お考え直して、ひどいとお思いになる一族が多くて、一方ならず人目を 忍んでいらっしゃるので、あまり無理をしてまでお便り申し上げることもなさらずに終わった。
二条院の財産を紫の上に託す、人々の身辺の始末
原文 口語訳
[第六段 藤壷に離京の挨拶]
明日とて、暮には、院の御墓拝みたてまつりたまふとて、北山へ詣でたまふ。暁かけて月出づるころなれば、まづ、 入道の宮に参うでたまふ。近き御簾の前に御座参りて、御みづから聞こえさせたまふ。春宮の御事をいみじううしろ めたきものに思ひきこえたまふ。
かたみに心深きどちの御物語は、よろづあはれまさりけむかし。なつかしうめでたき御けはひの昔に変はらぬに、 つらかりし御心ばへも、かすめきこえさせまほしけれど、今さらにうたてと思さるべし、わが御心にも、なかなか 今ひときは乱れまさりぬべければ、念じ返して、ただ、 「かく思ひかけぬ罪に当たりはべるも、思うたまへあはすることの一節になむ、空も恐ろしうはべる。惜しげなき 身はなきになしても、宮の御世にだに、ことなくおはしまさば」 とのみ聞こえたまふぞ、ことわりなるや。
宮も、みな思し知らるることにしあれぼ、御心のみ動きて、聞こえやりたまはず。大将、よろづのことかき集め思し 続けて、泣きたまへるけしき、いと尽きせずなまめきたり。 「御山に参りはべるを、御ことつてや」 と聞こえたまふに、とみにものも聞こえたまはず、わりなくためらひたまふ御けしきなり。
「見しはなくあるは悲しき世の果てを 背きしかひもなくなくぞ経る」 いみじき御心惑ひどもに、思し集むることどもも、えぞ続けさせたまはぬ。
「別れしに悲しきことは尽きにしを またぞこの世の憂さはまされる」
[第六段 藤壷に離京の挨拶] 明日という日、夕暮には、院のお墓にお参りなさろうとして、北山へ参拝なさる。明け方近くに月の出るころな ので、最初、入道の宮にお伺いさる。近くの御簾の前にご座所をお設けになって、ご自身でご応対あそばす。 東宮のお身の上をたいそうご心配申し上げなさる。
お互いに感慨深くお感じになっている者同士のお話は、何事もしみじみと胸に迫るものがさぞ多かったことで あろう。慕わしく素晴らしいご様子が変わらないので、恨めしかったお気持ちも、それとなく申し上げたいが、 いまさら嫌なこととお思いになろうし、自分自身でも、かえって一段と心が乱れるであろうから、思い直して、 ただ、 「このように思いもかけない罪に問われますにつけても、思い当たるただ一つのことのために、天の咎めも恐ろ しゅうございます。惜しくもないわが身はどうなろうとも、せめて東宮の御世だけでも、ご安泰でいらっしゃれば」 とだけ申し上げなさるのも、もっともなことである。
宮も、すっかりご存知のことであるので、お心がどきどきするばかりで、お返事申し上げられない。大将、あれ からこれへとお思い続けられて、お泣きになる様子、とても言いようのないほど優艷である。
「山陵に詣でますが、お言伝は」 と申し上げなさるが、すぐにはお返事なさらず、ひたすらお気持ちを鎮めようとなさるご様子である。
「院は亡くなられ生きておいでの方は悲しいお身の上の世の末を 出家した甲斐もなく泣きの涙で暮らしています」
ひどくお悲しみの二方なので、お思いになっていることがらも、十分にお詠みあそばされない。
「故院にお別れした折に悲しい思いを尽くしたと思ったはずなのに またもこの世のさらに辛いことに遭います」
藤壺に別れ
原文 口語訳
[第七段 桐壷院の御墓に離京の挨拶]
月待ち出でて出でたまふ。御供にただ五、六人ばかり、下人もむつましき限りして、御馬にてぞおはする。さらな ることなれど、ありし世の御ありきに異なり、皆いと悲しう思ふなり。
なかに、かの御禊の日、仮の御随身にて仕う まつりし右近の将監の蔵人、得べきかうぶりもほど過ぎつるを、つひに御簡削られ、官も取られて、はしたなければ 、御供に参るうちなり。
賀茂の下の御社を、かれと見渡すほど、ふと思ひ出でられて、下りて、御馬の口を取る。
「ひき連れて葵かざししそのかみを 思へばつらし賀茂の瑞垣」
と言ふを、「げに、いかに思ふらむ。人よりけにはなやかなりしものを」と思すも、心苦し。
君も、御馬より下りたまひて、御社のかた拝みたまふ。神にまかり申したまふ。
「憂き世をば今ぞ別るるとどまらむ 名をば糺の神にまかせて」
とのたまふさま、ものめでする若き人にて、身にしみてあはれにめでたしと見たてまつる。 御山に詣うでたまひて、おはしましし御ありさま、ただ目の前のやうに思し出でらる。限りなきにても、世に亡く なりぬる人ぞ、言はむかたなく口惜しきわざなりける。よろづのことを泣く泣く申したまひても、そのことわりをあ らはに承りたまはねば、「さばかり思しのたまはせしさまざまの御遺言は、いづちか消え失せにけむ」と、いふかひ なし。
御墓は、道の草茂くなりて、分け入りたまふほど、いとど露けきに、月も隠れて、森の木立、木深く心すごし。 帰り出でむ方もなき心地して、拝みたまふに、ありし御面影、さやかに見えたまへる、そぞろ寒きほどなり。
「亡き影やいかが見るらむよそへつつ 眺むる月も雲隠れぬる」
[第七段 桐壷院の御墓に離京の挨拶]
月を待ってお出かけになる。お供にわずか五、六人ほど、下人も気心の知れた者だけを連れて、お馬でいらっ しゃる。言うまでもないことだが、以前のご外出と違って、皆とても悲しく思うのである。
その中で、あの御禊の日、仮の御随身となってご奉仕した右近将監の蔵人、当然得るはずの五位の位にも時期が 過ぎてしまったが、とうとう殿上の御簡も削られ、官職も剥奪されて、面目がないので、お供に参る一人である。
賀茂の下の御社を、それと見渡せる辺りで、ふと思い出されて、下りて、お馬の轡を取る。
「お供をして葵を頭に挿した御禊の日のことを思うと 御利益がなかったのかとつらく思われます、賀茂の神様」
と詠むのを、「本当に、どんなに悲しんでいることだろう。誰よりも羽振りがよく振る舞っていたのに」とお思 いになると、気の毒である。
君も御馬から下りなさって、御社の方、拝みなさる。神にお暇乞い申し上げなさる。
「辛い世の中を今離れて行く、後に残る 噂の是非は、糺の神に委ねて」
とお詠みになる様子、感激しやすい若者なので、身にしみてご立派なと拝する。
御陵に参拝なさって、御在世中のお姿、まるで眼前の事にお思い出しになられる。至尊の地位にあった方でも、 この世を去ってしまった人は、何とも言いようもなく無念なことであった。何から何まで泣く泣く申し上げなさって も、その是非をはっきりとお承りにならないので、「あれほどお考え置かれたいろいろなご遺言は、どこへ消え失 せてしまったのだろうか」と、何とも言いようがない。
御陵は、参道の草が生い茂って、かき分けてお入りになって行くうちに、ますます露に濡れると、月も雲に隠れて 、森の木立は木深くぞっとする。帰る道も分からない気がして、参拝なさっているところに、御生前の御姿、はっき りと現れなさった、鳥肌の立つ思いである。
「亡き父上はどのように御覧になっていられることだろうか 父上のように思って見ていた月の光も雲に隠れてしまった」
故院の御陵に参拝、亡霊を見る
原文 口語訳
[第九段 離京の当日]
その日は、女君に御物語のどかに聞こえ暮らしたまひて、例の、夜深く出でたまふ。狩の御衣など、旅の御よそひ 、いたくやつしたまひて、
「月出でにけりな。なほすこし出でて、見だに送りたまへかし。いかに聞こゆべきこと多くつもりにけりとおぼえ むとすらむ。一日、二日たまさかに隔たる折だに、あやしういぶせき心地するものを」
とて、御簾巻き上げて、端にいざなひきこえたまへば、女君、泣き沈みたまへるを、ためらひて、ゐざり出でたま へる、月影に、いみじうをかしげにてゐたまへり。
「わが身かくてはかなき世を別れなば、いかなるさまにさすらへ たまはむ」と、うしろめたく悲しけれど、思し入りたるに、いとどしかるべければ、
「生ける世の別れを知らで契りつつ 命を人に限りけるかな
はかなし」 など、あさはかに聞こえなしたまへば、
「惜しからぬ命に代へて目の前の 別れをしばしとどめてしがな」
「げに、さぞ思さるらむ」と、いと見捨てがたけれど、明け果てなば、はしたなかるべきにより、急ぎ出でたまひぬ。
道すがら、面影につと添ひて、胸もふたがりながら、御舟に乗りたまひぬ。日長きころなれば、追風さへ添ひて、 まだ申の時ばかりに、かの浦に着きたまひぬ。
かりそめの道にても、かかる旅をならひたまはぬ心地に、心細さもをかしさもめづらかなり。大江殿と言ひける所 は、いたう荒れて、松ばかりぞしるしなる。
「唐国に名を残しける人よりも 行方知られぬ家居をやせむ」
渚に寄る波のかつ返るを見たまひて、「うらやましくも」と、うち誦じたまへるさま、さる世の古言なれど、珍しう聞きなされ、悲しとのみ御供の人々思へり。うち顧みたまへるに、来し方の山は霞はるかにて、まことに「三千里の外」の心地するに、櫂の雫も堪へがたし。
「故郷を峰の霞は隔つれど 眺むる空は同じ雲居か」
つらからぬものなくなむ。
[第九段 離京の当日]
出発の当日は、女君にお話を一日中のんびりとお過ごし申し上げなさって、旅立ちの例で、夜明け前にお立ちに なる。狩衣のご衣装など、旅のご装束、たいそう質素なふうになさって、
「月も出たなあ。もう少し端に出て、せめて見送ってください。どんなにお話申し上げたいことがたくさん積もったと思うことでしょう。一日、二日まれに離れている時でさえ、不思議と気が晴れない思いがしますものを」
とおっしゃって、御簾を巻き上げて、端近にお誘い申し上げなさると、女君、泣き沈んでいらっしゃたが、気持ちを抑えて、膝行して出ていらっしゃったのが、月の光にたいそう美しくお座りになった。「わが身がこのようにはかない世の中を離れて行ったら、どのような状態でさすらって行かれるのであろうか」と、不安で悲しく思われるが、深いお悲しみの上に、ますます悲しませるようなので、
「生きている間にも生き別れというものがあるとは知らずに 命のある限りは一緒にと信じていたことよ はかないことだ」
などと、わざとあっさりと申し上げなさったので、
「惜しくもないわたしの命に代えて、今のこの 別れを少しの間でも引きとどめて置きたいものです」
「なるほど、そのようにもお思いだろう」と、たいそう見捨てて行きにくいが、夜がすっかり明けてしまったら、きまりが悪いので、急いでお立ちになった。
道中、面影のようにありありとまぶたに浮かんで、胸もいっぱいのまま、お舟にお乗りになった。日の長いころ なので、追い風までが吹き加わって、まだ申の時刻に、あの浦にお着きになった。
ほんのちょっとのお出ましであっても、こうした旅路をご経験のない気持ちで、心細さも物珍しさも並大抵では ない。大江殿と言った所は、ひどく荒れて、松の木だけが形跡をとどめているだけである。
「唐国で名を残した人以上に 行方も知らない侘住まいをするのだろうか」
渚に打ち寄せる波の寄せては返すのを御覧になって、「うらやましくも」と口ずさみなさっているご様子、誰でも知っている古歌であるが、珍しく聞けて、悲しいとばかりお供の人々は思っている。振り返って御覧になると、来た方角の山は霞が遠くにかかって、まことに、「三千里の外」という心地がすると、櫂の滴も耐えきれない。
「住みなれた都を峰の霞は遠く隔てるが 悲しい気持ちで眺めている空は同じ空なのだ」
辛くなく思われないものはないのであった。
出発、須磨到着
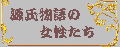 写真の無断転載はご遠慮下さい
写真の無断転載はご遠慮下さい