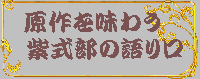
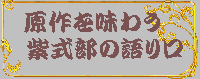
原文 口語訳 [第一段 二月二十余日、紫宸殿の桜花の宴]
如月の二十日あまり、南殿の桜の宴せさせたまふ。后、春宮の御局、左右にして、参う上りたまふ。 弘徽殿の女御、中宮のかくておはするを、をりふしごとにやすからず思せど、物見にはえ過ぐしたまはで、 参りたまふ。
日いとよく晴れて、空のけしき、鳥の声も、心地よげなるに、親王たち、上達部よりはじめて、その道のは皆、 探韻賜はりて文つくりたまふ。宰相中将、「春といふ文字賜はれり」と、のたまふ声さへ、例の、人に異なり。 次に頭中将、人の目移しも、ただならずおぼゆべかめれど、いとめやすくもてしづめて、声づかひなど、ものもの しくすぐれたり。さての人びとは、皆臆しがちに鼻白める多かり。地下の人は、まして、帝、春宮の御才かしこく すぐれておはします、かかる方にやむごとなき人多くものしたまふころなるに、恥づかしく、はるばると曇りなき 庭に立ち出づるほど、はしたなくて、やすきことなれど、苦しげなり。年老いたる博士どもの、なりあやしくやつれ て、例馴れたるも、あはれに、さまざま御覧ずるなむ、をかしかりける。
楽どもなどは、さらにもいはずととのへさせたまへり。やうやう入り日になるほど、春の鴬囀るといふ舞、 いとおもしろく見ゆるに、源氏の御紅葉の賀の折、思し出でられて、春宮、かざしたまはせて、せちに責めのたま はするに、逃がれがたくて、立ちてのどかに袖返すところを一折れ、けしきばかり舞ひたまへるに、似るべきもの なく見ゆ。左大臣、恨めしさも忘れて、涙落したまふ。
[第一段 二月二十余日、紫宸殿の桜花の宴]
如月の二十日過ぎ、(帝は)南殿の桜の宴をお催しなさる。皇后、春宮の御座所、左右に設定して、参上なさる。 弘徽殿の女御、中宮がこのようにお座りになるのを、機会あるごとに不愉快にお思いになるが、見物だけはお見 過ごしできないで、参上なさる。
その日はとてもよく晴れて、空の様子、鳥の声も、気持ちよさそうな折に、親王たち、上達部をはじめとして、 その道の人々は皆、韻字を戴いて詩をお作りになる。宰相中将源氏が、「春という文字を戴きました」と、おっしゃる声 までが、例によって、他の人とは格別である。次に頭中将、(源氏を見た)その目で次に見られるのも、どう思われるかと不安の ようだが、とても好ましく落ち着いて、声の上げ方など、堂々として立派である。その他の人々は、皆気後れして おどおどした様子の者が多かった。地下の人は、それ以上に、帝、春宮の御学問が素晴らしく優れていらっしゃる 上に、このような作文の道に優れた人々が多くいられるころなので、気後れがして、広々と晴の庭に立つ時は、 体裁が悪くて、簡単なことであるが、困った様子である。高齢の博士どもの、姿恰好が見すぼらしく貧相だが、 場馴れているのも、しみじみと、あれこれ御覧になるのは、興趣あることであった。
舞楽類などは、改めて言うまでもなく万端御準備あそばしていた。だんだん日が傾く頃、春鴬囀という舞が、 とても興趣深く見えるので、源氏の御紅葉の賀の折を、自然とお思い出しなされて、春宮が、挿頭をお下しになり、 しきりに御所望なさるので、(源氏は)お断りし難くて、立ってゆっくり袖を返すところを一さし、形ばかりお舞いに なると、似るものがなく素晴らしく見える。左大臣は、恨めしさも忘れて、涙を落としなさる。
桜花を背景に始まる
*桐壺帝の全盛期である。紫宸殿での桜花の宴。帝の両脇に中宮、東宮の座が用意される。 中宮には東宮の母である弘徽殿女御をさしおいて、皇子を産んだ藤壺を擁立していた。
*この晴れの場で、年若い藤壺に高貴な座を奪われ、自分は東宮の母でありながら、 臣下の女御の座に甘んじなければならない。その弘徽殿の悔しさはいうまでもない。並みの遊びなら、知らん顔して出席しない で抵抗している弘徽殿であるが、春の桜花の宴は、秋の月見の宴にならぶ最大の遊びの場。やはり見逃すことは出来ないで、出席した。
*桜花の宴といっても、ただ桜を眺めるのではない。詩歌管弦の遊びをするのだ。 最初に高級な漢詩作文の遊び。遊びといっても学問そのものの才がなければ出来ない。源氏がもっとも優れていて、 次が頭中将。順番はいつも決まっている。最高の貴公子源氏のすぐ次に登場する頭中将は分が悪いことこの上ないが、 かれは実に堂々としていて、見劣りがしない。この二人はタイプは違うが、全ての面においてよくライバルだ。
*帝・東宮の学問もすばらしいという。それに対して、身分が下がるに従い、学問もおとり、地下人などは、晴れの 場に参加していること自体、緊張と引け目で苦しそうだという。例外は、老齢の博士。身分が低くてみすぼらしい風采をしているけれど、 学問の専門家だとの自負から、場慣れして振る舞っているのが、(その道しかない人間の )哀れさを感じさせるといった風に、高い身分から見ると、さまざまな身分の物立ちの生態がみえて面白いものだ、 と語り手は観察している。
*紫式部の家系は曽祖父兼輔が後撰集の選者、父は為時は学問(漢学)の才があることでかろうじて人から評価された人物で ある。紫式部が成人式を迎えた頃は10年近く無官で経済的にも不遇、ようやく得た国司の国が小さな国だったので、sぽれを 嘆く漢詩を書いて上奏したところ学問好きの一条天皇の目にとまり、天皇がしきりに感心した。それを見た道長が 天皇のご機嫌を取るために家人に与えることになっていた越前の国司を譲ってやり、為時に恩を着せた。 その恩義で娘の紫式部は中宮彰子に出仕することになったのだった。
*そういう学問でしか、世に出ることの出来ない親を持った式部なのに、この場面の学者の描き方は少々揶揄的だ。 これがもっと露骨に出るのは、夕霧が進士の試験に及第する場面。そこでの博士は世間知らずの、学問ばかりにこりかたまった 人間として、並みには扱われていない。こういう冷たさは枕草子にもあるが、清少納言の方が同情的だ。 式部は学者に対して特に冷たい。こういう視点には、どのような彼女の意識が籠められているのだろうか。
*作文(さくもん)が終わり、季節にふさわしい「春鶯囀」の舞を見たいと、みなおもう。それにつけても思い出すのは、 あの「紅葉賀」のときの、源氏の舞姿。東宮が挿頭(髪飾り)を源氏にあたえて、舞を催促。源氏は全曲を舞うのでなく、 袖をかざす場面をかたちだけ、舞ってみせる。それをみる左大臣は、家に寄りつかない婿殿源氏のあまりの美しさに 普段の恨み言も忘れて感涙した。
原文 口語訳
夜いたう更けてなむ、事果てける。上達部おのおのあかれ、后、春宮帰らせたまひぬれば、 のどやかになりぬるに、月いと明うさし出でてをかしきを、源氏の君、酔ひ心地に、見過ぐしがたく おぼえたまひければ、「上の人びともうち休みて、かやうに思ひかけぬほどに、もしさりぬべき隙もやある」と、 藤壷わたりを、わりなう忍びてうかがひありけど、語らふべき戸口も鎖してければ、うち嘆きて、なほあらじに、 弘徽殿の細殿に立ち寄りたまへれば、三の口開きたり。
女御は、上の御局にやがて参う上りたまひにければ、人少ななるけはひなり。奥の枢戸も開きて、人音もせず。 「かやうにて、世の中のあやまちはするぞかし」と思ひて、やをら上りて覗きたまふ。人は皆寝たるべし。 いと若うをかしげなる声の、なべての人とは聞こえぬ、「朧月夜に似るものぞなき」とうち誦じて、 こなたざまには来るものか。いとうれしくて、ふと袖をとらへたまふ。
女、恐ろしと思へるけしきにて、「あな、むくつけ。こは、誰そ」とのたまへど、 「何か、疎ましき」とて、「深き夜のあはれを知るも入る月の おぼろけならぬ契りとぞ思ふ」とて、 やをら抱き下ろして、戸は押し立てつ。あさましきにあきれたるさま、いとなつかしうをかしげなり。
わななくわななく、「ここに、人」と、のたまへど、「まろは、皆人に許されたれば、召し寄せたりとも、 なんでふことかあらむ。ただ、忍びてこそ」 とのたまふ声に、この君なりけりと聞き定めて、いささか慰めけり。わびしと思へるものから、情けなく こはごはしうは見えじ、と思へり。酔ひ心地や例ならざりけむ、許さむことは口惜しきに、 女も若うたをやぎて、強き心も知らぬなるべし。
らうたしと見たまふに、ほどなく明けゆけば、心あわたたし。女は、まして、さまざまに思ひ乱れたる けしきなり。 「なほ、名のりしたまへ。いかでか、聞こゆべき。かうてやみなむとは、さりとも思されじ」 とのたまへば、 「憂き身世にやがて消えなば尋ねても 草の原をば問はじとや思ふ」 と言ふさま、艶になまめきたり。「ことわりや。聞こえ違へたる文字かな」とて、 「いづれぞと露のやどりを分かむまに 小笹が原に風もこそ吹け わづらはしく思すことならずは、何かつつまむ。もし、すかいたまふか」 とも言ひあへず、人々起き騒ぎ、上の御局に参りちがふけしきども、しげくまよへば、いとわりなくて、 扇ばかりをしるしに取り換へて、出でたまひぬ。
夜もたいそう更けて御宴は終わったのであった。 上達部はそれぞれ退出し、中宮、春宮も還御あそばしたので、静かになったころに、 月がとても明るくさし出て美しいので、源氏の君、酔心地に見過ごし難くお思いになったので、 「殿上の宿直の人々も寝んで、このように思いもかけない時に、もしや都合のよい機会もあろうか」と、 藤壷周辺を、無性に人目を忍んであちこち窺ったが、手引を頼むはずの戸口も閉まっているので、 溜息をついて、なおもこのままでは気がすまず、弘徽殿の細殿にお立ち寄りになると、三の口が開いている。
女御は、上の御局にそのまま参上なさったので、人気の少ない感じである。奥の枢戸も開いていて、 人のいる音もしない。 「このような無用心から、男女の過ちは起こるものだ」と思って、そっと上ってお覗きになる。 女房たちは皆眠っているのだろう。とても若々しく美しい声で、並の身分とは思えず、 「朧月夜に似るものはない」と口ずさんで、こちらの方に来るではないか。とても嬉しくなって、 とっさに袖をお捉えになる。
女、怖がっている様子で、「あら、嫌ですわ。これは、どなたですか」とおっしゃるが、 「どうして、嫌ですか」と言って、「趣深い春の夜更けの情趣をご存知でいられるのも 前世からの浅からぬ御縁があったものと存じます」と詠んで、そっと抱き下ろして、 戸は閉めてしまった。あまりの意外さに驚きあきれている様子、とても親しみやすくかわいらしい感じである。
怖さに震えながら、「ここに、人が」と、おっしゃるが、「わたしは、誰からも許されているので、 人を呼んでも、何ということありませんよ。ただ、じっとしていなさい」とおっしゃる声で、 この君であったのだと理解して、少しほっとするのであった。やりきれないと思う一方で、 物のあわれを知らない強情な女とは見られまい、と思っている。酔心地がいつもと違っていたからであろうか、 手放すのは残念に思われるし、女も若くなよやかで、強情な性質も持ち合わせてないのであろう。
かわいらしいと御覧になっていらっしゃるうちに、間もなく明るくなって行ったので、気が急かれる。 女は、男以上にいろいろと思い悩んでいる様子である。 「やはり、お名前をおっしゃってください。どのようして、お便りを差し上げられましょうか。 こうして終わろうとは、いくら何でもお思いではあるまい」 とおっしゃると、 「不幸せな身のまま名前を明かさないでこの世から死んでしまったなら 野末の草の原まで尋ねて来ては下さらないのかと思います」と詠む態度、優艶で魅力的である。 「ごもっともだ。先程の言葉は申し損ねました」と言って、 「どなたであろうかと家を探しているうちに 世間に噂が立ってだめになってしまうといけないと思いまして 迷惑にお思いでなかったら、何の遠慮がいりましょう。ひょっとして、おだましになるのですか」 とも言い終わらないうちに、女房たちが起き出して、上の御局に参上したり下がって来たりする様子が、 騒がしくなってきたので、まことに仕方なくて、扇だけを証拠として交換し合って、お出になった。
春は朧の月の下で
原文 口語訳
桐壷には、人びと多くさぶらひて、おどろきたるもあれば、かかるを、 「さも、たゆみなき御忍びありきかな」 とつきじろひつつ、そら寝をぞしあへる。入りたまひて臥したまへれど、寝入られず。
「をかしかりつる人のさまかな。女御の御おとうとたちにこそはあらめ。まだ世に馴れぬは、 五、六の君ならむかし。帥宮の北の方、頭中将のすさめぬ四の君などこそ、よしと聞きしか。 なかなかそれならましかば、今すこしをかしからまし。六は春宮にたてまつらむとこころざしたまへるを、 いとほしうもあるべいかな。わづらはしう、尋ねむほどもまぎらはし、さて絶えなむとは思はぬけしきなりつるを、 いかなれば、言通はすべきさまを教へずなりぬらむ」 など、よろづに思ふも、心のとまるなるべし。かうやうなるにつけても、まづ、「かのわたりのありさまの、 こよなう奥まりたるはや」と、ありがたう思ひ比べられたまふ。
桐壷には、女房が大勢仕えていて、目を覚ましている者もいるので、このようなのを、 「何とも、ご熱心なお忍び歩きですこと」と突つき合いながら、空寝をしていた。 お入りになって横になられたが、眠ることができない。
「美しい人であったなあ。女御の御妹君であろう。まだうぶなところから、五の君か六の君であろう。 帥宮の北の方や、頭中将が気にいっていない四の君などは、美人だと聞いていたが。かえってその人たちで あったら、もう少し味わいがあったろうに。六の君は春宮に入内させようと心づもりをしておられるから、 気の毒なことであるなあ。厄介なことだ、尋ねることもなかなか難しい、あのまま終わりにしようとは思って いない様子であったが、どうしたことで、便りを通わす方法を教えずじまいにしたのだろう」 などと、いろいろと気にかかるのも、心惹かれるところがあるのだろう。このようなことにつけても、 まずは、「あの周辺の有様が、どこよりも奥まっているな」と、世にも珍しくご比較せずにはいらっしゃれない。
謎の美女の正体は?
原文 口語訳 [第二段 三月二十余日、右大臣邸の藤花の宴]
かの有明の君は、はかなかりし夢を思し出でて、いともの嘆かしうながめたまふ。春宮には、卯月ばかりと 思し定めたれば、いとわりなう思し乱れたるを、男も、尋ねたまはむにあとはかなくはあらねど、いづれとも 知らで、ことに許したまはぬあたりにかかづらはむも、人悪く思ひわづらひたまふに、弥生の二十余日、 右の大殿の弓の結に、上達部、親王たち多く集へたまひて、やがて藤の宴したまふ。花盛りは過ぎにたるを、 「ほかの散りなむ」とや教へられたりけむ、遅れて咲く桜、二木ぞいとおもしろき。新しう造りたまへる殿を、 宮たちの御裳着の日、磨きしつらはれたり。はなばなとものしたまふ殿のやうにて、何ごとも今めかしう もてなしたまへり。
源氏の君にも、一日、内裏にて御対面のついでに、聞こえたまひしかど、おはせねば、口惜しう、ものの栄なし と思して、御子の四位少将をたてまつりたまふ。 「わが宿の花しなべての色ならば 何かはさらに君を待たまし」 内裏におはするほどにて、主上に奏したまふ。 「したり顔なりや」と笑はせたまひて、「わざとあめるを、早うものせよかし。女御子たちなども、 生ひ出づるところなれば、なべてのさまには思ふまじきを」などのたまはす。御装ひなどひきつくろひたまひて、 いたう暮るるほどに、待たれてぞ渡りたまふ。
桜の唐の綺の御直衣、葡萄染の下襲、裾いと長く引きて。皆人は表の衣なるに、あざれたる大君姿の なまめきたるにて、いつかれ入りたまへる御さま、げにいと異なり。花の匂ひもけおされて、なかなか ことざましになむ。 遊びなどいとおもしろうしたまひて、夜すこし更けゆくほどに、源氏の君、いたく酔ひ悩めるさまにもてなし たまひて、紛れ立ちたまひぬ。
[第二段 三月二十余日、右大臣邸の藤花の宴]
あの有明の君は、夢のようにはかなかった逢瀬をお思い出しになって、とても物嘆かしくて物思いに沈んで いらっしゃる。春宮には、卯月ころとご予定になっていたので、とてもたまらなく悩んでいらっしゃったが、 男も、お捜しになるにも手がかりがないわけではないが、どちらとも分からず、特に好ましく思っておられ ないご一族に関係するのも、体裁の悪く思い悩んでいらっしゃるところに、弥生の二十日過ぎ、右の大殿の 弓の結があり、上達部、親王方、大勢お集まりになって、引き続いて藤の宴をなさる。花盛りは過ぎてしまったが、 「他のが散りってしまった後に」と、教えられたのであろうか、遅れて咲く桜、二本がとても美しい。 新しくお造りになった殿を、姫宮たちの御裳着の儀式の日に、磨き飾り立ててある。派手好みでいらっしゃる ご家風のようで、すべて当世風に洒落た行き方になさている。
源氏の君にも、先日、宮中でお会いした折に、ご案内申し上げなさったが、おいでにならないので、残念で、 折角の催しも見栄えがしない、とお思いになって、ご子息の四位少将をお迎えに差し上げなさる。 「わたしの邸の藤の花が世間一般の色をしているのなら どうしてあなたをお待ち致しましょうか」 宮中においでの時で、お上に奏上なさる。 「得意顔だね」と、お笑いあそばして、「わざわざお迎えがあるようだから、早くお行きになるのがよい。 女御子たちも成長なさっている所だから、赤の他人とは思っていまいよ」などと仰せになる。 御装束などお整えになって、たいそう日が暮れたころ、待ち兼ねられて、お着きになる。
桜襲の唐織りのお直衣、葡萄染の下襲、裾をとても長く引いて。参会者は皆袍を着ているところに、 しゃれた大君姿の優美な様子で、丁重に迎えられてお入りになるお姿は、なるほどまことに格別である。 花の美しさも圧倒されて、かえって興醒めである。 管弦の遊びなどもとても興趣深くなさって、夜が少し更けていくころに、源氏の君、たいそう酔って 苦しいように見せかけなさって、人目につかぬよう座をお立ちになった。
あえて右大臣邸のへ藤花の宴へ
原文 口語訳
寝殿に、女一宮、女三宮のおはします。東の戸口におはして、寄りゐたまへり。藤はこなたの妻にあたりて あれば、御格子ども上げわたして、人びと出でゐたり。袖口など、踏歌の折おぼえて、ことさらめきもて出でたる を、ふさはしからずと、まづ藤壷わたり思し出でらる。
「なやましきに、いといたう強ひられて、わびにてはべり。かしこけれど、この御前にこそは、蔭にも 隠させたまはめ」とて、妻戸の御簾を引き着たまへば、 「あな、わづらはし。よからぬ人こそ、やむごとなきゆかりはかこちはべるなれ」と言ふけしきを見たまふに、 重々しうはあらねど、おしなべての若人どもにはあらず、あてにをかしきけはひしるし。
そらだきもの、いと煙たうくゆりて、衣の音なひ、いとはなやかにふるまひなして、心にくく奥まりたるけはひ はたちおくれ、今めかしきことを好みたるわたりにて、やむごとなき御方々もの見たまふとて、この戸口は 占めたまへるなるべし。さしもあるまじきことなれど、さすがにをかしう思ほされて、「いづれならむ」と、 胸うちつぶれて、「扇を取られて、からきめを見る」と、うちおほどけたる声に言ひなして、寄りゐたまへり。
「あやしくも、さま変へける高麗人かな」といらふるは、心知らぬにやあらむ。いらへはせで、ただ時々、 うち嘆くけはひする方に寄りかかりて、几帳越しに手をとらへて、 「梓弓いるさの山に惑ふかな ほの見し月の影や見ゆると 何ゆゑか」 と、推し当てにのたまふを、え忍ばぬなるべし。 「心いる方ならませば弓張の 月なき空に迷はましやは」 と言ふ声、ただそれなり。いとうれしきものから。
寝殿に、女一の宮、女三の宮とがいらっしゃる。東の戸口にいらっしゃって、寄り掛かってお座りになった。 藤はこちらの隅にあったので、御格子を一面に上げわたして、女房たちが端に出て座っていた。袖口などは、 踏歌の時を思い出して、わざとらしく出しているのを、似つかわしくないと、まずは藤壷周辺を思い出さずには いらっしゃれない。
「苦しいところに、とてもひどく勧められて、困っております。恐縮ですが、この辺の物蔭にでも隠させて ください」と言って、妻戸の御簾を引き被りなさると、 「あら、困りますわ。身分の賎しい人なら、高貴な縁者を頼って来るとは聞いておりますが」と言う様子を 御覧になると、重々しくはないが、並の若い女房たちではなく、上品で風情ある様子がはっきりと分かる。
空薫物、とても煙たく薫らせて、衣ずれの音、とても派手な感じにわざと振る舞って、心憎く奥ゆかしい 雰囲気は欠けて、当世風な派手好みのお邸で、高貴な御方々が御見物なさるというので、こちらの戸口は座を お占めになっているのだろう。そうしてはいけないことなのだが、やはり興味をお惹かれになって、「どの姫君で あったのだろうか」と、胸をどきどきさせて、「扇を取られて、辛い目を見ました」 と、わざとのんびりとした声で言って、近寄ってお座りになった。
「妙な、変わった高麗人ですね」と答えるのは、事情を知らない人であろう。返事はしないで、 わずかに時々、溜息をついている様子のする方に寄り掛かって、几帳越しに、手を捉えて、 「月の入るいるさの山の周辺でうろうろと迷っています かすかに見かけた月をまた見ることができようかと なぜでしょうか」 と、当て推量におっしゃるのを、堪えきれないのであろう。 「本当に深くご執心でいらっしゃれば たとえ月が出ていなくても迷うことがありましょうか」 と言う声、まさにその人のである。とても嬉しいのだが。
弘徽殿の御殿にいる女性
原文 口語訳 [第一段 源氏、尚侍朧月夜と逢瀬を重ねる]
帝は、院の御遺言違へず、あはれに思したれど、若うおはしますうちにも、御心なよびたるかたに過ぎて、 強きところおはしまさぬなるべし、母后、祖父大臣とりどりしたまふことは、え背かせたまはず、世のまつりごと、 御心にかなはぬやうなり。
わづらはしさのみまされど、尚侍の君は、人知れぬ御心し通へば、わりなくてと、おぼつかなくはあらず。 五壇の御修法の初めにて、慎しみおはします隙をうかがひて、例の、夢のやうに聞こえたまふ。かの、 昔おぼえたる細殿の局に、中納言の君、紛らはして入れたてまつる。人目もしげきころなれば、常よりも端近なる、 そら恐ろしうおぼゆ。
朝夕に見たてまつる人だに、飽かぬ御さまなれば、まして、めづらしきほどにのみある御対面の、 いかでかはおろかならむ。女の御さまも、げにぞめでたき御盛りなる。重りかなるかたは、いかがあらむ、 をかしうなまめき若びたる心地して、見まほしき御けはひなり。
ほどなく明け行くにや、とおぼゆるに、ただここにしも、「宿直申し、さぶらふ」と、声づくるなり。 「また、このわたりに隠ろへたる近衛司ぞあるべき。腹ぎたなきかたへの教へおこするぞかし」と、 大将は聞きたまふ。をかしきものから、わづらはし。 ここかしこ尋ねありきて、「寅一つ」と申すなり。
女君、「心からかたがた袖を濡らすかな 明くと教ふる声につけても」とのたまふさま、はかなだちて、いとをかし。 「嘆きつつわが世はかくて過ぐせとや 胸のあくべき時ぞともなく」 静心なくて、出でたまひぬ。
夜深き暁月夜の、えもいはず霧りわたれるに、いといたうやつれて、振る舞ひなしたまへるしも、 似るものなき御ありさまにて、承香殿の御兄の藤少将、藤壷より出でて、月の少し隈ある立蔀のもとに立てり けるを、知らで過ぎたまひけむこそいとほしけれ。もどききこゆるやうもありなむかし。
かやうのことにつけても、もて離れつれなき人の御心を、かつはめでたしと思ひきこえたまふものから、 わが心の引くかたにては、なほつらう心憂し、とおぼえたまふ折多かり。
[第一段 源氏朧月夜と逢瀬を重ねる]
帝は、院の御遺言に背かず、親しくお思いであったが、お若くいらっしゃるうえにも、お心が優し過ぎて、 毅然としたところがおありでないのであろう、母后、祖父大臣、それぞれになさる事に対しては、反対することが おできあそばされず、天下の政治も、お心通りに行かないようである。
厄介な事ばかりが多くなるが、尚侍の君は、密かにお心を通わしているので、無理をなさりつつも、長い途絶えが あるわけではない。五壇の御修法の初日で、お慎しみあそばす隙間を狙って、いつものように、夢のように お逢い申し上げる。あの、昔を思い出させる細殿の局に、中納言の君が、人目を紛らしてお入れ申し上げる。 人目の多いころなので、いつもより端近なのが、何となく恐ろしく思わずにはいられない。
朝夕に拝見している人でさえ、見飽きないご様子なので、まして、まれまれにある逢瀬であっては、どうして 並々のことであろうか。女のご様子も、なるほど素晴しいお盛りである。重々しいという点では、どうであろうか、 魅力的で優美で若々しい感じがして、好ましいご様子である。
間もなく夜も明けて行こうか、と思われるころに、ちょうどすぐ側で、 「宿直申しの者、ここにおります」と、声を上げて申告するようである。「自分以外にも、この近辺で密会して いる近衛府の官人がいるのだろう。こ憎らしい傍輩が教えてよこしたのだろう」と、大将はお聞きになる。 面白いと思う一方、厄介である。 あちこちと探し歩いて、「寅一刻」と申しているようだ。
女君、「自分からあれこれと涙で袖を濡らすことですわ 夜が明けると教えてくれる声につけましても」 とおっしゃる様子、いじらしくて、まことに魅力的である。 「嘆きながら一生をこのように過ごせというのでしょうか 胸の思いの晴れる間もないのに」 慌ただしい思いで、お出になった。
夜の深い暁の月夜に、何ともいいようのない霧が立ちこめていて、とてもたいそうお忍び姿で、振る舞って いらっしゃるのが、他に似るものがないほどのご様子で、承香殿の兄君の藤少将が、藤壷から出て来て、 月の光が少し蔭になっている立蔀の側に立っていたのを知らないで、お通り過ぎになったことはお気の毒で あったなあ。きっとご非難申し上げるようなこともあるだろうよ。
このような事につけても、よそよそしくて冷たい方のお心を、一方では立派であるとお思い申し上げては いるものの、自分勝手な気持ちからすれば、やはり辛く恨めしい、と思われなさる時が多い。
危険なアバンチュールにのめり込む
原文 口語訳 [第二段 源氏、朧月夜と密会中、右大臣に発見される]
そのころ、尚侍の君まかでたまへり。瘧病に久しう悩みたまひて、まじなひなども心やすくせむとてなりけり。 修法など始めて、おこたりたまひぬれば、誰も誰も、うれしう思すに、例の、めづらしき隙なるをと、聞こえ 交はしたまひて、わりなきさまにて、夜な夜な対面したまふ。 いと盛りに、にぎははしきけはひしたまへる人の、すこしうち悩みて、痩せ痩せになりたまへるほど、 いとをかしげなり。
后の宮も一所におはするころなれば、けはひいと恐ろしけれど、かかることしもまさる御癖なれば、 いと忍びて、たび重なりゆけば、けしき見る人びともあるべかめれど、わづらはしうて、宮には、さなむと啓せず。
大臣、はた思ひかけたまはぬに、雨にはかにおどろおどろしう降りて、神いたう鳴りさわぐ暁に、殿の君達、 宮司など立ちさわぎて、こなたかなたの人目しげく、女房どもも怖ぢまどひて、近う集ひ参るに、いとわりなく、 出でたまはむ方なくて、明け果てぬ。 御帳のめぐりにも、人びとしげく並みゐたれば、いと胸つぶらはしく思さる。心知りの人二人ばかり、 心を惑はす。
神鳴り止み、雨すこしを止みぬるほどに、大臣渡りたまひて、まづ、宮の御方におはしけるを、村雨のまぎれにて え知りたまはぬに、軽らかにふとはひ入りたまひて、御簾引き上げたまふままに、 「いかにぞ。いとうたてありつる夜のさまに、思ひやりきこえながら、参り来でなむ。中将、宮の亮など、 さぶらひつや」など、のたまふけはひの、舌疾にあはつけきを、大将は、もののまぎれにも、左の大臣の 御ありさま、ふと思し比べられて、たとしへなうぞ、ほほ笑まれたまふ。げに、入り果ててものたまへかしな。
尚侍の君、いとわびしう思されて、やをらゐざり出でたまふに、面のいたう赤みたるを、「なほ悩ましう思さ るるにや」と見たまひて、「など、御けしきの例ならぬ。もののけなどのむつかしきを、修法延べさすべかりけり」 とのたまふに、薄二藍なる帯の、御衣にまつはれて引き出でられたるを見つけたまひて、あやしと思すに、また、 畳紙の手習ひなどしたる、御几帳のもとに落ちたり。
「これはいかなる物どもぞ」と、御心おどろかれて、 「かれは、誰れがぞ。けしき異なるもののさまかな。たまへ。それ取りて誰がぞと見はべらむ」とのたまふにぞ、 うち見返りて、我も見つけたまへる。紛らはすべきかたもなければ、いかがは応へきこえたまはむ。 我にもあらでおはするを、「子ながらも恥づかしと思すらむかし」と、さばかりの人は、思し憚るべきぞかし。 されど、いと急に、のどめたるところおはせぬ大臣の、思しもまはさずなりて、畳紙を取りたまふままに、 几帳より見入れたまへるに、いといたうなよびて、慎ましからず添ひ臥したる男もあり。今ぞ、やをら顔ひき 隠して、とかう紛らはす。あさましう、めざましう心やましけれど、直面には、いかでか現はしたまはむ。 目もくるる心地すれば、この畳紙を取りて、寝殿に渡りたまひぬ。
尚侍の君は、我かの心地して、死ぬべく思さる。大将殿も、「いとほしう、つひに用なき振る舞ひのつもりて、 人のもどきを負はむとすること」と思せど、女君の心苦しき御けしきを、とかく慰めきこえたまふ。
[第二段 源氏、朧月夜と密会中、右大臣に発見される]
そのころ、尚侍の君が退出なさっていた。瘧病に長く患いなさって、加持祈祷なども気楽に行おうとして であった。修法など始めて、お治りになったので、どなたもどなたも、喜んでいらっしゃる時に、例によって、 めったにない機会だからと、お互いに示し合わせなさって、無理を押して、毎夜毎夜お逢いなさる。 まことに女盛りで、豊かで派手な感じがなさる方が、少し病んで痩せた感じにおなりでいらっしゃるところ、 実に魅力的である。
后宮も同じ邸にいらっしゃるころなので、感じがとても恐ろしい気がしたが、このような危険な逢瀬 こそかえって思いの募るご性癖なので、たいそうこっそりと、度重なってゆくと、気配を察知する女房たちも きっといたにちがいないだろうが、厄介なことと思って、宮には、そうとは申し上げない。
大臣は、もちろん思いもなさらないが、雨が急に激しく降り出して、雷がひどく鳴り轟いていた暁方に、 殿のご子息たちや、后宮職の官人たちなど立ち騒いで、ここかしこに人目が多く、女房どももおろおろ恐がって、 近くに参集していたので、まことに困って、お帰りになるすべもなくて、すっかり明けてしまった。 御帳台のまわりにも、女房たちがおおぜい並び伺候しているので、まことに胸がどきどきなさる。事情を 知っている女房二人ほど、どうしたらよいか分からないでいる。
雷が鳴りやんで、雨が少し小降りになったころに、大臣が渡っていらして、まず最初、宮のお部屋に いらしたが、村雨の音に紛れてご存知でなかったところへ、気軽にひょいとお入りになって、御簾を巻き上げ なさりながら、「いががですか。とてもひどい昨夜の荒れ模様を、ご心配申し上げながら、お見舞いにも 参りませんでしたが。中将、宮の亮などは、お側にいましたか」などと、おっしゃる様子が、早口で軽率なのを、 大将は、危険な時にでも、左大臣のご様子をふとお思い出しお比べになって、比較しようもないほど、 つい笑ってしまわれる。なるほど、すっかり入ってからおっしゃればよいものを。
尚侍の君、とてもやりきれなくお思いになって、静かにいざり出なさると、顔がたいそう赤くなって いるのを、「まだ苦しんでいられるのだろうか」と御覧になって、 「どうして、まだお顔色がいつもと違うのか。物の怪などがしつこいから、修法を続けさせるべきだった」 とおっしゃると、薄二藍色の帯が、お召物にまつわりついて出ているのをお見つけになって、変だとお思い になると、また一方に、懐紙に歌など書きちらしたものが、御几帳のもとに落ちていた。
「これはいったいどうしたことか」と、驚かずにはいらっしゃれなくて、 「あれは、誰のものか。見慣れない物だね。見せてください。それを手に取って誰のものか調べよう」 とおっしゃるので、振り返ってみて、ご自分でもお見つけになった。ごまかすこともできないので、 どのようにお応え申し上げよう。呆然としていらっしゃるのを、「我が子ながら恥ずかしいと思っていられる のだろう」と、これほどの方は、お察しなさって遠慮すべきである。しかし、まことに性急で、ゆったりした ところがおありでない大臣で、後先のお考えもなくなって、懐紙をお持ちになったまま、几帳から 覗き込みなさると、まことにたいそうしなやかな恰好で、臆面もなく添い臥している男もいる。 今になって、そっと顔をひき隠して、あれこれと身を隠そうとする。あきれて、癪にさわり腹立たしいけれど、 面と向かっては、どうして暴き立てることがおできになれようか。目の前がまっ暗になる気がするので、 この懐紙を取って、寝殿にお渡りになった。
尚侍の君は、呆然自失して、死にそうな気がなさる。大将殿も、「困ったことになった、とうとう、 つまらない振る舞いが重なって、世間の非難を受けるだろうことよ」とお思いになるが、女君の気の毒なご様子を、 いろいろとお慰め申し上げなさる。
右大臣にみつかる
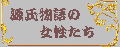 写真の無断転載はご遠慮下さい
写真の無断転載はご遠慮下さい