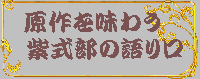
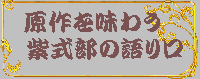
原文 口語訳
[第一段 須磨の住居]
おはすべき所は、行平の中納言の、「藻塩垂れつつ」侘びける家居近きわたりなりけり。海づらはやや入りて、 あはれにすごげなる山中なり。
垣のさまよりはじめて、めづらかに見たまふ。茅屋ども、葦葺ける廊めく屋など、をかしうしつらひなしたり。 所につけたる御住まひ、やう変はりて、「かからぬ折ならば、をかしうもありなまし」と、昔の御心のすさび思し 出づ。
近き所々の御荘の司召して、さるべきことどもなど、良清朝臣、親しき家司にて、仰せ行なふもあはれなり。 時の間に、いと見所ありてしなさせたまふ。水深う遣りなし、植木どもなどして、今はと静まりたまふ心地、うつ つならず。国の守も親しき殿人なれば、忍びて心寄せ仕うまつる。かかる旅所ともなう、人騒がしけれども、はか ばかしう物をものたまひあはすべき人しなければ、知らぬ国の心地して、いと埋れいたく、「いかで年月を過ぐさ まし」と思しやらる。
[第一段 須磨の住居]
お住まいになる所は、行平中納言が、「藻塩たれつつ」と詠んだ侘住まい付近なのであった。海岸からは少し入り 込んで、身にしみるばかり寂しい山の中である。
垣根の様子をはじめとして、物珍しく御覧になる。茅葺きの建物、葦で葺いた回廊のような建物など、風情のある 造作がしてあった。場所柄にふさわしいお住まい、風変わりに思われて、「このようなでない時ならば、興趣深くも あったであろうに」と、昔のお心にまかせたお忍び歩きのころをお思い出しになる。
近い所々のご荘園の管理者を呼び寄せて、しかるべき事どもを、良清朝臣が、側近の家司として、お命じになり取 り仕切るのも感に耐えないことである。暫くの間に、たいそう風情があるようにお手入れさせなさる。遣水を深く流 し、植木類を植えたりして、もうすっかりと落ち着きなさるお気持ち、夢のようである。国守も親しい家来筋の者な ので、こっそりと好意をもってお世話申し上げる。このような旅の生活にも似ず、人がおおぜい出入りするが、まと もにお話相手となりそうな人もいないので、知らない他国の心地がして、ひどく気も滅入って、「どのようにしてこ れから先過ごして行こうか」と、お思いやらずにはいられない。
源氏、須磨での生活開始
原文 口語訳 [第二段 京の人々へ手紙]
やうやう事静まりゆくに、長雨のころになりて、京のことも思しやらるるに、恋しき人多く、女君の思したりし さま、春宮の御事、若君の何心もなく紛れたまひしなどをはじめ、ここかしこ思ひやりきこえたまふ。
京へ人出だし立てたまふ。二条院へたてまつりたまふと、入道の宮のとは、書きもやりたまはず、昏されたまへ り。
宮には、
「松島の海人の苫屋もいかならむ
須磨の浦人しほたるるころ
いつとはべらぬなかにも、来し方行く先かきくらし、『汀まさりて』なむ」
尚侍の御もとに、例の、中納言の君の私事のやうにて、中なるに、
「つれづれと過ぎにし方の思うたまへ出でらるるにつけても、
こりずまの浦のみるめのゆかしきを
塩焼く海人やいかが思はむ」
さまざま書き尽くしたまふ言の葉、思ひやるべし。
大殿にも、宰相の乳母にも、仕うまつるべきことなど書きつかはす。
[第二段 京の人々へ手紙]
だんだんと落ち着いて行くころ、梅雨時期になって、京のことがご心配になられて、恋しい人々が多く、女君の 悲しんでいらした様子、東宮のお身の上、若君が無邪気に動き回っていらしたことなどをはじめとして、あちらこ ちら方をお思いやりになる。
京へ使者をお立てになる。二条院に差し上げなさるのと、入道の宮のとは、筆も思うように進まず、涙に目も 暮れなさった。
宮には、
「出家されたあなた様はいかがお過ごしでしょうか
わたしは須磨の浦で涙に泣き濡れております今日このごろです
悲しさは常のことですが、過去も未来もまっ暗闇といった感じで、『汀まさりて』という思いです」
尚侍のお許に、例によって、中納言の君への私事のようにして、その中に、
「所在なく過ぎ去った日々の事柄が自然と思い出されるにつけても、
性懲りもなくお逢いしたく思っていますが
あなた様はどう思っておいででしょうか」
いろいろとお心を尽くして書かれた言葉というのを想像してください。
大殿邸にも、宰相の乳母のもとに、ご養育に関する事柄をお書きつかわしになる。
源氏、京の方々へ便り
原文 口語訳
京には、この御文、所々に見たまひつつ、御心乱れたまふ人びとのみ多かり。
二条院の君は、そのままに起きも 上がりたまはず、尽きせぬさまに思しこがるれば、さぶらふ人びともこしらへわびつつ、心細う思ひあへり。
もてならしたまひし御調度ども、弾きならしたまひし御琴、脱ぎ捨てたまへる御衣の匂ひなどにつけても、今はと 世になからむ人のやうにのみ思したれば、かつはゆゆしうて、少納言は、僧都に御祈りのことなど聞こゆ。二方に 御修法などせさせたまふ。かつは、「思し嘆く御心静めたまひて、思ひなき世にあらせたてまつりたまへ」と、心 苦しきままに祈り申したまふ。
旅の御宿直物など、調じてたてまつりたまふ。かとりの御直衣、指貫、さま変はりたる心地するもいみじきに、 「去らぬ鏡」とのたまひし面影の、げに身に添ひたまへるもかひなし。
出で入りたまひし方、寄りゐたまひし真木柱などを見たまふにも、胸のみふたがりて、ものをとかう思ひめぐらし、 世にしほじみぬる齢の人だにあり、まして、馴れむつびきこえ、父母にもなりて生ほし立てならはしたまへれば、 恋しう思ひきこえたまへる、ことわりなり。ひたすら世になくなりなむは、言はむ方なくて、やうやう忘れ草も生ひ やすらむ、聞くほどは近けれど、いつまでと限りある御別れにもあらで、思すに尽きせずなむ。
京では、このお手紙を、あちこちで御覧になって、お心を痛められる方々ばかりが多かった。
二条院の君は、あれからお枕も上がらず、尽きぬ悲しみに沈まれているので、伺候している女房たちもお慰め困 じて、互いに心細く思っていた。
日頃お使いになっていらした御調度などや、お弾き馴れていらしたお琴、お脱ぎ置きになったお召し物の薫りな どにつけても、今はもうこの世にいない人のようにばかりお思いになっているので、ごもっともと思う一方で縁起 でもないので、少納言は、僧都にご祈祷をお願い申し上げる。お二方のために御修法などをおさせになる。 ご帰京を祈る一方では、「このようにお悲しみになっているお気持ちをお鎮めくださって、物思いのないお身の上に させて上げてください」と、おいたわしい気持ちでお祈り申し上げなさる。
旅先でのご寝具など、作ってお届けなさる。かとりのお直衣、指貫、変わった感じがするにつけても悲しいのに、 「去らない鏡の」とお詠みになった面影が、なるほど目に浮かんで離れないのも詮のないことである。
始終出入りなさったあたり、寄り掛かりなさった真木柱などを御覧になるにつけても、胸ばかりが塞がって、 よく物事の分別がついて、世間の経験を積ん年輩の人でさえそうであるのに、まして、お馴れ親しみ申し、父母に もなりかわってお育て申されてきたので、恋しくお思い申し上げなさるのも、ごもっともなことである。まるでこ の世から去られてしまうのは、何とも言いようがなく、だんだん忘れることもできようが、聞けば近い所であるが、 いつまでと期限のあるお別れでもないので、思えば思うほど悲しみは尽きないのである。
二条院の女君の悲しみ
原文 口語訳
入道宮にも、春宮の御事により思し嘆くさま、いとさらなり。御宿世のほどを思すには、いかが浅く思されむ。 年ごろはただものの聞こえなどのつつましさに、「すこし情けあるけしき見せば、それにつけて人のとがめ出づる こともこそ」とのみ、ひとへに思し忍びつつ、あはれをも多う御覧じ過ぐし、すくすくしうもてなしたまひしを、 「かばかり憂き世の人言なれど、かけてもこの方には言ひ出づることなくて止みぬるばかりの、人の御おもむけも、 あながちなりし心の引く方にまかせず、かつはめやすくもて隠しつるぞかし。」あはれに恋しうも、いかが思し出 でざらむ。
御返りも、すこしこまやかにて、
「このころは、いとど、
塩垂るることをやくにて松島に
年ふる海人も嘆きをぞつむ」
尚侍君の御返りには、
「浦にたく海人だにつつむ恋なれば
くゆる煙よ行く方ぞなき
さらなることどもは、えなむ」 とばかり、いささか書きて、中納言の君の中にあり。思し嘆くさまなど、いみじう言ひたり。あはれと思ひきこ えたまふ節々もあれば、うち泣かれたまひぬ。
入道の宮におかれても、春宮の御将来のことでお嘆きになるご様子、いうまでもない。御宿縁をお考えになると 、どうして並大抵のお気持ちでいられようか。近年はただ世間の評判が憚られるので、「少しでも同情の素振りを見 せたら、それにつけても誰か咎めだてすることがありはしまいか」とばかり、一途に堪え忍び忍びして、愛情をも 多く知らないふりをして、そっけない態度をなさっていたが、「これほどにつらい世の噂ではあるが、少しもこの ことについては噂されることなく終わったほどの、あの方の態度も、一途であった恋心の赴くままにまかせず、一 方では無難に隠したのだ」。しみじみと恋しいが、どうしてお思い出しになれずにいられようか。
お返事も、いつもより情愛こまやかに、
「このごろは、ますます、
涙に濡れているのを仕事として
出家したわたしも嘆きを積み重ねています」
尚侍の君のお返事には、
「須磨の浦の海人でさえ人目を隠す恋の火ですから
人目多い都にいる思いはくすぶり続けて晴れようがありません
今さら言うまでもございませんことの数々は、申し上げるまでもなく」
とだけ、わずかに書いて、中納言の君の手紙の中にある。お嘆きのご様子など、たくさん書かれてあった。 いとしいとお思い申されるところがあるので、ふとお泣きになってしまった。
藤壺の思い、朧月夜の返事
原文 口語訳
姫君の御文は、心ことにこまかなりし御返りなれば、あはれなること多くて、
「浦人の潮くむ袖に比べ見よ
波路へだつる夜の衣を」
ものの色、したまへるさまなど、いときよらなり。何ごともらうらうじうものしたまふを、思ふさまにて、 「今は他事に心あわたたしう、行きかかづらふ方もなく、しめやかにてあるべきものを」と思すに、いみじう口 惜しう、夜昼面影におぼえて、堪へがたう思ひ出でられたまへば、「なほ忍びてや迎へまし」と思す。またうち返 し、「なぞや、かく憂き世に、罪をだに失はむ」と思せば、やがて御精進にて、明け暮れ行なひておはす。
大殿の若君の御事などあるにも、いと悲しけれど、「おのづから逢ひ見てむ。頼もしき人々ものしたまへば、 うしろめたうはあらず」と、思しなさるるは、なかなか、子の道の惑はれぬにやあらむ。
姫君のお手紙は、格別に心こめたお返事なので、しみじみと胸を打つことが多くて、
「あなたのお袖とお比べになってみてください
遠く波路隔てた都で独り袖を濡らしている夜の衣と」
お召物の色合い、仕立て具合など、実に良く出来上がっていた。何事につけてもいかにも上手にお出来になるのが 、思い通りであるので、 「今ではよけいな情事に心せわしく、かかずらうこともなく、落ち着いて暮らせるはずものを」とお思いになると 、ひどく残念に、昼夜なく面影が目の前に浮かんで、堪え難く思わずにはいらっしゃれないので、「やはりこっそり と呼び寄せようかしら」とお思いになる。また一方で思い返して、「どうして出来ようか、このようにつらい世であ るから、せめて罪障だけでも消滅させよう」とお考えになると、そのままご精進の生活に入って、明け暮れお勤めを なさる。
大殿の若君のお返事などあるにつけ、とても悲しい気がするが、「いずれ再会の機会はあるであろう。信頼できる 人々がついていらっしゃるから、不安なことはない」と、思われなされるのは、子供を思う煩悩の方は、かえってお 惑いにならないのであろうか。
女君からの返事、女君への思い
(「伊勢の御息所へ手紙」と「朧月夜尚侍の参内」は省略した。)「須磨」の巻 3 「須磨の秋」
原文 口語訳
[第一段 須磨の秋]
須磨には、いとど心尽くしの秋風に、海はすこし遠けれど、行平中納言の、「関吹き越ゆる」と言ひけむ浦波、夜々はげにいと近く聞こえて、またなくあはれなるものは、かかる所の秋なりけり。 御前にいと人少なにて、うち休みわたれるに、一人目を覚まして、枕をそばだてて四方の嵐を聞きたまふに、波ただここもとに立ちくる心地して、涙落つともおぼえぬに、枕浮くばかりになりにけり。琴をすこしかき鳴らしたまへるが、我ながらいとすごう聞こゆれば、弾きさしたまひて、
「恋ひわびて泣く音にまがふ浦波は 思ふ方より風や吹くらむ」
と歌ひたまへるに、人びとおどろきて、めでたうおぼゆるに、忍ばれで、あいなう起きゐつつ、鼻を忍びやかにかみわたす。
「げに、いかに思ふらむ。我が身ひとつにより、親、兄弟、片時立ち離れがたく、ほどにつけつつ思ふらむ家を別れて、かく惑ひあへる」と思すに、いみじくて、「いとかく思ひ沈むさまを、心細しと思ふらむ」と思せば、昼は何くれとうちのたまひ紛らはし、つれづれなるままに、色々の紙を継ぎつつ、手習ひをしたまひ、めづらしきさまなる唐の綾などに、さまざまの絵どもを描きすさびたまへる屏風の面どもなど、いとめでたく見所あり。
人びとの語り聞こえし海山のありさまを、遥かに思しやりしを、御目に近くては、げに及ばぬ磯のたたずまひ、二なく描き集めたまへり。
「このころの上手にすめる千枝、常則などを召して、作り絵仕うまつらせばや」 と、心もとながりあへり。なつかしうめでたき御さまに、世のもの思ひ忘れて、近う馴れ仕うまつるをうれしきことにて、四、五人ばかりぞ、つとさぶらひける。
[第一段 須磨の秋]
須磨では、ますます心づくしの秋風が吹いて、海は少し遠いけれども、行平中納言が、「関吹き越ゆる」と詠んだ という波音が、夜毎夜毎にそのとおりに耳元に聞こえて、またとないほど淋しく感じられるものは、こういう所の秋 なのであった。
御前にはまったく人少なで、皆寝静まっている中で、独り目を覚まして、枕を立てて四方の嵐を聞いていらっしゃ ると、波がまるでここまで立ち寄せて来る感じがして、涙がこぼれたとも思われないうちに、枕が浮くほどになって しまった。琴を少し掻き鳴らしていらっしゃったが、自分ながらひどく寂しく聞こえるので、お弾きさしになって、
「恋いわびて泣くわが泣き声に交じって波音が聞こえてくるが
それは恋い慕っている都の方から風が吹くからであろうか」
とお詠みになったことに、供の人々が目を覚まして、素晴らしいと感じられたが、堪えきれずに、わけもなく起き出 して座り直し座り直しして、鼻をひそかに一人一人かんでいる。
「なるほど、どのように思っていることだろう。自分一人のために、親、兄弟が片時でも離れにくく、身分相応に 大事に思っているだろう家人に別れて、このようにさまよっているとは」とお思いになると、ひどく気の毒で、 「まことこのように沈んでいる様子を、心細いと思っているだろう」とお思いになると、昼間は何かとおっしゃって お紛らわしになり、なすこともないままに、色々な色彩の紙を継いで手習いをなさり、珍しい唐の綾などに、さまざ まな絵を描いて気を紛らわしなさった屏風の絵など、とても素晴らしく見所がある。
供の人々がお話申し上げた海や山の様子を、遠くからご想像なさっていらっしゃったが、お目に近くなさっては、 なるほど想像も及ばない磯のたたずまいを、またとないほど素晴らしくたくさんお描きになった。
「近年の名人と言われる千枝や常則などを召して、彩色させたいものだ」 と言って、皆残念がっていた。優しく立派なご様子に、世の中の憂さが忘れられて、お側に親しくお仕えできるこ とを嬉しいことと思って、四、五人ほどが、ぴったりと伺候していたのであった。
須磨の秋、絵を描いて寂しさを紛らわす
原文 口語訳
前栽の花、色々咲き乱れ、おもしろき夕暮れに、海見やらるる廊に出でたまひて、たたずみたまふさまの、ゆゆしうきよらなること、所からは、ましてこの世のものと見えたまはず。白き綾のなよよかなる、紫苑色などたてまつりて、こまやかなる御直衣、帯しどけなくうち乱れたまへる御さまにて、 「釈迦牟尼仏の弟子」 と名のりて、ゆるるかに読みたまへる、また世に知らず聞こゆ。
沖より舟どもの歌ひののしりて漕ぎ行くなども聞こゆ。ほのかに、ただ小さき鳥の浮かべると見やらるるも、心細げなるに、雁の連ねて鳴く声、楫の音にまがへるを、うち眺めたまひて、涙こぼるるをかき払ひたまへる御手つき、黒き御数珠に映えたまへる、故郷の女恋しき人びと、心みな慰みにけり。
「初雁は恋しき人の列なれや
旅の空飛ぶ声の悲しき」
とのたまへば、良清、
「かきつらね昔のことぞ思ほゆる
雁はその世の友ならねども」
民部大輔、
「心から常世を捨てて鳴く雁を
雲のよそにも思ひけるかな」
前右近将督、
「常世出でて旅の空なる雁がねも
列に遅れぬほどぞ慰む
友まどはしては、いかにはべらまし」
と言ふ。親の常陸になりて、下りしにも誘はれで、参れるなりけり。下には思ひくだくべかめれど、ほこりかにもてなして、つれなきさまにしありく。
前栽の花、色とりどりに咲き乱れて、風情ある夕暮れに、海が見える廊にお出ましになって、とばかり眺めていらっしゃる様子が、不吉なまでにお美しいこと、場所柄か、ましてこの世の方とはお見えにならない。白い綾で柔らかなのと、紫苑色のなどをお召しになって、濃い縹色のお直衣、帯をゆったりと締めてくつろいだお姿で、 「釈迦牟尼仏の弟子」 と唱えて、ゆっくりと読経なさっているのが、また聞いたことのないほど美しく聞こえる。
沖の方をいくつもの舟が大声で歌いながら漕いで行くのが聞こえてくる。かすかに、まるで小さい鳥が浮かんでいるように遠く見えるのも、頼りなさそうなところに、雁が列をつくって鳴く声、楫の音に似て聞こえるのを、物思いに耽りながら御覧になって、涙がこぼれるのを袖でお払いなさるお手つき、黒い数珠に映えていらっしゃるお美しさは、故郷の女性を恋しがっている人々の、心がすっかり慰めてしまったのであった。
「初雁は恋しい人の仲間なのだろうか
旅の空を飛んで行く声が悲しく聞こえる」
とお詠みになると、良清、
「次々と昔の事が懐かしく思い出されます
雁は昔からの友達であったわけではないのだが」
民部大輔、
「自分から常世を捨てて旅の空に鳴いて行く雁を
ひとごとのように思っていたことよ」
前右近将監、
「常世を出て旅の空にいる雁も
仲間に外れないでいるあいだは心も慰みましょう
道にはぐれては、どんなに心細いでしょう」
と言う。親が常陸介になって、下ったのにも同行しないで、お供して参ったのであった。心中では悔しい思いをしているようであるが、うわべは元気よくして、何でもないように振る舞っている。
飛ぶ雁に思いを述べる主従
原文 口語訳
[第二段 配所の月を眺める]
月のいとはなやかにさし出でたるに、「今宵は十五夜なりけり」と思し出でて、殿上の御遊び恋しく、「所々眺めたまふらむかし」と思ひやりたまふにつけても、月の顔のみまもられたまふ。 「二千里外故人心」 と誦じたまへる、例の涙もとどめられず。入道の宮の、「霧や隔つる」とのたまはせしほど、言はむ方なく恋しく、折々のこと思ひ出でたまふに、よよと、泣かれたまふ。 「夜更けはべりぬ」 と聞こゆれど、なほ入りたまはず。
「見るほどぞしばし慰むめぐりあはむ
月の都は遥かなれども」
その夜、主上のいとなつかしう昔物語などしたまひし御さまの、院に似たてまつりたまへりしも、恋しく思で出できこえたまひて、 「恩賜の御衣は今此に在り」 と誦じつつ入りたまひぬ。御衣はまことに身を放たず、かたはらに置きたまへり。
「憂しとのみひとへにものは思ほえで
左右にも濡るる袖かな」
[第二段 配所の月を眺める]
月がとても明るく出たので、「今夜は十五夜であったのだ」とお思い出しになって、殿上の御遊が恋しく思われ、「あちこち方で物思いにふけっていらっしゃるであろう」とご想像なさるにつけても、月の顔ばかりがじっと見守られてしまう。 「二千里の外故人の心」 と朗誦なさると、いつものように涙がとめどなく込み上げてくる。入道の宮が、「九重には霧が隔てているのか」とお詠みになった折、何とも言いようもがなく恋しく、折々のことをお思い出しになると、よよと、泣かずにはいらっしゃれない。 「夜も更けてしまいました」 と申し上げたが、なおも部屋にお入りにならない。
「見ている間は暫くの間だが心慰められる、また廻り逢える
月の都は、遥か遠くであるが」
その夜、主上がとても親しく昔話などをなさった時の御様子、故院にお似申していらしたのも、恋しく思い出し申し上げなさって、 「恩賜の御衣は今此に在る」 と朗誦なさりながらお入りになった。御衣は本当に肌身離さず、側にお置きになっていた。
「辛いとばかり一途に思うこともできず
恋しさと辛さとの両方に濡れるわが袖よ」
十五夜に宮廷の月見の夜を思いだす
(筑紫の五節との和歌贈答は省略)
原文 口語訳
[第四段 都の人々の生活]
都には、月日過ぐるままに、帝を初めたてまつりて、恋ひきこゆる折ふし多かり。春宮は、まして、常に思し出 でつつ忍びて泣きたまふ。見たてまつる御乳母、まして命婦の君は、いみじうあはれに見たてまつる。
入道の宮は、春宮の御ことをゆゆしうのみ思ししに、大将もかくさすらへたまひぬるを、いみじう思し嘆かる。
御兄弟の親王たち、むつましう聞こえたまひし上達部など、初めつ方はとぶらひきこえたまふなどありき。あは れなる文を作り交はし、それにつけても、世の中にのみめでられたまへば、后の宮聞こしめして、いみじうのたま ひけり。
「朝廷の勘事なる人は、心に任せてこの世のあぢはひをだに知ること難うこそあなれ。おもしろき家居して、世 の中を誹りもどきて、かの鹿を馬と言ひけむ人のひがめるやうに追従する」 など、悪しきことども聞こえければ、わづらはしとて、消息聞こえたまふ人なし。
二条院の姫君は、ほど経るままに、思し慰む折なし。東の対にさぶらひし人びとも、みな渡り参りし初めは、 「などかさしもあらむ」と思ひしかど、見たてまつり馴るるままに、なつかしうをかしき御ありさま、まめやかな る御心ばへも、思ひやり深うあはれなれば、まかで散るもなし。なべてならぬ際の人びとには、ほの見えなどした まふ。「そこらのなかにすぐれたる御心ざしもことわりなりけり」と見たてまつる。
[第四段 都の人々の生活]
都では、月日が過ぎて行くにつれて、帝をおはじめ申して、恋い慕い申し上げる折節が多かった。東宮は、 まして誰よりも、いつでもお思い出しなさっては忍び泣きなさる。拝見する御乳母や、それ以上に王命婦の君は、 ひどく悲しく拝し上げる。
入道の宮は、東宮のお身の上をそら恐ろしくばかりお思いであったが、大将もこのように流浪の身となっておし まいになったのを、ひどく悲しくお嘆きになる。
ご兄弟の親王たち、お親しみ申し上げていらした上達部など、初めのうちはお見舞い申し上げなさることもあっ た。しみじみとした漢詩文を作り交わし、それにつけても、世間から素晴らしいとほめられてばかりいらっしゃる ので、后宮がお聞きあそばして、きついことをおっしゃったのだった。
「朝廷の勅勘を受けた者は、勝手気ままに日々の享楽を味わうことさえ難しいというものを。風流な住まいを 作って、世の中を悪く言ったりして、あの鹿を馬だと言ったという人のように追従しているとは」 などと、良くないことが聞こえてきたので、厄介なことだと思って、手紙を差し上げなさる方もいない。
二条院の姫君は、時が経つにつれて、お心のやすらぐ折がない。東の対にお仕えしていた女房たちも、みな移り 参上した当初は、「まさかそんなに優れた方ではあるまい」と思っていたが、お仕えし馴れていくうちに、お優し く美しいご様子、日常の生活面についてのお心配りも、思慮深く立派なので、お暇を取って出て行く者もいない。 身分のある女房たちには、ちらっとお姿をお見せなどなさる。「たくさんいる夫人方の中でも格別のご寵愛も、 もっともなことだわ」と拝見する。
京に残る人々のその後の生活
(須磨での冬の生活は省略)
原文 口語訳
[第六段 明石入道の娘]
明石の浦は、ただはひ渡るほどなれば、良清の朝臣、かの入道の娘を思ひ出でて、文など遣りけれど、返り事も せず、父入道ぞ、 「聞こゆべきことなむ。あからさまに対面もがな」 と言ひけれど、「うけひかざらむものゆゑ、行きかかりて、むなしく帰らむ後手もをこなるべし」と、屈じいた うて行かず。
世に知らず心高く思へるに、国の内は守のゆかりのみこそはかしこきことにすめれど、ひがめる心はさらにさも 思はで年月を経けるに、この君かくておはすと聞きて、母君に語らふやう、
「桐壷の更衣の御腹の、源氏の光る君こそ、朝廷の御かしこまりにて、須磨の浦にものしたまふなれ。吾子の御 宿世にて、おぼえぬことのあるなり。いかでかかるついでに、この君にをたてまつらむ」 と言ふ。
母、 「あな、かたはや。京の人の語るを聞けば、やむごとなき御妻ども、いと多く持ちたまひて、そのあまり、忍び 忍び帝の御妻さへあやまちたまひて、かくも騒がれたまふなる人は、まさにかくあやしき山賤を、心とどめたまひ てむや」 と言ふ。
腹立ちて、 「え知りたまはじ。思ふ心ことなり。さる心をしたまへ。ついでして、ここにもおはしまさせむ」 と、心をやりて言ふもかたくなしく見ゆ。まばゆきまでしつらひかしづきけり。
母君、 「などか、めでたくとも、ものの初めに、罪に当たりて流されておはしたらむ人をしも思ひかけむ。さても心を とどめたまふべくはこそあらめ、たはぶれにてもあるまじきことなり」 と言ふを、いといたくつぶやく。
「罪に当たることは、唐土にも我が朝廷にも、かく世にすぐれ、何ごとも人にことになりぬる人の、かならずあ ることなり。いかにものしたまふ君ぞ。故母御息所は、おのが叔父にものしたまひし按察使大納言の御娘なり。 いとかうざくなる名をとりて、宮仕へに出だしたまへりしに、国王すぐれて時めかしたまふこと、並びなかりける ほどに、人の嫉み重くて亡せたまひにしかど、この君のとまりたまへる、いとめでたしかし。女は心高くつかふべ きものなり。おのれ、かかる田舎人なりとて、思し捨てじ」 など言ひゐたり。
この娘、すぐれたる容貌ならねど、なつかしうあてはかに、心ばせあるさまなどぞ、げに、やむごとなき人に劣 るまじかりける。身のありさまを、口惜しきものに思ひ知りて、 「高き人は、我を何の数にも思さじ。ほどにつけたる世をばさらに見じ。命長くて、思ふ人びとに後れなば、尼に もなりなむ、海の底にも入りなむ」 などぞ思ひける。
父君、所狭く思ひかしづきて、年に二たび、住吉に詣でさせけり。神の御しるしをぞ、人知れず頼み思ひける。
[第六段 明石入道の娘]
明石の浦は、ほんの這ってでも行けそうな距離なので、良清の朝臣、あの入道の娘を思い出して、手紙などをや ったのだが、返事もせず、父の入道が、 「申し上げたいことがある。ちょっとお会いしたい」 と言ったが、「承知してくれないようなのに、出かけて行って、空しく帰って来るような後ろ姿もばからしい」 と、気がふさいで行かない。
世にまたとないほど気位高く思っているので、播磨の国中では守の一族だけがえらい者と思っているようだが、 偏屈な気性はまったくそのようなことも思わず歳月を送るうちに、この君がこうして来ていらっしゃると聞いて、 母君に言うことには、 「桐壷の更衣がお生みになった、源氏の光る君は、朝廷の勅勘を蒙って、須磨の浦にこもっていらっしゃるとい う。わが娘のご運勢によって、思いがけないことがあるのです。何とかこのような機会に、娘を差し上げたいもの です」 と言う。
母は、 「まあ、とんでもない。京の人の話すのを聞くと、ご立派な奥方様たちをとてもたくさんお持ちになっていらして 、その他にも、こっそりと帝のお妃まで過ちを犯しなさって、このような騷ぎになられた方が、いったいこのよう な賤しい田舎者に心をとめてくださいましょうか」 と言う。
腹を立てて、 「ご存知あるまい。考えが違うのです。その心づもりをしなさい。機会を作って、ここにお出でいただこう」 と、思いのままに言うのも頑固に見える。眩しいくらい立派に飾りたて大事にお世話していた。
母君は、 「どうして、ご立派な方とはいえ、初めての縁談に、罪に当たって流されていらしたような方を考えるのでしょう。 それにしても、心をおとめくださるようならともかくも、冗談にもありそうにないことです」 と言うので、ひどくぶつぶつと不平を言う。
「罪に当たることは、唐土でもわが国でも、このように世の中に傑出して、何事でも人に抜きんでた人には必ず あることなのだ。どういうお方でいらっしゃると思うか。亡くなった母御息所は、わたしの叔父でいらした按察大 納言の御娘である。まことに素晴らしい評判をとって、宮仕えにお出しなさったところ、国王も格別に御寵愛あそ ばすこと、並ぶ者がなかったほどであったが、皆の嫉妬が強くてお亡くなりになってしまったが、この君が生いき ていらっしゃる、大変に喜ばしいことである。女は気位を高く持つべきなのだ。わたしが、このような田舎者だか らといって、お見捨てになることはあるまい」 などと言っていた。
この娘、すぐれた器量ではないが、優しく上品らしく、賢いところなどは、なるほど、高貴な女性に負けないよう であった。わが身の境遇を、ふがいない者とわきまえて、 「身分の高い方は、わたしを物の数のうちにも入れてくださるまい。身分相応の結婚はまっぴら嫌。長生きして、 両親に先立たれてしまったら、尼にもなろう、海の底にも沈みもしよう」 などと思っているのであった。
父君は、仰々しく大切に育てて、一年に二度、住吉の神に参詣させるのであった。神の御霊験を、心ひそかに期 待しているのであった。
明石の入道とその娘のこと
「須磨」の巻 4 「須磨で新年を迎える」
原文 口語訳
[第一段 須磨で新年を迎える]
須磨には、年返りて、日長くつれづれなるに、植ゑし若木の桜ほのかに咲き初めて、空のけしきうららかなるに、 よろづのこと思し出でられて、うち泣きたまふ折多かり。
二月二十日あまり、去にし年、京を別れし時、心苦しかりし人びとの御ありさまなど、いと恋しく、「南殿の桜、 盛りになりぬらむ。一年の花の宴に、院の御けしき、内裏の主上のいときよらになまめいて、わが作れる句を誦じ たまひし」も、思ひ出できこえたまふ。
「いつとなく大宮人の恋しきに
桜かざしし今日も来にけり」
いとつれづれなるに、大殿の三位中将は、今は宰相になりて、人柄のいとよければ、時世のおぼえ重くてものした まへど、世の中あはれにあぢきなく、ものの折ごとに恋しくおぼえたまへば、「ことの聞こえありて罪に当たるとも いかがはせむ」と思しなして、にはかに参うでたまふ。
うち見るより、めづらしううれしきにも、ひとつ涙ぞこぼれける。 住まひたまへるさま、言はむかたなく唐めいたり。所のさま、絵に描きたらむやうなるに、竹編める垣しわたして 、石の階、松の柱、おろそかなるものから、めづらかにをかし。
山賤めきて、ゆるし色の黄がちなるに、青鈍の狩衣、指貫、うちやつれて、ことさらに田舎びもてなしたまへる しも、いみじう、見るに笑まれてきよらなり。
取り使ひたまへる調度も、かりそめにしなして、御座所もあらはに見入れらる。碁、双六盤、調度、弾棊の具な ど、田舎わざにしなして、念誦の具、行なひ勤めたまひけりと見えたり。もの参れるなど、ことさら所につけ、興 ありてしなしたり。
海人ども漁りして、貝つ物持て参れるを、召し出でて御覧ず。浦に年経るさまなど問はせたまふに、さまざま安 げなき身の愁へを申す。そこはかとなくさへづるも、「心の行方は同じこと。何か異なる」と、あはれに見たまふ。 御衣どもなどかづけさせたまふを、生けるかひありと思へり。御馬ども近う立てて、見やりなる倉か何ぞなる稲取 り出でて飼ふなど、めづらしう見たまふ。
[第一段 須磨で新年を迎える]
須磨では、年も改まって、日が長くすることもない頃に、植えた若木の桜がちらほらと咲き出して、空模様もう ららかな感じがして、さまざまなことがお思い出されなさって、ふとお泣きになる時が多くあった。
二月二十日過ぎ、過ぎ去った年、京を離れた時、気の毒に思えた人たちのご様子など、たいそう恋しく、「南殿の 桜は、盛りになっただろう。去る年の花の宴の折に、院の御様子、主上がたいそう美しく優美に、わたしの作った 句を朗誦なさった」のも、お思い出し申される。
「いつと限らず大宮人が恋しく思われるのに
桜をかざして遊んだその日がまたやって来た」
何もすることもないころ、大殿の三位中将は、今では宰相に昇進して、人柄もとてもよいので、世間の信頼も厚 くいらっしゃったが、世の中がしみじみつまらなく、何かあるごとに恋しく思われなさるので、「噂が立って罪に 当たるようなことがあろうともかまうものか」とお考えになって、急にお訪ねになる。
一目見るなり、珍しく嬉しくて、同じく涙がこぼれるのであった。 お住まいになっている様子、いいようもなく唐風である。その場所の有様、絵に描いたような上に、竹を編んで 垣根をめぐらして、石の階段、松の柱、粗末ではあるが、珍しく趣がある。
山人みたいに、許し色の黄色の下着の上に、青鈍色の狩衣、指貫、質素にして、ことさら田舎風にしていらっし ゃるのが、実に、見るからににっこりせずにはいられないお美しさである。
お使いになっていらっしゃる調度も、一時の間に合わせ物にして、ご座所もまる見えにのぞかれる。碁、双六の 盤、お道具、弾棊の具などは、田舎風に作ってあって、念誦の具は、勤行なさっていたように見えた。お食事を差 し上げる折などは、格別に場所に合わせて、興趣あるもてなしをした。
海人たちが漁をして、貝の類を持って参ったのを、召し出して御覧になる。海辺に生活する様子などを尋ねさせ なさると、いろいろと容易でない身の辛さを申し上げる。とりとめもなくしゃべり続けるのも、「心労は同じことだ 。何の身分の上下に関係あろうか」と、しみじみと御覧になる。御衣類をお与えさせになると、生きていた甲斐が あると思った。幾頭ものお馬を近くに繋いで、向こうに見える倉か何かにある稲を取り出して食べさせているのを、 珍しく御覧になる。
須磨での新年、三位の中将の訪れ
原文 口語訳
[第二段 上巳の祓と嵐]
弥生の朔日に出で来たる巳の日、 「今日なむ、かく思すことある人は、御禊したまふべき」 と、なまさかしき人の聞こゆれば、海づらもゆかしうて出でたまふ。いとおろそかに、軟障ばかりを引きめぐら して、この国に通ひける陰陽師召して、祓へせさせたまふ。舟にことことしき人形乗せて流すを見たまふに、よそ へられて、
「知らざりし大海の原に流れ来て
ひとかたにやはものは悲しき」
とて、ゐたまへる御さま、さる晴れに出でて、言ふよしなく見えたまふ。
海の面うらうらと凪ぎわたりて、行方も知らぬに、来し方行く先思し続けられて、
「八百よろづ神もあはれと思ふらむ
犯せる罪のそれとなければ」
とのたまふに、にはかに風吹き出でて、空もかき暮れぬ。 御祓へもし果てず、立ち騒ぎたり。肱笠雨とか降りき て、いとあわたたしければ、みな帰りたまはむとするに、笠も取りあへず。
さる心もなきに、よろづ吹き散らし、 またなき風なり。波いといかめしう立ちて、人びとの足をそらなり。海の面は、衾を張りたらむやうに光り満ちて、 雷鳴りひらめく。落ちかかる心地して、からうしてたどり来て、
「かかる目は見ずもあるかな」
「風などは吹くも、けしきづきてこそあれ。あさましうめづらかなり」
と惑ふに、なほ止まず鳴りみちて、雨の脚当たる所、徹りぬべく、はらめき落つ。「かくて世は尽きぬるにや」 と、心細く思ひ惑ふに、君は、のどやかに経うち誦じておはす。
暮れぬれば、雷すこし鳴り止みて、風ぞ、夜も吹く。
「多く立てつる願の力なるべし」
「今しばし、かくあらば、波に引かれて入りぬべかりけり」
「高潮といふものになむ、とりあへず人そこなはるるとは聞けど、いと、かかることは、まだ知らず」 と言ひあへり。
暁方、みなうち休みたり。君もいささか寝入りたまへれば、そのさまとも見えぬ人来て、
「など、宮より召しあるには参りたまはぬ」
とて、たどりありくと見るに、おどろきて、「さは、海の中の龍王の、いといたうものめでするものにて、見 入れたるなりけり」と思すに、いとものむつかしう、この住まひ堪へがたく思しなりぬ。
[第二段 上巳の祓と嵐] 三月の上旬にめぐって来た巳の日に、 「今日は、このようにご心労のある方は、御禊をなさるのがようございます」 と、知ったかぶりの人が申し上げるので、海辺も見たくてお出かけになる。ひどく簡略に、軟障だけを引きめ ぐらして、この国に行き来していた陰陽師を召して、祓いをおさせなになる。舟に仰々しい人形を乗せて流すの を御覧になるにつけても、わが身になぞらえられて、
「見も知らなかった大海原に流れきて
人形に一方ならず悲しく思われることよ」
と詠んで、じっとしていらっしゃるご様子、このような広く明るい所に出て、何とも言いようのないほど素晴ら しくお見えになる。
海の表面もうららかに凪わたって、際限も分からないので、過去のこと将来のことが次々と胸に浮かんできて、
「八百万の神々もわたしを哀れんでくださるでしょう
これといって犯した罪はないのだから」
とお詠みになると、急に風が吹き出して、空もまっ暗闇になった。お祓いもし終えないで、騒然となった。 肱笠雨とかいうものが降ってきて、ひどくあわただしいので、皆がお帰りになろうとするが、笠も手に取ること ができない。
こうなろうとは思いもしなかったが、いろいろと吹き飛ばし、またとない大風である。波がひどく荒々しく立って きて、人々の足も空に浮いた感じである。海の表面は、衾を広げたように一面にきらきら光って、雷が鳴りひらめ く。落ちてきそうな気がして、やっとのことで、家にたどり着いて、
「このような目には遭ったこともないな」
「風などは、吹くが、前触れがあって吹くものだ。思いもせぬ珍しいことだ」
と困惑しているが、依然として止まず鳴りひらめいて、雨脚の当たる所、地面を突き通してしまいそうに、音を 立てて落ちてくる。「こうして世界は滅びてしまうのだろうか」と、心細く思いうろたえているが、君は、落ち着 いて経を誦していらっしゃる。
日が暮れたので、雷は少し鳴り止んだが、風は、夜も吹く。
「たくさん立てた願の力なのでしょう」
「もうしばらくこのままだったら、波に呑みこまれて海に入ってしまうところだった」
「高潮というものに、何を取る余裕もなく人の命がそこなわれるとは聞いているが、まこと、このようなこと は、まだ見たこともない」 と言い合っていた。
明け方、みな寝んでいた。君もわずかに寝入りなさると、誰ともわからない者が来て、
「どうして、宮からお召しがあるのに参らないのか」
と言って、手探りで捜してしるように見ると、目が覚めて、「さては海龍王が、美しいものがひどく好きなもの で、魅入ったのであったな」とお思いになると、とても気味が悪く、ここの住まいが耐えられなくお思いになった。
弥生の朔日に嵐、海王の使い来る
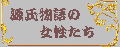 写真の無断転載はご遠慮下さい
写真の無断転載はご遠慮下さい