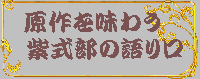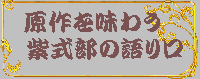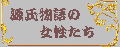| 原文 | 口語訳 |
斎宮の御下り、近うなりゆくままに、御息所、もの心細く思ほす。
やむごとなくわづらはしきものにおぼえたまへりし大殿の君も亡せたまひて後、
さりともと世人も聞こえあつかひ、宮のうちにも心ときめきせしを、
その後しも、かき絶え、あさましき御もてなしを見たまふに、まことに憂しと
思すことこそありけめと、知り果てたまひぬれば、よろづのあはれを思し捨てて、
ひたみちに出で立ちたまふ。
親添ひて下りたまふ例も、ことになけれど、いと見放ちがたき御ありさまなるに
ことつけて、「憂き世を行き離れむ」と思すに、大将の君、さすがに、今はと
かけ離れたまひなむも、口惜しく思されて、御消息ばかりは、あはれなるさまにて、
たびたび通ふ。
対面したまはむことをば、今さらにあるまじきことと、女君も思す。
「人は心づきなしと、思ひ置きたまふこともあらむに、我は、今すこし思ひ乱るることの
まさるべきを、あいなし」と、心強く思すなるべし。
もとの殿には、あからさまに渡りたまふ折々あれど、いたう忍びたまへば、大将殿、
え知りたまはず。たはやすく御心にまかせて、参うでたまふべき御すみかにはたあらねば、
おぼつかなくて月日も隔たりぬるに、院の上、おどろおどろしき御悩みにはあらで、
例ならず、時々悩ませたまへば、いとど御心の暇なけれど、「つらき者に思ひ果てたまひなむも、
いとほしく、人聞き情けなくや」と思し起して、野の宮に参うでたまふ。
九月七日ばかりなれば、「むげに今日明日」と思すに、女方も心あわたたしけれど、
「立ちながら」と、たびたび御消息ありければ、「いでや」とは思しわづらひながら、
「いとあまり埋もれいたきを、物越ばかりの対面は」と、人知れず待ちきこえたまひけり。
|
斎宮の御下向が、近づくにつれて、御息所は何となく心細くいらっしゃる。
重々しくけむたいものだと思っていらした大殿の姫君もお亡くなりになって後、
いくら何でも(今度こそは)と世間の人々もお噂申し、御殿の人々も期待していたのに、それから後、
すっかりお通いがなく、あまりにひどいおとりあつかいを御覧になると、「本当にいやだとお思いになる事が
あったにちがいない」と、すっかりお分かりになってしまったので、一切の未練をお捨てになって、
一途にご出立なさるのである。
母親が付き添ってお下りになる先例も、特にないが、(斎宮がお若くて)とても手放し難いご様子なのにかこつけて、
「つらい生活から出て行こう」とお思いになるが、大将の君は、さすがに、これが最後と遠くへ
行っておしまいになるのも残念にお思いなさって、お手紙だけは情のこもった書きぶりで、
度々交わす。
お会いになることは、「今さらあってはならない事」と、女君も思っていらっしゃる。
「相手は気にくわないと、根に持っていらっしゃることがあろうに、自分は、今以上に悩むことが
きっと増すにちがいないので、無益なこと」と、固くご決心されているのだろう。
もとのご殿には、ほんのちょっとお帰りになる時々もあるが、たいそう内々にしていらっしゃるので、
大将殿は、お知りになることができない。(野の宮は)簡単にお心のままに参ってよいようなお住まいでは勿論ないので、
気にかかりながら月日も経ってしまったところに、院の上がたいそう重い御病気というのではないが、
普段と違って、時々お苦しみあそばすので、ますますお気持ちに余裕がないけれど、
「薄情な者とお思い込んでしまわれるのも、おいたわしいし、人が聞いても冷淡な男だと思われはしまいか」
とご決心されて、野の宮にお伺いなさる。
九月七日ころなので、「(下向の日も)まったく今日明日だ」とお思いになると、女の方でも気忙しいが、
「立ちながらでも」と、何度もお手紙があったので、「どうしたものか」とお迷いになりながらも、
「あまりに控え目過ぎるし、物越しにお目にかかるくらいなら」と、人知れずお待ち申し上げて
いらっしゃるのであった。
|
伊勢下向を控え、源氏野の宮訪問へ
*斎宮の伊勢下向の日が近づいたという。桐壺院退位によって新斎宮に定められてから、丸2年経ったのだ。葵上のしから1年、
「葵」の巻の最後の場面から半年経っている。
伊勢への下向は3年目の9月と定められている。伊勢斎宮は、現天皇の在位中は解任されることはない。何十年と伊勢に住むことになるかもしれないのだ。
その斎宮に従っていくとなれば、御息所は、源氏との別れだけでなく、かの地での死も覚悟することになる。心細さはこのうえない。
*一方で、周囲では、源氏の本妻葵が死んだのだから、次の本妻として、身分上もこの御息所がおなりになるのではないかと
思っている。特に御息所の御殿にお仕えする人々の期待は大きい。
*ところが、その期待に反して、源氏の訪問がすっかり絶えてしまったのだ。今までは、葵の見舞いのためという建て前の理由が
あった。今はその理由は成り立たない。としたら、源氏はすっかり自分のことを嫌になるようなことがあったのだ。自分が出した弔問の手紙に対する返事の、
あの言葉はやはり自分の怨念の深さを見知ってしまったという意味だったのだ。御息所だけには源氏の本心が見て取れるのだから、
周囲がどう期待しようと、自分は伊勢に行くほかはない。
*源氏の側は、御息所のいる野の宮は神域なのだから訪問しにくい上に、父院がこのところ具合が悪い日がつづく。院ももう40歳の半ばになる。
藤壺との間の若宮を東宮位につけるという念願が叶って、ほっとしたのだろうか。そんな心配で気持ちが落ち着かない頃になって、
源氏は御息所を訪問しようと決心する。理由は、相手が自分を冷たい男と思いこんだままになるのはかわいそうだ、ということがひとつ。
もう一つ、世間の人が自分の仕打ちをどう見るかということだ。
いずれも、自分の心からの思いではない。相手や世間から良く思われていたいという世間体だ。ここにももう源氏の御息所を見限っていることがわかる。
*源氏から、9月7日に訪問したいと事前に連絡があった。出発の準備で忙しいと断っても、「時間は取らせない、立ちながらでも
ちょっと。」とかさねて要請があった。
「今になってまた合うのはどうか」と思い、また、相手が訪問したいというのを断るのは、社交人としては引っ込み思案すぎるし、
とあれこれ考えてから、「物越しだけの対面なら」と自分に言い訳できる妥協した形を思いついて、訪問を受け入れることにした。
*ところが、「あの方が来る」と思えた途端に、心はもう”待つ”こころになってしまっている。
|
| 原文 | 口語訳 |
遥けき野辺を分け入りたまふより、いとものあはれなり。秋の花、みな衰へつつ、
浅茅が原も枯れ枯れなる虫の音に、松風、すごく吹きあはせて、そのこととも聞き分かれぬほどに、
物の音ども絶え絶え聞こえたる、いと艶なり。
むつましき御前、十余人ばかり、御随身、ことことしき姿ならで、いたう忍びたまへれど、
ことにひきつくろひたまへる御用意、いとめでたく見えたまへば、御供なる好き者ども、
所からさへ身にしみて思へり。御心にも、「などて、今まで立ちならさざりつらむ」と、過ぎぬる方、
悔しう思さる。
ものはかなげなる小柴垣を大垣にて、板屋どもあたりあたりいとかりそめなり。
黒木の鳥居ども、さすがに神々しう見わたされて、わづらはしきけしきなるに、神司の者ども、
ここかしこにうちしはぶきて、おのがどち、物うち言ひたるけはひなども、他にはさま変はりて見ゆ。
火焼屋かすかに光りて、人気すくなく、しめじめとして、ここにもの思はしき人の、月日を隔てたまへ
らむほどを思しやるに、いといみじうあはれに心苦し。
|
広々とした野辺に分け入りなさるなり、いかにもものあわれな感じがする。秋の花、みな萎れかかって、
浅茅が原も枯れがれとなり虫の音も鳴き嗄らしているところに、松風が身にしみて音を添えて、
何の楽器とも聞き分けられないくらいに、楽の音が絶え絶えに聞こえて来るのは、まことに優艶である。
気心の知れた御前駆の者、十余人ほど、御随身も目立たない服装で、たいそうお忍びのふうをして
いられるが、格別にお気を配っていらっしゃる源氏の君のご様子は、まことに素晴らしくお見えになるので、
お供の風流者など、場所が場所だけに身にしみて感じ入っていた。君のご内心でも、「どうして、今までしげしげと
来なかったのだろう」と、過ぎ去ったこれまでを、後悔なさる。
ちょっとした小柴垣を外囲いにして、板屋が幾棟もあちこちに仮普請のようである。黒木の鳥居どもは、
やはり神々しく眺められて、気後れのする辺りの様子であるが、神官どもが、あちこちで咳払いをして、
お互いに何か話している様子なども、他所とは様子が変わって見える。火焼屋が、微かに明るくて、人影も少なく、
しんみりとしていて、ここで物思いに沈んでいる人が、幾月日も世間から離れて過ごしてこられた間のことを
ご想像なさると、とてもたまらなくおいたわしい。
|
秋の風情が身にしみる
*9月7日(新暦の10月上中旬)源氏が野の宮訪問のために嵯峨野に足を踏み入れる。
名所としての「秋の嵯峨野」を定着させたのが、この場面。
現代でも嵯峨野にいくには京都駅からバスで2,30分はかかる。源氏の邸宅二条近辺からは、馬でいっても一時間はかかるだろう。
*嵯峨野は洛外だ。洛中には、京の南の果て羅生門の両隣に東寺と西寺が都の守護寺として建てられたが、
それ以外はみな、寺社は京洛の外に建てられた。嵯峨野は嵯峨天皇の皇子源融(源氏のモデルと言われる)の別荘を寺とした清涼寺(嵯峨釈迦堂)
がある。この寺は平安時代の末期、多くの出家者を庇護する役目を果たしたため、平家物語に出て来る、祇王祇女の隠れた祇王寺や滝口寺、常寂光寺などの
世を逃れた人々が住む庵が点在し、独特の風土を生み出す。清涼寺は「松風」の巻で嵯峨野に住む明石の君に会う為の名目で
源氏が嵯峨に寺を建てる、その寺のモデルだ。
*嵯峨野はいまでこそ、渡月橋から天竜寺のあたりにかけて、タレントのショップが建ち並んで、ありふれた観光地の風になってしまったが、
2,30年前までは(一昔も前だが)、天竜寺の横を一歩入ると、竹林が鬱そうとして、細い小道を辿っていくと、
これも小さな黒木の鳥居だけを前にして、野の宮がひっそりと佇んでいた。そこから右手に道なりに進み、これも薄暗い小倉池を経て、二尊院・常寂光寺へと辿る道は
本当に心休まる道だった。今は、どこを行こうにも木立は切り開かれ、けばけばしい土産店が立ち並んでいる。小倉池など釣り堀になってしまった。
嵯峨野の面影を遺すのは、竹やぶの奥の山上にある大河内山荘の付近だけか。
*閑話休題、今源氏が足を踏み入れた嵯峨野はまだ釈迦堂などもない頃。広々とした一面の原だ。
秋の七草(萩・尾花=すすき・葛花・なでしこ・おみなえし・藤袴・あさがお=桔梗)は、日本の中部には自然に咲く花々だ。
それらの花も盛りを過ぎて枯れ枯れで、下地にはえる浅茅も一面に黄色と赤みのまざった草紅葉となっている。
*目に映るものに加えて、虫の音もまた涸れ涸れの声を聞かせ、松林を吹く松籟の音がいっそうものすごさを感じさせる。
その中に、遠く弦楽器の音が風にとぎれとぎれとなって聞こえてくる。この荒涼とした中で琴を弾くのは野の宮にひそむ
あの御息所の人々以外にはない。
*寂しげなその音のもとにいる女君。そこをおとずれる貴公子源氏。
今日は一段と身だしなみをととのえている。供人は、嵯峨野を背景にした源氏を一幅の絵のように見て、その美しさを堪能している。
源氏自身、この風情をもっと早くから堪能すれば良かったとすこし後悔している。
*やがて野の宮のたたずまいが見えてきた。
野の宮は伊勢斎宮や賀茂斎院があらたに定められた時に、二度目の潔斎場所として作られ、
それがすんだら、取り壊されるものだったらしい。簡素を旨として、鳥居も「黒木」つまり、皮を剥がないままの檜の丸太で作られる。
建物も、木の皮を葺いた屋根。垣根も築地塀ではなく、柴(木の枝)を編んだ小柴垣というものだ。斎宮のはここ嵯峨野に。斎院のは紫野に建てられた。
*その野の宮の薄暗い簡素さがかえって神々しい雰囲気を醸しだし、また源氏の目に見なれぬ格好の神官が、この場違いな
不意の訪問者をすこし見とがめるかのように、せきばらいをし、またひそひそとしゃべり合っている。
*すべてがしめっぽいこのたたずまいの中に、あの気位の高い御息所が1年ものあいだ、息を潜めるようにして時を過ごしていたのだと思うと、
さすがに源氏の心が痛んだ。互いにこれが最後の訪問とわかっている、このわずかな時間で、
長い間苦しんだ女君の心を癒すことなど出来るのだろうか。
|
| 原文 | 口語訳 |
北の対のさるべき所に立ち隠れたまひて、御消息聞こえたまふに、遊びはみなやめて、心にくきけはひ、
あまた聞こゆ。
何くれの人づての御消息ばかりにて、みづからは対面したまふべきさまにもあらねば、
「いとものし」と思して、「かうやうの歩きも、今はつきなきほどになりにてはべるを、思ほし知らば、
かう注連のほかにはもてなしたまはで。いぶせうはべることをも、あきらめはべりにしがな」と、
まめやかに聞こえたまへば、
人びと、「げに、いとかたはらいたう」「立ちわづらはせたまふに、いとほしう」
など、あつかひきこゆれば、「いさや。ここの人目も見苦しう、かの思さむことも、若々しう、出でゐむが、
今さらにつつましきこと」と思すに、いともの憂けれど、情けなうもてなさむにもたけからねば、
とかくうち嘆き、やすらひて、ゐざり出でたまへる御けはひ、いと心にくし。
「こなたは、簀子ばかりの許されははべりや」とて、上りゐたまへり。
|
北の対の適当な場所に立ち隠れなさって、ご来訪の旨をお申し入れなさると、管弦のお遊びはみな止めて、
奥ゆかしい気配が、いろいろ聞こえる。
何やかやと女房を通じてのご挨拶ばかりで、ご自身はお会いなさる様子もないので、「まことに面白くない」と
お思いになって、「このような外出も、今では相応しくない身分になってしまったことを、お察しいただければ、
このような注連の外には、立たせて置くようなことはなさらないで。胸に溜まっていますことをも、晴らしたい
ものです」と、真面目に申し上げなさると、
女房たちが、「本当に。とても見てはいられませんわ」
「立ったままでお困りでいらっしゃっては、お気の毒で」などと、お取りなし申すので、「さてねえ、どうしたものか。
ここの女房たちの目にも体裁が悪いだろうし、あの方も年甲斐もなくとお思いになるだろうし、また端近に出て
行くのが、今さらに気後れして」とお思いになると、とても気が重いが、冷淡な態度をとるほど気強くも
ないので、あれこれ溜息をつき、ためらって、いざり出ていらっしゃったご様子、まことに奥ゆかしい。
「こちらでは、簀子に上がるくらいのお許しはございましょうか」と言って、君は上がっておすわりになった。
|
ためらいながらいざり出る御息所
*御息所のお住まいは北の建物のようだ。正殿には斎宮がおいでになるのであろう。
源氏は建物の外、ひと目に着かない場所に立って来訪を伝える。部屋の中では急いで楽器を片づけたり、
几帳の位置を直したりする物音や女房の衣擦れの音が聞こえる。しかし、それらは、静かなたしなみの感じられる気配である。
こんなところにも御息所の優雅さが示されている。ずっと後のことであるが、六条院での蹴鞠を見物する女三宮の部屋の騒がしさが
描写されるが、女房達のたしなみの有無は、女主人の教養の有無そのものなのだ。
*御息所は来訪した源氏に対面しようとしない。女房を介してのやりとりしかしないのだ。このよそよそしい扱いに源氏は不満を感じる。
「今は身分が高くなって忍び歩きもふさわしくない程なのに、こうしてはるばる嵯峨野(くんだり)までやって来た私を
こうして、”注連(しめ)の外に置く”=部外者あつかいするのは不当だ。あなたの胸の中につもっている思いがあろう、
それを晴らして差し上げたい。(それには、じかに私の顔をご覧になる以外にはないはず)」とまじめに言う。
*源氏の顔を見たい思いは切実ながら、そうしてしまったら自分の未練がまた募る、だからじっとこらえている御息所。
それを知っていながら、御息所の恨みの心をほぐすには、自分の顔見せるのが一番だと計算している。「立ちながら」と自分から言ったはずが、
部屋に上げろというのだ。
*なにがあっても源氏の味方である女房たちが口をそろえて、お気の毒だという。
いつまでもこうして我を張っているのは、女房の手前もみっともないし、相手も年甲斐のないすねようと思うだろうし、
でも端近に出て行くのも気恥ずかしいし・・」とあれこれ迷ったあげく、心底は会いたいのだから、冷たい態度をとり続けられなくて、
ため息をつきながら、いざり出る。
「ゐざり出でたまへり」とあるが、身分の高い女性が部屋の中を移動するのには、立って足で歩くのでなく、
中腰で膝をついて、膝で移動するのだ。「膝行(しっこう)という。だからよく「髪が身の丈に余る」というが、実際は膝くらいの長さなのではないかと私は推測している。
*御息所が移動してきたのは、廂の間。「こちらでは簀の子ぐらいはお許し下さいますか」と、源氏はそのまえの
簀の子(濡れ縁)に上がり込む。御息所との隔ては御簾(壁代もあるが)一枚になった。声が直に聞こえる位置に互いが居る。
|
| 原文 | 口語訳 |
はなやかにさし出でたる夕月夜に、うち振る舞ひたまへるさま、匂ひに、似るものなくめでたし。
月ごろのつもりを、つきづきしう聞こえたまはむも、まばゆきほどになりにければ、榊をいささか折りて
持たまへりけるを、挿し入れて、
「変らぬ色をしるべにてこそ、斎垣も越えはべりにけれ。さも心憂く」
と聞こえたまへば、
「神垣はしるしの杉もなきものを
いかにまがへて折れる榊ぞ」
と聞こえたまへば、
「少女子があたりと思へば榊葉の
香をなつかしみとめてこそ折れ」
おほかたのけはひわづらはしけれど、御簾ばかりはひき着て、長押におしかかりてゐたまへり。
|
明るく照り出した夕月の光に、立ち居振る舞いなさるご様子、美しさに、似るものがなく素晴らしい。
幾月ものご無沙汰を、もっともらしく言い訳申し上げなさるのも、面映ゆいほどになってしまったので、
榊を少し折って持っていらしたのを、御簾の中に差し入れて、
「(この色のように)変わらない私の心に導かれて、禁制の神の垣根も越えて参ったのです。それなのに
何とも薄情な」と申し上げなさると、
「ここには人のお出でを待つ目印の杉もないのに
どう間違えて折って持って来た榊なのでしょう」
と申し上げなさると、
「少女子がいる辺りだと思うと
榊葉の香が慕わしくて探し求めて折ったのです」
周囲の雰囲気は憚られるが、君は御簾だけを引き被って、長押に持たれかかって座っていらっしゃる。
|
月光の下の歌の贈答
*9月7日の月は、半月。夕方、辺りが暗くなると、南の空高く左半分の月が輝きをます。
その月の光を身に受けて、簀の子に座る源氏の姿は、御簾のうちにいる女君の目に、光りの後背をもっているかのように
輝いて見える。おもわずため息をつく女君であろう。
*何ヶ月にもわたる無沙汰の理由をいまさらこしらえるのも、いくら源氏でもさすがに照れくさく、折りとって手にしていた榊を
御簾の中に差し入れて、言う。「常緑の榊の変わらぬ色と同じく、変わらぬ愛を持つ自分の心を確かな道案内として、
畏れおおい神の垣根もこえてこうしてやってきました。それなのに貴女の仕打ちは冷たい。」と、例のように相手の薄情をなじるやり方だ。
*御息所は「相手のお出でを待つ印という、目印の杉の木のないのに、何を間違って杉でなく榊を折って(勘違いして)
お出でになったのでしょう。(もう貴女をお待ちしてなどいませんのに。)」
*「うるわしい乙女のいる辺りだと思うと、素っ気ない榊の葉の香りまで慕わしくて、探し求めて(やっと尋ねあてて)
折ってきたのですよ。」とひたすら、慕う気持ちを全面に出して詠みかける源氏。
*この両者の贈答はひたすら古歌をふまえた詠みぶりになる。古歌をふまえ、引用をし、ひたすら教養のかぎりを歌に出す。
優雅な歌は、単なる意味を伝える三十一文字だけでなく、古歌に歌われた情景・情緒をも取り込むことで、二重三重の複雑な思いを表現する。
ここでは、源氏の言葉(「変らぬ色をしるべにて」「斎垣も越えはべりにけれ」)は、二つの歌の合体だ。
「ちはやぶる神がき山のさか木葉は時雨に色も変らざりけり」(後撰集・巻八冬)
「ちはやぶる神の斎垣も越えぬべし今は我が身の惜しけくもなし」(拾遺集・巻十四、恋)
御息所の歌は、「わが庵は三輪の山本恋しくはとぶらひきませ杉立てる門」(古今集・巻十八、雑)をふまえている。
源氏の返歌は、「さか木葉の香をかぐはしみ尋めくれば八十氏人ぞまどゐせりける」(拾遺集・巻十、神楽歌)をふまえている。
これらの歌を知っている物語の聞き手は、「ああ、あの歌のセリフだわ。そう季節もまもなく冬だからね。ここは神域の神々しさが生きているわ。」
などと味わいながら、二人のやりとりをじっくりと味わうのである。味わう時間が長いから、描写の文は短くても、
楽しみの時間は十分とれる。鑑賞の時間を物語の時間にかさねる効果で、語り手は、時間の推移をわざわざ説明しないでも済む。
*さて、精進潔斎の場であるあたり一帯の気配は、こうした男女のやりとりにはふさわしくなく、気が引けるが、
ここはそれ、当初の目的のためには、今一歩積極的に行動しないと、と、源氏は榊を御簾の中に差し入れたついでに
自分の上半身も、御簾の中に入れ、御簾を半分引きかぶった形で、廂の間の下長押に体を寄りかからせる。
下長押は高さ20cmくらい。廂の間にいる御息所をちょっと見上げる形だ。これがこの場面の最初の姿勢。
ときが流れていくならば、この不自然な姿勢がそう長い間続くはずがない。源氏の全身が御簾の中に入るのも
まもなくだろう。
|
| 原文 | 口語訳 |
心にまかせて見たてまつりつべく、人も慕ひざまに思したりつる年月は、のどかなりつる御心おごりに、
さしも思されざりき。
また、心のうちに、「いかにぞや」、疵ありて、思ひきこえたまひにし後、はた、あはれもさめつつ、
かく御仲も隔たりぬるを、めづらしき御対面の昔おぼえたるに、「あはれ」と、思し乱るること限りなし。
来し方、行く先、思し続けられて、心弱く泣きたまひぬ。
女は、さしも見えじと思しつつむめれど、え忍びたまはぬ御けしきを、いよいよ心苦しう、
なほ思しとまるべきさまにぞ、聞こえたまふめる。
月も入りぬるにや、あはれなる空を眺めつつ、怨みきこえたまふに、ここら思ひ集めたまへるつらさも
消えぬべし。やうやう、「今は」と、思ひ離れたまへるに、「さればよ」と、なかなか心動きて、思し乱る。
殿上の若君達などうち連れて、とかく立ちわづらふなる庭のたたずまひも、げに艶なるかたに、
うけばりたるありさまなり。思ほし残すことなき御仲らひに、聞こえ交はしたまふことども、
まねびやらむかたなし。
|
思いのままにお目にかかることができ、相手も自分を慕っているようにお思いになっていらっしゃった
年月の間は、のんびりといい気になって、それほどまでご執心なさらなかった。
また一方、心の中に、「いかがなものか、欠点があって」と、お思い申してから後、やはり、
情愛も次第に褪めて、このように仲も離れてしまったのを、久しぶりのご対面が昔のことを思い出させるので、
「ああ」と、悩ましさで胸が限りなくいっぱいになる。今までのこと、将来のこと、それからそれへとお思い
続けられて、心弱く泣いてしまった。
女は、そうとは見せまいと気持ちを抑えていられるようだが、とても我慢がおできになれないご様子を、
ますますお気の毒に、やはりお思い止まるように、お制止申し上げになるようである。
月も入ったのであろうか、しみじみとした空を物思いに耽って見つめながら、恨み言を申し上げなさると、
積もり積もっていらした恨みもきっと消えてしまうことだろう。だんだんと、「今度が最後」と、
未練を断ち切って来られたのに、「やはり思ったとおりだ」と、かえって心が揺れて、お悩みになる。
殿上の若公達などが連れ立って、何かと佇んでは心惹かれたという庭の風情も、なるほど優艶という点では、
どこの庭にも負けない様子である。物のあわれの限りを尽くしたお二人の間柄で、お語らいになった内容、
そのまま筆に写すことはできない。
|
来し方、行く先を思い合う心
*女とのながい年月を思い返す男の心中である。
源氏と御息所との関係がいつ始まったかははっきりしないが、最初に六条の女君として登場するのは、
「夕顔」の巻。夕顔を知るきっかけが、六条辺りのお忍びの途中で、五条に住む乳母の病気見舞いに立ち寄ったことだったから、
それ以前からの関係ということになる。夕顔との愛におぼれる場面では、もうすでに六条の女君の執着を疎む心が出て来ているから、
始まりは少なくとのその1年くらい前であろう。源氏16,7歳。御息所は夫の東宮が亡くなってもう十年以上経っているはずだから
年齢は30歳前後。源氏との年齢差は13,4歳はあろうかという計算になる。
*二人の始まりはどのようであったかは語られていないが、始めはとにかく源氏の熱心な求愛からだ。それを受け入れてしまってから後は、
若い貴公子の美しさに魅了され、はげしく惹かれてしまった御息所であった。
手の届かない高貴な人、そういう意味では御息所は藤壺と同じ立場にいたのだ。一方は源氏が一度思いを遂げた後も
けっして靡こうとせず、退け続けるのに対して、こちらは独り身であるがゆえに、タブーは自身の気位以外になく、
一度受け入れてしまってからは若い貴公子を激しく愛し求めた。「逃げれば追う、追えば逃げる」のゲームの心理で、若い男は、年上の女の愛情をいたぶる。
残酷な「心おごり」であった。
*自分の仕打ちが相手を苦しめ、生き霊とさせてしまったのに、まざまざとそれを知ってしまってからは、
もうすっかり厭わしさがつのり、顔も見たくなかった。それなのに、今、こうして秋の嵯峨野を背景に訪れてみると、
これはまた、またとない、男女の愛の舞台であった。つらい思いを胸に潜めた女の風情のうつくしさよ。
この人以上に洗練された女性は二人といないのだ。この人が、寂しい嵯峨野からさらに遠い伊勢に旅立って二度と帰ってこないのだ。
悲痛な思いで胸締めつけられ、よよと泣く。涙と声を出して泣くのは男の方だ。
*女は、じっと堪えようとするが堪えきれずに忍び音がもれる。男はいっそう泣きながら、女に「行かないで」とすがる。
今はこの瞬間の男の涙には嘘はない。その声を聞きながら、女は初めて自分に迫ってきた時の若者を思い出す。
あの時のこの若者の純情にほだされて私は受け入れたのだ。あの時と同じ今この瞬間がいとおしい。そう思いながら女の心はやわらかく溶けていく。
*7日の月は夜半には沈む。人の心のようにかき暗れた空を見上げながら、思いのたけをつづける男の言葉を聞く女。
その心には、押さえていた思いがまた浮上してくる。「ああ、やはり、こうなる私の心」と心はまた大きく揺れる。
*語り手は、この場面に来て、突然また庭の描写をする。なぜか。
「庭の風情はまことに艶なることを自慢にしているかのようですよ。ですから庭だけでなく、
部屋の中の艶なることはいうまでもないでしょう。」と言いたいのだ。
お二人がこのあと、どのように語らい、時をおすごしになったか、いろいろあったはずだが、
お二人の語らいのあれこれはもうこれ以上、ここに再現することもできないほどの、
味わいのあるものだったでしょう。野暮な観察者はもうお側にはいませんでしたから。
|
| 原文 | 口語訳 |
やうやう明けゆく空のけしき、ことさらに作り出でたらむやうなり。
「暁の別れはいつも露けきを
こは世に知らぬ秋の空かな」
出でがてに、御手をとらへてやすらひたまへる、いみじうなつかし。
風、いと冷やかに吹きて、松虫の鳴きからしたる声も、折知り顔なるを、さして思ふことなきだに、
聞き過ぐしがたげなるに、まして、わりなき御心惑ひどもに、なかなか、こともゆかぬにや。
「おほかたの秋の別れも悲しきに
鳴く音な添へそ野辺の松虫」
悔しきこと多かれど、かひなければ、明け行く空もはしたなうて、出でたまふ。道のほどいと露けし。
女も、え心強からず、名残あはれにて眺めたまふ。ほの見たてまつりたまへる月影の御容貌、
なほとまれる匂ひなど、若き人びとは身にしめて、あやまちもしつべく、めできこゆ。
「いかばかりの道にてか、かかる御ありさまを見捨てては、別れきこえむ」
と、あいなく涙ぐみあへり。
|
だんだんと明けて行く空の風情、特別に作り出したかのようである。
「明け方の別れにはいつも涙に濡れたが
今朝の別れは今までにない涙に曇る秋の空ですね」
帰りにくそうに、お手を捉えてためらっていられる、たいそう優しい。
風、とても冷たく吹いて、松虫が鳴き嗄らした声も、気持ちを知っているかのようなのを、
それほど物思いのない者でさえ、聞き過ごしがたいのに、まして、どうしようもないほど思い乱れて
いらっしゃるお二人には、かえって、歌も思うように行かないのだろうか。
「ただでさえ秋の別れというものは悲しいものなのに
さらに鳴いて悲しませてくれるな野辺の松虫よ」
悔やまれることが多いが、しかたのないことなので、明けて行く空も体裁が悪くて、お帰りになる。
道程はまことに露っぽい。
女も、気強くいられず、その後の物思いに沈んでいらっしゃる。ほのかに拝見なさった月の光に照らされたお姿、
まだ残っている匂いなど、若い女房たちは身に染みて、心得違いをしかねないほど、お褒め申し上げる。
「どれほどの余儀ない旅立ちだからといっても、あのようなお方をお見限って、お別れ申し上げられようか」
と、わけもなく涙ぐみ合っていた。
|
暁の秋の別れ
*時間は経過し、しだいに東の空が明らんでいく。その空は格別に別れの時を演出するかのような趣である。
*男は詠む。「暁の別れはいつも涙で濡れるものですが、これはまた今まで経験したことのない露けき秋の空ですね。」
昨夜の美しい半月の空とはちがって、今朝の空はどんよりとしめっぽく曇っているようだ。
男は帰りがたい思いをこめて、いつまでも女の手を取ったまま、腰を上げない。女にはうれしい男の態度だ。
*あたりは、風が冷たく吹き、夜中鳴いていた虫ももうなきつくしたかのように、声をからして、女の気持ちを代弁している。
朝の別れの歌は心をこめて詠むものだが、今朝は歌どころではない二人は、いつものような技巧を凝らした名歌は詠めそうにない。
じつにその場に即した限りの素直な歌だ。
*女の歌。「秋の別れ+涸れがれの虫の音=悲しい」と、常套的な歌いぶりで、ただひたすら悲しいというのみである。
*男は、いままでのしこりの日々を思い起こすと、後悔することばかりだが、もう時は元に戻せない。二人は別れるほかないのだ。
別れると決まっているからこそ、この一夜は美しく”演出”しようと、互いが心を合わせて振る舞えたのだ。
明るみを増す空に促されて、男はいよいよ出て行く。帰り道、嵯峨野の草には朝露がびっしょり降りて、男の目からも涙がこぼれ落ちる。
*一方、あとに残された女も、男とすごしたひとときの思いをかみしめて、ずっと外を眺めやる。男が本当に尋ねてきた、その知らせをうけた、
あの数時間前が夢のように思いかえされる。御簾越しに目にした月影に浮かび出た男の姿。胸が締めつけられた。
いまも自分の体のまわりに残っている男のかぐわしい匂い。女はしみじみと名残に身を沈めている。
*その女君の気持ちを語り手は女房の気持ちであるかのようにすりかえていく。
若い女房たちは口々に源氏のすばらしさを讃えて言う。
「どうして、ご主人様はあんなすばらしい源氏の君を見捨てて、伊勢の片田舎に引きこもろうなんてお考えなのかしら。
都に居れば私たちだってまた源氏様のお姿を拝見できるというのに。」
*「源氏を見ていたい、でもそれはできないのだ。」女君の孤独は、今去っていった源氏にしか分からない。
|
| 原文 | 口語訳 |
御文、常よりもこまやかなるは、思しなびくばかりなれど、またうち返し、定めかねたまふべきことならねば、
いとかひなし。
男は、さしも思さぬことをだに、情けのためにはよく言ひ続けたまふべかめれば、まして、
おしなべての列には思ひきこえたまはざりし御仲の、かくて背きたまひなむとするを、口惜しうもいとほしうも、
思し悩むべし。
旅の御装束よりはじめ、人びとのまで、何くれの御調度など、いかめしうめづらしきさまにて、
とぶらひきこえたまへど、何とも思されず。あはあはしう心憂き名をのみ流して、あさましき身のありさまを、
今はじめたらむやうに、ほど近くなるままに、起き臥し嘆きたまふ。
斎宮は、若き御心地に、不定なりつる御出で立ちの、かく定まりゆくを、うれし、とのみ思したり。
世人は、例なきことと、もどきもあはれがりも、さまざまに聞こゆべし。何ごとも、人にもどきあつかはれぬ
際はやすげなり。なかなか世に抜け出でぬる人の御あたりは、所狭きこと多くなむ。
|
後朝の御文、いつもより情愛濃やかなのは、お気持ちも傾きそうなほどであるが、また改めて、
お思い直しなさるべき事でもないので、まことにどうにもならない。
男は、それほどお思いでもないことでも、恋路のためには上手に言い続けなさるようなので、まして、
並々の相手とはお思い申し上げていられなかったお間柄で、このようにしてお別れなさろうとするのを、
残念にもおいたわしくも、お思い悩んでいられるのであろう。
旅のご装束をはじめとして、女房たちの物まで、何かとご調度類など、立派で目新しいさまに仕立てて、
お餞別を申し上げになさるが、何ともお思いにならない。軽々しく嫌な評判ばかりを流してしまって、
あきれはてた身の有様を、今さらのように、下向が近づくにつれて、起きても寝てもお嘆きになる。
斎宮は、幼な心に、決定しなかったご出立が、このように決まってゆくのを、嬉しい、とばかりお思いでいた。
世間の人々は、先例のないことだと、非難も同情も、いろいろとお噂申しているようだ。何事でも、
人から非難されないような身分の者は気楽なものである。かえって世に抜きん出た方のご身辺は窮屈なことが
多いことである
|
出立へと時はすすむ
*男から後朝(きぬぎぬ)の文が届く。男の訪問は、あの葵上が生きていた時、久しぶりに訪問した源氏を御息所が
心をひらかずに迎えた時以来。あの時は、後朝の文はなく、夕暮れにそっけない手紙が来ただけであった。あの時は、
訪問があったけれど、かえって男の本心が見えた感じで、一層女の気持ちは悶々としたのであった。
*今、男は情愛の籠もった手紙をよこした。別れた後の気持ちのなごりのまま、女は伊勢への決意も鈍りそうになるが、もう今更取りやめできるものではない。
*男は、さすがに女をいたわしく思う気持ちは強くなっているので、せめて御息所の旅支度を豪勢ににしてやろうとする。
これから何年過ごすか分からない季節ごとの女房たちの衣装や部屋の調度品まで贈る。
女房たちは感激するが、女君はこうなるまでの我が身の不運を思い出して嘆いている。
*ここで語り手は、今まで登場させなかった斎宮について語りだす。斎宮は、やっと出発の日が決まってホッとしていると言うのだ。
*この斎宮は、本当は20歳近いはずだが、語り手(と作者紫式部)は、御息所の歳をこの直後30歳と明言するので、
斎宮の歳は14歳ということになる。20歳では「斎宮が幼くて親が後見について行く」という理由もつけられなくなる。
物語の語り手は、知らん顔して「あら、前に御息所のお歳をわたし言いましたっけ?」としらを切るのだ。
*その14歳の斎宮は、任命されてからもう2年、斎院の方は、初度の御禊も二度の御禊も、父院と母弘徽殿の威光を受けて、
定め以上に、盛大に行ったというのに、父のいない自分は唯一の庇護者の母が具合が悪く、いつまでも何も執り行ってくれない。
どさくさに紛れてという形で、初度と二度との御禊をまとめて形だけ行ったのが、去年の秋。
*それ以後、一応定め通りに自分はこの野の宮で潔斎の日々に入ったが、母は、あいかわらず具合が悪く伏せったままの日々。
あの男とのことで悩んでいるのは私にだって分かっているけれど、母は一言も私には言おうとしない。
母のためにも、はやく伊勢に行って男のことを忘れさせてやらなければ。
母さん、私がずっと見守っていてあげるから、二人で静かに過ごそうね。
*この人が、斎宮の任を解かれて帰京するのが五年後。人々の前に姿をあらわしたこの斎宮の性格や落ち着いた人柄から
判断して、14歳といえど、物事を見知っていたはずの斎宮である。
*世間の人々はあいかわらずさまざまに噂する。語り手は言う。「私たちみたいにだれも注目しない身分は気軽でいいわ。
身分の高い人はみんなが注目するから、いろいろ噂の種になるのよね。かわいそうに。」女房の視点はご主人に厳しいのだ。
去りゆく六条御息所・死んでいく父院ーー心から愛してくれた人はいなくなる
*十六日に桂川でお祓いし、その日午後宮中に出立の挨拶に行く。御息所も御輿に乗って参内する。
かつて、十六歳で東宮妃として入内し、二十歳で死に後れ、今三十歳で再び宮中を見ることよと感慨深い御息所よ、と語り手は書く。
先に言ったように、この三十歳という歳は明らかに物語の筋立てから言うと計算が合わないのだが、
20・30と語呂あわせがいいからではないかと、玉上琢弥氏は言う。
かつての参内は、大臣の姫、東宮の一の妃として最高の栄誉の中での入内だった。
今、さまざまなスキャンダルにまみれ、娘に添うての前例のない伊勢下向のために、恥を忍んでの参内である。
こうして、源氏を心から愛してしまった一人の女性が、源氏から離れるために、自分から姿を消していった。
*その一ヶ月後、具合の悪かったと伝えられた父院が急に重態となり、そのまま亡くなった。
亡くなる直前、心残りの源氏のことを兄である帝にくれぐれも重んじるようにと言い、藤壺との間の東宮がまだ幼いことを心配し
、後見として源氏を頼りにするようにと言い残す。
*しかし、父院の心配は、亡くなればすぐ現実になるのだ。
我が子が帝位についても、桐壺院がにらみをきかせている間は、思い通りにふるまえなかった弘徽殿・右大臣方は、
待っていましたとばかりに、力を発揮する。
*源氏の邸にさかんに出入りしていた人々がパタっと姿を見せなくなり、春の除目に、源氏方の人々のあるべき任命は一つもなかった。
紫上の父兵部卿宮も手のひらを返して、源氏のもとを去る。
*藤壺も桐壺院亡き後、院の御所から出なくてはならず、東宮のいる御所は弘徽殿の目が光っているので、近寄れない。
三条の兄の邸に身を寄せる。
*今まで、光る君として、全てが許されてきた源氏には、まったく思いも寄らない世の姿であった。
源氏の絶望感は、凶暴な憤りとなって、行動の抑制がきかなくなっていく。
欲するものを手に入れたい、世間がなんだ。彼は二人の女性に迫る。
一人は、右大臣の娘、弘徽殿の妹、兄の妃、すべてにわたって、源氏の敵の側に属する女性・朧月夜。
今は尚侍の名目で天皇妃として出仕している。かつて、まだ独り身だった時とは違うのだ。
その人に宮中で、父右大臣の家で姉の目を盗んで逢瀬を重ねていく。
(朧月夜のおはなしは 第五章 「情熱と理性 朧月夜・朝顔斎院」へつづきます。)
*今一人は、藤壺中宮。夫である父院はもういない。その重しがはずれた源氏は大胆に、三条宮へ忍んでいったのだ。
これには、藤壺は恐怖を感じる。なんの恐怖か。我が子東宮がその位を追われるかも知れないという恐れだ。
子を産んだ藤壺は、今、母としての存在になって、我が子を救うために、苦肉の策として出家を決意する。
出家者は男も敵も手をつけられない聖なる位置を獲得するらしい。
*こうして、源氏を愛する人に引きつづいて、源氏が激しく愛する人も源氏の前から姿を消していくのだ。孤独に、須磨明石をさすらう運命に陥る源氏。
(以下は、第六章 「去りゆく藤壺・源氏須磨へ・明石の君登場」へつづきます。)
|