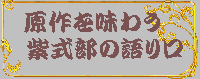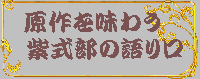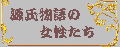| 原文 | 口語訳 |
御息所は、ものを思し乱るること、年ごろよりも多く添ひにけり。つらき方に思ひ果てたまへど、
今はとてふり離れ下りたまひなむは、「いと心細かりぬべく、世の人聞きも人笑へにならむこと」と思す。
さりとて立ち止まるべく思しなるには、かくこよなきさまに皆思ひくたすべかめるも、やすからず、
「釣する海人の浮けなれや」と、起き臥し思しわづらふけにや、御心地も浮きたるやうに思されて、悩ましうしたまふ。
大将殿には、下りたまはむことを、「もて離れてあるまじきこと」なども、妨げきこえたまはず、
「数ならぬ身を、見ま憂く思し捨てむもことわりなれど、今はなほ、いふかひなきにても、御覧じ果てむや、浅からぬにはあらむ」
と、聞こえかかづらひたまへば、定めかねたまへる御心もや慰むと、立ち出でたまへりし御禊河の荒かりし瀬に、
いとど、よろづいと憂く思し入れたり。
|
御息所は、あれこれ物思いなさることが、ここ数年来よりも多く加わってしまった。(君のお仕打ちは)つれないものとすっかりお諦めになったが、
もうこれきりと振り切って(伊勢に)お下りになるのは、「とても心細いだろうし、世間の人の噂でも、物笑いの種になるだろうこと」
とお思いになる。そうかといって、京に留まるようなお気持ちになるには、これ以上の恥はないほどに誰もが見下げることで
あろうのも穏やかでなく、「(私は)漁夫が釣する時の浮きなのか」と、寝ても起きても悩んでいられるせいか、
魂も浮いたようにお感じになられて、お具合が悪くいらっしゃる。
大将殿におかれては、(御息所が伊勢に)お下りになろうとしていることを、「まったくとんでもないことだ」
などとも、お引き止め申しもなさらないで、
「わたしのようなつまらない者を、見るのも嫌だとお思い捨てなさるのもごもっともですが、今はやはりつまらない
私でも、最後までお見限りなさらないのが、浅からぬ情愛というものではないでしょうか」
と、絡んだようなおっしゃりようなので、決断しかねていらしたお気持ちも紛れることがあろうかと、外出なさった御禊見物の
あの荒々しかった事件のため、いっそう、万事がとても辛くお思いつめになっていた。
|
私を引き留めてほしい
*車争い後の御息所の様子である。源氏の冷たい態度を辛く思い、伊勢に下ろうかと思ったが、男に捨てられて伊勢にいくという世間の噂を
気に病む。京にとどまろうにも、あの御禊見物の際の左大臣家から受けた恥辱を世間の皆が知っているのだから、それもできない。
どちらにもさだめかねる我が身を釣りのうきのように定まらないものと嘆く。
*しかし、そんな世間体を気にする心理も、もし、源氏が伊勢行きをやめるように強く言ってきたならば、源氏が引き留めてくれるならば、
いっさい消えてしまうはずのものなのだ。
「私を引きとめてほしい」「私が必要だと言ってほしい」。
*けれどいままで源氏からは、持って回ったようなねちこさで、
「一度関係した以上、私をお見捨てにならないのが、情愛というものではないでしょうか。」と、御息所に責任をかぶせるような言い方。
決して、「私が貴女を愛しているから、行かないで」とは言わない。御息所の情の深さを知り尽くした上での、真綿で首を絞めるような言いかた。
*悩む心のせめてもの一時の慰めにと、密かに源氏の姿を見に行ったあの御禊見物だったが、それがあろうことか、
左大臣家が、自分を「婿の愛人」扱いにした根に持ったやり方で、侮辱した。
源氏の冷たさを嘆き、一般的な世間の噂を気に病んでいたが、今は、自分を侮辱した正妻葵に対する恨みが加わって、なにもかも辛いと思い詰める。
葵上にとりつく物の怪
*一方、左大臣家では葵上が、物の怪にとりつかれてたいそう具合が悪い。ご祈祷によってさまざまの
物の怪がよりましに移り、姿を現すが、どうしても正体を現さず、じっと取り憑いたままなのが一つある。女房たちは六条の女君か、二条院の女君の恨みが強いのだろうと噂する。
院までが葵上の見舞いを頻繁にし、特別の祈祷までさせると聞いて、御息所は顧みられない我が身を思い、ますます妬ましさが募る。
そんな御息所の心を、権勢の絶頂にいる左大臣家では思いもよらないでいる。
|
| 原文 | 口語訳 |
かかる御もの思ひの乱れに、御心地、なほ例ならずのみ思さるれば、ほかに渡りたまひて、御修法などせさせたまふ。
大将殿聞きたまひて、いかなる御心地にかと、いとほしう、思し起して渡りたまへり。
例ならぬ旅所なれば、いたう忍びたまふ。心よりほかなるおこたりなど、罪ゆるされぬべく聞こえつづけたまひて、
悩みたまふ人の御ありさまも、憂へきこえたまふ。
「みづからはさしも思ひ入れはべらねど、親たちのいとことことしう思ひまどはるるが心苦しさに、
かかるほどを見過ぐさむとてなむ。よろづを思しのどめたる御心ならば、いとうれしうなむ」
など、語らひきこえたまふ。常よりも心苦しげなる御けしきを、ことわりに、あはれに見たてまつりたまふ。
うちとけぬ朝ぼらけに、出でたまふ御さまのをかしきにも、なほふり離れなむことは思し返さる。
「やむごとなき方に、いとど心ざし添ひたまふべきことも出で来にたれば、一つ方に思ししづまりたまひなむを、
かやうに待ちきこえつつあらむも、心のみ尽きぬべきこと」
なかなかもの思ひのおどろかさるる心地したまふに、御文ばかりぞ、暮れつ方ある。
「日ごろ、すこしおこたるさまなりつる心地の、にはかにいといたう苦しげにはべるを、え引きよかでなむ」
とあるを、「例のことつけ」と、見たまふものから、
「袖濡るる恋路とかつは知りながら
おりたつ田子のみづからぞ憂き
『山の井の水』もことわりに」
とぞある。
「御手は、なほここらの人のなかにすぐれたりかし」と見たまひつつ、「いかにぞやもある世かな。心も容貌も、
とりどりに捨つべくもなく、また思ひ定むべきもなきを」。苦しう思さる。御返り、いと暗うなりにたれど、
「袖のみ濡るるや、いかに。深からぬ御ことになむ。
浅みにや人はおりたつわが方は
身もそほつまで深き恋路を
おぼろけにてや、この御返りを、みづから聞こえさせぬ」
などあり。
|
(御息所は)このようなお悩みのせいで、お加減が、やはり普段のようではなくお感じになるので、別の御殿に
お移りになって、御祈祷などをおさせになる。
大将殿はお聞きになって、どのようなご容態なのかと、おいたわしく、進まぬ気持ちをふるい起こしなさって
お見舞いにいらっしゃった。
いつもと違った仮のご宿所なので、(君は)たいそう忍んでいらっしゃる。心ならずもご無沙汰している
ことなど、罪を許してもらえるよう詫び言を縷々申し上げなさって、ご病気の方(葵)のご様子についても、訴え申される。
「私自身はそれほども心配しておりませんが、親たちがとても大変な心配のしようなのが気の毒で、
そのような時を側についていようと存じておりましたもので。万事おおらかに見ていてくださるお気持ちならば、
まこと嬉しいのですが」 などと、こまごまとお話し申し上げなさる。(君は御息所の)いつもよりも痛々しげな
ご様子を、無理もないことと、しみじみ哀れに拝見なさる。
互いに打ち解けぬまま迎えた明け方に、お帰りになるそのお姿の美しさにつけても、やはり振り切って
遠くに行くことは、思い直しなさってしまう。
「ご身分の高い所に、ますますご愛情がお増しになるに違いないおめでたが生じたので、お一方の所に気持ちが
落ち着きなさってしまわれるに違いないのに、このようにお出を待ち申しているのも、気ばかりもめることだろう。」
かえって物思いを新たになさっていたところに、後朝の文だけが、夕方にある。
「ここ数日来、少し回復して来たようだった(病人の)気分が、急にとてもひどく苦しそうに見えましたので
、どうしても目を放すことができませんで」
とあるのを、(御息所は)「例によって言い訳を」と、御覧になるものの、(お返しに)
「物思いに袖の濡れる恋の路とは知りながらも、
その泥沼に自分から深入りしてしまうわが身がつろうございます
『山の井の水』も、もっともなことです」
とある。
「ご筆跡は、やはり数多い女性の中で抜きん出ている」と(源氏は)御覧になりながら、「どうしてこうも
思うようにならないのかなあ。気立ても容貌も、それぞれに捨ててよいものでなく、その反面これぞと思える人も
いないことだ」。苦しくお思いになる。お返事は、たいそう暗くなってしまったが、
「袖だけが濡れるとは、どうしたことで。愛情が深くないということなのでしょう。
袖が濡れるとはあなたは浅い所にお立ちなのでしょうか
わたしは全身ずぶ濡れになるほど深い恋路に立っておりますのに
並々の気持ちでしょうか、このお返事を、直接に訴え申し上げないのは。(直接伺えないくらい葵上の具合が悪
くて、仕方なくお手紙でお返事を差し上げています。)」
などとある。
|
久しぶりの訪問ーすれ違う心
*具合の悪い御息所は、祈祷を受けるために、余所に移る。六条の御殿には、神に仕える準備の斎宮がお住まいだから、
仏教の僧侶を招くわけにはいかない。それを源氏が聞き、御息所の気持ちを宥める必要を感じ、重い腰を上げて、
訪問することにした。
*久しぶりに再会した相手に対して、源氏は無沙汰の言い訳をあれこれと上手にする。一番の言い訳は葵上の具合の悪さだ。
親たちが心配して仕方がないので、その手前、自分も側を離れられないのだ、と。
*真剣に相手のことを考えたなら、御息所の恨みの気持ちが今、葵上に向かっていることを推測しえたはず。そうすれば
言い訳に葵を使うのが逆効果だとわかったであろう。
言い訳すればするほど、御息所は苦しげになる。お気の毒とはみても、それ以上に本気になって心を慰めようとはしていない。
*互いに心通い合うことなく、一夜を過ごした。朝ぼらけの源氏の美しさを見ては、女君の心は乱れる。でも、あちらに子ができた今、
ますますあの人の気持ちは、自分から離れていくのは道理。待っていても今まで以上に辛いだけ。
男君を見送った女君が煩悶しているうちに時間は経つ。とうとう「後朝の文」はこない。「ああ、やはり私のことなんか、もうどうでもいいのね。」と
ますますつらく、時を過ごす。ようやく、夕暮れになって、手紙が来る。
*「病人が急に具合が悪くて、側を離れられなくて」とある。「またいつもの言い訳」とおもう女である。
語り手は、御息所の煩悶を描くと、すぐ、入れ替わりに左大臣家の病人の具合が悪いと書く。それがなんども繰り返されるのだ。
聞き手は、そろそろ見当が付く。やはり御息所の苦しみの心が葵に取り憑いているのだと。まだ、御息所自身は気づいていない。
*歌を詠んでいない無礼な男の手紙だが、女はルールをふまえて、歌を詠む。
「こひぢ」とは[接頭語「小」+「ひぢ(泥土)」]と[恋路]との掛詞。「田子」は農夫。
辛い農作業と分かっていても、泥土に降り立ち袖をぬらし汚す農夫に、自分をたとえ、涙で袖をぬらす辛い恋と分かっていても
その恋の道に自分から入り込んでしまった我が身が恨めしい。
*あの「山の井の水」の古歌の心は本当にその通りでした。あなたの浅い愛情を自分で汲み取ろうとしたばかりに、袖をぬらすばかりです。
修辞法を用いているとはいえ、恋の道に踏み込んで脚を抜けないで苦しんでいる女の気持ちがそのまま、詠まれている。
切実な歌だ。
*それに対して、源氏が見て最初に思うのは、「字が美しい」ということ。さらに、「この人は教養趣味は最高。
でも心がちょっと。だれそれは容姿が良いけれど、教養はどうも。どうも完全無欠な人にはなかなか巡り会えないなあ、
思うようにいかない世だ。」御息所の切実さに対して、なんとも真剣みのない軽薄な源氏だ。
*返歌は、相手の言葉尻をとらえた形で、「袖だけ濡れる」あなたと「全身濡れる」私の差だと。しらじらしい。
逢えなければ辛いが、逢ってかえって相手の薄情を思い知るという「恋の泥沼」に落ち込んだ女君だけが、浮かび上がる一段だ。
*それにしても、語り手は、ここで意図的にこういう源氏を描いているのだろうか?古来、「美の化身、最高の恋人」とあがめられてきている「光源氏」だが、
こうして、本文を丹念に読み進めていくと、源氏の心の軽薄さ、驕りたかぶりはかなり鼻につく。空蝉や六条の御息所を
描く時、作者はやはり女たちに肩入れして描いているようだ。若紫や朧月夜を登場させる時とは、すこし作者のスタンスが違っている。
第一部の中で、わずかにこの二人の女性で試みられた「女の生」のテーマを、「紫上」を主人公に全面にだして描きたいと思うようになって、
第二部ができあがったのだろう。
|
| 原文 | 口語訳 |
大殿には、御もののけいたう起こりて、いみじうわづらひたまふ。「この御生きすだま、故父大臣の御霊など
言ふものあり」と聞きたまふにつけて、思しつづくれば、
「身一つの憂き嘆きよりほかに、人を悪しかれなど思ふ心もなけれど、もの思ひにあくがるなる魂は、さもやあらむ」
と思し知らるることもあり。
年ごろ、よろづに思ひ残すことなく過ぐしつれど、かうしも砕けぬを、はかなきことの折に、人の思ひ消ち、
なきものにもてなすさまなりし御禊の後、ひとふしに思し浮かれにし心、鎮まりがたう思さるるけにや、
すこしうちまどろみたまふ夢には、かの姫君とおぼしき人の、いときよらにてある所に行きて、とかく引き
まさぐり、うつつにも似ず、たけくいかきひたぶる心出で来て、うちかなぐるなど見えたまふこと、
度かさなりにけり。
「あな、心憂や。げに、身を捨ててや、往にけむ」と、うつし心ならずおぼえたまふ折々もあれば、
「さならぬことだに、人の御ためには、よさまのことをしも言ひ出でぬ世なれば、ましてこれは、いとよう
言ひなしつべきたよりなり」と思すに、いと名たたしう、
「ひたすら世に亡くなりて、後に怨み残すは世の常のことなり。それだに、人の上にては、罪深うゆゆしきを、
うつつのわが身ながら、さる疎ましきことを言ひつけらるる宿世の憂きこと。すべて、つれなき人にいかで心も
かけきこえじ」と思し返せど、思ふもものをなり。
|
大殿邸では、御物の怪がひどく起こって、大変にお苦しみになる。「自分の生霊や、故大臣の死霊だなど
と言う人がいる」とお聞きになるにつけて、お考え続けになると、
「我が身一人の不運を嘆いているより他には、他人を悪くなれと呪う気持ちはないのだが、悩み事があると
抜け出て行くという魂は、このようなことなのだろうか」
と、お気づきになることもある。
数年来、何かと物思いの限りを尽くしてきたが、こんなにも苦しい思いをしたことはなかったのに、
ちょっとした事の折に、相手が無視し、蔑ろにした態度をとった御禊の後は、あの一件によって抜け出るように
なった魂、鎮まりそうもなく思われるせいか、少しうとうととなさる夢には、あの姫君と思われる人の、
とても清浄にしている所に行って、あちこち引き掻き廻し、普段とは違い、猛々しく激しい乱暴な心が出てきて、
荒々しく叩くのなどが現れなさること、度重なった。
「ああ、何と忌まわしいことか。なるほど、身体を抜け出して出て行ったのだろう」と、正気を失ったように
思われなさる時が度々あるので、
「何でもないことでさえも、他人の事では、よいような噂は立てないのが世間の常なので、ましてこのことは、
何とでも噂立てられる絶好の種だ」とお思いになると、とても評判になりそうで、
「もう亡くなってしまって、後に怨みを残すのは世間にもあることだ。それでさえ、人の身の上については、
罪深く忌まわしいのに、生きている身でありながら、そのような忌まわしいことを、噂される因縁の辛いこと。
もう一切、薄情な方に決して心をお掛け申すまい」
とお考え直しになるが、思うまいと思うのも物思うことである。
|
魂の抜け出す時
*六条の御息所が源氏の来訪を受けた後、左大臣家では葵上の容態が一段と悪くなる。
大臣家では、女房達がひそひそと噂する。「取り憑いているのは御息所ご本人やその父の故大臣だろう」と。
聞き手にとっては意外な父の大臣の話題である。御息所の父が大臣クラスであったことは予想されたこと。でも、なぜ、父大臣の死霊がでるのか。
*葵上の父左大臣もその位に就く時には前任者をけ落とす悪どいやり方をしていたのかも知れない。
左大臣は結構若くして高位に上っている。桐壺帝の妹宮を妻に迎え、源氏を婿に迎え、自分の息子はライバル右大臣の婿にし、と
、結構政略的な行動をしている。まあ、当時としては、普通の行動であったろうが・・・。
なんにしろ、父の死霊と自分の生き霊とが葵に取り憑いているなどという噂は、立てられる方はたまらない。
*御息所の理性は考える。「自分自身を悩み苦しむことはすれ、他人様を悪くしたいなどと言う心は私はもっていないはず。」
でも、なにか、自分の理性のコントロールを越えて、「私の心がさまよい出る感じはしている。」と密かに思う。
*だれにも言えない秘密として、自分の見る夢を考えている。夜も昼も苦しく伏せって、うとうとまどろんでいる。
その夢に、いつも同じ自分が登場するのだ。夢の中の自分は邸を抜け出て、見たことのない邸の美しい調度に囲まれた部屋に入っていく。
そこには美しい姫が横たわっている。その姫を乱暴に引きかきむしり、叩く自分だ。
*現実には、人に手を掛けることなどしたこともない。あの乱暴された車争いの場でも、じっと車の壁をつかんで叫び声
ひとつたてずに、たしなみだけは失わなかった私なのだ。
その私の本当にしたかったことは、この夢のなかの私がしている。
噂の通り、わたしの魂は抜け出して、あちらで祟っているのだろう。
*世間というものは他人様のことは、良い噂はしたがらない、悪い事だけはみなが大喜びでするものなのだ。
今の私は、本当に世間の絶好の噂の種だ。
死霊になって祟る話を人ごととして聞いてもいまわしいのに、私はこうして生きている生身の体で生き霊として
噂されるのだ。これ以上の恥辱はない。
*これも私があの人を慕う心を持ってしまったからなのだ。
もう忘れよう。心からあの人を消そう。
*語り手は哀れみの気持ちもこめて言う。
「そう、心に言い聞かせること自体、あのひとを思っている証拠なのだ。古来いうではないか、『思はじと思ふもものを思ふなりけり』と。」
*この場面の六条の御息所の悩みは、「世間のしがらみ」にとらわれた、今の女性たちにも共通している悩みだ。「世間」というものの実態をこれほど
端的に言い表したのは、「お見事!」というしかない。
*「世間の物笑い」になることをおそれ、じっと息を潜めて何人の女性が自分を押さえて過ごしてきただろう。
狭い共同体の、身分や家柄や財産やなにやかやを知っている人間達だけで作りあげている世界。その「世間」を気にして生きるほかない人生。
*これはなにも、平安時代の貴族の女性だけではない。
江戸時代の集落で、現代の農村で、あるいはOL勤めの会社で、多くの女性たちが自分を押し殺して、生きてきた。
自分の力で生きていくこと、食べていくことのできない人間は他に依存するがゆえに、自分を取り巻く「世間」の網に捕まれていたのだ。
*御息所の苦しみは、自分の本心としての源氏への思慕が、「世間」と対立してしまう苦しみだ。
*御息所と対照的なのは、朧月夜と朝顔だ。朧月夜は自分の本心を最後までつらぬいて、帝妃でありながら、最後まで自分の意志で源氏との関係を続け、
あっさりと「世間」を越えて生き抜いてしまう女性だ。
朝顔は、御息所を反面教師として、源氏を受け入れることを自分に拒否し、男を否定することで、自分のプライドを保った女性だ。
朧月夜と朝顔は、セックスの有無において一見対照的ながら、他者に依存しない女として、現代のジェンダーフリーの若い女性につながるかもしれない。
朝顔と朧月夜については、第五章 「情熱と理性 朧月夜・朝顔斎院」へ (準備中)
|
| 原文 | 口語訳 |
おどろおどろしきさまにはあらず、そこはかとなくて、月日を過ぐしたまふ。
大将殿も、常にとぶらひきこえ
たまへど、まさる方のいたうわづらひたまへば、御心のいとまなげなり。
まださるべきほどにもあらずと、皆人もたゆみたまへるに、にはかに御けしきありて、悩みたまへば、
いとどしき御祈り、数を尽くしてせさせたまへれど、例の執念き御もののけ一つ、さらに動かず、やむごとなき
験者ども、めづらかなりともてなやむ。
さすがに、いみじう調ぜられて、心苦しげに泣きわびて、
「すこしゆるべたまへや。大将に聞こゆべきことあり」とのたまふ。
「さればよ。あるやうあらむ」
とて、近き御几帳のもとに入れたてまつりたり。
むげに限りのさまにものしたまふを、聞こえ置かまほしきこともおはするにやとて、大臣も宮もすこし退きたまへり。加持の僧ども、声しづめて法華経を誦みたる、いみじう尊し。
御几帳の帷子引き上げて見たてまつりたまへば、いとをかしげにて、御腹はいみじう高うて臥したまへるさま、
よそ人だに、見たてまつらむに心乱れぬべし。まして惜しう悲しう思す、ことわりなり。白き御衣に、色あひ
いとはなやかにて、御髪のいと長うこちたきを、引き結ひてうち添へたるも、
「かうてこそ、らうたげになまめきたる方添ひてをかしかりけれ」と見ゆ。
御手をとらへて、
「あな、いみじ。心憂きめを見せたまふかな」
とて、ものも聞こえたまはず泣きたまへば、例はいとわづらはしう恥づかしげなる御まみを、いとたゆげに
見上げて、うちまもりきこえたまふに、涙のこぼるるさまを見たまふは、いかがあはれの浅からむ。
あまりいたう泣きたまへば、「心苦しき親たちの御ことを思し、また、かく見たまふにつけて、口惜しう
おぼえたまふにや」と思して、
「何ごとも、いとかうな思し入れそ。さりともけしうはおはせじ。いかなりとも、かならず逢ふ瀬あなれば、
対面はありなむ。
大臣、宮なども、深き契りある仲は、めぐりても絶えざなれば、あひ見るほどありなむと思せ」
と、慰めたまふに、
「いで、あらずや。身の上のいと苦しきを、しばしやすめたまへと聞こえむとてなむ。かく参り来むとも
さらに思はぬを、もの思ふ人の魂は、げにあくがるるものになむありける」
と、なつかしげに言ひて、
「嘆きわび空に乱るるわが魂を
結びとどめよしたがへのつま」
とのたまふ声、けはひ、その人にもあらず、変はりたまへり。
「いとあやし」と思しめぐらすに、ただ、かの御息所なりけり。
あさましう、人のとかく言ふを、
よからぬ者どもの言ひ出づることも、聞きにくく思して、のたまひ消つを、目に見す見す、「世には、
かかることこそはありけれ」と、疎ましうなりぬ。
「あな、心憂」と思されて、
「かくのたまへど、誰とこそ知らね。たしかにのたまへ」
とのたまへば、ただそれなる御ありさまに、あさましとは世の常なり。
人々近う参るも、かたはらいたう思さる。
|
ひどく苦しいという様子ではなく、どこが悪いということもなくて、月日をお過ごしになる。
大将殿も欠かさず
お見舞い申し上げなさるが、さらに大事な方がひどく患っていられるので、お気持ちの余裕がないようである。
まだその時期ではないと、誰も彼もが油断していられたところ、急に産気づかれてお苦しみになるので、
これまで以上の御祈祷の有りったけを尽くしておさせになるが、例の執念深い物の怪が一つだけ全然動かず、
霊験あらたかな験者どもは、珍しいことだと困惑する。
とはいっても、たいそう調伏されて、いたいたしげに泣き苦しんで、
「少し緩めてください。大将に申し上げる事がある」とおっしゃる。
「やはりそうであったか。何かわけがあるのだろう」
と言って、近くの御几帳の側にお入れ申し上げた。
とてももうだめかと思われるような容態でいられるので、ご遺言申し上げて置きたいことでもあるのだろうかと
思って、大臣も宮も少しお下がりになった。
加持の僧どもは、声を低めて法華経を読んでいる、たいそう尊い。
御几帳の帷子を引き上げて拝見なさると、とても美しいお姿で、お腹はたいそう大きくて臥していられる様子、
他人であっても、拝見しては心動かさずにはいられないであろう。まして惜しく悲しくお思いになるのは、
もっともである。白いお着物に、色合いがとてもくっきりとして、髪がとても長くて豊かなのを、引き結んで
横に添えてあるのも、「こうあってこそかわいらしげで優美な点が加わり美しいのだなあ」と見える。
お手を取って、
「ああ、ひどい。辛い思いをおさせになるとは」
と言って、何も申し上げられずにお泣きになると、いつもはとても煩わしく気が引けて近づきがたいまなざしを、
とても苦しそうに見上げて、じっとお見つめ申していらっしゃると、涙がこぼれる様子を御覧になるのは、
どうして情愛を浅く思うであろうか。
あまりひどくお泣きになるので、「気の毒なご両親のことをご心配され、また、このように御覧になるに
つけても、残念にお思いになってのことだろうか」とお思いになって、
「何事につけても、ひどくこんなに思いつめなさるな。いくら何でも大したことはありません。
万が一のことがあっても、必ず逢えるとのことですから、きっとお逢いできましょう。
大臣、宮なども、深い親子の縁のある間柄は、転生を重ねても切れないと言うから、お逢いできる時があるとご安心なさい」
と、お慰めになると、
「いえ、そうではありません。身体がとても苦しいので、少し休めて下さいと申そうと思って。このように
参上しようとはまったく思わないのに、物思いする人の魂は、なるほど抜け出るものだったのですね」
と、親しげに言って、
「悲しみに堪えかねて抜け出たわたしの魂を
結び留めてください、下前の褄を結んで」
とおっしゃる声、雰囲気、この人ではなく、変わっていらっしゃった。
「たいそう変だ」とお考えめぐらすと、まったく、あの御息所その人なのであった。
あきれて、人が何かと噂をするのを、下々の者たちが言い出したことも、聞くに耐えないとお思いになって、
無視していられたが、目の前にまざまざと、「本当に、このようなこともあったのだ」と、気味悪くなった。
「ああ、嫌な」と思わずにはいらっしゃれず、
「そのようにおっしゃるが、誰とも分からぬ。はっきりと名乗りなさい」
とおっしゃると、まったく、その方そっくりのご様子なので、あきれはてるという言い方では平凡である。
女房たちがお側近くに参るのも、気が気ではない。
|
源氏の前に現れた生霊の正体
*相変わらず、どこということなく具合の悪い御息所であった。
けれど、源氏はそれどころではない。葵上の具合は一層悪いのだ。
*その葵上はまだ出産には間があると思う頃なのに、急に激しく苦しみだし陣痛が来た模様。苦しみをすこしでも和らげるために、
一層、盛んな祈祷を行うが、あのいつもの物の怪が一つ、どうしてもよりましに移ろうとしないで取り憑いたまま。
それが葵上に取り憑いたまま、調伏にあい、苦しみ泣いて、「祈祷をゆるめてください。大将に申し上げたいことがある」と
葵上の口を借りて言う。
側に着いている女房は「やはりね。訳があるのだろう。」とささやき合う。女房達の想像が当たっていたのか、物の怪は大将に関係しているものなのだ。
大将を招じ入れる座を用意する。
しかし、大臣や大宮は、危篤状態のような苦しみの葵が夫になにか言い残したいのかと考えて、夫婦二人にしてやるために、
その場を少し離れた。
*ここのところで、語り手は、女房達の推測と、親たちの推測とのズレをさりげなく示している。
地の文の最初を読めば、「苦しげになきわぶ」のは、物の怪である。しかし、親たちの考えでは、「大将に言い置きたい」というのは葵上本人である。
普通、物の怪が正体を現し、物を言うのはよりましの女の体に移ってから、よりましの口を通してである。
ここでは、よりましに移らず、葵上の口を通してものを言う。しかし、それは葵上本人の言葉かどうか不分明である。
このような例のない場面を紫式部は作り出したのだ。
*呼ばれた源氏は臨月の葵上を初めて直に見る。無防備に横たわっている葵上の大きな腹部のふくらみ、白い妊婦の服、横たえられた黒髪、
初めて見る葵上の姿を、源氏は美的感覚で眺める。異様ななまめかしさをもった美しさだと。
*私自身2度の出産を経験しているが、脂汗をかきながら陣痛の苦しみに堪えている時に、夫にあたる男にこのような見方をされたら、
許せない。
紫式部はなぜこういう美意識をここで源氏に発揮させるのか、この後死んでいく葵上を源氏が艶なる存在として
惜しむ場面を用意するための伏線のつもりなのだろうか。それにしても、ここの描き方はあまり良い趣味とは思えないのだが。
*源氏は葵上の手を取って、泣く。苦しげな葵上が力なく目をあけて源氏を見る。その目尻から涙がこぼれる。源氏は胸がつまる。
葵上がひどく泣くので、源氏は、「死にゆく葵が親たちの悲しみを思い、またこの美しい自分と別れることを残念に思って泣くのか。」
と思い、慰める。
①いくら何でも死ぬなんてことはありませんよ。大丈夫ですよ。②万一、ここであなたが先立つことになっても、
この世で夫婦になった私たちは、仏の教えのように輪廻する先の世で、必ず会えるでしょう。親子もまた会えるの
ですから、安心なさい。
そう、葵上に互いの夫婦の契りの深さを言って慰める。相手の死を前提にして言う言葉だ。これが慰めになるのか、現代の私たちの感覚では違和感がある。
*すると葵上の口から、きっぱりとした激しい言葉がでてきた。「いえ、ちがいます。さっきは、祈祷で調伏されて苦しい
から、しばらくやめてくださいと言ったんです。」その次の言葉は
「本当に物思いをする人の魂というのは、こうしてさまよい出てくるものなんですねェ。」その声音はいかにも源氏を慕わしく思っている声。
さらに歌を詠みかける。「嘆いて空にさまようわたしの魂をあなたの愛で呼び戻し、わたしの体に結びつけてほしい」声も表情もまったく、口に出している
本人葵上ではない。別の人のものに変わっている。
*「何だこれは、変だ」と思って、面変わりしたその葵上の表情が似ているはだれかと、思いめぐらすと、御息所そのものだった。
今まで人が、葵上に取り憑いているは御息所ではないかなどと噂しているのを、為にする噂と思って否定してきたのに、
今自分の目でまざまざと見てしまった気色の悪さ。
*物の怪に怖じない為に、強く言ってみた。「そんなこと言ったって、私にはだれだか見当が付かない。名前を名のれ。」
すると、葵上の顔を借りたそのものは、にっと笑みをうかべて、源氏に流し目をおくる時の御息所そのものの表情になって見せた。
もう、まちがいない、御息所の生き霊が取り憑いているのだ。
さっきから、自分が話しかけていたのは、葵上でなく御息所だったのか、涙を流していたのはどちらなのか。今となるともう分からない。
*すこし、苦しみの声が鎮まっていたので、離れていた女房が様子を見に近づいてくる。御息所の取り憑いたこんな葵上の表情を
見られたら大変だ。気が気でない源氏である。
|
| 原文 | 口語訳 |
すこし御声もしづまりたまへれば、隙おはするにやとて、宮の御湯持て寄せたまへるに、かき起こされたまひて
、ほどなく生まれたまひぬ。
うれしと思すこと限りなきに、人に駆り移したまへる御もののけども、ねたがりまどふ
けはひ、いともの騒がしうて、後の事、またいと心もとなし。
言ふ限りなき願ども立てさせたまふけにや、たひらかに事なり果てぬれば、山の座主、何くれやむごとなき僧ども
、したり顔に汗おしのごひつつ、急ぎまかでぬ。
多くの人の心を尽くしつる日ごろの名残、すこしうちやすみて、「今はさりとも」と思す。御修法などは、
またまた始め添へさせたまへど、まづは、興あり、めづらしき御かしづきに、皆人ゆるべり。
院をはじめたてまつりて、親王たち、上達部、残るなき産養どもの、めづらかにいかめしきを、夜ごとに見のの
しる。男にてさへおはすれば、そのほどの作法、にぎははしくめでたし。
かの御息所は、かかる御ありさまを聞きたまひても、ただならず。「かねては、いと危ふく聞こえしを、たひらか
にもはた」と、うち思しけり。
あやしう、我にもあらぬ御心地を思しつづくるに、御衣なども、ただ芥子の香に染み返りたるあやしさに、
御ゆする参り、御衣着替へなどしたまひて、試みたまへど、なほ同じやうにのみあれば、
わが身ながらだに疎ましう思さるるに、まして、人の言ひ思はむことなど、人にのたまふべきことならねば、心ひとつに思し嘆くに、
いとど御心変はりもまさりゆく。
大将殿は、心地すこしのどめたまひて、あさましかりしほどの問はず語りも、心憂く思し出でられつつ、
「いとほど経にけるも心苦しう、また気近う見たてまつらむには、いかにぞや。うたておぼゆべきを、人の御ため
いとほしう」、よろづに思して、御文ばかりぞありける。
|
少しお声も静かになられたので、一時収まったのかと、宮がお薬湯を持って来させになったので、抱き起こされ
なさって、間もなくお生まれになった。
嬉しいとお思いになることこの上もないが、憑坐にお移しになった物の怪
どもが、悔しがり大騷ぎする様子、とても騒々しくて、後産の事も、またとても心配である。
数え切れないほどの願文どもを立てさせなさったからか、無事に後産も終わったので、山の座主、誰彼といった
尊い僧どもが、得意顔に汗を拭いながら、急いで退出した。
大勢の人たちが心を尽くした幾日もの看病の後の緊張が、少し解けて、「今はもう大丈夫」とお思いになる。
御修法などは、再びお始めさせなさるが、差し当たっては、楽しくあり、おめでたいお世話に、皆ほっとしている。
院をお始め申して、親王方、上達部が、残らず誕生祝いの贈り物、珍しく立派なのを、夜毎に見て大騷ぎする。
男の子でさえあったので、そのお祝いの儀式、盛大で立派である。
あの御息所は、このようなご様子をお聞きになっても、おもしろくない。「以前には、とても危ないとの噂で
あったのに、安産であったとは」と、お思いになった。
不思議に、自分が自分でないようなご気分を思い辿って御覧になると、お召物なども、すっかり芥子の香が
滲み着いている奇妙さに、髪をお洗いになり、着物をお召し替えになったりなどして、お試しになるが、依然と
して前と同じようにばかり臭いがするので、
自分の身でさえありながら疎ましく思わずにはいらっしゃれないのに、
それ以上に、他人が噂し推量するだろう事など、誰にもおっしゃれるような内容でないので、心一つに収めて
お嘆きになっていると、ますます気が変になって行く。
大将殿は、気持ちが少し落ち着きなさって、何とも言いようのなかったあの時の問わず語りを、何度も不愉快に
お思い出しになられて、
「まこと日数が経ってしまったのも気の毒だし、また身近にお逢いすることは、
どうであろうか。きっと不愉快に思われようし、相手の方のためにも気の毒だろうし」と、
いろいろとお考えになって、お手紙だけがあるのだった。
|
葵上、無事出産ー生き霊の自覚
*長く苦しんでいたわりに、葵上の出産はあっけない程簡単だった。
大宮がもってきた薬湯を飲ませる為に、女房たちが葵上の状態を起こして、まもなく、
生まれたのだ。
当時の出産の体勢は「座産」。上体を起こした座った形で産むのだ。平安時代の草紙絵の中にも、両手を支えられて、
上体を起こした形で出産する妊婦の絵がある。部屋の外では魔よけの鳴弦をする侍の姿が描かれていたりする。
出産の喜びの傍らで、よりましに移った物の怪が悔しがって大騒ぎするという。実は例の生き霊はまだよりましに移っていないことを
記憶しておくべきだ。
*人々は後産が終わるまでは心配だとまた一生懸命祈祷させる。後産も無事すむ。
天台座主をはじめ、祈祷に携わった僧たちが、してやったりと得意げに汗をぬぐい帰っていく。山のようなお布施を貰ったはずだ。
人々もやっと一安心した。無事の出産と聞いて、生まれた赤子の祖父に当たる院をはじめ、全ての上達部から産養いの品がゾクゾクと届く。
その豪華さはたいしたものだ。
*そんな様子は御息所の所にも伝わり、彼女は思う。「あちらはいのちも危ういと聞いていたのに、無事だなんて、まあ。」
世間が大騒ぎで祝っているから、なおさら御息所の気持ちは修まらない感じだ。
そんな自分の心を見つめていると、ふと自分の衣が芥子の香りがするのに気づいた。
「この香り、あの夢の中でかいだ護摩にくすべた芥子の香りだ。」と思った途端、自分の身が忌まわしくなって、
急いで、髪を「ゆする(米のとぎ汁)で梳きけずり、着替えをしたが、香りは消えない。我が身に染みとおってしまっている。
「ああ、やはり私は生き霊となってあちらに祟っていたのだ。なんと疎ましい我が身よ。」そして思うのは「世間」のこと。
「人にはどう思われるのか、つらい。」でも、そのつらさは誰にも言えない。
忠実そうな女房たち、でも彼女たちに私の苦しんでいることを訴えようなら、口ではなんとでも慰めを言いながら、
心の中では、舌を出して蔑むに決まっている。まして、これから神に仕える清純な愛娘には、源氏に恋いこがれていることさえ、
知られてはならないのだ。そう思いつめる御息所の心はますます常軌を逸してくる。
*一方、源氏は、出産が無事すんで、人々の祝いをうけて、ホッと一段落すると、あの御息所の生き霊が自分に向かって
語りかけた場面を思い出す。
あの人は苦しんでいるのだ。こんなに無沙汰をしてしまって、申し訳ないが、さりとて、
直接お会いしたら、きっと、生き霊となった人だという思いが生じて、疎ましく感じ顔にも出てしまうだろう。
相手に分からせてしまうのはお気の毒だ。」あれこれ考えて、お手紙だけのお見舞いをした。
*ここで、源氏が思いきって、自分の心を押し殺して、演技だけでも良いから、直接、御息所を見舞って、慰めたなら、あるいは
この後の事態は避けられたかも知れない。けれど、突然、葵上の顔がかわって、御息所になっていったあの時の身の毛のよだつ思いは
そう簡単に消せない。源氏はどうしても御息所を見ることが出来なかったのだ。
葵上、死ぬ
*その源氏が次にしたことは、こともあろうに、藤壺との間の我が子、東宮の顔を見に行くこと。葵上の産んだ赤子をみたら、
しゃにむに、東宮を見たくなったという。この時の源氏の、赤子(のちの夕霧)に対する冷たさは、ちょっと想像できない。
葵上が死ぬこのあとずっと、我が子は祖父母まかせだ。
*もう一方、真剣みがなかった人々がいる。一安心した左大臣が、政治家の本領を発揮して、除目の場を取り仕切るべく
参内する。葵の兄や他の子ども達もわれもわれもと父大臣について行く。除目で取り立てて貰わなければいけないから。
こんな所がさりげなく書かれている源氏物語だ。
*邸内から人気が消えたとき、葵上がまた急に今までのように、胸を詰まらせて苦しんだと思ったら、そのまま息が絶えた。
語り手は「例の」の一言以外何も言わないが、葵上に取り憑いていた生き霊が、隙をねらって一気に葵上を取り殺したのだ。
御息所の「御心変わりもまさりゆく」と対応した場面のはずだ。
*葵上急死の報で、宮中は除目どころではなくなった。みな退出してしまった。
左大臣家では、葵上の死が信じられなくて、死者をねかせる北枕にせず、息を吹き返してくれるのを必死に願ったが、
三日経って、死体の気配がどうにも否定できなくなって、ようやく弔いの準備に入る。
*御息所は、丁重なおくやみの文を源氏に出した。それを見た源氏は、気分が良くない。おもわず、返事に、
「人のいのちははかないものとさとりました。どうかあなたもっもう、物を思い詰めないでください。」と書いてしまった。
それを読んだ御息所は、「ああ、あの人は私が生き霊となったことを知っているのだわ。もう私はおしまいだ。」と悟った。
|