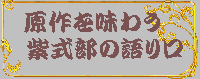
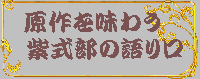
| 原文 | 口語訳 |
| 日もいと永きに、つれづれなれば、夕暮のいたう霞みたるに紛れて、かの小柴垣のほ どに立ち出でたまふ。人びとは帰したまひて、惟光朝臣と覗きたまへば、ただこ の西面にしも、仏据ゑたてまつりて行ふ、尼なりけり。簾すこし上げて、花たて まつるめり。中の柱に寄りゐて、脇息の上に経を置きて、いとなやましげに読み ゐたる尼君、ただ人と見えず。四十余ばかりにて、いと白うあてに、痩せたれど、 つらつきふくらかに、まみのほど、髪のうつくしげにそがれたる末も、なかなか 長きよりもこよなう今めかしきものかなと、あはれに見たまふ。 | 日も永いし、何もすることがないので、夕暮のたいそう霞わたっているのに紛れて、 あの小柴垣の付近にお立ち出でになる。供人はお帰しになって、惟光朝臣とお覗きになると、 ちょうどこの西面に、仏を安置申して勤行している、それは尼なのであった。簾を少し上げて、 花を供えているようである。中の柱に寄り掛かって座って、脇息の上にお経を置いて、 とても大儀そうに読経している尼君は、普通の人とは見えない。四十過ぎくらいで、 とても色白で上品で、痩せてはいるが、頬はふっくらとして、目もとのぐあいや、 髪がきれいに切り揃えられている端も、かえって長いのよりも、この上なく新鮮な感じだなあ、 と感心して御覧になる。 |
|
*「若紫」の巻は、「わらはやみにわづらひ給ひて、」と語り出す。「わらはやみ」とは子どもが罹りやすかったから付いたな名らしいが、 1日おきに発熱する病気でマラリアのようなものかという。流行病らしい。 *主人公はそれに罹って症状が治まらず、ある人の薦めで、北山の聖に治療してもらう為、身をやつして山に登る。 聖の加持祈祷の合間に、あたりの風景を眺めていると、山寺にはめずらしいしゃれた庵があり、そこには若い女房や子どもの姿が見えると供人が言う。 *また、付近の山のたたずまいなど、都を離れたことのない主人公にはめずらしい感じがしていると、 あちこちの国に赴任したことのある供人たちは、諸国の山や海のすばらしいさなど語り聞かせる。播磨国守の子が、 明石の浦には、国守を辞任して出家した男が大切に傅いている娘がいるという話をする。 *文庫本2ページ近くにわたって、供人の語る明石の出家者の娘の話は、後に重要な意味を持ってくることになる。 *さて上記本文である。 お忍びの山寺行きだったので、日帰りするつもりが、聖の勧めで山寺に一泊することになった主人公は、夕暮れ時、例の小柴垣の庵をのぞき見する。 お供は惟光朝臣だけ。 *惟光は「夕顔」の巻で、源氏の乳母大弐乳母の子として登場し、源氏を夕顔に手引きすることから始まって、 夕顔急死の後始末一切をした家臣。ここで、主人公は誰とまだ語られないが、惟光が登場したことで、聴き手には「源氏」だと分かる。 *源氏は小柴垣からのぞき見する。「垣間見(かいまみ)」である。物語の主人公達が思いがけない人を発見するのがこの垣間見。 しかもここは出家者である僧都の庵というのに、若い女房の姿が見えた謎の住まい。身をやつした源氏にとって、好奇心をみたすはじめての経験。 *ところが、のぞいて見ると、主は期待したような若い女性ではなく、尼であった。 源氏のちょうど正面で、 まさかのぞき見する人がいるとは思わず、春のよい日和ゆえ、簾を巻き上げて勤行している。年、40あまり、体調が良くなさそうな人だが、 品の良い顔立ちで尼そぎ髪も優美な人であった。 *語り手はのぞく源氏の目を通して語っていく。この尼君は、最高の美の具現者「光る君」に尼姿を「こよなう今めかしき」と評価されているのだ。なかなかのものである。 |
| 原文 | 口語訳 |
| 清げなる大人二人ばかり、さては童女ぞ出で入り遊ぶ。中に十ばかりやあらむ と見えて、白き衣、山吹などの萎えたる着て、走り来たる女子、あまた見えつる 子どもに似るべうもあらず、いみじく生ひさき見えて、うつくしげなる容貌なり。 髪は扇を広げたるやうにゆらゆらとして、顔はいと赤くすりなして立てり。 | 小綺麗な女房二人ほど、他には童女が出たり入ったりして遊んでいる。 その中に、十歳くらいかと見えて、白い袿の上に、山吹襲などの、糊気の落ちた表着を着て、駆けてきた女の子は、 大勢見えた子供とは比べものにならず、たいそう将来性が見えて、かわいらしげな顔かたちである。 髪は扇を広げたようにゆらゆらとして、顔はとても赤く手でこすって立っている。 |
|
*今度は女房である。「大人」とはこの場合、年配の女房のこと。「清げなる大人」と源氏の目に映る女房、こういう女房が仕えているこの尼君はそれ相当な身分の主人のはず。 ますます興味が持たれる。 *そして、主人の尼君にはふさわしくない童女達。と、思ったらそこに飛び込んできた女の子。 かわいらしい顔がどうなるかも気にしないで、大泣きした顔を手でこすって真っ赤にしている。 *この、活発で、他者の目を気にしない”自分そのもの”として、登場するのが「若紫」だ。 その属性は「いみじく生ひさき見えて」と一言で言い当てている。 *「活発さ・自分の感情に素直・未来に今現在よりも美しく」この3点がこの女の子の本質なのだ。 |
| 原文 | 口語訳 |
| 「何ごとぞや。童女と腹立ちたまへるか」とて、尼君の見上げたるに、すこし おぼえたるところあれば、「子なめり」と見たまふ。 「雀の子を犬君が逃がしつる。伏籠のうちに籠めたりつるものを とて、いと 口惜しと思へり。このゐたる大人、 「例の、心なしの、かかるわざをして、さいなまるるこそ、いと心づきなけれ。 いづ方へかまかりぬる。いとをかしう、やうやうなりつるものを。烏などもこそ 見つくれ」とて、立ちて行く。髪ゆるるかにいと長く、めやすき人なめり。少納 言の乳母とこそ人言ふめるは、この子の後見なるべし。 | 「どうしたの。童女とけんかをなさったのですか」 と言って、尼君が見上げた顔に、少し似ているところがあるので、「その子どもなのだろう」と御覧になる。 「雀の子を、犬君が逃がしちゃったの。伏籠の中に、閉じ籠めておいたのに」 と言って、とても残念がっている。ここに座っていた女房が、 「いつもの、うっかり者が、このようなことをして、責められるとは、ほんと困ったことね。どこへ飛んで行ってしまいましたか。 とてもかわいらしく、だんだんなってきたものを。烏などが見つけたら大変だわ」 と言って、立って行く。髪はゆったりととても長く、見苦しくない女のようである。 少納言の乳母と皆が呼んでいるらしい人は、この子の後見役なのだろう。 |
|
*顔を伏せて経を読んでいた尼君が顔を上げた。よく似ている。母子か? *会話が聞こえる。雀の子を童の一人がいたずらして逃がしてしまったのだ。怒ってその子とけんかしたのだろう。 でも逃げた雀の子は捕まえられない。泣いている女の子。 *いつもいつもトラブルをおこす童を愚痴り、女の子の為に雀の子を探しに「大人」の一人が立っていく。 これは女の子の乳母なのだろう。語り手はその名も明かす、「少納言の乳母」と。なぜなら今後も重要な登場人物になるから。 |
| 原文 | 口語訳 |
| 尼君、「いで、あな幼や。言ふかひなうものしたまふかな。おのが、かく、今日 明日におぼゆる命をば、何とも思したらで、雀慕ひたまふほどよ。罪得ることぞと、 常に聞こゆるを、心憂く」とて、「こちや」と言へば、ついゐたり。 つらつきいとらうたげにて、眉のわたりうちけぶり、いはけなくかいやりたる 額つき、髪ざし、いみじううつくし。「ねびゆかむさまゆかしき人かな」と、目 とまりたまふ。さるは、「限りなう心を尽くしきこゆる人に、いとよう似たてま つれるが、まもらるるなりけり」と、思ふにも涙ぞ落つる。 | 尼君が、 「何とまあ、幼いことよ。お話にならなく(おさなく)いらっしゃることね。わたしの、このように、 今日明日にも思われる寿命を、何ともお考えにならず、雀を追いかけていらっしゃることよ。 (生き物をとらえるのは)罪を得ることですよと、いつも申し上げていますのに、情けなく」と言って、 「こちらへ、いらっしゃい」と言うと、ちょこんと座った。 顔つきがとてもかわいらしげで、眉のあたりがほんのりとして、子供っぽく掻き上げた額つきや、 髪の生え際は、大変にかわいらしい。「成長して行くさまが楽しみな人だなあ」と、(源氏の君は) お目がとまりなさる。それと言うのも、「限りなく心を尽くし申し上げている方に、とてもよく似ているので、 目が引きつけられるのであったなあ」と、思うにつけても涙が落ちる。 |
|
*尼君は具合が悪いのである。それにつけても自分の亡き後、この子がどうなるか心配しているのだ。 *そういわれて神妙に座る女の子。まだ眉を抜いていない幼い顔だが、成長していく先がたいそう期待出来る顔立ちだ、と思った源氏。 次の瞬間、ハッとした。 *「この子はあの方にとてもよく似ているのだ、だから目が惹きつけられるのだ。」 この子の後ろにあの方の姿が思い浮かぶだけで涙が出て来る源氏である。 *女の子に「目とまりたまふ」源氏は、語り手により敬われている。しかし、「さるは(というのは、じつは)」と、その心の奥の真相を暴いた語り手は、 女の子の背後にあの方を慕う心を隠し持つ源氏に対しては、「思ふにも涙ぞ落つる」と言うだけで、敬意を一切表さない。厳しい批判意識を持つ語り手である。 |
| 原文 | 口語訳 |
|
尼君、髪をかき撫でつつ、「梳ることをうるさがりたまへど、をかしの御髪や。
いとはかなうものしたまふこそ、あはれにうしろめたけれ。かばかりになれば、いとかからぬ人もあるものを。
故姫君は、十ばかりにて殿に後れたまひしほど、いみじうものは思ひ知りたまへりしぞかし。
ただ今、おのれ見捨てたてまつらば、いかで世におはせむとすらむ」とて、いみじく泣くを見たまふも、すずろに悲し。
幼心地にも、さすがにうちまもりて、伏目になりてうつぶしたるに、こぼれかかりたる髪、つやつやとめでたう見ゆ。
「生ひ立たむありかも知らぬ若草をおくらす露ぞ消えむそらなき」 またゐたる大人、「げに」と、うち泣きて、 「初草の生ひ行く末も知らぬまにいかでか露の消えむとすらむ」 と聞こゆるほどに、 |
尼君が、髪をかき撫でながら、
「梳くことをお嫌がりになるが、美しい御髪ですね。とても子供っぽくいらっしゃることが、かわいそうで心配です。
これくらいの年になれば、とてもこんなでない人もありますものを。亡くなった姫君は、
十歳程で父殿に先立たれなさった時、たいそう物事の意味は弁えていらっしゃいましたよ。
この今、わたしがお見捨て申して逝ってしまったら、どのように過ごして行かれるおつもりなのでしょう」
と言って、たいそう泣くのを(源氏の君が)御覧になると、何とも言えず悲しい。
子供心にも、やはりじっと見つめて、伏し目になってうつむいているところに、こぼれかかった髪が、
つやつやとして素晴らしく見える。
「これからどこでどう育って行くのかも分からない若草のようなあなたを 残してゆく露のようにはかないわたしは死ぬに死ねない思いです」 もう一人の座っている女房が、「本当に」と、涙ぐんで、 「初草のように若い姫君のご成長も御覧にならないうちに どうして尼君様は先立たれるようなことをお考えになるのでしょう」 と申し上げているところに、 |
|
*尼君の言葉が聞こえてくる。「亡くなった姫君」がいたのだ。その人が10歳くらいの時に父が死んでいる。 父に死なれた姫は恵まれた結婚は望めない。その姫がだれかと結婚し、この女の子を産み、その姫も若くして死んでいった。 *今はこの祖母尼君がひとりで、孫の女の子を育てているのだ。「自分が死んだらこの子はどうなるのか」と泣く尼君なのだ。 *祖母の言葉をじっと聞く女の子、源氏の目にはただひたすらかわいらしく美しく見える。 *悲しみの思いは歌に表す。「若草ー露ー消ゆ」と、春の季節に合った「若草」に女の子をたとえ、縁語の「露」にわが身をなぞらえ、 今まさに死にゆく身を「露が消える」という。露は朝日にあってはかなく蒸発し、空中に昇ってゆく、けれどあなたのことが心配な私は安心して消えてゆくことができないよ、と。 *それを聞く、二人いたうちのもう一人の女房、この人が尼君づきの女房であろう、もらい泣きしながらこの人が応える。 「初草ー露ー消ゆ」と尼君の歌いぶりを受け止め、「若草」を「初草」と読み替えて、あとは尼君の歌の場をそのまま受け継いでいる。 *特にひねった歌い方ではなく、なだらかな読み方で、相手の気持ちを十分に汲んだことが伝わる。 主の気持ちに共感をしめしつつ、励ます女房の役目を果たした歌だ。 「この幼い姫の成長を見届けるのはあなた様しかおられない、気持ちをしっかりお持ちになってくださいませ」と励ますのだ。 *源氏とともに、物語の聴き手の姫達も、ここに登場した女の子の境遇に悲しみ、将来を心配する。 すると、部屋の奥になにやら気配が・・・。 |
| 原文 | 口語訳 |
| 僧都、あなたより来て、「こなたはあらはにやはべらむ。今日しも、端におはし ましけるかな。この上の聖の方に、源氏の中将の瘧病まじなひにものしたま ひけるを、ただ今なむ、聞きつけはべる。いみじう忍びたまひければ、知りはべ らで、ここにはべりながら、御とぶらひにもまでざりける」とのたまへば、「あな いみじや。いとあやしきさまを、人や見つらむ」とて、簾下ろしつ。 「この世に、ののしりたまふ光る源氏、かかるついでに見たてまつりたまはむ や。世を捨てたる法師の心地にも、いみじう世の憂へ忘れ、齢延ぶる人の御あり さまなり。いで、御消息聞こえむ」とて、立つ音すれば、帰りたまひぬ。 | 僧都が、あちらから来て、「ここは人目につくのではないでしょうか。今日に限って、端近にいらっしゃいますね。この上の聖の坊に、源氏中将が瘧病のまじないにいらっしゃったのを、たった今、聞きつけました。ひどくお忍びでいらっしゃったので、知りませんで、ここにおりながら、お見舞いにも上がりませんでした」とおっしゃると、 「まあ大変。とても見苦しい様子を、誰か見たでしょうかしら」と言って、簾を下ろしてしまった。 「世間で、大評判でいらっしゃる光源氏を、この機会に拝見なさいませんか。俗世を捨てた法師の気持ちにも、たいそう世俗の憂えを忘れ、寿命が延びるご様子の方です。どれ、ご挨拶を申し上げよう」 と言って、立ち上がる音がするので、お帰りになった。 |
|
*この庵の主である僧都がかえってきたのだ。 *尼君は気持ちよい日和に外気を受けて身体をいたわっていたのだが、僧都は「今日に限って人目に付く端かにおいでですね」と、ちょっとはしゃぎながら、ビッグニュースを伝える。 「源氏の君が聖のところにお出でになっている」と。 *あわてて簾をおろす尼君。源氏の夢のような垣間見のひとときは終わった。 *僧都は言う、「世間で大評判の源氏のお姿を拝見しませんか。法師の自分が見ても寿命が延びる気分になる美しさだ。」と。 ということはこの僧都は源氏を見たことがあるのだ。 *情報を伝えた僧都はまたあたふたと立ち上がる、「さあ、ご挨拶にうかがおう。」と。 *これは大変、こういしてはいられない、僧都が来る前に自分の宿坊に戻っていなければ・・。あわててかえる源氏であった。 |
| 原文 | 口語訳 |
| 「あはれなる人を見つるかな。かかれば、この好き者どもは、かかる歩きをの みして、よくさるまじき人をも見つくるなりけり。たまさかに立ち出づるだに、 かく思ひのほかなることを見るよ」と、をかしう思す。「さても、いとうつくし かりつる児かな。何人ならむ。かの人の御代はりに、明け暮れの慰めにも見ばや」 と思ふ心、深うつきぬ。 | 「しみじみと心惹かれる人を見たなあ。これだから、この好色な連中は、このような忍び歩きばかりをして、 よく意外な人を見つけるのだな。まれに外出しただけでも、このように思いがけないことに出会うことよ」と、 興味深くお思いになる。「それにしても、とてもかわいかった少女であるよ。どのような人であろう。 あのお方の代わりとして、毎日の慰めに見たいものだ」という考えが、強く起こった。 |
|
*庵の前を去って宿坊へと帰る道すがらの源氏の心中である。 後ろには、惟光ひとりが従っている。 *「この好き者どもは」という「この」は、惟光を指している。惟光のような身軽な身分の者たちはよく忍び歩きをして、 隠れた所にひっそりと住む、魅力的な女性を探し当てて恋人として通うという話を源氏は聞かされていたのだ。 *瘧りやみの治療のためという理由でおとずれた山寺ー女っ気などとおよそ縁の無いはずの場所ーに、初めて足を踏み入れたわけだが、 その最初の時にこのような心惹かれる女性ーまだ少女だがーを見つけたのだ。好き者どもの話を聞いて、そんなことがそうあるはずはないと思っていたが、 自分の身にも起こったのが面白いと思う源氏である。 *しかし、そうおかしがる気持ちのすぐ後ろにわき上がってくるのは、「あの方」のこと。この「女の子」を身代わりに傍に置いておきたいという 尋常でない心が生じてきた。「思ふ心、深うつきぬ。」と、ここでも語り手は敬意抜きで突き放すように描写する。 |
*このあと、源氏は僧都からの誘いを受けていそいそと、僧都の庵へ出向く。そこで知った女の子の素性は、 なんとあの藤壺の姪だった。あに兵部卿の宮が通っていたのが尼君の娘である故大納言の姫。その姫が正妻の仕打ちを気に病みながら早世して 後に残した娘がこの女の子。祖母尼君が育てていた。父兵部卿の宮は正妻の手前、引き取ろうともせず関心も持たない娘だった。 *身元が分かったとたん矢も楯もたまらず、自分に世話させてくれと申し込む源氏。祖母も乳母も「まだ少女のこの子をどうして?」と 驚いて本気では取り合わない。 *翌朝早く、源氏の所在を探し当てた左大臣が、頭中将以下の君達を迎えによこしたため、源氏は多くの人々とともに帰京する。 *心配する帝にご挨拶し、その足で久々に左大臣邸に。相も変わらぬ冷たい姫の態度に嘆息するしかない源氏であった。 *心にかかるのは、あの女の子。北山に手紙を出し、姫の世話をしたいと重ねて言うが、執心の事情を知らない尼君に断られる。 惟光を使者にたて、少納言の乳母に連絡を取らせたりもする。 *このように、北山であった姫が忘れられない源氏を描いた直後に、語り手は藤壺の宮の里下がりを述べる。文庫本のページにしてわずか4ページにも満たない中で 源氏の密会・藤壺の懐妊・参内へと続くのである。 |
| 原文 | 口語訳 |
| 藤壺の宮、悩みたまふことありて、まかでたまへり。上の、おぼつかながり、 嘆ききこえたまふ御気色も、いといとほしう見たてまつりながら、かかる折だに と、心もあくがれ惑ひて、何処にも何処にも、まうでたまはず、内裏にても里に ても、昼はつれづれと眺め暮らして、暮るれば、王命婦を責めありきたまふ。 | 藤壺の宮は、ご病気で、ご退出された。主上が、お気をもまれ、ご心配申し上げていらっしゃるご様子も、 まことにおいたわしく拝見しながらも、せめてこのような機会にもと、魂も浮かれ出て、 どこにもかしこにもお出かけにならず、内裏にいても里邸にいても、昼間は所在なくぼうっと物思いに沈んで、 夕暮れになると、王命婦にあれこれとおせがみになる。 |
|
*宮中は神聖な場所ゆえ、病気をした身はいてはならない。それで、後宮の女性達は里(実家)に下がる。 宮中は人目が多く、父帝がいつも藤壺を傍から放さない。源氏は藤壺を遠くから声を聞くだけしかできないでいる。 *藤壺が里下がりしたと言う情報に、ただもう、これが密会のチャンスと、そればかり考え、他の一切が考えられない源氏である。 *「心があくがれ惑ふ」と語り手は言う。魂が自分の身体から出て相手を求めてさまよい出てしまう状態を「あくがる」というのだ。 源氏は、父が藤壺を心配していることは承知しても自分の気持ちは抑えようもないでいる。 *ここで帝のことを想像してみると、愛しい藤壺が体調がすぐれないのも心配だし、もう一人の源氏も瘧の治療に北山に祈祷に行き、 なんとか直ったと思っていたのに、また具合が悪くなっているらしいと、宮中を一歩も出られない身で、ひたすら心配をしているはずだ。 父帝は藤壺と源氏を同じように、いつもじっと見守っている。 *さて、昼間は魂が抜けたような源氏だが、夕方になると実に行動的だ。藤壺の里邸に行き、 藤壺の側近の女房王命婦(おうみょうぶ)を責め立てて、密会のチャンスを作らせようとする。 *藤壺の女房名「王命婦」とは、父が「王(天皇の子で親王ではない人、または親王の子)」である女性で、宮中に出仕した上級女房の意味である。 つまり出自は皇族なのだ。皇族の身分の女性といえども、生活のためにより身分の高い人の女房勤めをするのが生きる道なのだ。 藤壺入内にあたって、付き従って来た女房であろう。乳母子の女房は「弁のおもと」とよばれる別人である。 *寝殿造りの中の女主人は実は非常に不用心な存在だ。御殿は四隅の戸を閉めるだけで、室内は全部開放された造作だ。 自分で戸締まりをすることも出来ない。廻りはいつも腹心の女房に取り囲まれている。 *その女房が男君と示し合わせて、戸の錠を開けておけば、いつでも男は女主人の所に忍び込める。 若菜下で柏木が女三宮のもとに忍び込むのも女房の手引きだ。 *だから男達は、自分の妻や愛人の女房をいつも手なづけておく必要がある。多くの場合、肉体関係を結ぶという方法で気脈を合わせる。 それらの女房は「召人(めしうど)」と呼ばれ、「愛人」格でもない、しもべの位置なのだ。 あの六条御息所が年下の源氏の愛人の位置に苦しんでいたが、その女房の「中将の君」は源氏の「召人」だったのだ。 *紫式部が道長の召人だったという説が根強くある。真偽のほどはまだ判明しないが、可能性は大いにある。 その召人となった女房の女主人に対する心理というものはどういうものか興味深い所だ。第二部になると、紫上の女房がちらりとそれをかいま見させる。 *話がそれたが、ここでの源氏は王命婦を召人にしているわけではなさそうだが、彼独特の魅力で一途に藤壺を慕う苦しさを訴え、 同情を取り付けてしまうようである。15歳は年長の帝よりも、5歳年下の源氏の方が藤壺には似つかわしいという思いが生じてしまったのかも知れない。 |
| 原文 | 口語訳 |
| いかがたばかりけむ、いとわりなくて見たてまつるほどさへ、現とはおぼえぬ ぞ、わびしきや。宮も、あさましかりしを思し出づるだに、世とともの御もの思 ひなるを、さてだにやみなむと深う思したるに、いと憂くて、いみじき御気色な るものから、なつかしうらうたげに、さりとてうちとけず、心深う恥づかしげな る御もてなしなどの、なほ人に似させたまはぬを、「などか、なのめなることだ にうち交じりたまはざりけむ」と、つらうさへぞ思さるる。何ごとをかは聞こえ 尽くしたまはむ。くらぶの山に宿りも取らまほしげなれど、あやにくなる短夜に て、あさましう、なかなかなり。 | どのように手引したのだろうか、とても無理してお逢い申している間さえ、現実とは思われないのは、辛いことであるよ。 宮も、思いもしなかった出来事をお思い出しになるだけでも、生涯忘れることのできないお悩みの種なので、 せめてそれきりで終わりにしたいと深く決心されていたのに、とても情けなくて、ひどく辛そうなご様子でありながらも、 優しくいじらしくて、そうかといって馴れ馴れしくなく、奥ゆかしく気品のある御物腰などが、やはり普通の女人とは違っていらっしゃるのを、 「どうして、わずかの欠点すら少しも混じっていらっしゃらなかったのだろう」と、辛くまでお思いになられる。 どのようなことをお話し申し上げきれようか。鞍馬の山に泊まりたいところだが、あいにくの短夜なので、情けなく、 かえって辛い逢瀬である。 |
|
*藤壺と源氏との密通の唯一の場面である。戦前には、この場面が削除されて出版されたこともあるとか。 しかし、削除する程の描写もない、たいそうおぼめかした表現である。 *「いかがたばかりけむ」と語り手の感想を挿入しただけで、王命婦の手引きの様など書かず、場面は一気に源氏が藤壺を見ている ところになる。 *「見たてまつるほどさへ」が「現(うつつ)とはおぼえぬ」ようだ、と言う。「さへ」はあることAに、このことBが加わる様。 つまり、会えずに恋いこがれていた時が「現でな」かったが、今の会っている最中までが「現でな」い時として加わった。 せっかく会えたのに、そしてこれが最後のチャンスになるかも知れないのに、しっかりと記憶にとどめる現実感がもてないなんて、「辛い」と思う源氏。 *一方の「宮も」と、語り出す語り手は、読者の予想もしなかったことを言う。 「あさましかりしを思し出づるだに、」「さてだにやみなむと深う思したるに」だと。体験過去の「き」がこんなに恐ろしい効果を持つというのが 物語の言説である。藤壺には忘れようもない「あさましかりし」体験があったのだ。 *「さてだに(せめてそれ一回の体験だけで)」「やみなむと深う思したるに」、今また同じことが生じてしまったのだ。辛く思っている藤壺である。 *藤壺のこの夜の様子を、語り手は、「いと憂くて、いみじき御気色なるものから、」「なつかしうらうたげに、」「さりとてうちとけず、心深う恥づかしげな る御もてなしなど」と言う。当然のことながら、なかなか複雑な様子である。 *二度と繰り返してはならないと自分に言い聞かせていたことが、また起こってしまった辛さがまずある。しかし、気強く相手を拒む態度ではないのだ。 *源氏は藤壺の様子を「なつかしう」「らうたげに」と感じている。 「なつかし」は「心がひかれる」「慕わしい」「親しみやすい」など、自分にとって離れがたい気持ちを感じる相手の様子をいう。 「らうたげなり」は「いじらしいく」「かわいらしく」感じる様で、自分がたくさん世話をしてやりたい感じが基本だ。 藤壺の様子は相手に十分な情愛を感じさせるものなのだ。 *逢ってはならない義理の息子源氏。しかし、自分を激しく愛する源氏に藤壺もまた心惹かれているのだ。 源氏の愛を受けて、うれしい女の感情を持ちながら、しかし、決してその愛欲におぼれるのではなく、「うちとけず」身分にふさわしい上品なみのこなしをする。 *その、愛情と抑制の心から出た振る舞いを、源氏は「なほ人に似させたまはぬ」と思う。 ここは、「いつもうちとけず」つんとすましている葵上を念頭において、比較している源氏の心がうかがえる。 北山から帰って左大臣邸に行った時の、つめたいく取り澄ます葵上を、極端と思える程、強調していたが、 おなじく「うちとけず」の態度でも、こちらは、自分にとって、なに一つ欠点のないすばらしい方で、「欠点一つないから、自分の心がこんなに惹かれてしまうのだ」 と、自分の道理に合わない感情を相手のせいにしてしまう。 *源氏がなにを語ったか、藤壺がどんな声音で応対したか、何一つ語られていない。 しかし、藤壺は決して源氏を嫌っているのではないのだ。彼を避けるのは、身分・立場上であって、 もし二人が互いに一人の男女として会ったならば、心を通わせあったことであろう、と推測できる余地を残している。 |
| 原文 | 口語訳 |
| 「見てもまた逢ふ夜まれなる夢のうちに やがて紛るる我が身ともがな」 と、むせかへりたまふさまも、さすがにいみじければ、 「世語りに人や伝へむたぐひなく 憂き身を覚めぬ夢になしても」 思し乱れたるさまも、いと道理にかたじけなし。命婦の君ぞ、御直衣などは、 かき集め持て来たる。 | 「お逢いしても再び逢うことの難しい夢のようなこの世なので 夢の中にそのまま消えてしまいとうございます」 と、涙にひどくむせんでいられるご様子も、何と言ってもお気の毒なので、 「世間の語り草として語り伝えるのではないでしょうか、 この上なく辛い身の上を覚めることのない夢の中のこととしても」 お悩みになっている様子も、まことに道理で恐れ多い。命婦の君が、お直衣などは、取り集めて持って来た。 |
|
*「見てもまた逢ふ夜まれなる夢」とよみかけるのは源氏。「あなたにこうして逢っても、 次ぎに再び逢うことがほとんど不可能な夢のような世(二人のなか)」だから、その「夢のうちに(逢っている最中の今)」 「やがて(そのまま)」「夢の中に夢と同じくはかなく消えてしまうわが身であったらなあ」 *どうせもう逢えないのなら、藤壺と逢っている今の今、一緒に死んでしまいたい、と情死の願望を述べる源氏である。 *藤壺は応える。たとえ、ここで二人が死んでもそれで終わりにはならない、「世語りに人や伝へむ(世間の語りぐさになっていくでしょう)」と。 この辛い身を現実から消してしまっても。 *藤壺も決して二人の情死のイメージを否定はしていない。でもそうしても、世は二人をそのまま忘れ去ってはくれない、それで終わりとはならないのだ。 ここで、源氏の気持ちを受け止めつつ、これ以上暴走しないようにたしなめるしかない藤壺である。 *この世間を考えざるをえない藤壺が、このあと、世間に隠しようもない妊娠・出産の現実をわが身に引き受けざるを得なくなったとき 彼女は、最大級に理性を働かす女性になっていく。入内当初からのあの堂々とした振る舞いを、これから一生、演技し通すのだ。 *夏の短夜が開ける前に、源氏を退出させねばならない。命婦が源氏の直衣をかき集めて、支度を急がせるという。 やはり命婦が一切をお膳立てしたのだ。夏の夜の短い逢瀬はこうして終わった。 |
| 原文 | 口語訳 |
| 殿におはして、泣き寝に臥し暮らしたまひつ。御文なども、例の、御覧じ入れ ぬよしのみあれば、常のことながらも、つらういみじう思しほれて、内裏へも参 らで、二、三日籠もりおはすれば、また、「いかなるにか」と、御心動かせたま ふべかめるも、恐ろしうのみおぼえたまふ。 | お邸にお帰りになって、泣き臥してお暮らしになった。お手紙なども、例によって、御覧にならない旨ばかりなので、 いつものことながらも、全く茫然自失とされて、内裏にも参内せず、二、三日閉じ籠もっていらっしゃるので、また、 「どうかしたのだろうか」と、ご心配あそばされているらしいのも、恐ろしいばかりに思われなさる。 |
|
*自邸の二条殿に帰った源氏である。泣き寝をして部屋からでない。 後朝のことゆえ、特別の気持ちで藤壺にお手紙を出しても、藤壺はいつものように、目になさらない、という。 源氏はいままでも、お手紙だけはしばしば差し上げようとしていたのだ。 *しかし、藤壺はあの第一回の逢瀬いらい、一度も源氏からの手紙はご覧になろうとしなかったのだ。 今回のお手紙をご覧になってくれないのも、いつものことだとは思っても、夢のような逢瀬の後なので、 せめてなにか思ってくださってほしい、と思う気持ちがいっぱいでとても辛くて、涙にくれている。 *一方、宮中では、父帝が心配している。里下がりした藤壺の健康を心配するだけでなく、こんどは、顔を見せない息子のことまでが心配な帝。 その息子が自分の妻に懸想してあげく密通したとは知らずに、いつもの愛情を傾けて気遣っている。 *自分の犯した罪の深さに恐れ震える源氏である。 |
|
*藤壺は一層気分がすぐれず、自身は思い当たることがあるので辛くなる。 やがて3ヶ月過ぎて世話をする女房に知られる。知らせを受けた帝は喜ぶが、命婦は不運にあきれる思い。 源氏は不吉な夢でそれと思い知る。 *帰参した藤壺を一層寵愛する帝のまえに伺候する源氏。 御簾を隔てて、あの日を思い、こらえきれない気持ちになる二人であった。 *ここまでを大急ぎで語った、語り手は、再びあの北山の少女の身の上に話を移す。 *尼君が帰京したと聞いて、源氏は見舞いに訪れ、前よりも熱心に少女の世話を申し入れる。 尼君はなかなかはっきりした返事をしないうちに、10月に亡くなった。 *喪に服する寂しい家にたびたび源氏は弔問の使者を立て、 また自身も訪れる。乳母の少納言はしみじみとした対応をすることが出来る女房であり、 少女を父宮邸に引き取る話がすすんでいることを源氏に伝える。 *少女は父が来たと思って出て来るが、間違えたと知って恥ずかしそうであったが、やがて、たびたび訪れるこの父より美しい貴公子に親しむ。 |
| 原文 | 口語訳 |
|
「かしこに、いとせちに見るべきことのはべるを思ひたまへ出でて、立ちかへり参り来なむ」とて、出でたまへば、 さぶらふ人びとも知らざりけり。 わが御方にて、御直衣などはたてまつる。惟光ばかりを馬に乗せておはしぬ。 門うちたたかせたまへば、心知らぬ者の開けたるに、御車をやをら引き入れさせて、大夫、妻戸を鳴らして、しはぶけば、 少納言聞き知りて、出で来たり。 「ここに、おはします」と言へば、 「幼き人は、御殿籠もりてなむ。などか、いと夜深うは出でさせたまへる」と、もののたよりと思ひて言ふ。 「宮へ渡らせたまふべかなるを、そのさきに聞こえ置かむとてなむ」とのたまへば、 「何ごとにかはべらむ。いかにはかばかしき御答へ聞こえさせたまはむ」 とて、うち笑ひてゐたり。 |
「あちらに、どうしても処理しなければならない事がございますのを思い出しまして、すぐに戻って来ます」と言って、 お出になるので、お側の女房たちも知らないのであった。 ご自分のお部屋の方で、お直衣などはお召しになる。惟光だけを馬に乗せてお出になった。 門を打ち叩かせなさると、何も事情を知らない者が開けたので、お車を静かに引き入れさせて、惟光大夫が、 妻戸を叩いて、合図の咳払いをすると、少納言の乳母が察して、出て来た。 「ここに、おいでになっています」と言うと、 「若君は、お寝みになっております。どうして、こんな暗いうちにお出あそばしたのでしょうか」と、 どこかからの帰りがけと思って言う。 「宮邸へお移りあそばすそうですが、その前にお話し申し上げておきたいと思って参りました」とおっしゃると、 どのようなことでございましょうか。どんなにしっかりしたお返事ができましょう」 と言って、微笑んでいた。 |
|
*祖母尼君が亡くなって、頼りのない若紫、父兵部卿宮の邸に引き取らることになった。 いよいよ明日には父宮が迎えに来ると聞いた源氏は、今夜を逃してはこの女の子を手に入れることが出来なくなると 行動を起こすことにした。 *妻葵に口実を作り、惟光ひとりを伴って左大臣邸をひそかに抜け出すと、故尼君の邸へ。 |
| 原文 | 口語訳 |
|
君、入りたまへば、いとかたはらいたく、「うちとけて、あやしき古人どものはべるに」と聞こえさす。 「まだ、おどろいたまはじな。いで、御目覚ましきこえむ。かかる朝霧を知らでは、寝るものか」 とて、入りたまへば、「や」とも、え聞こえず。 君は何心もなく寝たまへるを、抱きおどろかしたまふに、おどろきて、宮の御迎へにおはしたると、 寝おびれて思したり。 御髪かき繕ひなどしたまひて、「いざ、たまへ。宮の御使にて参り来つるぞ」とのたまふに、 「あらざりけり」と、あきれて、恐ろしと思ひたれば、「あな、心憂。まろも同じ人ぞ」 とて、かき抱きて出でたまへば、大輔、少納言など、「こは、いかに」と聞こゆ。 「ここには、常にもえ参らぬがおぼつかなければ、心やすき所にと聞こえしを、心憂く、渡りたまへるなれば、 まして聞こえがたかべければ。人一人参られよかし」とのたまへば、心あわたたしくて、 「今日は、いと便なくなむはべるべき。宮の渡らせたまはむには、いかさまにか聞こえやらむ。 おのづから、ほど経て、さるべきにおはしまさば、ともかうもはべりなむを、いと思ひやりなきほどのことにはべれば、 さぶらふ人びと苦しうはべるべし」と聞こゆれば、 「よし、後にも人は参りなむ」とて、御車寄せさせたまへば、あさましう、いかさまにと思ひあへり。 若君も、あやしと思して泣いたまふ。 少納言、とどめきこえむかたなければ、昨夜縫ひし御衣どもひきさげて、 自らもよろしき衣着かへて、乗りぬ。 | 源氏の君が、お入りになると、とても困って、
「気を許して、見苦しい年寄たちが寝ておりますので」とお制し申し上げる。
「まだ、お目覚めではありますまいね。どれ、お目をお覚まし申しましょう。このような素晴らしい朝霧を知らないで、 寝ていてよいものですか」 とおっしゃって、ご寝所にお入りになるので、「もし」とも、お止めできない。 紫の君は何も知らないで寝ていらっしゃったが、源氏の君が抱いてお起こしなさるので、目を覚まして、 父宮がお迎えにいらっしゃったと、寝惚けてお思いになった。 お髪を掻き繕いなどなさって、 「さあ、いらっしゃい。父宮さまのお使いとして参ったのですよ」 とおっしゃる声に、「違う人であったわ」と、びっくりして、恐いと思っているので、 「ああ、情けない。わたしも同じ人ですよ」 と言って、抱いてお出なさるので、大輔や少納言の乳母などは、「これは、どうなさいますか」と申し上げる。 「ここには、常に参れないのが気がかりなので、気楽な所にと申し上げたが、残念なことに、宮邸にお移りになるそうなので、 ますますお話し申し上げにくくなるだろうから。誰か一人付いて参られよ」 とおっしゃるので、気がせかれて、 「今日は、まことに都合が悪うございましょう。宮さまがお越しあそばした時には、どのようにお答え申し上げましょう。 自然と、年月をへて、そうなられるご縁でいらっしゃれば、ともかくなられましょうが、何とも考える暇もない急な事でございますので、 お仕えする者どももきっと困りましょう」と申し上げると、 「よし、後からでも女房たちは参ればよかろう」と言って、お車を寄せさせなさるので、驚きあきれて、 どうしたらよいものかと困り合っていた。 若君も、変な事だとお思いになってお泣きになる。 少納言の乳母は、お止め申し上げるすべもないので、昨夜縫ったご衣装類をひっさげて、自分も適当な着物に着替えて、 車に乗った。 |
|
*応対に出た少納言の乳母の困惑もお構いなしに、室内に入り、寝ている姫君を抱き上げ、 車に乗り込む。こういう場合に、大騒ぎも出来ない女房達。 *源氏の振る舞いを無茶だと思っても、父宮の邸に行っても姫に幸せが待っているとは思えない。 源氏は姫の世話をしたいと言い続けてきたが、果たしてそれはどういう扱いをしようとしているのか、まだ信じられない。 この姫を守る親族がいない今では、女房が姫の為に一番いいと思うことを考えてやらねばならないが、 その判断がつきかねるのだ。 そういう状態では、この源氏の無体な行動を明確に拒否することができないのだ。 *やむをえず牛車に一緒に乗っていくことにした少納言は、昨夕縫い上げたばかりの姫の衣をかき集め、 自分も大急ぎで上着だけ少しはましなものに着替えて。 *この物語の語り口がリアリテイを持つのは、迷いながら牛車に乗る少納言が、昨夜一生懸命に縫った姫の衣装をもち、 自分も着替えているというこの現実感。大局の判断が出来なくても、日常生活で大事な衣装をすばやく手に取ることにできる この少納言という人はなかなか機転の利く人物である。しかも人に見られる自分の服装までを気にすることができている。 この女房がついていれば姫の身も心配はないだろうと聞き手はほっとする。 |
| 原文 | 口語訳 |
|
二条院は近ければ、まだ明うもならぬほどにおはして、西の対に御車寄せて下りたまふ。若君をば、 いと軽らかにかき抱きて下ろしたまふ。 少納言、「なほ、いと夢の心地しはべるを、いかにしはべるべきことにか」と、やすらへば、 「そは、心ななり。御自ら渡したてまつりつれば、帰りなむとあらば、送りせむかし」 とのたまふに、笑ひて下りぬ。 にはかに、あさましう、胸も静かならず。「宮の思しのたまはむこと、いかになり果てたまふべき御ありさまにか、 とてもかくも、頼もしき人びとに後れたまへるがいみじさ」と思ふに、涙の止まらぬを、さすがにゆゆしければ、念じゐたり。 |
二条院は近いので、まだ明るくならないうちにお着きになって、西の対にお車を寄せてお下りになる。
若君を、とても軽々と抱いてお下ろしになる。
少納言の乳母が、 「やはり、まるで夢のような心地がしますが、どういたしましたらよいことなのでしょうか」と、ためらっているので、 「それはあなたの考え次第でしょう。ご本人はお移し申し上げてしまったのだから、帰ろうと思うなら、 送ってやろうよ」とおっしゃるので、苦笑して下りた。 急な事で、驚きあきれて、心臓がどきどきする。「宮さまがお叱りになられることや、 どうおなりになる姫君のお身の上だろうか、とにもかくにも、身内の方々に先立たれたことが本当にお気の毒」と思うと、 涙が止まらないのを、何と言っても不吉なので、じっと堪えていた。 |
|
*二条邸につくと、源氏は西の対に姫をおろす。さすがにためらう少納言に対して、「姫は連れてきた、目的は達したから、 そなたは好きなように。帰りたければ送らせるよ」と余裕たっぷり。いまさら戻れない少納言。 姫のさい先の為にも、これは幸せなことと思わなければと、涙をこらえる。 |
| 原文 | 口語訳 |
|
こなたは住みたまはぬ対なれば、御帳などもなかりけり。惟光召して、御帳、御屏風など、あたりあたり仕立てさせたまふ。 御几帳の帷子引き下ろし、御座などただひき繕ふばかりにてあれば、東の対に、御宿直物召しに遣はして、大殿籠もりぬ。 若君は、いとむくつけく、いかにすることならむと、ふるはれたまへど、さすがに声立ててもえ泣きたまはず。 「少納言がもとに寝む」とのたまふ声、いと若し。 「今は、さは大殿籠もるまじきぞよ」と教へきこえたまへば、いとわびしくて泣き臥したまへり。 乳母はうちも臥されず、ものもおぼえず起きゐたり。 |
こちらはご使用にならない対の屋なので、御帳などもないのであった。惟光を呼んで、御帳や、御屏風など、
ここかしこに整えさせなさる。御几帳の帷子を引き下ろし、ご座所など、ちょっと整えるだけで使えるので、
東の対にお寝具類などを取り寄せに人をやって、お寝みになった。
若君は、とても気味悪くて、どうなさる気だろうと、ぶるぶると震えずにはいらっしゃれないが、 やはり声を出してお泣きになれない。 「少納言の乳母の所で寝たい」とおっしゃる声は、まことに幼稚である。 「今からは、もうそのようにお寝みになるものではありませんよ」 とお教え申し上げなさると、とても悲しくて泣きながら横におなりになった。 少納言の乳母は横になる気もせず、何も考えられず起きていた。 |
|
*源氏の居間は東の対で、こちらは客用の間。普段使用していないので、何のしつらいもない。 惟光に命じ、大急ぎで支度させる。まだ夜が明けないし、昨夜来の緊急行動で寝ていない源氏は、姫と一緒に御帳台の中で寝ることにした。 いったい何が起こったのかと怖さでぶるぶる震えていた姫が、「少納言と一緒に寝るの」というが許さない。 今まで一度の泣かなかった姫もさすがにベソをかく。 *少納言は一睡もしないで、傍らで夜を過ごした。 |
| 原文 | 口語訳 |
|
明けゆくままに、見わたせば、御殿の造りざま、しつらひざま、さらにも言はず、庭の砂子も玉を重ねたらむやうに見えて、 かかやく心地するに、はしたなく思ひゐたれど、こなたには女などもさぶらはざりけり。 け疎き客人などの参る折節の方なりければ、男どもぞ御簾の外にありける。 かく、人迎へたまへりと、聞く人、「誰れならむ。おぼろけにはあらじ」と、ささめく。御手水、御粥など、こなたに参る。 日高う寝起きたまひて、「人なくて、悪しかめるを、さるべき人びと、夕づけてこそは迎へさせたまはめ」 とのたまひて、対に童女召しにつかはす。「小さき限り、ことさらに参れ」とありければ、いとをかしげにて、四人参りたり。 |
夜が明けて行くにつれて、見渡すと、御殿の造りざまや、調度類の様子は、改めて言うまでもなく、
庭の白砂も宝石を重ね敷いたように見えて、光り輝くような感じなので、きまり悪い感じでいたが、
こちらの対には女房なども控えていないのであった。たまのお客などが参った折に使う部屋だったので、
男たちが御簾の外に控えているのであった。
このように、女をお迎えになったと、聞いた人は、「誰であろうか。並大抵の人ではあるまい」と、ひそひそ噂する。 御手水や、お粥などを、こちらの対に持って上がる。 日が高くなってお起きになって、 「女房がいなくて、不便であろうから、しかるべき人々を、夕方になってから、お迎えなさるとよいだろう」 とおっしゃって、東の対に童女を呼びに人をやる。「小さい子たちだけ、特別に参れ」と言ったので、 とてもかわいらしい格好して、四人が参った。 |
|
*夜が明けると、朝の光りの中に浮かび上がる二条邸の美しさに目を見張る少納言。 普段使用していない西の対にはお仕えする女房がいないので、室内には自分だけ。ややほっとする少納言である。 *御簾の外に御用を受けるために控えている男達のささやき声が聞こえる。「女君をむかえたらしい、 源氏の君がお迎えになる方だ、なまじのかたではあるまい、どなただろうね」と。 「ああ、姫君のことをそう噂しあっているのだわ。本当に女君としてお迎えになっていただけたのだったらうれしいけれど・・。 」と思った少納言であろう。 *日が高くなって起き出した源氏は「誰もいないのは不便だから、夕方になったら、ふさわしい女房をお迎えなさい」といって、 今は童女を東の対から遊び相手として呼び寄せる。 |
| 原文 | 口語訳 |
|
君は御衣にまとはれて臥したまへるを、せめて起こして、 「かう、心憂くなおはせそ。すずろなる人は、かうはありなむや。女は心柔らかなるなむよき」 など、今より教へきこえたまふ。 御容貌は、さし離れて見しよりも、清らにて、なつかしううち語らひつつ、をかしき絵、 遊びものども取りに遣はして、見せたてまつり、御心につくことどもをしたまふ。 |
> 紫の君はお召物にくるまって臥せっていらっしゃったのを、無理に起こして、
「こんなふうに、お嫌がりなさいますな。いい加減な男は、このように親切にしましょうか。
女性というものは、気持ちの素直なのが良いのです」
などと、今からお教え申し上げなさる。
ご容貌は、遠くから見ていた時よりも、美しいので、優しくお話をなさりながら、興趣ある絵や、 遊び道具類を取りにやって、お見せ申し上げ、お気に入ることどもをなさる。 |
|
*姫君はお着物にくるまったまま起きてこようとしない。自分の誠意を自分から口に出して、 「女は素直なのが良いんですよ」などと、姫の教育を始める源氏。 *ひるまの明るさの中で間近で見る姫の予想以上の美しさに改めて感動する源氏は、姫を喜ばせようと 絵を見せたり、子どもの遊び道具で一緒に遊ぶ。 |
|
*このあと、源氏が東の対に渡って一人になった姫は、美しい室内の様子や屏風絵を眺めたり、 庭の前栽のたたずまいやその間を忙しく行き来する家人達の姿を珍しそうに眺めて心がなごんでいく様子。 *このうつくしく、素直で柔軟性のある姫の姿を眺めるだけで自分も心がなごむ源氏は、2,3日どこにも 外出せず、姫との遊びに時を過ごす。絵を描いてやったり、歌を書いてやったり、それはすべて姫に対する英才教育である。 かつて、宮中で母のない自分を父帝が手ずから教えてくれたあれこれの再現であったろう。それを吸収しすばらしく開花する才能を持つ姫でもある。 *姫に書いてやった歌には、古歌をふまえて「紫のゆかり」として、姫を藤壺のゆかりと思う気持ちを詠んだ。 「知らねども武蔵野といへばかこたれぬよしやさこそは紫のゆゑ」(行ったことはないが、武蔵野というとため息が出るよ。それはそこにある紫草が懐かしいからだ) (「古今六帖」)。 そして自分の歌「ねは見ねどあはれとぞ思ふ武蔵野の露分けわぶる草のゆかりを」(根は見ないが、寝てはみないが、かわいいと思う。 武蔵野の露を分けえず、我がものとできない草(藤壺)のゆかりのこの草を)。 *そして姫は手習いに、返歌を書く。「『武蔵野といへばかこたれぬ』とおっしゃっても、かこつ理由が分かりません。 私はいったいどんな草(人)のゆかりなのでしょう」と。 *物語の本文では、手習いをする姫と教える源氏の姿だけ記述するが、 この手習いにかこつけた源氏と姫との歌の内容は、ふかく重いものがある。 特に幼い姫が自分を誰かの身代わりとして自覚していることを注目しなければならない。 *歳よりも幼いと幼さを強調されている今の若紫だが、ここでの返歌では、源氏の歌の意味を正しく理解している。 そして歌の込められた意味「紫のゆかり」とはなにかを問うている。永遠に答えの得られない問いを。 *紫上は、自分と源氏との関係についてしばしば振り返ることの多い後半生のなかで、 「愛している」という言葉だけ繰り返す源氏に「身柄」を保護されている自分の運命について、 苦しみの節々で、 この最初の贈答歌の意味を思い起こしたはずである。 *「自分は誰かの身代わりとして愛されているのだ。源氏の愛は自分そのものへ向けられたものではないのではないか」 「若菜」以後、紫上はいつも、この日の源氏の歌の真意を思い起こし苦しみ続けていくことになる。 |
| 原文 | 口語訳 |
|
[第一段 源氏、紫の君と新枕を交わす] 二条院には、方々払ひみがきて、男女、待ちきこえたり。上臈ども皆参う上りて、 我も我もと装束き、化粧じたるを見るにつけても、かのゐ並み屈じたりつるけしきどもぞ、 あはれに思ひ出でられたまふ。 御装束たてまつり替へて、西の対に渡りたまへり。衣更えの御しつらひ、くもりなくあざやかに見えて、 よき若人童女の、形、姿めやすくととのへて、「少納言がもてなし、心もとなきところなう、心にくし」と 見たまふ。 姫君、いとうつくしうひきつくろひておはす。 「久しかりつるほどに、いとこよなうこそ大人びたまひにけれ」 とて、小さき御几帳ひき上げて見たてまつりたまへば、うちそばみて笑ひたまへる御さま、飽かぬところなし。 「火影の御かたはらめ、頭つきなど、ただ、かの心尽くしきこゆる人に、違ふところなくなりゆくかな」 と見たまふに、いとうれし。 いとつれづれに眺めがちなれど、何となき御歩きも、もの憂く思しなられて、思しも立たれず。 姫君の、何ごともあらまほしうととのひ果てて、いとめでたうのみ見えたまふを、似げなからぬほどに、はた、 見なしたまへれば、けしきばみたることなど、折々聞こえ試みたまへど、見も知りたまはぬけしきなり。 つれづれなるままに、ただこなたにて碁打ち、偏つぎなどしつつ、日を暮らしたまふに、心ばへのらうらうじく 愛敬づき、はかなき戯れごとのなかにも、うつくしき筋をし出でたまへば、思し放ちたる年月こそ、 たださるかたのらうたさのみはありつれ、しのびがたくなりて、心苦しけれど、いかがありけむ、 人のけぢめ見たてまつりわくべき御仲にもあらぬに、男君はとく起きたまひて、女君はさらに起きたまはぬ朝あり。 人びと、「いかなれば、かくおはしますならむ。御心地の例ならず思さるるにや」と見たてまつり嘆くに、 君は渡りたまふとて、御硯の箱を、御帳のうちにさし入れておはしにけり。 人まにからうして頭もたげたまへるに、引き結びたる文、御枕のもとにあり。何心もなく、ひき開けて見たまへば、 「あやなくも隔てけるかな夜をかさね さすがに馴れし夜の衣を」 と、書きすさびたまへるやうなり。「かかる御心おはすらむ」とは、かけても思し寄らざりしかば、 「などてかう心憂かりける御心を、うらなく頼もしきものに思ひきこえけむ」 と、あさましう思さる。 昼つかた、渡りたまひて、 「悩ましげにしたまふらむは、いかなる御心地ぞ。今日は、碁も打たで、さうざうしや」 とて、覗きたまへば、いよいよ御衣ひきかづきて臥したまへり。人びとは退きつつさぶらへば、寄りたまひて、 「など、かくいぶせき御もてなしぞ。思ひのほかに心憂くこそおはしけれな。人もいかにあやしと思ふらむ」 とて、御衾をひきやりたまへれば、汗におしひたして、額髪もいたう濡れたまへり。 「あな、うたて。これはいとゆゆしきわざぞよ」 とて、よろづにこしらへきこえたまへど、まことに、いとつらしと思ひたまひて、つゆの御いらへもしたまはず。 「よしよし。さらに見えたてまつらじ。いと恥づかし」 など怨じたまひて、御硯開けて見たまへど、物もなければ、「若の御ありさまや」と、らうたく見たてまつりたまひて、 日一日、入りゐて、慰めきこえたまへど、解けがたき御けしき、いとどらうたげなり。 「第二段 三日夜の祝い」 その夜さり、亥の子餅参らせたり。かかる御思ひのほどなれば、ことことしきさまにはあらで、こなたばかりに、 をかしげなる桧破籠などばかりを、色々にて参れるを見たまひて、君、南のかたに出でたまひて、惟光を召して、 「この餅、かう数々に所狭きさまにはあらで、明日の暮れに参らせよ。今日は忌ま忌ましき日なりけり」 と、うちほほ笑みてのたまふ御けしきを、心とき者にて、ふと思ひ寄りぬ。惟光、たしかにも承らで、 「げに、愛敬の初めは、日選りして聞こし召すべきことにこそ。さても、子の子はいくつか仕うまつらすべうはべ らむ」 と、まめだちて申せば、 「三つが一つかにてもあらむかし」 とのたまふに、心得果てて、立ちぬ。「もの馴れのさまや」と君は思す。人にも言はで、手づからといふばかり、 里にてぞ、作りゐたりける。 君は、こしらへわびたまひて、今はじめ盗みもて来たらむ人の心地するも、いとをかしくて、「年ごろあはれと思ひ きこえつるは、片端にもあらざりけり。人の心こそうたてあるものはあれ。今は一夜も隔てむことのわりなかるべき こと」と思さる。 のたまひし餅、忍びて、いたう夜更かして持て参れり。「少納言はおとなしくて、恥づかしくや思さむ」と、 思ひやり深く心しらひて、娘の弁といふを呼び出でて、 「これ、忍びて参らせたまへ」 とて、香壷の筥を一つ、さし入れたり。 「たしかに、御枕上に参らすべき祝ひの物にはべる。あな、かしこ。あだにな」 と言へば、「あやし」と思へど、 「あだなることは、まだならはぬものを」 とて、取れば、 「まことに、今はさる文字忌ませたまへよ。よも混じりはべらじ」 と言ふ。若き人にて、けしきもえ深く思ひ寄らねば、持て参りて、御枕上の御几帳よりさし入れたるを、君ぞ、 例の聞こえ知らせたまふらむかし。 人はえ知らぬに、翌朝、この筥をまかでさせたまへるにぞ、親しき限りの人びと、思ひ合はすることどもありける。 御皿どもなど、いつのまにかし出でけむ。花足いときよらにして、餅のさまも、ことさらび、いとをかしう調へたり。 少納言は、「いと、かうしもや」とこそ思ひきこえさせつれ、あはれにかたじけなく、思しいたらぬことなき御心 ばへを、まづうち泣かれぬ。 「さても、うちうちにのたまはせよな。かの人も、いかに思ひつらむ」 と、ささめきあへり。 |
[第一段 源氏、紫の君と新枕を交わす]
二条院では、あちこち掃き立て磨き立てて、男も女も、お待ち申し上げていた。上臈の女房どもは、皆参上して、我も我もと美しく着飾り、化粧しているのを御覧になるにつけても、あの居並んで沈んでいた様子を、しみじみかわいそうに思い出されずにはいらっしゃれない。 お召物を着替えなさって、西の対にお渡りになった。衣更えしたご装飾も、明るくすっきりと見えて、美しい若い女房や童女などの、身なり、姿が好ましく整えてあって、「少納言の采配は、行き届かないところがなく、奥ゆかしい」と御覧になる。 姫君は、とてもかわいらしく身繕いしていらっしゃる。 「久しくお目にかからなかったうちに、とても驚くほど大きくなられましたね」 と言って、小さい御几帳を引き上げて拝見なさると、横を向いて笑っていらっしゃるお姿、何とも申し分ない。 「火影に照らされた横顔、頭の恰好など、まったく、あの心を尽くしてお慕い申し上げている方に、少しも違うところなく成長されていくことだなあ」 と御覧になると、とても嬉しい。 とても所在なく物思いに耽りがちだが、何でもないお忍び歩きも億劫にお思いになって、ご決断がつかない。 姫君が、何事につけ理想的にすっかり成長なさって、とても素晴らしくばかり見えなさるのを、もう良い年頃だと 、やはり、しいて御覧になっているので、それを匂わすようなことなど、時々お試みなさるが、まったくお分りにな らない様子である。 所在ないままに、ただこちらで碁を打ったり、偏継ぎしたりして、毎日お暮らしになると、気性が利発で好感がも て、ちょっとした遊びの中にもかわいらしいところをお見せになるので、念頭に置かれなかった年月は、ただそのような かわいらしさばかりはあったが、抑えることができなくなって、気の毒だけれど、どういうことだったのだろうか、 周囲の者がお見分け申せる間柄ではないのだが、男君は早くお起きになって、女君は一向にお起きにならない朝が ある。 女房たちは、「どうして、こうしていらっしゃるのだろうかしら。ご気分がすぐれないのだろうか」と、お見上げ申して嘆くが、君はお帰りになろうとして、お硯箱を、御帳台の内に差し入れて出て行かれた。 人のいない間にやっと頭を上げなさると、結んだ手紙、おん枕元にある。何気なく開いて御覧になると、 「どうして長い間何でもない間柄でいたのでしょう 幾夜も幾夜も馴れ親しんで来た仲なのに」 と、お書き流しになっているようである。「このようなお心がおありだろう」とは、まったくお思いになってもみなかったので、 「どうしてこう嫌なお心を、疑いもせず頼もしいものとお思い申していたのだろう」 と、悔しい思いがなさる。 昼ころ、お渡りになって、 「ご気分がお悪いそうですが、どんな具合ですか。今日は、碁も打たなくて、張り合いがないですね」 と言って、お覗きになると、ますますお召物を引き被って臥せっていらっしゃる。女房たちは退いて控えているので、お側にお寄りになって、 「どうして、こう気づまりな態度をなさるの。意外にも冷たい方でいらっしゃいますね。皆がどうしたのかと変に思うでしょう」 と言って、お衾を引き剥ぎなさると、汗でびっしょりになって、額髪もひどく濡れていらっしゃった。 「ああ、嫌な。これはとても大変なことですよ」 と言って、いろいろと慰めすかし申し上げなさるが、本当に、とても辛い、とお思いになって、一言もお返事をなさらない。 「よしよし。もう決して致しますまい。とても恥ずかしい」 などとお怨みになって、お硯箱を開けて御覧になるが、何もないので、「なんと子供っぽいご様子か」と、かわいらしくお思い申し上げなさって、一日中、お入り居続けになって、お慰め申し上げなさるが、打ち解けないご様子、ますますかわいらしい感じである。 [第二段 三日夜の祝い] その晩、亥の子餅を御前に差し上げた。こうした喪中の折なので、大げさにはせずに、こちらだけに美しい桧破籠などだけを、様々な色の趣向を凝らして持参したのを御覧になって、君は、南面にお出になって、惟光を呼んで、 「この餅を、このように数多くあふれるほどにはしないで、明日の暮れに参上させよ。今日は日柄が吉くない日であった」 と、ほほ笑んでおっしゃるご様子から、機転の働く者なので、ふと気がついた。惟光、詳しいことも承らずに、 「なるほど、おめでたいお祝いは、吉日を選んでお召し上がりになるべきでしょう。ところで子の子の餅はいくつお作り申しましょう」 と、真面目に申すので、 「三分の一ぐらいでよいだろう」 とおっしゃるので、すっかり呑み込んで、立ち去った。「物馴れた男よ」と、君はお思いになる。誰にも言わないで、手作りと言ったふうに実家で作っていたのだった。 君は、ご機嫌をとりかねなさって、今初めて盗んで来たような人の感じがするのも、とても興趣が湧いて、「数年来かわいいとお思い申していたのは、片端にも当たらないくらいだ。人の心というものは得手勝手なものだなあ。今では一晩離れるのさえ堪らない気がするに違いないことよ」とお思いになる。 お命じになった餅、こっそりと、たいそう夜が更けてから持って参った。「少納言は大人なので、恥ずかしくお思いになるだろうか」と、思慮深く配慮して、娘の弁という者を呼び出して、 「これをこっそりと、差し上げなさい」 と言って、香壷の箱を一具、差し入れた。 「確かに、お枕元に差し上げなければならない祝いの物でございます。ああ、勿体ない。あだや疎かに」 と言うと、「おかしいわ」と思うが、 「浮気と言うことは、まだ知りませんのに」 と言って、受け取ると、 「本当に、今はそのような言葉はお避けなさい。決して使うことはあるまいが」 と言う。若い女房なので、事情も深く悟らないので、持って参って、お枕元の御几帳の下から差し入れたのを、君が、例によって餅の意味をお聞かせ申し上げなさるのであろう。 女房たちは知り得ずにいたが、翌朝、この箱を下げさせなさったので、側近の女房たちだけは、合点の行くことがあったのだった。お皿類なども、いつの間に準備したのだろうか。花足はとても立派で、餅の様子も、格別にとても素晴らしく仕立ててあった。 少納言は、「とてもまあ、これほどまでも」とお思い申し上げたが、身にしみてもったいなく、行き届かない所のない君のお心配りに、何よりもまず涙が思わずこぼれた。 「それにしてもまあ、内々にでもおっしゃって下さればよいものを。あの人も、何と思ったのだろう」 と、ひそひそ囁き合っていた。 |
|
*葵の上の死後の場面である。ずっと左大臣邸にこもって喪に服していた源氏が、四十九日の弔いが済み、 院や中宮のもとを訪れてから、久しぶりに二条院の帰ってきた。十月一日の衣替えをへて、すっかり冬のしつらいにかわった二条院では 紫の君をはじめ若い女房や童女は美しく着飾って久しぶりの源氏を迎える。 *紫の君は14歳、すっかり美しく成長していた。源氏はこの美しい姫と今までのようにままごと状態ではいられなくなり、 まったく思いもしていなかった姫と強引に関係を結ぶ。 それは”朝、いつまでも起き出さない姫”という描写によって、暗示される。 信頼していた保護者が突然”男”に豹変した驚きと怒りで、姫は源氏を許さない。衣をかぶったまま、汗びっしょりになって寝所にこもって出てこない。 手を焼きながらもそれを新鮮に感じてかわいいと思っている源氏である。 *時は十月の最初の亥の日。亥の子餅で祝う日で、餅が献上されると、源氏は惟光を呼んで「今日は日が悪い、明日の暮れに持ってくるように」と言う。 いつも源氏の秘め事につきあい、後始末をするのに慣れている惟光は、すぐ察知して言う。「子の子餅はいくつがいいでしょうか。」と。 *亥の次の日は子の日。それが三日夜だと推測して、三日夜の祝いの餅を「子の子の餅」としゃれて見せたのだ。 惟光は、自宅こっそりと用意して、翌日の暮れに、少納言の娘でまだこどもっぽく感づかないであろう弁を呼んで、枕元に差し上げさせる。 *翌朝、この餅の箱をさりげなく部屋の外に出したので、人々は事の次第を知った。 源氏が姫君との結婚を正式のものと扱ったことを知って、少納言の乳母は感動する。 *六条御息所が悩みながら野宮に引きこもり、それでも心のどこかで、正妻葵の死に一縷の望みをかけているその時に、 源氏は藤壺のゆかりの姫と正式に結婚していたのだ。 退路を断たれた御息所は、舞台から去っていくことになる。 第四章 「六条御息所の悲劇 つづき 賢木の別れ」へつづく *このあと、源氏は順番が逆になったが、姫の裳着の儀式を行うことにする。その際、正式に姫の父兵部卿の宮に事の いきさつを告げ、腰結いの役を依頼する。姫の行方をさがすこともさっさと諦めていた父は、娘が源氏の妻になった事を知り、 わが身にも栄花のもたらされることを単純に喜ぶ。北の方は自分の娘よりも若紫が幸運になったことを悔しがる。 第三章 「中の品の女性たち 空蝉・夕顔・末摘花」へつづく (準備中) 第四章 「六条御息所の悲劇 愛とプライドのはざまで」へつづく 「原作を味わう 目次」へもどる 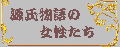 写真の無断転載はご遠慮下さい
写真の無断転載はご遠慮下さい
|