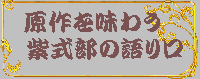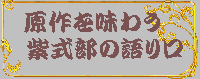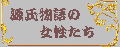| 原文 | 口語訳 |
六条わたりにも、とけがたかりし御気色をおもむけ聞こえたまひて後、ひき返し、なのめならむはいとほしかし。
されど、よそなりし御心惑ひのやうに、あながちなる事はなきも、いかなることにかと見えたり。
女は、いとものをあまりなるまで、思ししめたる御心ざまにて、齢のほども似げなく、人の漏り聞かむに、
いとどかくつらき御夜がれの寝覚め寝覚め、思ししをるること、いとさまざまなり。
霧のいと深き朝、いたくそそのかされたまひて、ねぶたげなる気色に、うち嘆きつつ出でたまふを、中将のおもと、
御格子一間上げて、見たてまつり送りたまへ、とおぼしく、御几帳引きやりたれば、御頭もたげて見出だしたまへり。
前栽の色々乱れたるを、過ぎがてにやすらひたまへるさま、げにたぐひなし。廊の方へおはするに、中将の君、御供に参る。
紫苑色の折にあひたる、羅の裳、鮮やかに引き結ひたる腰つき、たをやかになまめきたり。
見返りたまひて、隅の間の高欄に、しばし、ひき据ゑたまへり。うちとけたらぬもてなし、髪の下がりば、めざましくも、
と見たまふ。
「咲く花に移るてふ名はつつめども 折らで過ぎ憂き今朝の朝顔
いかがすべき」とて、手をとらへたまへれば、いと馴れてとく、
「朝霧の晴れ間も待たぬ気色にて 花に心を止めぬとぞ見る」
と、おほやけごとにぞ聞こえなす。
|
六条辺りの御方にも、気の置けたころのご様子をお靡かせ申し上げてから後は、うって変わって、
通り一遍なお扱いのようなのは気の毒である。けれど、他人でいたころのご執心のように、無理無体なことがないのも、
どうしたことかと思われた。
この女性は、たいそうものごとを度を越すほどに、深くお思い詰めなさるご性格なので、年齢も釣り合わず、人が漏れ聞いたら、
ますますこのような辛い君のお越しにならない夜な夜なの寝覚めを、お悩み悲しまれることが、とてもあれこれと多いのである。
霧のたいそう深い朝、ひどくせかされなさって、眠そうな様子で、溜息をつきながらお出になるのを、中将のおもとが、
御格子を一間上げて、お見送りなさいませ、という心遣いらしく、御几帳を引き開けたので、御頭をもち上げて外の方へ
目をお向けになっていらっしゃる。
前栽の花が色とりどりに咲き乱れているのを、見過ごしにくそうにためらっていらっしゃる姿が、評判どおり二人といない。
渡廊の方へいらっしゃるので、中将の君が、お供申し上げる。紫苑色で季節に適った、薄絹の裳、それをくっきりと結んだ腰つきは、
しなやかで優美である。
振り返りなさって、隅の間の高欄に、少しの間、お座らせになった。きちんとした態度、黒髪のかかり具合、見事なものよ、
と御覧になる。
「咲いている花に心を移したという風評は憚られますが
やはり手折らずには素通りしがたい今朝の朝顔の花です
どうしよう」
と言って、手を捉えなさると、まことに馴れたふうに素早く、
「朝霧の晴れる間も待たないでお帰りになるご様子なので
朝顔の花に心を止めていないものと思われます」
と、主人のことにしてお返事申し上げる。
|
六条の貴婦人のお話
*「夕顔」の巻は薄幸のヒロイン夕顔を描く巻だが、実はこの巻にはもう一人の不幸な女主人公六条の女君が初めて登場する巻でもあった。
「夕顔」の住む五条は、六条の女君の所へ通う道筋だった。
夕顔の女を惟光に探索させている間に、六条の女の元へ通う源氏の姿が描かれる。
しかし、それは女の所へ”行く”源氏の姿ではなく、女の元から朝”帰っていく”源氏である。
女は自分の元から”離れていく”源氏を見送るというシチュエーションで、われわれ読者の前に登場するのだ。
これはこの六条の女君の置かれた状況を象徴する場面である。
*この女君の正体は知れない。しかし、二人の関係の始まりは語られる。
最初はなかなかうちとけず源氏にとって気の置ける方だったのだ。その方を自分になびかせるまでの源氏の積極さが暗示されている。
「よそなりし御心惑ひのやうに、あながちなる事はなきも」つまり、相手が自分の手に届かないところにいるときは、
強引に自分の思いを相手にぶつけ、相手をなびかせたのだ。
それが、いざ、その方が自分の思い通りになると、うってかわって「なのめなる」態度になる。
女にとっては、自分がなびいてしまった後こそ、「あながちなる」態度で愛情を表現して欲しいのに。これでは恋愛ゲームの賭けもののよう。
*語り手は女の性格を言う、「いとものをあまりなるまで、思ししめたる御心ざまにて」と。執着心が強く、思いこみの強い方なのだ。
しかも、女は年上で、その年齢差による世間体を気にしている。そのために、なかなか若い源氏になびかなかったのだ。
気位が高く、思慮分別のあるこの方を愛人として手に入れてしまった源氏は、ややこの女君をもてあまし始めている。
*男君が帰る朝、女は眠むたげを装い、ため息をつきながらしぶしぶにじり出る。思いくんじているのだ。
その女主人に対して、格子を上げ、几帳をどかして見送るように促すのは、女房である。、「中将のおもと」と名前が出て来る女房はただ者ではない。
*女君の目に、朝霧のなかに咲き乱れる秋草を背景にその花よりもさらにうつくしい若者の姿が映る。「この美しい若者を私は愛してしまったのだ。
けれど、もう、この若者の心には私のいる場所は無くなろうとしている。この若者はあかるい外の世界の中へ出て行く。私をこうして取り残して・・。」
*語り手の視点は、女君の視線の彼方に移動していく。廊を渡っていく源氏。その姿はもう部屋の中の女の目からは見えない。
*お供について行く女房の「中将の君」。紫苑色の薄い裳をまとった美しい若女房だ。
その女房の身体を押さえてその場に座らせて、歌を詠みかける源氏。「手折らずに素通りしがたい朝顔だ」と言う。
「いと馴れてとく(まことに馴れたふうに素早く)」返歌する中将の君。今日のところは「おほやけごとにぞ聞こえなす。」
いつもは私的な関係の歌を詠みかわす仲なのだ。
*この時代の女房仕えをするということは、時に男主人のお手つきになることなのだ。「召人(めしうど)」と呼ばれ、
「愛人」にさえ数えられない存在なのだ。
この「中将の君」が源氏の「召人」であることを露骨に表した場面である。
*源氏が女君にしつように迫った時、手引きをしたのがこの女房なのだろう。「将を射んとすれば先ず馬を射よ」という。なかなか自分になびかない女君に忍び寄るには、
女房を手なずけるのが常道である。手なづけ方は源氏にとっては色仕掛けが一番簡単だ。なにしろ源氏に言い寄られてなびかない若い女はいないのだから。
*初めは女君に近づく手段だったこの女房との戯れだったが、女君の情が重く感じられる今は、かえって、こちらが気安い楽しみになっている。
*女主人の寝所の傍らに侍る女房に、女君と源氏との心のすれ違いが感じられないはずがない。だからこそ、無理に見送りをさせるということもさせていたのだ。
帰り際に自分に戯れる主人の「愛人」である源氏。中将の心に、「このお方は自分の方を好んでいるのだ。」とほんの少しの優越感がわき上がっていないはずがない。
*女君との気の重い一夜を過ごした後の、源氏の軽々しい女房への戯れ姿は、かなたの女君の姿が見えないからこそ、
読者には、無惨な女君が想像できる。
*六条に住むこの女君は誰なのか、それをあかさないまま、「夕顔」の物語は進行し、
源氏は五条の粗末な家に住む不思議な若い女を知って、通い出す。六条の女君と対照的な、
なよなよとした、自分を主張しないこの女におぼれていく。
女君の夜離れの悩みはますます深くなる。
*その女君の正体が明かされたのが、「葵」巻冒頭であった。
|
「葵」の巻 1 「御代替わりー六条御息所の身分が明かされる」
| 原文 | 口語訳 |
世の中かはりて後、よろづもの憂く思され、御身のやむごとなさも添ふにや、軽々しき御忍び歩きもつつましうて、ここもかしこも、おぼつかなさの嘆きを重ねたまふ、報いにや、なほ我につれなき人の御心を、尽きせずのみ思し嘆く。
今は、ましてひまなう、ただ人のやうにて添ひおはしますを、今后は心やましう思すにや、内裏にのみさぶらひたまへば、立ち並ぶ人なう心やすげなり。折ふしに従ひては、御遊びなどを好ましう、世の響くばかりせさせたまひつつ、今の御ありさましもめでたし。ただ、春宮をぞいと恋しう思ひきこえたまふ。御後見のなきを、うしろめたう思ひきこえて、大将の君によろづ聞こえつけたまふも、かたはらいたきものから、うれしと思す。
まことや、かの六条御息所の御腹の前坊の姫君、斎宮にゐたまひにしかば、大将の御心ばへもいと頼もしげなきを、「幼き御ありさまのうしろめたさにことつけて下りやしなまし」と、かねてより思しけり。
院にも、かかることなむと、聞こし召して、
「故宮のいとやむごとなく思し、時めかしたまひしものを、軽々しうおしなべたるさまにもてなすなるが、いとほしきこと。斎宮をも、この御子たちの列になむ思へば、いづかたにつけても、おろかならざらむこそよからめ。心のすさびにまかせて、かく好色わざするは、いと世のもどき負ひぬべきことなり」
など、御けしき悪しければ、わが御心地にも、げにと思ひ知らるれば、かしこまりてさぶらひたまふ。
「人のため、恥ぢがましきことなく、いづれをもなだらかにもてなして、女の怨みな負ひそ」
とのたまはするにも、「けしからぬ心のおほけなさを聞こし召しつけたらむ時」と、恐ろしければ、かしこまりてまかでたまひぬ。
また、かく院にも聞こし召し、のたまはするに、人の御名も、わがためも、好色がましういとほしきに、いとどやむごとなく、心苦しき筋には思ひきこえたまへど、まだ表はれては、わざともてなしきこえたまはず。
女も、似げなき御年のほどを恥づかしう思して、心とけたまはぬけしきなれば、それにつつみたるさまにもてなして、院に聞こし召し入れ、世の中の人も知らぬなくなりにたるを、深うしもあらぬ御心のほどを、いみじう思し嘆きけり。
|
帝の御代が替わってから後、何事につけ億劫にお思いになり、ご身分の高さも加わってか、軽率なお忍び歩きも
遠慮されて、あちらでもこちらでも、ご訪問のない嘆きを重ねていらっしゃる、その罰であろうか、相変わらず自分
につれない方のお心を、どこまでもお嘆きになっていらっしゃる。
ご譲位後の今では、以前にも増して、臣下の夫婦のようにご一緒においでになるのを、今后は不愉快に
お思いなのか、宮中にばかりおいでになるので、競争者もなく気楽そうである。折々につけては、管弦の御遊などを
興趣深く、世間に評判になるほどにお催しあそばしたりして、現在のご生活のほうがかえって結構である。ただ、
春宮のことだけをとても恋しく思い申し上げなさる。ご後見役のいないのを、気がかりにお思い申されて、大将の君
に万事ご依頼申し上げるにつけても、源氏の君は気の咎める思いがする一方で、嬉しいとお思いになる。
それはそうと、あの六条御息所のご息女の前坊の姫宮が、斎宮にお決まりになったので、大将のご愛情も
まことに頼りないので、「幼いありさまに託つけて伊勢に下ってしまおうかしら」と、前々からお考えになっているのだった。
桐壺院も、このような事情があると、お耳にあそばして、
「(御息所は)故宮がたいそう大切にお思いで、ご寵愛なさったのに、軽々しく並の女性と同じように扱っている
そうなのが、気の毒なこと。斎宮をも、わが皇女たちと同じように思っているのだから、どちらからいっても疎略に
しないのがよかろう。遊び半分の気持ちで、このような浮気をするのは、まことに世間の非難を受けるにちがいない事である」
などと、御機嫌が悪いので、またご自分でも、仰せのとおりだと思わずにはいられないので、恐縮して控えていらっしゃる。
「相手の人のために、恥となるようなことはせず、どの夫人をも波風が立たないようにとりあつかって、
女の恨みを受けてはならぬぞ」
と仰せになるにつけても、「あるまじき大それた不埒さをお聞きつけあそばした時には」と恐ろしいので、恐縮し
て退出なさった。
また一方、このように院におかれてもお耳に入れられ、仰せられるにつけ、相手のご名誉のためにも、
自分にとっても、好色がましく困ったことであるので、以前にも増して大切に思い、気の毒にお思い申し上げていら
れるが、まだ表面立っては、特別にお扱い申し上げなさらない。
女も、不釣り合いなお年のほどを恥ずかしくお思いになって、うちとけなさらない様子なので、それに
(源氏が)遠慮しているような態度をとって、院のお耳にお入れになり、世間の人も知らない者がいなくなってしまっているのに、
深くもないご愛情のほどを、(御息所は)ひどくお嘆きになるのだった。
|
御息所の扱いを父院にたしなめられる源氏
*「葵」巻の冒頭である。「世の中かわりて後」という出だしで、
桐壺帝の退位、朱雀帝の即位があったことが知らされる。源氏の昇進もあって大将になっていることがすぐあとで分かる。
父が上皇としてまだ威光を放っているとしても、やはり、今上帝とその外戚の右大臣方の勢が強くなってくるのはいなめない。
かすかな心理的圧迫感を感じている源氏である。
*藤壺に中宮の位を奪われて悔しがっていた弘徽殿女御は、今、天皇の母として皇太后の位を得た。宮中に住んだまま、藤壺のいる院には来ない。
相変わらず怒りはおさまっていない模様だ。覇気のない息子=帝をうまく操縦しなければならないから、宮中で目を光らせているのだ。
*譲位した父は院の御所で、藤壺と二人、普通の夫婦のような睦まじい生活を楽しんでいて、在位中よりずっと楽しそうだ。
源氏が藤壺に密かに会うチャンスは皆無になったといってよい。
*「まことや、」と、語り手は忘れていたことを今思い出したかのように語り出した。「かの六条の御息所の御腹の
前坊姫宮」が「斎宮」になったと。物語の聞き手には初めての情報だ。
①「夕顔」の巻に登場したあの六条にすむ女君は、東宮妃だった。
②東宮は帝位に即くことなくもう故人となっていた。③東宮との間に一人の姫宮が誕生していた。④御代替わりにあたって
その姫宮が斎宮に定められた。
*源氏のその方に対してのふるまいが相手の身分にふさわしくないという話が、父桐壺院の耳にも入っていて、父から厳しく叱責された。
「いづれをもなだらかにもてなして、女の怨みな負ひそ(どの女性をもなだらかにとりあつかって、女の恨みをかうようなことをするな)」
と忠告する父である。
この方自身、若い時、誰の忠告も聞き入れずに桐壺更衣を寵愛したことを知っている私たちはおもわず笑ってしまう言葉だ。
今40代半ば、堂々たる貫禄の院が、息子に対して女性問題の忠告をしている。
*その息子は、かつて父の目を盗んで、その妻を犯していた。何も知らない父は生まれた子を我が子と信じて、その子に帝位を受け渡すために、
自分の威勢が及ぶ間に譲位し、その子を東宮にした。東宮が無事即位するまでは、臣下の源氏に後見するように命じている。
源氏は恐ろしくもあり、また我が子への後見を託されたことをうれしくも思う。
*一方、あの六条の女君は、源氏の愛の薄さを嘆きながら、わが身を源氏から引き離すために、娘の斎宮に付き従って
伊勢に下ってしまおうかとおもう。
*大和朝廷の天武帝は壬申の乱後、朝廷の安泰を祈願するため、伊勢神宮に娘の大来皇女をお仕えさせた。初代伊勢斎宮である。
大来皇女は天武帝崩御により任を解かれて帰京するが、そのときは最愛の弟大津皇子が政略争いで義母(のちの持統天皇)にやぶれ死罪となっていた。
伊勢斎宮は、現地に下り、御代替わりがあるまで帰京できない。六条の御息所が伊勢に下るなら、それは生きて
都に帰らないことになるかもしれない。源氏との永遠の別れを意味するのだ。
*しかし、「下りやしなまし」と使っている助動詞「まし」は、「反実仮想」とよばれる用法の助動詞で、
これは基本的には「事実に反することを仮に想定して考える」という用法である。つまり、女君の「伊勢に下ろうかしら」
は事実に反した想定、つまり本心から出た気持ちではないのだ。
女君の本心は「源氏に会いたい、その愛を十分に受けたい」という思いなのだ。
|
「葵」の巻 2 「御禊見物の車争いー御息所の苦悩の深まり」
| 原文 | 口語訳 |
そのころ、斎院も下りゐたまひて、后腹の女三宮ゐたまひぬ。帝、后と、ことに思ひきこえたまへる宮なれば、筋ことになりたまふを、
いと苦しう思したれど、こと宮たちのさるべきおはせず。儀式など、常の神わざなれど、いかめしうののしる。
祭のほど、限りある公事に添ふこと多く、見所こよなし。人がらと見えたり。
御禊の日、上達部など、数定まりて仕うまつりたまふわざなれど、おぼえことに、容貌ある限り、下襲の色、表の袴の紋、馬鞍までみな調へたり。
とりわきたる宣旨にて、大将の君も仕うまつりたまふ。かねてより、物見車心づかひしけり。
一条の大路、所なく、むくつけきまで騒ぎたり。所々の御桟敷、心々にし尽くしたるしつらひ、人の袖口さへ、いみじき見物なり。
大殿には、かやうの御歩きもをさをさしたまはぬに、御心地さへ悩ましければ、思しかけざりけるを、若き人びと、
「いでや。おのがどちひき忍びて見はべらむこそ、栄なかるべけれ。おほよそ人だに、今日の物見には、大将殿をこそは、あやしき山賤さへ見たてまつらむとすなれ。遠き国々より、妻子を引き具しつつも参うで来なるを。御覧ぜぬは、いとあまりもはべるかな」
と言ふを、大宮聞こしめして、
「御心地もよろしき隙なり。さぶらふ人びともさうざうしげなめり」
とて、にはかにめぐらし仰せたまひて、見たまふ。
|
そのころ、斎院も退下なさって、皇太后腹の女三の宮がおなりになった。帝、大后と、特にお思い申し上げていらっしゃる宮なので、
神にお仕えする身におなりになるのを、まことに辛くおぼし召されたが、他の姫宮たちで適当な方がいらっしゃらない。
儀式など、規定の神事であるが、盛大な騷ぎである。祭の時は、規定のある公事に付け加えることが多くあり、この上ない見物である。お人柄によると思われた。
御禊の日、上達部など、規定の人数で供奉なさることになっているが、声望が格別で、美しい人ばかりが、下襲の色、表袴の紋様、
馬の鞍のまですべて揃いの支度であった。特別の宣旨が下って、大将の君も供奉なさる。かねてから、見物のための車が心待ちしているのであった。
一条大路は、隙間なく、恐ろしいくらいざわめいている。ほうぼうのお桟敷に、思い思いに趣向を凝らした設定、女性の袖口までが、大変な見物である。
大殿におかれては、このようなご外出をめったになさらない上に、ご気分までが悪いので、考えもしなかったが、若い女房たちが、
「さあ、どんなものでしょうか。わたくしどもだけでこっそり見物するのでは、ぱあっとしないでしょう。関係のない人でさえ、今日の見物には、まず大将殿をと、賎しい田舎者までが拝見しようと言うことですよ。遠い国々から、妻子を引き連れ引き連れして上京して来ると言いますのに。御覧にならないのは、あまりなことでございますわ」
と言うのを、大宮もお聞きあそばして、
「ご気分も少しよろしい折です。お仕えしている女房たちもつまらなそうです」
と言って、急にお触れを廻しなさって、ご見物なさる。
|
斎院の御禊行列見物へ
*先に話に出た「斎宮」とは伊勢神宮にお仕えする神女であり、ここで話題の「斎院」とは賀茂神社にお仕えする神女である。
朱雀帝即位にあたって新斎院を決めるのに、適当な人がなく、桐壺院は弘徽殿女御の生んだ皇女二人のうちの下の皇女を差し出すことになった。
母とすると気が進まなかったろう。
せめて、御禊の行列は盛大にとの配慮から、行列に供奉する上達部には特別に源氏を奉仕させることになった。
*賀茂神社の祭礼の本番の数日前に、新斎院が賀茂川で禊ぎをする。その行列が内裏から一条大路を練っていくのを見物するのは、
身分の上下を問わず楽しみなことだったが、今年は行列に源氏が供奉するというセンセーショナルな話題が加わって、大騒ぎである。
良い場所を取ろうと、朝早くから装い立てた牛車がびっしりと大路を埋めていた。
*その御禊行列の当日、左大臣邸では、結婚十年目にして葵が懐妊し、気分が優れない。不断から深窓にこもる令嬢だった葵は、
まして今具合が悪いので、夫の晴れ姿を見に行こうとも思っていなかったが、それでは若い女房たちが承知しない。
「おのがどちひき忍びて見はべらむこそ、栄なかるべけれ。」自分たちだけで身分相応に見物するなんてつまらない。
今日の中心人物源氏の正妻且つ庇護者の左大臣家一行として見物するのでなければ面白くないと口々に言う。宮仕え人の虚栄心を
発揮できる最大のチャンスなのだ。
使用人を気持ちよく働かせるのは主人の役目、と母大宮は娘に見物を勧め、急きょ外出の準備を進める。
これが事件を引き起こし、ひいては娘を死に追いやることとなるとも知らずに・・。
|
| 原文 | 口語訳 |
日たけゆきて、儀式もわざとならぬさまにて出でたまへり。隙もなう立ちわたりたるに、よそほしう引き続きて立ちわづらふ。
よき女房車多くて、雑々の人なき隙を思ひ定めて、皆さし退けさするなかに、網代のすこしなれたるが、下簾のさまなどよしばめるに、
いたう引き入りて、ほのかなる袖口、裳の裾、汗衫など、ものの色、いときよらにて、ことさらにやつれたるけはひしるく見ゆる車、
二つあり。
「これは、さらに、さやうにさし退けなどすべき御車にもあらず」
と、口ごはくて、手触れさせず。
いづかたにも、若き者ども酔ひ過ぎ、立ち騒ぎたるほどのことは、えしたためあへず。おとなおとなしき御前の人びとは、
「かくな」など言へど、えとどめあへず。
斎宮の御母御息所、もの思し乱るる慰めにもやと、忍びて出でたまへるなりけり。つれなしつくれど、おのづから見知りぬ。
「さばかりにては、さな言はせそ」「大将殿をぞ、豪家には思ひきこゆらむ」
など言ふを、その御方の人も混じれば、いとほしと見ながら、用意せむもわづらはしければ、知らず顔をつくる。
|
日が高くなってから、お支度も特別なふうでなくお出かけになった。隙間もなく立ち混んでいる所に、物々しく引き連ねて場所を探しあぐねる。
身分の高い女車が多くて、下々の者のいない隙間を見つけて、みな退けさせた中に、網代車で少し使い馴れたのが、下簾の様子などが趣味がよいうえに、
とても奥深く乗って、わずかに見える袖口、裳の裾、汗衫などの衣装の色合、とても美しくて、わざと質素にしている様子がはっきりと分かる車が、
二台ある。
「この車は、決して、そのように押し退けたりしてよいお車ではありませぬ」
と、言い張って、手を触れさせない。
どちらの側も、若い供人同士が酔い過ぎて、争っている事なので、制止することができない。年輩のご前駆の人々は、「そんなことするな」などと言うが、とても制止することができない。
斎宮の御母御息所が、何かと悩んでいられる気晴らしにもなろうかと、こっそりとお出かけになっているのであった。何気ないふうを装っているが、自然と分かった。
「それくらいの者に、そのような口はきかせぬぞ」「大将殿を、笠に着ているつもりなのだろう」
などと言うのを、その方の供人も混じっているので、気の毒にとは思いながら、仲裁するのも面倒なので、知らない顔をする。
|
葵上の車が御息所の車をどかす
*身分の高い方の外出には相応の準備がいる。
「儀式もわざとならぬさまにて(外出の支度も特別でなく)」とあるが、それでも、左大臣家にふさわしい牛車(この場合姫君の常用は糸毛車であろう)を何台も用意する。
姫君だけでなくお供の女房のための牛車(ひとだまひ)も主人家が用意するのだ。
美しい色合いの下簾をたらし、牛にも立派な手綱をつけるだろう。牛飼いわらわや供人の人数をそろえるには、数時間はかかっただろう。
前々から準備怠りなかった世間の人々は、当日は朝のうちから外出しているのに、左大臣家の外出は日が高くなってからになった。
*当然、一条大路は見物の車や人々でぎっしりだ。そこに後から出かけた左大臣家の一行は、行列見物のための一等地
(身分の高い女房車が立ち並んでいて、下々の者が居ない所)を選んで、前からそこにいる車をどかす。相手は天下の一の人左大臣家だ。
みな渋々ながら場所をゆずる。
*そういう見物の車の中に、粗末な網代車でありながら下簾の色合い、乗り手の裳の色合いなどセンス抜群で、それゆえ、
かえってやつし車である事が一目でわかる車が2台あって、その車がどうしても場所を去ろうとしない。
左大臣家に向かって、「このお車は、さようにさしのけなどしてよいお車ではない」と供人が強硬なのだ。
*お忍びの車なのに、乗り手の身分の高さを供人が示してしまうのは、なんとも筋が通らないのだが、それが身分社会というものなのだろう。
ところが、左大臣家の家来は相手の身分が知れないのだから、自分たちを押し通そうとする。振舞酒でよった供人たちが騒ぎあう。
*そのうち、左大臣家の供人が、相手の供人に見知った顔を見つけてしまった。やつし車の主は六条御息所だと知った。
*相手が六条御息所だとわかるとなおさら勢いづいて、ここぞとばかりに、騒ぎ出す。
かねがね、家に寄りつかない婿の源氏の通い所を不快に思っている左大臣家だ。その主人の意を体した行動をするの
が家来たちである。やつしている事を暴き出して、侮辱しにかかる。「源氏の愛人だとおもって、源氏の威光を着ているのだろう」と。
*牛車に乗っている女性たちに外の争いの声は丸聞こえのはずだが、女主人はどちらも声を発しない。
顔を見せないのと同様、声も聞かせないのが礼儀だとはいえ、ハプニングに対してはなんらかの采配をふるっても良さそうだが、
御息所はやつしているのだから、仕方がないが、葵の上も外出などしたことがないし、自分が一番よい場所を取るのが当然と思っているから、
家来に任せたままだ。
*左大臣家一行の中に、実は源氏の家来も加わっていたという。正室様の外出のお供にかり出されているのだ。
これだけでも、いかに左大臣家の威光が高いかが誇示されている。
その源氏の供人は、時には六条御息所の邸にも源氏のお供で行っている。御息所の気位の高さも十分知っているのだ。
けれど、ここで多勢に無勢の御息所の肩をもとうとすると、とばっちりが身に降りかかりそうで面倒なので、
知らん顔をする。
|
| 原文 | 口語訳 |
つひに、御車ども立て続けつれば、ひとだまひの奥におしやられて、物も見えず。心やましきをばさるものにて、
かかるやつれをそれと知られぬるが、いみじうねたきこと、限りなし。榻などもみな押し折られて、すずろなる車の筒にうちかけたれば、
またなう人悪ろく、くやしう、「何に、来つらむ」と思ふにかひなし。
物も見で帰らむとしたまへど、通り出でむ隙もなきに、「事なりぬ」と言へば、さすがに、つらき人の御前渡りの待たるるも、
心弱しや。「笹の隈」にだにあらねばにや、つれなく過ぎたまふにつけても、なかなか御心づくしなり。
げに、常よりも好みととのへたる車どもの、我も我もと乗りこぼれたる下簾の隙間どもも、さらぬ顔なれど、ほほ笑みつつ後目にとどめたまふもあり。
大殿のは、しるければ、まめだちて渡りたまふ。御供の人びとうちかしこまり、心ばへありつつ渡るを、おし消たれたるありさま、こよなう思さる。
「影をのみ御手洗川のつれなきに 身の憂きほどぞいとど知らるる」
と、涙のこぼるるを、人の見るもはしたなけれど、目もあやなる御さま、容貌の、「いとどしう出でばえを見ざらましかば」と思さる。
|
とうとう、お車を立ち並べてしまったので、副車の奥の方に押しやられて、何も見えない。悔しい気持ちはもとより、
このような忍び姿を自分と知られてしまったのが、ひどく悔しいこと、この上ない。榻などもみなへし折られて、場違いな車の轂に掛けたので、
またとなく体裁が悪く悔しく、「いったい何しに、来たのだろう」と思ってもどうすることもできない。
見物を止めて帰ろうとなさるが、抜け出る隙間もないでいるところに、「行列が来た」
と言うので、そうは言っても、恨めしい方のお通り過ぎが自然と待たれるというのも、意志の弱いことよ。
「笹の隈」でもないからか、そっけなくお通り過ぎになるにつけても、かえって物思いの限りを尽くされる。
なるほど、いつもより趣向を凝らした幾台もの車が、自分こそはと競って見せている出衣の下簾の隙間隙間も、何くわぬ顔だが、
ほほ笑みながら流し目に目をお止めになる者もいる。大殿の車は、それとはっきり分かるので、真面目な顔をしてお通りになる。
お供の人々がうやうやしく、敬意を表しながら通るのを、すっかり無視されてしまった有様、この上なく堪らなくお思いになる。
「今日の御禊にお姿をちらりと見たばかりで そのつれなさにかえって我が身の不幸せがますます思い知られる」
と、思わず涙のこぼれるのを、女房の見る目も体裁が悪いが、目映いばかりのご様子、容貌が、「一層の晴れの場でのお姿を見なかったら」とお思いになる。
|
ひと目だけ、あの方の姿を・・・
*御息所の乗った車は、左大臣家の女房車の後ろに追いやられ、しかもながえを載せておく台は壊されてしまった。
牛車は車軸一本の両脇に大きな車輪が2つ着いただけの構造だ。それ自体では平衡を保てないから、引いている時は牛の背中に
長い柄の先(くびき)をつなぎ、牛の背の高さと車の台の高さを合わせて平衡を保つ。止めてある時は牛をはずし、ながえを
台に乗せて平らにする。
*今、台がないのだから、そのままでは乗り手は滑り台にのっているようなもので、滑り落ちてしまう。
仕方がないので、その場に居合わせた誰かの車の車軸に柄をたてかけさせてもらった。
みっともない事この上ない。
*源氏の姿を一目見たいという一念から、忍んで出て来たのに、そのお忍びを暴露された上に、このはずかしい様。
その場を逃れようにも、大混雑で車を動かす事が出来ない。
*「ああ」と思っていると、「行列が来た」という人々の声が聞こえた。「あの方が通る、姿を見たい」と思わずはやる心。
こんな状態でもまだ、「ひと目みたい」という思いが勝るとは、女心の弱さよ、と語り手の女房は痛烈だ。
*簾越しに必死で外を見ると、重なった車のほんのわずかの隙間からちらっと見えた馬上の源氏の姿。
儀式の装束で特別にきらびやかな源氏の姿。その源氏を見ようとしてわれもわれもと女房車から人がこぼれんばかりに
簾際による。この車あの車と源氏は心当たりの女性の車を見いだしては、流し目を送り、合図する。
葵上の車の前では、流し目ではなく、威儀をただして左大臣家への敬意を払って通っていく。愛する妻への笑顔はなく。
葵上は源氏を見ているのだろうか。夢中な女房をかたわらに車の奥で、気分が悪く伏せっていたのではないだろうか。
*わずかな隙間から必死で見つめる御息所には、源氏の振るまいがみな見て取れた。でも、源氏はとうとう自分には目もくれない。
自分が来ている事など源氏は知らないし、他の車の奥のやつし車など目に入らないのは当然だ。
けれど、御息所はそれが源氏の自分への愛の薄さであるかのように思ってしまう。
「影をのみ御手洗川のつれなきに 身の憂きほどぞいとど知らるる」おもわずこぼれる涙を、
同乗の女房に見られるのを恥と感じじっと堪えようとする。
*しかししかしである。源氏に顧みられない身を辛く思うその一方で、「目もあやなる御さま、容貌の、
『いとどしう出でばえを見ざらましかば』と思さる」御息所でもある。「見ざらましかば口惜しからまし」なのだ。
たとえ、相手が自分を見てくれなくても、自分はあの人の姿を一目見たから、やはりふるえるほどうれしいのだ。
*心の渇きのように、「あの人を見たい」と渇望する。そのこころにひとしずくあの人の姿が沁みていった。
恋に苦しむくるしい心がこれほどあざやかに描かれている場面も古今そうないだろう。
|