| 原文 | 口語訳 |
|
いづれの御時にか、女御、更衣あまたさぶらひたまひけるなかに、いとやむ
ごとなき際にはあらぬが、すぐれて時めきたまふありけり。
|
どの帝の御代であったか、女御や更衣が大勢お仕えなさっていたなかに、
たいして高貴な身分ではない方で、きわだって御寵愛をあつめていらっしゃる方があったそうだ。
|
昔むかしのお話
*「いづれの御時・・けり。」と物語は語られ始める。今となっては誰も体験した事のない昔のお話ですよ。だから私たちの知らない不思議な事も起こっていたのです。そう語り出す語り手は、お話の主人公の父と母との紹介を始める。
*舞台は女御や更衣が大勢お仕えしている後宮。父は世を治める方ー帝、母は最高の身分ではない方で、寵愛は独り占めにしている方。
*最初の昔話「竹取物語」は「今は昔、竹取の翁といふものありけり。野山にまじりて竹を取りつゝ、よろづの事に使ひけり。」と貧しい翁(主人公の養父)を登場させ、竹の中から見いだした輝く子を「妻の女にあづけて養はす。」
*「一寸法師」も「桃太郎」も「山に柴刈り」「川に洗濯」をする貧しい翁・媼の生活を描きながら、ふたりに授けられたこの世ならぬ聖性を負った子を登場させている。
*「源氏物語」もその昔語りの形式をふまえた語り出しだ。しかし、舞台は粗末な山里ならぬ最高に輝かしい場所宮中である。父の仕事は「まつりごと」母の仕事はその父に仕えること。華やかな場所に展開する数奇な物語のはじまり。
|
| 原文 | 現代語訳 |
|
はじめより我はと思ひ上がりたまへる御方がた、めざましきものにおとしめ
嫉みたまふ。同じほど、それより下臈の更衣たちは、ましてやすからず。朝夕
の宮仕へにつけても、人の心をのみ動かし、恨みを負ふ積もりにやありけむ、
いと篤しくなりゆき、もの心細げに里がちなるを、いよいよあかずあはれなる
ものに思ほして、人のそしりをもえ憚らせたまはず、世のためしにもなりぬべ
き御もてなしなり。
|
最初から自分こそはと気位い高くいらっしゃった女御方は、
不愉快な者だと見くだしたり嫉んだりなさる。同じ程度の更衣や、その方より下の更衣たちは、
いっそう心穏やかでない。朝晩のお側仕えにつけても、他の妃方の気持ちを不愉快ばかりにさせ、
嫉妬を受けることが積もり積もったせいであろうか、とても病気がちになってゆき、
何となく心細げに里に下がっていることが多いのを、帝はますますこの上なく不憫な方とお思いなされて、
誰の非難に対しても行動を慎みなさることがおできになれず、後世の語り草にもなってしまいそうなお取り扱いぶりである。
|
女だけで暮らす日常生活
*「・・けり」ではじまったこのお話は、2センテンス目でがらりと変って、「嫉みたまふ」と現在形になる。以後時制は物語の「現在」が基準となる。
お話の聴き手は、「昔々」のその場に一気に投げ込まれて、目の前に展開するごとくに話に聞き入る事になる。「今昔物語」などの説話の語りと決定的に違う「源氏物語」の記述だ。
*後宮に住む帝の夫人たちは、女御と更衣。それに仕える女房達。役人もすべて女官のみ。唯一出入りする男は帝一人。宦官という役人を発明しなかった日本の後宮は女だけの世界である。
*「おなじほど、それより下臈の更衣たち」とあることでこの人の身分は「更衣」だと分かる。更衣の中では上の身分。ひとりだけ、寵を受けるこの人は上からも下からも嫉まれる。
「女御」は三位相当、父は大臣クラス以上。だから身分の高さをよりどころにこの人を軽蔑できる。下の身分は、女御に「まして心やすからず」である。身分に頼れない彼女たちは自分の魅力によって帝の心をつかまなければならない位置にいる。
自分にかなわなかった事をやすやすと実現したこの人を思うと、胸がむかむかしてくるのだ。
*帝の所にいる時間は1日のわずか、それ以外の時間を過ごす後宮の日常で、開放式の建物の中の話し言葉は丸聞こえ、わざと聞こえよがしのうわさ話、けなし言葉、横目使いの冷たい仕草。
日々それを見聞きして、気に病んで体の具合が悪くなって実家に戻りがちなこの人。
それを知って帝はますますいとおしんで行く。帝の溺愛は程度を越えていく。
*帝とは個人ではない、世の秩序を維持する役目を負った存在であり、後宮の夫人たちもまたそれぞれに女でしかできない役目を負って奉仕しているのである。
その世界で、帝が個人として一人の女性だけを愛する事はルール違反なのであり、世の乱れの元なのだ。
|
| 原文 | 現代語訳 |
|
上達部、上人なども、あいなく目を側めつつ、いとまばゆき人の御おぼえ
なり。「唐土にも、かかる事の起こりにこそ、世も乱れ、悪しかりけれ」と、
やうやう天の下にもあぢきなう、人のもてなやみぐさになりて、楊貴妃の例
も引き出でつべくなりゆくに、いとはしたなきこと多かれど、かたじけなき
御心ばへのたぐひなきを頼みにてまじらひたまふ。
|
上達部や殿上人なども、むやみやたらに目をそらしそらしして(横目でにらみにらみして)、
とても眩しい(正視できない)ほどの御寵愛である。「唐国でも、このようなことが原因となって、国も乱れ、悪くなったのだ」と、
しだいに国中でも、困ったことに、人々のもてあましの種となって、楊貴妃の例までも引き合いに出されそうになってゆくので、
(更衣には)たいそういたたまれないことが数多くなっていくが、もったいない御愛情の類のないのを頼みとして、
宮仕え生活をしていらっしゃる。
|
楊貴妃のごとき「悪女」 実は心弱き人
*女御の父は、親王・摂関・大臣、更衣の父は大納言・中納言・参議など上達部。そしてその子息達は殿上人。娘達は父や兄たちの期待を背負って、天皇の男子を産む為に後宮に入ったのだ。
*だから帝のお呼びがなければ、そのチャンスもなく、父兄の願望を果たせない。ことは単なる女の争いではないのだ。
*清涼殿での管弦の遊びにしろ、歌合わせの場にしろ、帝の脇に侍る女性が自分の娘以外であれば、父達はやきもきし、「またあの女か」と思う。
*「目を側む」とは、瞳をまなじりに寄せること、つまり横目になる事だが、これの意味は二通りになる。①顔は正面で「目を側む」なら、「目をそらす」
②顔は横向きで「目を側む」なら、「横目でにらむ」になる。ここでの父兄の心理からは、「横目でにらむ」だろう。
*主人の貴族が不利になる事はそこの家に出入りする下僕下女達にも大事件。主人の世が開けなければ、そこに仕える自分たちの生活も浮かばれなくなる。ことは単なるゴシップでは済まないのだ。
悪意を込めて話に尾ひれが付き、この人は世間の噂では「楊貴妃」並みの天下を揺るがす大悪女となりはてる。
*その実、この人は、後宮のさまざまな嫌がらせの中で、心が痛み弱々しくなる一方の人だ。たった一つの頼みは帝の愛だけだと語り手は言う。ではこの人の後見の父はどうしてる?
|
| 原文 | 現代語訳 |
|
父の大納言は亡くなりて、母北の方なむいにしへの人のよしあるにて、親う
ち具し、さしあたりて世のおぼえはなやかなる御方がたにもいたう劣らず、な
にごとの儀式をももてなしたまひけれど、とりたててはかばかしき後見しなけ
れば、事ある時は、なほ拠り所なく心細げなり。
|
父親の大納言は亡くなって、母親の北の方が古い家柄の人で教養ある人なので、
両親とも揃っていて、今現在の世間の評判が勢い盛んな方々にもたいしてひけをとらず、
どのような事柄の儀式にも対処なさっていたが、これといったしっかりとした後見人がいないので、
こと改まった儀式の行われるときには、やはり頼りとする人がなく心細い様子である。
|
後見役なき桐壺更衣
*聴き手の関心が更衣の父に向かったところで、おもむろに語り手は情報を出す。「父の大納言は亡くなりて」と。
*「父大納言」は予想通りだったが、「亡くなりて」とはなんと言うことだろう、娘が寵愛を受けて利益を得るはずの父も兄もいないなんて。それではなぜこの人は入内したのか?大きな謎を残して、語り手は母北の方を紹介する。
*「旧家出身で教養のある人なので、何事の儀式にも対処する」と。それはどういうことか?宮中で催される様々な儀式・遊び事はすべて前例に則り、しきたりが定められている。
文書化されず口伝えに維持されている部分もおおい。いわゆる有職故実だ。旧家というのは経済力はなくとも文化の力を持っている。
季節にふさわしい重ねの色目、飾り物のしつらい、かづけものにも風流の粋をきかせて用意する。たった一人の後見役である母は必死におのれの身につけた
文化と教養によって、他の方々に対抗する。
*しかし、風流をきそうような遊びの場面は、まだそれでもなんとかこなしていけたが、本格的な宮中行事はむずかしい。端午の節会、重陽の節会、豊明の節会など年に何度となくおこなわれる
大きな宮中行事には、後宮の主たちは季節にあった裳唐衣の正装で列席する。その際のお付きの女房達の装束も主が供与するものだ。しかも装束は「出だし衣」によって衆人の目にさらされる。
後見の経済力に任せて美々しく新調する他の方々の衣装に比べて見劣りする事この上ない。
*更衣は自分自身だけでなく母の無念の思いの分もあわせて、さらにつらさが募る。
*ここまできて、さらに大きな疑問が聴き手にわき起こってくる。なぜ、後見のいないこの人はあえて後宮に入ったのか?なにが目的なのか?この謎は更衣の死後あかされる。
|
「桐壺」の巻 2 「光る皇子誕生・立ちはだかる弘徽殿女御」
| 原文 | 現代語訳 |
|
先の世にも御契りや深かりけむ、世になく清らなる玉の
男御子さへ生まれたま ひぬ。いつしかと心もとながらせたまひて、急ぎ参らせて
御覧ずるに、めづらか なる稚児の御容貌なり。
|
前世でも御宿縁が深かったのであろうか、この世にまたとなく美しい玉のような男の御子までが
お生まれになった。(帝は)早く早くとじれったくおぼし召されて、急いで参内させて御覧なさると、
たぐい稀な嬰児のお顔だちである
|
玉の男御子誕生
*この世での男と女のめぐり会いはすべて前世の宿縁により決定されていると、仏教の教えは告げる。帝の度を超した寵愛も宿縁のなせるわざであったのだ。
さらに宿縁の深さは二人の間に、①「世になく清らなる玉の」②「男」③「御子」までも誕生させたと、語り手は言う。
*
出産は里(実家)で行う。病気、出産、生理などは不浄とされて、聖なる場所宮中では許されなかったのであるが、逆にこれは女性の健康を気遣う配慮がなされている仕組みだ。
(出産を実家でというこの風習は現代の核家族化の日本でも当然のようにおこなわれている。生理休暇という現代の労基法にある休暇も日本のこの伝統を受け継いでいる日本独自の休暇である。)
*母親の産後の肥立ちと嬰児の成長(すくなくとも首が据わるまで3ヶ月)をみてからゆっくりと参内するのが普通であった。帝は「いつしかと心もとながらせたまひて」例よりも早く参上させるのであった。
「いつしか」という語は現代語にもあり、「いつのまにか」と言う意味で使われる。古代ではまだ生じていないことを「早く」生じて欲しい
と願う気持ちでも使われる。「こころもとなし」という形容詞は「心が基無し」で「心がしっかりしない」さま。「気がかりだ、じれったい、落ち着かない気分だ」の意。
我が子の誕生も間近で見る事の出来ない帝という存在のじれったさが伺える。
参内した我が子を見ると、噂に違わぬ美貌の御子であった。帝の喜びはいかほどか。ますます母子への寵愛は増すであろう。
更衣に対する寵愛ぶりでさえ、世を揺さぶりかねなかったのに、皇子誕生という事態はまたまた事件が起こりそうな予感。
*同一人の帝を父とした皇子の身分は母親の身分で決まる。同じ身分の母同士ならやはり生まれ順だ。それでは帝に他の皇子はいるのか?
|
| 原文 | 現代語訳 |
|
一の皇子は、右大臣の女御の御腹にて、寄せ重く、疑ひなき儲の君と、世にも
てかしづききこゆれど、この御にほひには並びたまふべくもあらざりければ、お
ほかたのやむごとなき御思ひにて、この君をば、私物に思ほしかしづきたまふこ
と限りなし。
|
第一皇子は、右大臣の娘の女御がお生みになった方なので、後見がしっかりしていて、
まちがいなく皇太子になられる君だと、世間でも大切にお扱い申し上げるが、この御子の輝く美しさにはお並びになりようも
なかったので、(父帝は)一通りの大切なお気持ちであって、この若君の方を、個人的な秘蔵っ子としておかわいがり
なさることはこの上ない。
|
右大臣の女御登場
*一の皇子は存在した。しかも右大臣家の女御がお産みになっている。家柄と言い、誕生順と良い、間違いない皇太子候補だ。
*しかし、美しさでは更衣の産んだ「玉の御子」には全くかなわない。そこに父帝の愛が注がれている。
*「一の皇子」に対する帝の態度を「おほかたのやむごとなき御思ひ」だと語り手はいう。
それに対して、この御子は「私物に思ほしかしづきたまふ」だという。帝という存在が、子供に対する愛情の上で「公」と「私」とにはっきり区別されているのだ。
*このように書き分ける作者紫式部は誰をモデルにしているのか、興味あるところである。あとの、
更衣に対する後宮のいじめぶりが明らかに「大鏡」などに記録されている史実をふまえている事を考えると、この寵愛ぶりも「村上帝」の芳子に対する寵愛ぶりがモデルとなっていると考えられる。
としたら、芳子に対する安子(師輔女)にあたる存在として、一の皇子の女御を聴き手は予測する。
|
| 原文 | 口語訳 |
初めよりおしなべての上宮仕へしたまふべき際にはあらざりき。おぼえいとや
むごとなく、上衆めかしけれど、わりなくまつはさせたまふあまりに、さるべき
御遊びの折々、何事にもゆゑある事のふしぶしには、まづ参う上らせたまふ。あ
る時には大殿籠もり過ぐして、やがてさぶらはせたまひなど、あながちに御前去
らずもてなさせたまひしほどに、おのづから軽き方にも見えしを、この御子生ま
れたまひて後は、いと心ことに思ほしおきてたれば、「坊にも、ようせずは、こ
の御子の居たまふべきなめり」と、一の皇子の女御は思し疑へり。人より先に参
りたまひて、やむごとなき御思ひなべてならず、皇女たちなどもおはしませば、
この御方の御諌めをのみぞ、なほわづらはしう心苦しう思ひきこえさせたまひけ
る。
|
(更衣は)最初から女房並みの帝のお側用をお勤めなさらねばならない身分ではなかった。
評判もとても高く、上流人の風格があったが、(帝が)むやみにお側近くにお召しなされ過ぎて、
しかるべき管弦の御遊の折々や、何事につけ雅趣ある催しがあるたびごとに、まっさきに参上させなさる。
ある時にはお寝過ごしなされて、そのまま伺候させておきなさるなど、むやみに御前から離さずに御待遇なされた
うちに、自然と身分の低い女房のようにも見えたが、この御子がお生まれになって後は、
たいそう格別にお考えおきなされるようになっていたので、「東宮坊にも、わるくすると、この御子がおなりになるかもしれない」
と、第一皇子の母女御はお疑いになっていた。誰よりも先に御入内なされて、(帝の)大切にお考えなさることは一通りでなく、
皇女たちなども生まれていらっしゃるので、この御方の御諌めだけは、さすがにやはりうるさいことだが無視できないことだと、
お思い申し上げなされるのであった。
|
変わる帝の態度 疑い出す一の女御
*この小節の表現は、桐壺の巻の中でも一番読みにくい所である。「桐壺」の巻自体が、「光る君」を主人公とした
長編物語の構想を立てた段階で、大急ぎで書き加えた主人公誕生話のあらすじとして読める。
だから、冒頭から、更衣の死までをひたすら大きなタッチでなぞっていくだけ。とかく有名作品は冒頭が名文だという教える側の先入観で、「桐壺」を読まされる高校生が「古典は難解でつまらない」と思いこまされる要因となってしまう。
はっきり言って、「桐壺」の巻はつまらない。
*だから、この小節も難解で悪文である。もし、ここだけで一つの短編小説を書こうと思ったら、もっとずっと短いセンテンスをたたみ込んで、場面が展開していくことだろう。
そうは言っても、実はここで言おうとしていることは、興味深い。少し、分析する価値はありそうだ。
*この4つのセンテンスから成る小節は、3つの時を含んでいる。「御子誕生以後」が現在である。その前の2つの時に遡って更衣に対する評価の変化が述べられる。
*まず、入内(じゅだい)当初である。「初めよりおしなべての上宮仕へしたまふべき際」ではなかったのだ。つまり、ある時点で「上宮仕へ」の扱いになってしまったのである。
「おぼえいとやむごとなく、上衆めかしけれ」だったという。「おぼえ」はここでは敬語「御」がないから、廻りの人々からの更衣の評判である。後宮の女性達の中で、この更衣は大納言家出身の身分にふさわしい敬意を払われていたのである。
*それがある時帝の目にとまり、特別の寵愛を受けるようになると、帝はとにかくこの方を側から放したがらない。
管弦の遊びなどの催しの際におそばに召すだけならとにかく、寝所にはべらせたその翌朝も、局に下がることを認めず、
朝餉のときも、着替えの時も(これは本来の更衣の仕事だったはず!!)そばにいさせて、奉仕させたがる。この仕事は当時では「上宮仕へ」の女官の仕事であった。
だから、更衣はその身分より低い扱いをされていることになり、そこに周囲の軽蔑の目が向けられていた。
まして、一の皇子の女御は自分の高い地位に座って、更衣など歯牙にかけずに済んでいたのだ。
*ところがである。この「玉の御子」誕生後、帝の態度が変わったのだ。母子に対する愛情は一層募っているはずなのに、
「いと心ことに思ほしおきてたれば」、つまり帝は心の中になにか考えを秘めて自分の行動を律していくようになった。以前のようにお側去らずの扱いをしなくなったのだ。
この変化に一の皇子の女御は反応した。
*御子の母が「上宮仕へ」の如き存在であれば、御子そのものが軽んじられる。帝が更衣の扱いを本来の身分に戻した。いや、御子の母として並みの更衣以上に敬意を払われるべき存在にした。
と言うことはこの御子を特別な存在とする布石なのではないか。「一の皇子の皇太子の座があやうい」。母女御は我が子の危機に対して果然として立ち上がった。
*語り手は興味津々で聞き入る聴き手に知らせる。「人より先に参りたまひて、やむごとなき御思ひなべてならず、皇女たちなどもおはしませば、」と。
それでは一の皇子の女御は、最初に入内した女御だったのだ。とすれば年齢は帝より上のはず。この人の諌言は帝も聞かざるを得ない。
今まで、後宮の他の妃たちの更衣に対する嫌がらせを黙認する程度だったこの方が、いまは表だって直接帝に言上しているのだ。
更衣排斥は、もう公認された。
*それにしても、と敏感な聴き手は思う。「一の女御さまは右大臣家の姫様なんだわ。左大臣家にはお姫様はいないの?」
臣下の一の人は「左大臣」。「右大臣」は大臣と言っても左大臣の補佐役。後見の重さは左大臣にはかなわないはず。この疑問は光る君成人の場であかされることになる。
あらすじのような書き方と言いながら、結構、計算尽くで描いている作者である。
|
| 原文 | 現代語訳 |
|
かしこき御蔭をば頼みきこえながら、落としめ疵を求めたまふ人は多く、わが
身はか弱くものはかなきありさまにて、なかなかなるもの思ひをぞしたまふ。御
局は桐壺なり。あまたの御方がたを過ぎさせたまひて、ひまなき御前渡りに、人
の御心を尽くしたまふも、げにことわりと見えたり。参う上りたまふにも、あま
りうちしきる折々は、打橋、渡殿のここかしこの道に、あやしきわざをしつつ、
御送り迎への人の衣の裾、堪へがたく、まさなきこともあり。またある時には、
え避らぬ馬道の戸を鎖しこめ、こなたかなた心を合はせて、はしたなめわづらは
せたまふ時も多かり。事にふれて数知らず苦しきことのみまされば、いといたう
思ひわびたるを、いとどあはれと御覧じて、後涼殿にもとよりさぶらひたまふ更
衣の曹司を他に移させたまひて、上局に賜はす。その恨みましてやらむ方なし
|
(更衣は)もったいない御庇護をお頼り申してはいるものの、軽蔑したり落度を探したりなさる方々は多く、
ご自身はか弱く何となく頼りない状態で、なまじ御寵愛を得たばっかりにしなくてもよい物思いをなさる。
お局は桐壺である。(帝が)おおぜいのお妃方の前をお素通りなさって、そのひっきりなしのお素通りに、
お妃方が気をもめ尽くしなさるのも、なるほどごもっともであると見えた。(更衣が)参上なさるにつけても、
あまり度重なる時々には、打橋や、渡殿のあちこちの通路に、けしからぬことをたびたびして、送り迎えの女房の着物の裾が、
がまんできないような、とんでもないことがある。またある時には、どうしても通らなければならない馬道の戸を鎖して閉じ籠め、
こちら側とあちら側とで示し合わせて、(進むも退くもならないように)困らせなさることも多かった。
何かにつけて数知れないほど辛いことばかりが増えていくので、たいそうひどく思い悩んでいるのを、
(帝は)ますますお気の毒におぼし召されて、後凉殿に以前から伺候していらっしゃった更衣の部屋を他に移させなさって、
上局としてお与えなさる。その方の恨みはなおいっそうに晴らしようがない。
|
「なかなかなるもの思ひー更衣の死の予感」
*後宮で四面楚歌の更衣を表して語り手は「なかなかなるもの思ひをぞしたまふ」という。形容動詞「なかなか(中中)なり」はなかなか含蓄のある語だ。
小学館古語辞典では「①中途半端なさま。どっちつかずだ。②なまじっかだ。なまはんかだ。かえって・・・しないほうがよい。」などと訳語をあげている。
*それを上記の現代語訳では「なまじ御寵愛を得たばっかりにしなくてもよい物思いをなさる。」と訳した。もっと言えば、「いっそご寵愛などなければよかったのに・・とまでお思いなさる」だ。
まあ、穏やかな訳語として、上記が適当だと思うが、それにしても、いったいこのお方は帝を愛していたのだろうか。一方的な寵愛を受けて、困惑していたという読み方は出来ないか。これは後に登場する藤壺にも紫上にもいえることだ。女主人公で自分の意志で男を愛したのはだれとだれか。考えてみると面白いテーマだ。
*閑話休題、後宮あげての更衣いじめはどのようにおこなわれるのか。語り手はここでこの人の局を教える。なんと「桐壺」なのだ。
帝の居所清涼殿から一番遠いところ。
*「ひまなき御前渡り」は、帝が、昼間、更衣の局にわたっていくこと。他の方々のお部屋の前を素通りなさっていくのだ。部屋の中で息を殺している方々の姿が透視できる。
そして「参う上りたまふ」のは更衣。夜、帝の寝所に参上なさるのである。お付きの女房をともなって、この方、あの方の前を通って、清涼殿に向かう更衣。帝のお渡りには何も出来ず歯がみするだけの人々が
手ぐすね引いて待っているのがこのとき。
*御殿の中廊下(馬道)を通っている時、一行が廊下の中に入ったタイミングをはかって、前方の扉がギイッとしまる。落ちる掛けがねの音。ハッとして後方を見るとあざ笑うように閉まる扉。
真っ暗闇に閉じこめられて叫び声を上げる事も出来ず、じっと相手の気の済むのを待つほかない。
*そして時には、廊下にまきちらしてある耐え難い汚物。一行の衣の裾がよごれ、そのままではとても御前に伺候できない。
当時、トイレという独立した場所はなかったのだ。部屋の中に壺が用意してある、そこに用を足したのだ。朝一番に女官(にょうかん)が始末する。
手近にある一番効果的なものを使ってのいやがらせだ。
*トイレがなかったというのは、現代の我々にはちょっと想像が付かないことだが、これはあのフランスのルイ王朝(18世紀ころ)でも同じこと。水洗トイレのためのパリの名高い下水道は、オーストリアから嫁いだマリー・アントワネットがパリの町や宮殿のあまりの汚さに改革させたもの。
イタリアの映画、ルキノ・ビスコンテイ監督の「山猫」は近世貴族の一族の栄光と没落を描いた映画だったが、
豪華絢爛たるパーテイーの開かれている大広間の隣の部屋には、高さ1mくらいの大きなこれも見た目は豪華な壺が、何本も並んでいた。
*およそ考えられる限りの悪質な嫌がらせを受けていく更衣であった。(この嫌がらせの仕方の数々もまた作者の創作ではない、大鏡の中に記述されている有名な後宮のお話にもとづいている。
こういう形で、人々の知っている週刊誌種レベルのスキャンダルを取り込んで描いていったのが第一部である。読み手におもねる姿勢が感じられる。)
*更衣の到着が遅いのを迎えに行かせた命婦(帝付きの女房)からの報告を聞いて(とは、私の推測)事態を知る帝。
いちいち桐壺に戻らなくても済むように、上局を与えようとする。弘徽殿と藤壺に住むお方以外には用意されていないはずの上局なのだ。
どこにしようかと探して、後涼殿に曹司(部屋)を持っていた更衣をどかしたのだ、と語り手は言う。「その恨みましてやらむ方なし」
帝の配慮は更衣にとってはみな逆効果となる。
*それにしても、この帝にはいったい何人の妃がいたのだろう。後涼殿は帝の食事の準備や日常生活のための作業をする為の建物で、後宮ではない。
そこにまで更衣の曹司があるということは、後宮の決まり以上に妃が多いということ。上達部達が競って自分の娘を妃に差し出したいとおもう程の力量のある天皇ということになる。
後に見るように在位期間の長さ、天皇として政務を取り仕切る力量といい、桐壺帝のモデルはあの「延喜式」を制定し、平安期の政治制度を確立した天皇醍醐帝だといわれるゆえんである。
「更衣の死ー御子の成長」
*さて、上局を頂こうがそんなことで解決されない後宮あげてのいじめに遭い、更衣がどのようになっていくか、もう予想は付く。
御子3歳の袴着を見届けるように、更衣の命はつきていく。夏であった。盆地である京都の夏は、湿気がつよく耐え難い。もうその暑さに耐えるエネルギーは残っていなかった。
ほんの数日で、衰弱していく更衣。
*作者紫式部は、二人の別れを、長恨歌になぞらえて描く。男の教養である漢詩の長恨歌などを引いて描く所に、学者一家に生まれその才を「男の子だったら」と父に嘆息させたという作者の自慢がのぞいている。
実際、この物語が女こどものものでなく、一条帝や道長らを愛読者とさせたのは、こういう部分の力があったろうが、
今読むと鼻につく。第二部以降にはこのような部分は姿を潜めている。
*唯一、この別れの場面での表現として私が注目するのは、語り手によるこの人の呼称がこの場面で「女」とされることである。御子を産んで以後、「御息所」と、
皇子をうんだ人の一般名称で呼ばれてきた更衣が、帝と別れの歌を交わすここでは、「女は」と書かれるのだ。最後の場で、身分のしがらみを離れて、ただ「男」と「女」の二人だけの世界に入っていることを表す表現だ。
このあと、紫式部は男女の山場でこの表現をしばしば用いる。「賢木」の巻で六条御息所と源氏のわかれの場でも「女は」「男は」と書く。
*しかし、これさえも紫式部の独創とは言いがたいことは、「和泉式部日記」で式部が主人公である自分を「女は」と書いている事で分かる。
いわば、同時代の女流作家達が共同で編み出した表現効果なのだろう。
*更衣の死後、母のいる里に帝の名代として靫負の命婦が弔問に訪れる。ここは、話のテンポが他と違っていて、時が止まったような静けさでゆっくりと描かれる。
「桐壺」巻中の名文と言われるだけのことはある。帰参を急ぐ命婦をひきとめて、母北の方は、真実を言う。娘の死は「横ざまなる死」だと。
「横死」とは、「災害や殺害などによる死。非業の死」。母は言うのだ、娘はいびり殺されたのだと。そしてそうなった原因を作った帝を恨む。
こんなことになるなら入内などさせなかったのに。
*聴き手のいだいていた疑問、なぜ父がいないのに入内したのかという疑問には、母はこう説明する。「父大納言の期待の娘で、入内は大納言が亡くなる時の遺言だったから」
やや説得不足の感のある説明だが、作者は、非業の死を遂げ、幼子にその面影すら残さずに死んだ母という存在を創り出した。
*更衣の退出時には宮中にとどめられた御子だったが、母の死という喪に服する為には里に下がらなければならない。祖母のもとで暮らす御子を早く内裏に戻したい帝であったが、
娘の唯一の形見であると思いこむ祖母はなかなか放さない。御子が参内するのは何年もたって、祖母がなくなる少し前であった。
ここから、藤壺入内とあわせて、御子の成人までの話を一気に語っておわる「桐壺」の巻である。
*「大納言であった父が死んでいる人」はこのあともう一人登場する。その女性も正妻のいじめに遭い、亡くなっている。そしてその女性亡き後、祖母によって育てられていた遺児がやがて光る君の前に登場してくることになる。
|
第二章
「紫のゆかり 藤壺~若紫へ」へつづく (準備中)
「原作を味わう 目次」へもどる
[HOME]]
[紅梅組]
[リンク集]
(c)copyright 2004 ゆうなみ
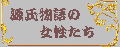 写真の無断転載はご遠慮下さい
写真の無断転載はご遠慮下さい
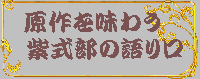
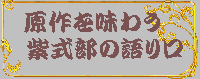
写真の無断転載はご遠慮下さい