| 原文 | 口語訳 |
|
年月に添へて、御息所の御ことを思し忘るる折なし。「慰むや」と、さるべき人びと参らせたまへど、「なずらひに思さるるだにいとかたき世かな」と、疎ま
しうのみよろづに思しなりぬるに、先帝の四の宮の、御容貌すぐれたまへる聞こえ高くおはします、母后世になくかしづききこえたまふを、主上にさぶらふ典侍
は、先帝の御時の人にて、かの宮にも親しう参り馴れたりければ、いはけなくおはしましし時より見たてまつり、今もほの見たてまつりて、「亡せたまひにしに
御息所の御容貌に似たまへる人を、三代の宮仕へに伝はりぬるに、え見たてまつりつけぬを、后の宮の姫宮こそ、いとようおぼえて生ひ出でさせたまへりけれ。
ありがたき御容貌人になむ」と奏しけるに、「まことにや」と、御心とまりて、ねむごろに聞こえさせたまひけり。
|
年月がたつにつれて、御息所のことをお忘れになる折がない。
「心慰めることができようか」と、しかるべき女性方をお召しになるが、
「せめて準ずる程に思われなさる人さえめったにいない世の中だ」と、
厭わしいばかりに万事がお思いなされていたところ、先帝の四の宮で、
ご容貌が優れておいでであるという評判が高くいらっしゃる方で、
母后がまたとなく大切にお世話申されていられる方を、主上にお仕えする典侍は、
先帝の御代からの人で、あちらの宮にも親しく参って馴染んでいたので、
(四の宮が)ご幼少でいらっしゃった時から拝見し、今でもちらっと拝見して、
「お亡くなりになった御息所のご容貌に似ていらっしゃる方を、
三代の帝にわたって宮仕えいたしてまいりまして、一人も拝見できませんでしたが、
后の宮の姫宮さまは、たいそうよく似てご成長あそばしていますわ。
世にもまれなご器量よしのお方でございます」と奏上したところ、
「ほんとうにか」と、お心が止まって、丁重に礼を尽くしてお申し込みあそばしたのであった。
|
先帝の四宮登場~更衣にうり二つのお方
*「時が悲しみを癒す」とよく言うが、桐壺帝にとっては、「時」も更衣の死の悲しみを癒すことはなく、
他の女性を召して気を紛らわせようとしてみるが、更衣と比較する気持ちばかり働いて、ますます更衣の愛しさが募り他の女性が厭わしくなる。召された女性にしてみればたまったものではない。
気持ちの晴れない帝は本来の仕事である政治もおろそかになる。更衣に対する寵愛ぶりも異例であったが、亡き後の落胆ぶりも異例である。
なんとか帝の気持ちを更衣からそらす道はないか。そこに、一人天皇三代にわたって仕えたという典侍が登場する。かなりの年配の典侍だ。
*「先帝の四宮が亡き更衣にそっくりに成長なさっている」と。この典侍は「先帝の御時の人」であるという。自身の言葉では「三代の宮仕え」をしていると言っている。
この典侍の仕えた三代の天皇とは現「桐壺帝」とその父「一院」と「先帝」であろう。
*「一院」と「先帝」のどちらが先に天皇であったか?前後関係は文中では明示されていないが、この「先帝」は「院」と呼ばれていないことから、在位中に死去したと見られる。
そして「桐壺帝」即位時の「東宮」が桐壺帝の弟宮であるらしいことから、この「先帝」には皇位を継承するにふさわしい皇子がいなかったことになる。
ここに登場する「四の宮」の兄「兵部卿宮」は「后腹」でありながら、立太子できなかった親王だ。後見役の重しがなかったとみられる。
さきの問、天皇の順としては、「一院」ー「先帝」ー「桐壺帝」ー「先の東宮(桐壺帝弟宮)」ー「東宮(桐壺帝一の皇子)」という順位を想定できる。
*それでは、典侍の仕えた「先帝の御時の人」という表現との関係は?これについては、「典侍」役が「先帝」から引き続いているということで、
「三代の宮仕え」は「典侍」以前からの宮仕えを含んだ言い方ではないかと思う。
*さて、「桐壺更衣にうり二つ」のことばに心を動かされた帝であった。帝じきじきに入内の要請がある。「聞こゆ」は「言ふ」の謙譲語で「四の宮」方を敬う。「させ給ふ」の最高敬語は「言ふ」動作主である帝を敬う。
|
| 原文 | 口語訳 |
母后、「あな恐ろしや。春宮の女御のいとさがなくて、桐壺の更衣の、あらはにはかなくもてなされにし例もゆゆしう」と、思しつつみて、すがすがしうも思
し立たざりけるほどに、后も亡せたまひぬ。
心細きさまにておはしますに、「ただ、わが女皇女たちの同じ列に思ひきこえむ」と、いとねむごろに聞こえさせたまふ。さぶらふ人びと、御後見たち、御兄
の兵部卿の親王など、「かく心細くておはしまさむよりは、内裏住みせさせたまひて、御心も慰むべく」など思しなりて、参らせたてまつりたまへり
|
母后は、「まあ怖いこと。東宮の母女御がたいそう意地が悪くて、桐壺の更衣が、
露骨に亡きものにされてしまった例も不吉で」と、おためらいなさって、すらすらとご決心もつかなかったうちに、
母后もお亡くなりになってしまった。
(姫君が)心細い有様でいらっしゃるので、「ただ、わが姫皇女たちと同列にお思い申そう」と、
たいそう丁重に礼を尽くしてお申し上げあそばす。お仕えする女房たちや、御後見人たち、
ご兄弟の兵部卿の親王などは、「こうして心細くおいでになるよりは、内裏でお暮らしあそばして、
きっとお心が慰むように」などとお考えになって、参内させ申し上げなさった。
|
母后の心配・よりどころのない内親王は後宮へ
*ところが桐壺帝の申し込みを聞いて恐れたのが、「四の宮」の母后。
「桐壺更衣がいびり殺された所に娘はやれない」という本音が語られる。「春宮の女御」とは「弘徽殿の女御」。今は息子の地位も安泰となり、後宮では誰はばかる事なく力を揮っている。
その人のことを「さがなくて」と言えるのは、先帝の后という身分があるからこそ。
*その母后が死んでしまった。庇護者がなく心細い状態になるのが内親王という存在。これはあの常陸宮の姫「末摘花」の例が語るところである。
帝は母后の憂慮を解消するために言う、「後宮に仕える人としてでなく、私の娘扱いでもてなそう」と。
そして、ここに登場するのが兄兵部卿の宮。帝の熱意を利用しない手はないとばかりに、妹に入内を勧める。
*「①参ら(せ)/②たてまつり/③たまふ」と三つの敬語が重なる表現がある。主語は兵部卿の宮、動作の対象は目的語(・・を)としての四の宮と、
補語(・・へ)としての帝。兵部卿の宮が四の宮を宮中(帝のところ)へ行かせる、の意。①の「参る」で、帝に対する敬意、②で行かせる対象四の宮への敬意、
③で動作主兵部卿の宮への敬意、と3人を敬う表現である。
「参らす」は一語の謙譲語としても使われ、「参る」より謙譲の度合いがたかい。ここで帝に対する敬意だから対象に最高に敬意を払う「参らす」が使われるべきかと考えるところだが、
文意から「せ」は使役の用法となる。「源氏物語」の表記法では、使役の「す・さす」と、敬意をしめす「す・さす」とは二重には使わない。
文意としての使役の用法を優先している。これが「大鏡」になると、「取ら・せ・させ・たまふ」のように、
使役の助動詞と尊敬の助動詞と二つの「す・さす」を重ねている。
*高貴な人が自分のしたい行動を臣下にさせる意の「す・さす」の使役の用法が、結果として高貴な人自身のしたかった動作の実現になる所から、
転じてその人自身に対する最高敬語として「せ・たまふ」「せ・おはす」の用法がでたのであろう。
だから本来それは同一の助動詞であったから、二重に使用するという事は語感的にありえなかったのであろう。
*それが、時代が下り、身分を強調し、敬意を重々しく表現したい欲求が出て来た時に、別々の助動詞として重ねて使う表現が出て来たのではないか。
「大鏡」は、「源氏物語」より時代が下ること100年あまりで成立したと見られる。
*以上は私の見解であるが、日本語の語感の美しさをただ一人で追求して見せた紫式部には、たとえ、「せ・させ・たまふ」の表現がその時代に行われていたにしても、
このサ行音の擦れる音の重複はさけたかったはずだ。
*文法的な話題はこのくらいで、登場人物について。妹の入内を熱心に勧める兄兵部卿に注目しよう。
母は娘の精神的苦労を心配した。兄は生活上の心配をする、というよりも妹が入内した場合の自身の政治的効果を優先したのだ。
先細りの「先帝」の血筋にこだわってはいられない。時の人がこぞって娘を差し出す現天皇の政治力の一端に自分が連なるには、願ってもないチャンスだ。
こういう計算をしたことが明白な記述ではないか。
*この人こそ、藤壺の血を伝えた姫「若紫」の父なのだ。
|
| 原文 | 口語訳 |
|
藤壺と聞こゆ。げに、御容貌ありさま、あやしきまでぞおぼえたまへる。これは、人の御際まさりて、思ひなしめでたく、人もえおとしめきこえたまはねば、
うけばりて飽かぬことなし。かれは、人の許しきこえざりしに、御心ざしあやにくなりしぞかし。思し紛るとはなけれど、おのづから御心移ろひて、こよなう思
し慰むやうなるも、あはれなるわざなりけり。
|
藤壺と申し上げる。なるほど、ご容貌や姿は不思議なまでに(更衣に)よく似ていらっしゃった。
この方は、ご身分も一段と高いので、評判も素晴らしくて、お妃方もお貶み申すこともおできになれないので、
誰に憚ることなく何も不足ない。あの方(更衣)は、周囲の人がお許し申さなかったところに、
御寵愛が憎らしいと思われるほど深かったのである。(更衣に対する)ご愛情が紛れるというのではないが、
自然とお心が移って行かれて、格段にお慰みになるようなのも、人情の性というものであった。
|
更衣との比較・「身分」に守られた「藤壺」
*この方のお入りになるのは飛香舎(藤壺)。清涼殿に上局のあるお部屋の主。最高の身分として入内なさった。
あの弘徽殿の女御も手がでない。「うけばりて飽かぬことなし(誰に憚ることなく飽き足らない点がない)」若くても、堂々としていらっしゃる。
身分も後見もなくひっそりと心病んでいた方(桐壺更衣)とはずいぶんの違いだ。
*帝は次第に心を移し、更衣に対する悲しみが紛れていく。この人は誰に憚ることなく寵愛できる。
心の鬱屈が晴れていくのだった。政治的に考えるならば、外戚に顧慮することなく、
天皇親政をするにふさわしい妃を得たのだ。
|
| 原文 | 口語訳 |
源氏の君は、御あたり去りたまはぬを、ましてしげく渡らせたまふ御方は、
え恥ぢあへたまはず。いづれの御方も、われ人に劣らむと思いたるやはある、とりどりにいとめでたけれど、
うち大人びたまへるに、いと若ううつくしげにて、切に隠れたまへど、おのづから漏り見たてまつる。
母御息所も、影だにおぼえたまはぬを、「いとよう似たまへり」と、典侍の聞こえけるを、
若き御心地にいとあはれと思ひきこえたまひて、常に参らまほしく、「なづさひ見たてまつらばや」とおぼえたまふ。
|
源氏の君は、お側をお離れにならないので、誰より頻繁にお渡りあそばす御方は、
恥ずかしがってばかりいらっしゃれない。どのお妃方も自分が人より劣っていると思っていらっしゃる人があろうか、
それぞれにとても素晴らしいが、お年を召しておいでになるのに対して、(この藤壺は)
とても若くかわいらしい様子で、頻りにお姿をお隠しなさるが、自然と漏れ拝見する。
母御息所は、顔かたちすらご記憶でないのを、「大変によく似ていらっしゃる」と、典侍が申し上げたので、
幼心に(藤壺を)とても慕わしいとお思い申し上げなさって、いつもお側に参りたく、
「親しく拝見したい」と思われなさる。
|
母の面影を持つ人を慕う若宮
*さて、話題は御子に移る。ここで御子は「源氏の君」と呼ばれている。藤壺入内の少し前、父帝は御子を源氏にしていたのだ。
「源氏」姓は親王が臣下に下る時に与えられる姓のひとつ。在原や橘・平などもある。
7歳の時、御子を高麗の相人に占わせた帝は、その予言を顧慮して、御子を皇族からはずしたのだ。
*しかし、臣下となったと言っても、御子の日常生活は変わらない。相変わらずの宮中住まいだ。
「御あたり去りたまはぬ」とあるが、「御あたり」とは帝の辺り・傍のこと。御子がいつも父帝の傍についているのだ。
だから、帝が「渡る」(「せ・たまふ」がついているから動作主は帝)ときには、御子もちょこちょことついて行く。
*その先方の女性方の部屋にも当然のように一緒に入り込む。女性たちが一所懸命、扇で顔を隠しても、相手は子どものこと。
ちょこまか動いて、扇でかくしおおせるものではない。だから小さな御子は帝の夫人方の顔をみな見比べることができるのだ。
*夫人方の年齢は、例えば、弘徽殿女御は帝より年長であろう。その他の女御・更衣も父と同年代。
それに対して、藤壺はつい最近成人したばかり、16歳くらいと推測される。
*年齢が若い方と言うだけでも親しみを感じやすい。
まして、例の典侍が「藤壺さまは若君の亡き母上にそっくりでいらっしゃるのですよ」と教えたものだから、母に甘える気持ちでいつも傍にいたいと思う。
*「母御息所も、影だにおぼえたまはぬを」とあるが、「御息所」とは、天皇・東宮の妃で、御子を生んだ人を総称して呼ぶ言い方。
だから前東宮妃で、姫御子を生んだあの方は「六条御息所」と呼ばれる。「子どもを産んだ人」という範疇にその人を限定する表現だ。
桐壺更衣の場合は、更衣という下の身分を隠す言い方になったが、六条御息所の場合は、
「子どもを産んだ人=人妻だった人=今更若者との恋愛はふさわしくない人」のニュアンスがでてくる。
*またまた閑話休題、その「母御息所」の影(面影)「だに」知らない御子であるという。
「だに」は程度の軽いものをあげ、言外にもっと思い程度のものがあることを意識させる助詞。母本人がどういう人であったか、どんな声で何を話したかなど、
その人の事は何も知らない。顔のイメージさえも記憶にないのだ。なにしろ、母が死んだのは御子3歳の時。
数え年の3歳は今の1~2歳。人間の最初の記憶が残るのはたぶん満3歳から。
*御子は母という存在をこの藤壺に重ねて思い描くしかないのだ。
|
| 原文 | 口語訳 |
主上も限りなき御思ひどちにて、「な疎みたまひそ。あやしくよそへきこえつべき心地なむする。なめしと思さで、らうたくしたまへ。つらつき、まみなどは
、いとよう似たりしゆゑ、かよひて見えたまふも、似げなからずなむ」など聞こえつけたまへれば、幼心地にも、はかなき花紅葉につけても心ざしを見えたてま
つる。こよなう心寄せきこえたまへれば、弘徽殿の女御、またこの宮とも御仲そばそばしきゆゑ、うち添へて、もとよりの憎さも立ち出でて、ものしと思したり。
世にたぐひなしと見たてまつりたまひ、名高うおはする宮の御容貌にも、なほ匂はしさはたとへむ方なく、うつくしげなるを、世の人、「光る君」と聞こゆ。
藤壺ならびたまひて、御おぼえもとりどりなれば、「かかやく日の宮」と聞こゆ。
|
主上もこの上なくおかわいがりのお二方なので、「お疎みなさいますな。
不思議と若君の母君となぞらえ申してもよいような気持ちがする。(源氏を)失礼だとお思いなさらず、
いとおしみなさい。顔だちや、目もとなど、大変によく似ているため、母君のようにお見えになるのも、
母子として似つかわしくなくはない」などと、お頼み申し上げなさっているので、幼心にも、
ちょっとした花や紅葉にことつけても、お気持ちを表し申す。この上なく好意をお寄せ申していらっしゃるので、
弘徽殿の女御は、またこの宮ともお仲が好ろしくないので、それに加えて、もとからの憎しみももり返して、
不愉快だとお思いになっていた。
世の中にまたとないお方だと拝見なさり、評判高くおいでになる宮のご容貌に対しても、
(若君は)やはり照り映える美しさにおいては比較できないほど美しそうなので、世の中の人は、
「光る君」とお呼び申し上げる。藤壺もお並びになって、御寵愛がそれぞれに厚いので、
「輝く日の宮」とお呼び申し上げる。
|
帝の寵愛する「光る君」と「かかやくひの宮」
*帝は藤壺に言う。「この御子によそよそしくしないでください。
あなたはこの御子の母になぞらえてしまう。あなたとこの御子とは顔立ちがそっくりなので、母子として似つかわしい感じだ。」
*こうして、ここに擬似親子関係が成立する。「父桐壺帝・母藤壺・子光源氏」
母なれば親しみ敬していつもお側にいたいと思うのも自然の事。
やがて、逢う事の許されない関係になるのだとは子ども心には予想できなかった。
*一方、面白くないのは弘徽殿女御。やっと後宮から目障りなものが消えたと思ったら、
今度は自分より遙かに身分の高い姫宮がやって来て、またまた寵愛を独り占め。
しかもあの憎たらしい光る君と一緒とは。憎しみは一層掻きたてられる。
*「この宮に男御子が産まれたら・・。」その時を考えて、
我が子東宮の後見をますます強固なものにしなければならない弘徽殿側である。
*美しい擬似母子。どちらが美しいか、宮よりもこの御子の「匂はしさはたとへむ方なく、うつくしげなる」と言う。
「匂ふ」とは花などの色が美しく照り映える様をいう。つややかな色彩をもつ美しさである。その美においてこの君は、
美貌の女性である藤壺よりも遙かに美しいというのだ。
*世間の人は「光る君」と呼ぶ。貴公子「光源氏」の誕生である。
一方の藤壺を「輝く日の宮」と並称する。
*「ひの宮」は古くから「日の宮」と漢字書きされてきたが、
「光る」対「輝く」であれば「君」対「ひの宮」であるから、「日」の「宮」の二語でなく「妃の宮」の一語扱いが
妥当だという藤井貞和氏の説を私もとりたい。
早すぎる元服 ”母”に隔てられた子の情念が転化する悲劇
*桐壺帝は光る君12歳の時に元服させる。当時、女子の成人である裳着は12歳から16歳頃、
男子の元服である初冠は14歳から16歳頃。その子の成長の度合いに合わせて決める。
そして、元服とほぼ時を同じくして結婚する。こどもから一気に大人になるようなもので、
現代のような自由な青年時代としてのモラトリアムはないのだ。
*それにしても、源氏の12歳での元服は早いと言う印象だ。「光る君」は幼なおさなした子に見えたから。
父帝はなぜこんなに光る君の元服を急いだのか。
*冠のひもを結ぶ役(引き入れのおとど)は左大臣が務め、その夜の添い臥しに娘の葵を差し出した。
つまり光る君を娘婿として迎え入れたのだ。
婚姻を結んだ婿の面倒はすべて女方の親がみる。ここに元服した源氏の後見役が左大臣と決定したのだ。
左大臣の妻大宮は桐壺帝の妹宮。帝は愛児の後見を時の一の人左大臣家に託した。
*それにつけても面白くない弘徽殿女御方。我が子東宮の妃にぜひ葵をと望んでいたのに、
将来の天皇妃の位をソデにして、一介の臣下「源氏」を婿に取るなんて、あきらかに東宮・右大臣方に対する挑戦だ。
*ここにいたって、これからのお話の展開の図式が見えやすい構図となって示された。
《源氏ー桐壺帝ー藤壺ー左大臣方》←→《東宮ー弘徽殿女御ー右大臣方》
*そして、もう一つの構図も浮かび上がる。
*光源氏にとって大切な《桐壺更衣ー藤壺=母》が壊れたのだ。成人した男性には高貴な女性は姿を見せない。
いままで、父帝とともに、御簾の中でしたしく言葉を交わせた藤壺と源氏はもう会えないのだ。
自分は部屋の外、簀子(すのこ)に坐し、御簾の彼方の藤壺の遠い声を聞くだけ。
12歳の母無き子にとって、これは衝撃的な出来事だった。
*そして、自分の通うべき所は左大臣家で、
そこには、年上の姫「葵」が「妻」としている。すべては父の意思で決められた事。
自分をあれほど愛していたはずの父がこんな仕打ちをするなんて。そして愛する人を独り占めにしているのだ。
*妻だという葵は藤壺より1歳しかちがわない。
だとしたら、藤壺が「妻」でも良いのではないか。
*ここに《父の妻←藤壺→自分の思慕する理想の女性》の構図が源氏の心の中にできあがった。
今まで全てが帝の庇護の元に許されていた源氏が、帝に絶対知られてはならない許されない恋にとりつかれた。
|
この項つづく
第二章つづき
2 「若紫発見~紫のゆかり」 へつづく
「原作を味わう 目次」へもどる
[HOME]]
(c)copyright 2004 ゆうなみ
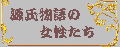 写真の無断転載はご遠慮下さい
写真の無断転載はご遠慮下さい
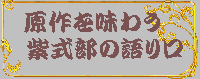
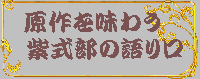
写真の無断転載はご遠慮下さい