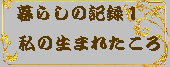
[HOME] [戦時下の少女時代] [私の子ども時代]
戦中に生を受けた私たち。
その生はどのような家族の生活の中で育まれていったか。
父はどこにいたか。母はどのような生活を送っていたか。
私たちの命は多く母の懸命の努力によって維持されてきたのだろう。
母から伝え聞いた戦中の生活の様子を辿ってみます。
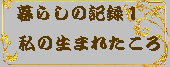
 信州での疎開生活
信州での疎開生活
|
|
 暖められて得た”命”
暖められて得た”命”
|
|
 「嫁」として送った母の疎開生活
「嫁」として送った母の疎開生活
|
|
 姉の心に刻まれた東京大空襲
姉の心に刻まれた東京大空襲
|
|
 左手の痛み
左手の痛み
|
|
 駆逐艦の艦長として戦死した父
駆逐艦の艦長として戦死した父
|
|
 中国・樺太から引き揚げた家族の戦後
中国・樺太から引き揚げた家族の戦後

|
|
 信州での疎開生活 信州での疎開生活
|
|
1943年6月19日、横浜市鶴見区市場町にて出生。父母と共に鶴見で暮らす。 <長野への疎開> まもなく、母の実家のある東京都大田区に移り、空襲を避けるため、母と私は防空壕に入ったりしていたが、 戦局の激しくなった昭和二十年、父の実家の長野市に母と二人で疎開し、伯父、叔母、従姉妹兄弟たちと、暮らす。 長野にも空襲があり、皆でリヤカーを引いて、戸隠山まで、逃げた。 八月十五日、疎開先の長野で玉音放送を聞いた母は、周囲の人々が、涙を流して聞いていたにもかかわらず、 これで戦争が終わったと思うと、無性に嬉しかったそうである。もちろん、私は何の記憶もない。 この頃の私はもんぺをはいて写真に写っている。 <空襲による死者> 父は東芝の鶴見研究所に勤務していたので、戦地にはいかずに済んだ。横浜が空襲に会い、 道の両側に死体の山ができていたが、そこを通った時、怖いとも、悲しいとも感じなくなっていたそうである。 戦争は、正常な感覚を麻痺させてしまうらしい。 父は横浜にいた自分の妹を、当てもなく探していると、 ある家の戸口から、ひょっこり、妹が出てきたので、再会を喜び合ったそうである。 <焼け残った我が家> 今住んでいる大田区も焼夷弾が落ちて、あちこち焼け、家からほんの二,三軒先も焼けた。 私たちの家は焼けなかったので、疎開から帰り、東京で戦後の食糧難の生活が始まった。 |
 暖められて得た”命” 暖められて得た”命”
|
|
私は、兵庫県西宮市の夙川という町で冬の最中に生まれました。 母の体が弱かった為、妊娠による重い腎臓障害から子癇をおこし、 8ヶ月で標準の半分の体重で生まれたという事です。 当時の状況では普通は育たなかったのでしょうが、母乳が良く出たのと、 母方の祖父母と同居していた為、何とか炭など手にいれて暖めてくれた、 周りの努力で、命を、得ました。 |
 「嫁」として送った母の疎開生活 「嫁」として送った母の疎開生活
|
|
私は、1944年1月7日に千葉県市川市菅野で出生、父母、2歳上の姉、祖父母の6人家族でした。 父は王子製紙の社員で、結婚前は上海に勤務していたことがあり、そこで「上海事変」を体験していた。 徴兵検査は、子どもの時のケガで右手の薬指の腱を切っていて曲がらないことから、丙種合格だった。 昭和18年頃から丙種のものにも召集が来るようになったので、内地勤務が出来る軍需工場に出向することにし、 木曽福島の工場の責任者になって現地に行っていることが多かったそうだ。 <焼夷弾落ちる> 昭和19年秋頃から、米軍のB29爆撃機による本土空襲が始まる。 江戸川を隔てて隣接する市川に、東京空襲の帰途、余った爆弾を落としていくことがあり、 家の勝手口に焼夷弾が落ちてボヤになった。東京では住人の疎開が始まっていた頃であり、我が家も疎開することに。 <木曽福島へ> 昭和19年12月から数ヶ月父の勤務地木曽福島に疎開した。 このときは戦時中の配給制度があり、また父の仕事上の地位の為もあって、食糧事情はそんなに悪くなく、 知らない土地であったが、母は過ごしやすかったようだ。 地元の人たちと一緒に景勝「寝覚ノ床」を見物に行った時の写真が一枚だけある。 まもなく1歳のわたしはもんぺ姿の母に抱かれている。このとき母は22歳だった。 <祖父母の故郷久留里へ疎開> 戦況の悪くなる中、長期の疎開先として、父方の祖父母の出身地である千葉県夷隅郡久留里へ疎開する。 久留里は江戸時代の譜代の小さな城下町で、祖父母とも貧しい士族の出だった。 そこでの疎開生活は終戦後も22年春まで続いた。 戦後の食糧難の苦しさはいうまでもないが、疎開地久留里の土地柄の古さと、 祖父母が労働力としての「嫁」あつかいをする仕方に母は苦労したようだ。 のちに、小学生になった私を相手によく母はその当時の体験を語った。 <士族と平民> 東京の女学校をでていた母の家は、のびのびした現代風の家族で、 休日は家族でそろって三越で買い物したり、映画を見たりする生活だったから、結婚して”家風”の違いに母はおどろいたが、 その違いは、婚家にあっては一方的に”士族”と”平民”の差として、何かと言えば、「おまえは平民の出だから・・」と言われたという。 「戦前はね、女学校に出す戸籍には、『華族』とか『士族』『平民』とか書いてある欄があったんだよ。 『ご華族のお嬢さん』には、先生が敬語を使っていたねえ。」と、母から聞いたことがある。 <「嫁は労働力」が疎開でも> 配給制度が無くなった戦後の食糧事情では、疎開している者は、まわりに田畑があり土地の人は十分食糧をもっているだけ、 一方的な需要と供給の関係にさらされ、物々交換で手に入れられる食糧はまったく乏しいものになった。 母が結婚支度で持ってきた晴れ着はみな米に変わったが、晴れ着一着で、 譲ってもらう食糧は米を一升桝にほんの何杯かとか。 「私の晴れ着をきて、親類の娘が何人も結婚していったよ。」 「残っているのはこれ一本だわ。」と言って、モダンな百合の花の刺繍の夏帯一本をなでていた母を思い出す。 つらがっている母に「お前が好きで売ってきたのだ。」と言い放った祖父だったそうだ。その祖父も先祖伝来の刀を米に代えていたらしいが、 「ねぎらいの言葉ひとことあれば気持ちが違うのに・・。」と母は語った。 <妊娠中の風呂の水くみ> そんな生活の中で母は妊娠し、21年の秋に妹が生まれるのだが、妊娠中も「妊娠は病気ではない、身体を動かした方が安産になる。」と、 力仕事は全部母にやらせたそうだ。 臨月のおなかを抱えて、隣の家の井戸からお風呂の水を運び続けた母は、 両足のふくらはぎに太い静脈瘤ができている。長さ20センチもあろうかと思うくらいの、太いミミズがのたくっているような静脈瘤だ。 祖父母は毎日のように親類の家によばれて、お茶やお菓子でもてなされていたらしい。そんな留守の時、 母の苦労を見るに見かねた隣家の”お嫁さん”が「今のうちにお食べよ。」 と言って、おいものふかしたのを持ってきてくれたことがあると、これも何度も聞かされた話だ。「その人もお嫁さんだから、苦労していたからね。」と。 <終戦後生まれの妹> 昭和21年は、一番食糧事情がわるかったせいであろうが、この年生まれた妹は赤ん坊の時から体が弱く、子ども時代よく熱を出したり、 リンパ腺を腫らしたりしていた。引きつけを起こしたこともあった。ほっそりして、こころのやさしい妹だったが、 38歳の時、白血病を発病し、3人の幼児をのこして、早世した。胎児の時の栄養状態がどこかで影響しているのではないかと、母は思っている。 <戦地体験は身近にない> 父は戦地に行かなかった。母の弟が中島飛行機に勤務していて、召集を受けて土浦にあった海軍の飛行隊にいたが、 出陣しないまま終戦を迎えた。だから、子どもの時に、戦場の話を聞くことはなく、私にとっての戦中の暮らしは、母から聞く疎開生活の苦労がほとんどだ。 疎開生活の様子を、聞かされた私は、子供心に、「なぜ、家族なのに、おじいさんやおばあさんは、苦しい時にお母さんばかり働かせたんだろう。」と思った。 孫には、しつけはきちんとしたが、決して理不尽に怖い祖父母ではなかったのに。 戦中・戦後の食糧難による生活苦が、男尊女卑や「嫁」への蔑視とあいまって、母をより一層苦しめていたようだ。 逆境にあったとき、助け合えるか、「弱いもの」を差別するか、これは「近代日本」の抱える問題そのものかもしれない。 |
[このページのトップに戻る]
 姉のこころに刻まれた東京大空襲 姉のこころに刻まれた東京大空襲
|
|
<疎開先から死ぬ覚悟で東京へ戻る> 私は、5人姉妹の末っ子で、疎開先の母の実家(静岡)で歩き始めたと聞いていま す。誰もが貧しい時代だったから仕方がなかったのかもしれませんが、兄嫁(伯母)は野良仕 事に行くとき、私の家族に食べられないようにと、卵に番号を付けたり、米びつのお 米の上に手形を押して出かけていったそうです。母は、そんな仕打ちに我慢できず、 どうせ死ぬなら家族一緒がいいと、東京の自宅に戻りました。 <大勢の親戚と同居生活> 警察官をしていた父は戦争に行かずにすみましたし、幸いなことに私の家は空襲を 免れたので、終戦後、焼け出された親せきや、上海から引き揚げてきた親せきが同居 していたことを覚えています。 狭い家の廊下や玄関にまで寝ていました。食事は、大 きなお釜ですいとんをつくり、交代で食べていました。 家族が多かったので、買い出しに行った母は、帰りの列車で摘発に遇い、せっかく 手に入れたお米を全部没収されて、悔しい思いをしたこともあったそうです。 <姉の体験した東京大空襲> 3月10日の東京大空襲のとき、私のいちばん上の姉は小学校6年生でした。 叔母一家が行方不明になり、姉は父と一緒に上野の山などを捜し回り、 隅田川で家族一緒にヒモで身体を巻き付けて死んでいた叔母と従兄弟たちを見つけたそうです。 そのとき目にした無残な死体の山が心に焼きついたままで、いまでもその当時のことは人に 話せないと言っています。 姉は小学校の教師をしていましたが、とうとう退職するまで教え子にその話を出来なかったそうです。 |
[このページのトップに戻る]
 左手の痛み 左手の痛み
|
|
<叩かれた左手> 「おかわり。」とお茶碗を差し出した時、私の左手を母は強く叩いたのです。御飯茶碗は畳の上に転がりました。 母は何も言わず恐ろしい顔をして私を睨みつけていました。 ほんの少しのバターのようなものを乗せ、お醤油を少々たらして食べる御飯は、本当に本当に美味しかったのです。 <樺太から引き揚げ> いつ頃の事であったのか確かでないが、私は1940年樺太(現サハリン)で生まれたのは確かです。父の鉄道関係の仕事で、 樺太に行っていたようです。樺太ではカニをよく食べたのを覚えています。 第二次世界大戦末期、ソ連軍が樺太に入って来るというので、 女性と子供達は早めに北海道へ引き揚げ開始。比較的大きな船に乗ったようです。 <大好きな花模様のワンピース> 私は、ワンピースやブラウス等をリックサックに入れたのですが、「兵隊が追いかけて来たら重いリックサックは邪魔!」 と言われ、泣きながら、大好きなワンピースを取り出しました。花模様のワンピースで、長い間忘れられませんでした。 家財などを焼いていた光景もうっすら目に浮かびます。 <親戚の家にたどりついて> 北海道について、屋根のない貨物車に乗り込んだ時、屋根の代わりに車両の上に材木が何本も渡してあったように思います。 身を隠してじっとしていたのでしょう。 疲れ果てて、親戚の家に着いて、温かい御飯。食料の乏しい時に、御飯を食べさせてくれた親戚のおばちゃん。 何も知らずに、「おかわり。」とお茶碗を差し出す私の左手を叩いた母。私は多分4才くらいだったのでしょうか。 <今も蘇る左手の痛み> 父母ともに他界し、また生存中も、つらかった事を思い出したくなかったのか、戦中・戦後のことをあまり詳しく は話してくれませんでした。でもあの時の左手の痛みは今でも蘇って来ます。 |
 駆逐艦の艦長として戦死した父
駆逐艦の艦長として戦死した父
|
|
<私の生まれた頃の我が家の状況> 1941年3月28日、私は千葉県館山市八幡の旧制安房中学(現安房高校)の校長官舎で生まれました。 というのは母方の祖父が現職の校長であったため、母は実家に帰って出産したのです。 その頃、父は1940年11月から、巡洋艦青葉の分隊長として洋上にあったため、両親の家はなかったの です。変な話ですが、海軍の軍人は船に乗れぱ、何ヵ月も洋上で過ごします。船が修理でドックに入り でもすれば帰港しますが、それ以外は家を留守にしているので、子供でも大きく学校に行くようになれ ば別ですが、そうでなければ、妻は夫の実家か、自分の実家で夫の帰りを待つという形だったようです。 両親は結婚した頃、父が舞鶴の海兵団の教官をしていたため、十ヵ月余の陸上での暮らしがあったよ うです。 <父の寄港地に母が駆けつけての結婚生活> 私が生まれた後、八月に磯風という駆逐艦に変わっているので、その転勤の時に、二週間ほどの休暇 があって館山に来たようですが、長い洋上生活で体調を崩し、何日間か床に着いていたようです。 1941年8月に磯風に移ってから、ハワイ攻撃作戦に始まって、1942年11月に海軍兵学校の教官になるま での一年余の間に十回もの海戦に参加し、赤道を七回も越えたということでした。 その間、二週間くら いの休暇が出来ると、母は父が入港した所へ私を連れて行き、そこで一緒に休暇を過ごし、父が出掛け ると父の実家(新潟県中蒲原郡村松町)で過ごしていたようです。一年間に六回の休暇があったようです が、その度に呉、横須賀、館山へ母は村松から長いときは二十四時間も汽車に乗って駆け付けたそうで す。 兵学校の教官として江田島で暮らした一年数か月が、両親にとっての結婚生活であったと思われます。 <フィリピン沖海戦で戦死> 父はその後、水雷学校の学生になりますが、駆逐艦「桃」の艦長が急病で入院したため、代わりに急遽 、着任して三ヵ月後の1944年12月15日に、フィリッピン西海沖で戦死しました。 「レイテ戦記」の中に 三ヶ所ほど父の艦の動向が出ていると、報せて下さった方があり、私も確認しました。 |
[このページのトップに戻る]
 中国・樺太から引き揚げた家族の戦後 中国・樺太から引き揚げた家族の戦後
|
|
父の生家である大分県東国東郡という国東半島の真ん中の山間の村で生まれました。観光地としても割合有名な、石仏のある地方で、六郷満山の両子寺(ふたごじ)は菩提寺です。石段のある町として知られている臼杵から、現在でも一日に何便かしかないバスで30分ほどかかる山間です。 <母親の元に戻った3人の息子とその家族達> 昭和二十年八月十五日に、父の母、つまり祖母は、近所の人と一緒に仏間で玉音放送を聞きました。その日から間もなくして、一人で農業と万屋をして暮らしていた祖母の家に長男、四男、六男の三組の夫婦と長男と四男の子供たちが戻ってきました。家族が十人増えて、十一人の共同生活が始まりました。戻って来たと言っても三人の妻と子供たちにとっては、始めての土地でした。 長男太郎は軍医で、二度召集され、家族を岡山に置いての中国への出征でした。太郎の息子達は中学生、娘は小学生。太郎は直に帰国ができて、従って五人は九月からここで生活を初めました。 四男夫婦は北京生まれの息子と中国から引揚げてきました。港近くにいくつもの家族がキャンプを張って帰国船を待機する毎日でした。やっと乗船できても、船上では新たな惨劇を目にしました。伯父達の居場所から十メートル程離れた所で母親に抱かれていた、従兄と同じ二歳の男の子が息を引取りました。私は、伯母の表情から、坊やは、船上でなく既に死んでいたのだと確信しましたが…..。係りが、直ちに子供を渡すように命じました。彼女の夫は現地で戦死していました。死因が何かは不明だったらしいですが、疫病が蔓延しては大変と、風呂敷に包まれた丸っこい静物はさっさと海に投げ込まれてしまいました。 これらを聞いたのは中国残留孤児が温かく迎えられているニュースが流れていた頃です。 六男である父は樺太から戻ってきました。昭和二十年の八月七日に「明日、内地行きの船が出るから、家族は乗船するように」という命令がでました。身の回りの荷物だけを纏めて母は父としばしの別れをして、乗船しました。ところが、翌々日には、父にも北海道内地へ勤務の命令が下り、父は前任者から譲り受けていた犬と猫を次ぎの任務の方に託しました。何時の間にか、父を追ってきた雑種の樺太犬が、桟橋で男性に必死にとり抑えられていました。猫は朝から見えなくなっていたそうです。 後年、両親は自分達の帰国の後に「船が出たかどうか」「民間人の方は元気でいるだろうか、会いに行って当時のお礼を言いたい」とよく口にしていましたが、引越しの多かった我が家での話しですので、私はふたりが、ただ昔を懐かしんで言っているばかりだと思い込んでいました。こうして、四男達と父達は、秋に生家に辿り着きました。 <涙を隠しかばい合って頑張った戦後の暮らし> こんな経験の人達が十一人で、鶏を増やし、粟や稗の食事をし、稲作をして配給に回し、畑を耕し、薪割り、敷地内とは言え、かなり離れた井戸で水を汲み、桶に入れて、風呂に運び、台所の甕に溜め、川で洗濯をし、柴を刈り、草をむしり、夜は鼬が来ないかと見張りをし、草取りをし、屋根を葺き替え、漬物をつけ、豆腐を作り、ランプの下で勉強をし、繕いものをして過ごしました。怪我をしたり、病気をしたり、病人の治療や看護をし、祭りや、近所の葬式には、隣近所と総動員で食事を作ったり、器を蔵から出したり、片付けたり。互いの不満を押し殺して、過ごしました。万屋の商品の買い付けは父の仕事でしたが、東京や大阪で仕入れ、利益を付けて販売しても、三ヶ月後の買い付けの時には、売却金額を全額使っても、仕入れ資金は足りないというインフレが進行する毎日でした。三人の妻達は、裕福な元氏族達だったので、すべてが初体験。それでも後年彼女たちから出る言葉は、「おばあちゃんは、偉かった、何でも教えてくれた。いかに、自分たちが何も知らないで育ったか 恥ずかしかった。」というものでした。 そして私が生まれました。庭のシャガの葉や池の杜若が美しい五月でした。両親の職場、つまり畦道で、私は、籠に入って大人しくしていたそうです。近所のおばさんが、母の麦藁帽子の中に「赤ちゃんに」と配給のお砂糖を入れてくれました。やっとしゃべれるようになった頃には、私は、十一人の食事の様子をみて、「タマタマ食べよんのう」と羨ましがったそうです。(大好きな卵を私には食べさせてくれないのに)皆は卵を食べているのか、という意味です。黄色い粟ご飯を、卵かけご飯と思ったらしいのです。このエピソードは貧しい一家を和ませたのか、私が余程何度もせがんだからなのか、どのいとこも覚えていて、後に何度もからかわれました。 三年間の十二人家族でしたが、その間に軍隊に貸出しをしていたシンガーミシンを含む両親の家財道具が樺太から戻ってきました。木箱が十五程あったそうです。もっとも荷物の殆どは、別府に引越してから殆ど泥棒に盗まれてしまいましたが。 長崎の母の生家は進駐軍の買上げになりました。樺太からの帰路に広島の惨状を目にして、この地にたどり着いた母は、学友達の事を想うまい考えまいと自分に言い聞かせ、水汲みをしたり、畑を耕したりしてそのうち私を産み、産んでからも、いっぱい仕事をして昭和の二十年代の前半を生きぬきました。 祖母は息子の二人を戦争で失くしました。それでも男手をすべて失った家族が村には沢山あったからでしょう。祖母の愚痴をどの妻達も聞いたことがなかったそうです。母の家族が好きだった小説の主人公の名前を私につけたいと申出た時、十一人が全員「良い名前だ。是非。」と言ってくれたそうです。母の父は病死ですが、兄は戦死。身寄りの無くなった母への皆からの気持ちのプレゼントだと嬉しかったと母は死ぬ前に言っていました。 誰も彼も、涙を心にいっぱい溜めて、それでもその涙を隠し合いかばいあって、少し前の数年間の過去は引き千切るように断ち切る努力をして必死に前だけしか見ないようにして生きていたのだと思います。 <遺言として残していく言葉「戦争はいけない」> 十二人のうち戦後六十年の今日、生きているのは、私を含めて四人になってしまいました。八人の誰もが死ぬ前に戦争はいけないと言い遺しました。 戦争体験の苦しみの深さを比較しても意味ないこととは言え、日本全体からみれば十二人の戦場は、恵まれていた方でしょう。でも、彼らは戦争はいけないといって死にました。他界の直前に、必ず遺した言葉です。私が生まれた頃を生きて通過した人は誰でもそう思っているのではないでしょうか。 |
[このページのトップに戻る]

|
|
|
[このページのトップに戻る]
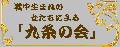 写真の無断転載はご遠慮下さい
写真の無断転載はご遠慮下さい