 ”食糧難”をへて、”二部授業”の小学校へ入学 ”食糧難”をへて、”二部授業”の小学校へ入学
- 語る人/ゆもと みちこ
- 生年月日/1943年6月19日
居住地/東京都大田区
|
<弟誕生>
はっきりした記憶があるのは、三歳からで、それは、弟が生まれたという、私にとっては、
大きな出来事があったからである。お産婆さんが来て母は家で出産した。
戦前、両親はせっせと貯金をしたが、戦後は新円の切り替えで、貨幣価値がすっかり変わり、出産費用もなくて、
母は毎日ミシンを踏み、祖父がどこからか手に入れてきた布で、ズボンを縫って、それを売り、費用にした。
昭和二十一年七月の頃であった。
<買い出し・叔父の帰還・家庭菜園>
食糧を求めて、母も祖母も、農家へ買い出しに行ったり、知り合いの人にさつまいもを分けてもらったりして、
世間一般と同じ苦労をした。
戦後、二,三年して母の弟が、お砂糖を少し持って、とても痩せて戦地から帰って来た。
五歳くらいの時、虱退治のため、頭にDDTをかけられたことはよく覚えている。
家庭にお風呂もなくて、夏はたらいを出して、行水をしたり、隣家のお風呂に入れてもらったりしていた。
近くの焼け跡には、家庭菜園を作り、南瓜、胡瓜、とうもろこし、トマトなどを作っていたが、
もぎたてのトマトは、青くさいような、トマトくささがおいしくて、今でも懐かしい。
<青空幼稚園>
1年保育で幼稚園に入ったが、はじめは、園長先生の自宅の応接間が幼稚園だった。すぐに、町会の建物に移り、
神社の境内が園庭となり、広くなった。
私の一歳上の人たちは、青空幼稚園といって、神社の庭の屋根のない幼稚園だった。
絵を描く紙がなっくて、古い雑誌をバラにしては、絵や字を書かされた。赤や黄色の色ページのところが欲しくてたまらなかった。
<傷痍軍人の姿>
この頃、繁華街には、白い着物を着て松葉杖を突いた傷痍軍人がアコーデオンを弾いて哀れみを乞うていた。この光景はその後
長い間見られた。また、戦禍で足を失った人が駅の階段をいざり降りたり、戦災孤児が靴磨きをしていた。
こうした光景は子供心にも戦争を憎み、とても悲しく映った。
<手作りのランドセル>
昭和二十五年四月、区立の小学校に入学。お古のランドセルや、売っていたズックのランドセルをしょっている子もいたが、
私は父の手作りの布製のランドセルで、母がたんぽぽの刺繍をしてくれた。
クレヨンもあり、二十四色の金や銀の入った
セットを買ってもらったのは、うれしかった。ノートは、古紙を再生したのか、少し色の付いた、ざらざらした粗末な
ものだった。
給食の粉ミルクは味が舌に残って、おいしいとは言えなかったが、栄養の足しにはなった。
小学校二年(昭和二十六年)には、児童数が増えて、二部授業になった。午前だったり、午後から授業だったりして、
落ち着かなかった。次の年には、普通の授業に戻った。
<朝鮮戦争の影>
世間では、また、戦争がどこかで起こった話がされていたが、私にはよくわからなかった。朝鮮戦争だった。
小さい頃の楽しみはもっぱらラジオだったが、舞鶴港に着いた引き揚げ船の名前が毎日のように放送されていたのを
覚えている。それがどんなことなのかは、考えもしなかったが。
<10年後の復興ぶり>
こうして、生き残った者も、新たに生まれた者も、物の無い、不自由な生活を我慢し、戦後の復興に向けて努力したので、
日々の生活は年々良くなっていった。家電製品も普及し、昭和30〜31年には、テレビのある家も出て来た。
原爆については六年生の時、教えられたが、憲法のことは、特に教わった記憶があまりない。
<やはり男が先>
男女平等になったとはいえ、
出席簿はいつも男子から始まり、なんとなく、女子は下に見られていたような感じがした。生徒会の会長は暗黙のうちに
男子と決まっていて、女子は副会長にしかなれなかった。だから、せめて、勉強だけでも男子を見返してやりたいと思っていた。
<新憲法との出会い>
中学でやっと旧憲法と新憲法の違いについて学んだ。
|
[このページのトップに戻る]
 子どもを寒さから守ろうとした先生 子どもを寒さから守ろうとした先生
- 語る人/ちぐさ きさこ
- 生年月日/1944年1月6日
居住地/兵庫県西宮市
|
<進駐軍の兵隊さん>
私が生まれたのは、兵庫県西宮市で夙川という町でした。家には焼夷弾の跡がありましたが、
全焼は免れた様で、ここの駅の近くの丘の一角は進駐軍の将校の住居として、接収されている、
と大人達が話していたのを、覚えております。
ジープに乗った兵隊さんたちが、子どもの姿を見るとキャンデイやガムをまいていたことを思い出します。
<教会の幼稚園に>
私の行った(と言っても殆ど登園拒否児だったのですが)幼稚園は後に遠藤周作の作品で彼がこの教会にいた事を
知ったのですが、カトリック夙川教会の幼稚園でした。
園長の記憶が無いのですが、ずっと後で、
神父が外国人であることから、戦時中拷問をうけて、体を壊していたとか、聞きました。
<寒さしのぎのストーブで>
小学校は、校舎が足りないため、二部授業でした。ある夜、空が真っ赤になって、学校が火事で焼けていると
大騒ぎになりました。六年生の授業を遅くまで指導していた先生が、寒いから、とストーブを燃やして
子供達に暖をとらせ、その不始末が原因だったとの事です。
先生には双子の男の子がいて、その子達は私と同級生でした。大人しい良く出来る子達でした。
先生は警察の取り調べを受け、しばらくして、学校を去られました。
先生のお別れの言葉は「冬来たりなば、春遠からじと申します。」というものでした。親達も先生に同情しました。
物の無い時代、子供達を寒さから守ろうとした先生の悲劇が今も思いだされます。
<春は来たが>
その後日本は戦後の復興の時代を
迎え、そういう意味では春が来たのですが。
|
[このページのトップに戻る]
 「サンフランシスコ・コーワジョウヤク」
「サンフランシスコ・コーワジョウヤク」
語る人/むらかみ あやこ
生年月日/1944年1月日
居住地/東京都
|
<多くの人の世話をした父母>
どういうわけかわかりませんが、わが家にはいつも家族以外の人が同居して、貧しかったけれど、にぎやかに暮らしていました。
父も母も、他人様をお世話する運命の下に生まれついたのかもしれませんし、困ったときはお互い様ということが普通の時代だったのでしょ
う。
<小学校入学>
小学校に入学したとき、校舎が焼けてしまったので、たしか二部授業だったと思います。
家で不要なものを持ち寄って、物々交換をしていた記憶があります。
<両親のいなかった友だちは>
近所の、両親のいない同級生の家に、駐留軍の米兵が来ると、もの珍しさで、近所の子どもたちがジープの
周りを取り囲んでいました。
彼女のお姉さんはパーマをかけ、真っ赤な口紅をつけて、派手なワンピースを着て、
近所ではとびきり目立つ存在だったので、今でも強烈に印象に残っています。
いつの間にか、その友だちはお姉さんと一緒にいなくなってしまいました。
<サンフランシスコ講和条約の日>
小学校2年生のころ、担任の水野トシ先生が「今日で、戦争が終わりました。サンフランシスコ講和条約が結ばれました」と
おっしゃったので、学校からの帰り道、忘れないように「サンフランシスコ・コーワジョウヤク、サンフランシスコ・コーワジョウ
ヤク」と繰り返していました。
戦争の記憶はありませんが、「戦争が終わった日」は先生に教えられました。
|
[このページのトップに戻る]
 「グリコース」の甘さ、のみ・シラミ、でも空は広かった 「グリコース」の甘さ、のみ・シラミ、でも空は広かった
- 語る人/なみひさ ゆうこ
- 生年月日/1944年1月7日
居住地/千葉県千葉市
|
<焼け跡での新生活>
私の記憶に浮かぶ最初の光景は、材木をけずる大工さんのカンナから、
シュルシュルと軽い音をたてて出て来るうすい紙のような削りくずだ。太陽をうけて光っていた。ずっと見つめていた自分がいる。3歳だった。
疎開先から引き上げて、千葉市の空襲の跡地をかりて、小さな家を建てて、戦後の生活が始まった。
近くの農家に食糧や薪をもらいにいって、母が大八車をうんうん言って、引いて帰って来る姿も覚えている。
<庭一面で野菜づくり>
家の庭は祖父母が全部耕して畑にしていた。鍬を入れると、瓦礫が出て来て、姉や私はそれを拾うのを手伝った。
作った野菜の種類は、今、考えるとびっくりするほど多い。じゃがいも、さつまいも、なす、かぼちゃ、きゅうり、とまと、インゲン、さといも、
えだまめ、とうもろこし、ほうれんそう、こまつな、にら、ごま、そばetc。
いまでも、葉っぱや苗をみただけで、
野菜の区別がつく。
家ではニワトリも飼っていて、お客さんが来ると、祖父が首をひねって殺し、私は羽をむしるのを手伝った。
力を入れると、プツッと抜けた。
つがいのチャボも飼っていたが、これは子どもの愛玩用にしてくれた。私の最初のペットだ。
<「グリコース」はどこにいった?>
お店で買うお菓子は、いつから食べただろう?千葉には占領軍はいなかったようで、GIからチョコレートやガムをもらう経験というのは、
東京生まれの夫はよくあったそうだが、私には無い。
グリコースという白い固まりがお菓子がわりに町内から配られたことがある。かじると、かすかなあまい味が口に拡がった。
このグリコースをもらったのは、ほんの2,3回だけだった。大きくなって、人に話しても、存在を知っている人は稀である。
<叫ぶ娘・復員兵ー戦争の影>
遊び場の空き地の隣に、伸び放題の樹にかこまれた大きな家があって、いつも雨戸が閉まり人気(ひとけ)がなかったので、
子ども達が「お化け屋敷」とよんでいた。ある日、その家から女の人の叫び声のようなものが聞こえたので、木立からのぞいてみると、
雨戸が一枚開いて、縁側に、赤い花柄のきれいな着物を着た髪の長い若い女の人が、着物の前をはだけて、踊っているような奇妙な振る舞いをしていた。
ことばは聞き取れなかったが、悲鳴のような歌うような声を上げていた。次の瞬間、誰かが、さっとその人を抱きかかえて、戸を閉めてしまった。
家に帰って、「女の人が叫んでいたよ」というと、母が恐い顔をして、「のぞいてはいけません。」といった。子ども心に、「気の狂ったかわいそうな人なんだ」と分かった。
戦争で愛する人を失った女性だったのだろう。いつのまにか、その家はなくなっていた。
同じ頃だったと思うが、一人の「おもらいの兵隊さん」がいた。
ときどきおもらいさん(乞食)が来て、勝手口で、「何かめぐんでくだせえ」ということがあったが、
その兵隊さんは、戸口に黙って立っているだけだった。カーキ色の兵隊服を着て足にはゲートルを巻いた背の高い人で、右手に欠けたお茶碗をささげて、いつまでもまっすぐ立ったままだった。
家の人は気味悪がって出て行こうとしなかったが、わたしはその人のお茶碗を受け取って、自分のごはんとおかずのめざしを載せて、上からみそ汁をかけて、
その人の右手にまた持たせた。「ごめんなさい、これしかないの」と言ったように記憶している。本当にごちそうを上げられないのが
済まない気がしたのだ。
整った顔立ちの若い人だった。
大きな眼を私に向けていたが、私ではないどこか遠いところを見ているような眼だった。静かに会釈をして、後ろを向いて去っていった。
小さいながら、「帰る家が分からなくなった兵隊さんなんだ。」と思った。
去年だったか、新聞の千葉版紙上で、復員兵で、気が狂ったり記憶喪失になったりして、故郷に帰れないまま、
施設で暮らして、年老い、死んでいく人たちの特集記事があった。あの時の「兵隊さん」もそういう一人として、
この繁栄の世のかたすみで生きていたのだろうか。
<DDTを浴びて>
5歳の時、弟誕生、8人家族になった。翌年、小学校入学。小学校は木造校舎で、最初の1年は二部授業、翌年から校舎がふえて、普通授業になった。
授業中、前の子の髪の毛に虱が動いているのが見えたりした。
学校では虱が見つかると、先生がDDTの粉を頭にふりかけた。いまでは禁止されているDDTはどの家でも必需品で、
夜、布団を敷く前には、蚤が来ないように、畳のへりに、DDTをまいた。寝間着の縫い目に潜っている蚤をツメでつぶすと、
プツッと音がして、つぶれたおなかから白い小さい卵が飛び出した。
DDTの毒性はいわゆる「環境ホルモン」であるが、その影響は大量に浴びた人自身でなく、その人の産んだ子どもに作用し、生殖能力を弱めると、
最近、専門書で読んだことがある。
私たちの子ども世代である、今の30代の人に、影響が出ているかも知れないのだ。
<貧乏暮らしでも子どもは元気>
学校の休み時間は、先生と一緒に押しくらまんじゅうをしたり、鬼ごっこをした。放課後も暗くなるまで、
校庭で思いっきり遊んでいると、手の空いた先生が職員室から出て来て、一緒に遊んでくれた。
クラスには、孤児院から通ってきている女の子がいた。
体の大きな、年よりも大人っぽい子で、クラスメイトの面倒見がとても良かった。
3年生の時に広島から転向してきた男の子は、お祖母さんに連れられて来た。
「両親が原爆で死んだかわいそうな子だから、みんな仲良くしてね。」とお祖母さんが言ったのを覚えている。
私の仲良しの女の子は、川のほとりのバラック(屋根や壁をトタン板で囲った粗末な家)に住んでいた。
その子の両親は廃品回収と焼き芋やさんをしていたので、学校から帰ると、長女のその子が弟妹の面倒を見ていた。
私も学校帰りに寄り道して、一緒に土手で遊んでいると、夕方、リヤカーを引いて帰ってきたおじさんが、
売れ残りの焼き芋をくれた。暖かくて、焦げ目のにおいがしてほんとにおいしかった。
家に帰っても、大人たちは生活のために悪戦苦闘していたから、子供にかまう暇はなく、
親のこごとは、「勉強しろ」ではなく、「家の手伝いをしろ」だった。
みんな、ほつれたセーターや、ツギのあたったズボンをはいていたし、兄姉のお下がりを着るのは当たり前で、
服は皆つんつるてんになるまで着ていた。
貧乏が当たり前だったから、だれも何とも思っていなかった。
<たんぼには生き物がいっぱい>
県庁から徒歩10分くらいの町中だったが、家の前には、6枚ほどの田があって、季節になると農家の人が田起こしにきて、
やがてきれいな畦ができて、水が入り、田植えをしていった。育っていく稲の間には、トノサマガエル、アカガエル、雨蛙、
ドジョウやアメンボやエビガニ(いまはザリガニといっている)、ヤゴ、ヒルなど、小さな生き物がいて、子ども達は一
日中、畦に出て遊んでいた。
秋には、稲穂にいっぱいイナゴが取りついているのを、両手をぱっと合わせて捕まえた。
ドジョウもイナゴも遊び相手だったから、いまだに食べたことはない。
空が一面に拡がり、夕暮れは、雁が列を成して飛んでいくのを眺めているうちに、
空の色があかね色から紫にかわり、いつのまにか真っ暗になっていった。
姉弟げんかをしたり、親にしかられたときにも、外に出て、夕暮れの景色を眺めていると、
いやなことはみな忘れ、心が静まった。
私の子ども時代、遊び道具もおもちゃもないが、こどもにとって必要な環境は全部あったような気がする。
(生き物がいっぱいいる田んぼは、こどもの最上の遊び場だったが、小学校が終わる頃、田に農薬をまくようになり、生き物の姿は消えていった。そのころ拾ってきてかわいがっていた犬は、
夏の初め、散歩に出て、農薬をなめて、血を吐いて死んでしまった。)
<デイズニー映画のプレゼント>
学校で映画を見に行った事がなんどもある。千葉劇場という映画館が、一般の上映前に、小学校の子どもにただで映画を見せてくれたのだ。
デイズニーの「白雪姫」「ミッキーマウス」「バンビ」「ダンボ」「シンデレラ姫」「砂漠は生きている」など、
全部、学校からみんなで列を作って行って、映画館でみたのだ。
「砂漠は生きている」のスローモー撮影で、サボテンの花がつぎつぎに開いていく美しさは目に焼き付いている。
子どもにただで見せてしまったら、お金を払って見るお客がどのくらいいたのか、
今考えると、よくやってくれたなあとおもう。映画館主が、焼け跡に育つ子どもに夢を与えてくれたのだ。
<「ピカドン」>
小学校6年の時だったとおもうが、学校からみんなで、「ピカドン」を見に行ったことがある。
いつも笑顔の先生が、まじめな顔で、「昭和20年の8月6日に広島に原爆が落ちて、大勢の人が一瞬で死んだり、大やけどをしたり
したんだ。そのときの様子を描いた絵を見に行くんだよ。良く見なさい。」と言ったから、ガキ大将たちもみな、静かに見ていた。
(そういえば、「原爆が落ちた」であって、アメリカが「原爆を落とした」という言い方ではなかった。
あたかも原爆は自動的に不可抗的に落ちるものであるかのようだ。)
「幽霊の行列」という絵を覚えている。手を体の前に浮かせるように伸ばしたはだかの人びとが、行列になって歩いている図だ。
腕からはぼろのようなものが垂れているのだった。
この絵は、のちに丸木位里、俊夫妻の画集「原爆の図」で再会した。
<心に突き刺さっている場面>
こうして小学校時代を思い出していると、フラッシュバックのように浮かんで、心に突き刺さる場面がひとつある。
クラスで一人だけいじめられていた少年がいたことだ。クラスの男の子達が特に理由もなく、
教室の隅でその子のことを蹴ったりした。その子は抵抗しないで、
上目づかいに相手を見つめて体を丸めているだけだった。
私は、どうしてその子がいじめられるのか分からなかったが、いちばん「変だ」と思ったのは、
弱い者いじめをしているのに、先生がその子をかばわないことだった。
その子は「金杉君」といった。
大学生になってから、その子が「在日」の人だったのだ、と思い当たった。
助けることもせず、遠くから見ているだけだった自分を思い出し、恥ずかしかった。
|
[このページのトップに戻る]
 終戦後 終戦後
- 語る人/みながわ ようこ
- 生年月日/1941年 3月28日
居住地/千葉県
|
<1.父の戦死の報>
父の戦死の報は亡くなって半年位後に、(新潟県の)村松にいる私どもの所に届いたようです。かすかな記憶で
すが、縁側に綜が吊してあった頃のようです。その頃私は、ようやく一命を取り留めた状態でした。と言うのは腎
孟炎にかかった私は、何週間(実際はもっと短かったのかも)も高熱に浮かされていたそうです。当時、抗生物質も
ない頃でしたので、手の施しようもなかったのです。母の新潟高女時代の親しい先輩が、新潟医大の先生になって
いたので、いろいろアドバイスを頂いていたそうですが、母は私が助かっても脳に障害が残るのではと懸念するほ
どであったとか。
私の病気が一段落した頃に母が具合が悪くなり、医者の診断を受けると、腹膜炎で絶対安静にしているようにと
言われたそうです。そんな矢先に父の戦死の報が届いたのです。勿論、遺骨もありませんが、葬儀を済ませ先祖累
代の墓に埋葬し、そんなこんなのごたごたで、母は床に着いていることできませんでした。弟は二歳、私は四歳に
なったばかりでした。
<2.新潟から千葉へ>
母はその後の生活を考えなくてはなりません。父は長男ではなかったので母は雪深い新潟で暮らすよりも、自分
の郷里の千葉で暮らすことを選びました。勿論、気候的にも暮らしやすいことと、何よりも母が仕事を持つとした
ら教員しかないと考え、結婚前、短期間であったけれど自分が教職に着いていた千葉を選んだのだと思います。
二十年初冬、私たち親子は母方の両親のいた館山に身を寄せました。その頃、慶応大学在学中に出征した叔父が
マラリヤに罹って南方より引き上げて来ていました。栄養不足と病気で年寄のようだったそうです。母の実家には
叔父二人、叔母二人がまだ年若く学生でおりました。そこに我々が帰ったのです。祖母は我儘な人でしたから、母
は余り居心地は良くなかったようです。
<3.木更津での暮らし>
そうこうする内に祖父の母親が木更津の家で寝付いた状態になってしまいました。祖母にとっては姑に当たる人
です。祖母は看取りのために自分の娘である母と我々を木更津の祖父の実家に転居させました。昭和二十一年のこ
とです。祖父は長男でしたが、勤めの関係で館山におりました。当時、高等師範学校出身の教員は移動の範囲は
全国規模でしたから、祖父も広島・神奈川・新潟・千葉と渡り歩いて来て、最終の勤務地が館山でした
祖父の実家には寝たきりの曾祖母と東京の大空襲で焼け出された祖父の弟の一家が住んでいました。私たちはそ
こへ帰ってきたのです。居心地は最悪でした。祖父の弟は今思えば、気の毒な人でもありました。東京外国語大学
の前身のフランス語学科を卒業し、外務省に勤務していました。彼のライフワークはフランス語の辞書を作ること
であったようです。勤務の傍ら作り続けた膨大な資料を全て空襲で灰にしてしまったわけです。そういう状況下、
精神的にも混乱していたのでしょう。自分の姪である母にずいぶんと酷いことを言ったりしたようです。
<4.母の就職と私の入学>
やがて祖父の弟も東京へ帰って行きました。木更津へ来てからが母にとって一番辛い時であったようです。畑に
藷や南瓜を育て、持っている着物や帯を食料に換えて暮らしをつないだようです。当時、近所は皆農家でしたから、
母が畑に苗を植え付けたりしても、素人に何が出来るものかと随分と馬鹿にされたようです。本と首っ引きの農作
業の結果、周囲も驚くほどの収穫を挙げたそうです。母曰く「何のことはない、長年使って居なかった土地がもたら
してくれたもの」と、当時を振り返っています。
昭和二十二年に私が小学校へ入ると同時に母も教員として再スタートしました。ただし、当時の月給はストッキ
ングー足で消えてしまう額だったそうです。勿論、母はストッキングなど買いませんが。そんな状態でしたから、
勤めと農業と私たちの衣服の仕立てと休む暇もない暮らしであったようです。
今では考えられない窮乏生活でしたが、多くの人が同様であったことでなんとか乗り越えられたのだと思います。
当時は洗濯機もなく、日曜日は盥で親子三人分の一週間の洗濯物を片付けるのに、朝からとりかかってもお昼ごろ
までかかる忙しさであったようです。
私が小学校に入る頃には祖父たちも館山から木更津に移って来ていました。叔母たちの学校が区切りがついたから
です。我が家の暮らしは七人になっていました。お弁当を持って出るのが、母と二人の叔母たちです。私も入学当
初はいらなかったお弁当が必要になっていましたが、どうしても言い出せなくて、暫らくはお弁当の時間は外で本
などを読んで過ごしていました。どのくらい続いたのか、今では忘れてしまいましたが、たいした期間ではなかった
のでしょうが、忘れられない記憶です
祖母は厳しい人で、学校から帰っても家に入るのが厭でした。母が勤めを終えて帰ってくるまで、私は外で編み
物をしたり、本を読んだりして時間をつぶしました。弟はいたずらで、幼稚園の頃にはあちらこちら遊び廻ってい
て、私は何時も一人で家の門のところで、暗くなる迄母の帰りを待っていたのを思いだします。
<5.今、思うこと>
私にとって物質的にも精神的にも一番辛い時期であったと思います。それは母にとっても同じであったはずです。
私が大学を卒業して結婚したとき、同僚の女の先生が強く退職を勧めました。女の幸せは結婚し、子供を育てるこ
とであると。その先生は勤めながらやってきたが、決して良いことはなかったというのが理由でした。
しかし、母は職を持ち続けることを強く勧めました。自分が夫となに不自由なく暮らした時と、夫亡きあと仕事を持って子育て
した時と両方経験して、仕事を持つことを勧めるというのです。私は結局、停年まで仕事を続けました。母の同僚
などで「私は停年までなんて仕事をしないわ。」と言いながら勤めている人がいるけれど、そういうことは決して
口にしてはいけないというのが母の言葉でした。何時でも投げ出せるような勤め方はいけないという考えだったの
だろうと思います。
|
[このページのトップに戻る]
 母の一生(悲しみをこえて) 母の一生(悲しみをこえて)
- 語る人/いしかわ ちほこ
- 生年月日/1940年 2月 1日
居住地/富山県
|
母、瑠璃子は19歳のとき、昭和12年9月3日の暑い日、玉永寺の長男、義之に嫁ぎました。日中全面戦争の中、すぐにも、戦地へ行くということで、急いで式をあげました。嫁いで一週間、祝い事が続き、9月12日、富山連隊冨士井部隊に入隊、10月12日中国郭宅で戦死いたしました。家は、義之の祖母のヤイ様、母のかずえ様、弟の雅楽様妹の人子様との5人家族となりました。
急きょ、寺の仕事を弟の雅楽が継ぐことになり、京都専修学院へ勉学に行き、その間、祖父の兄弟の高野様に寺の仕事をしてもらいました。
京都での学問を終え、教師資格を取得した雅楽は母と結婚。私が生まれ、三歳になって片言が言えるようになったころ、ほっとする間もなく、第二次世界大戦にて昭和17年1月28日、東京赤羽部隊に入隊され、父は戦地に旅立ちました。
戦争はますます激しくなっていきました。
玉永寺は、大正4年に本堂、昭和8年に庫裏が建立されました。苦労を重ねた祖父(義重)はその中で病に冒され、昭和10年、53歳心臓病で亡くなっていました。本堂は天井もなく、庫裏も中壁がしてあるだけ。風が吹くたびに、ぼろぼろと泥が落ち、まだ借金がある状態でした。
寺には東京大間窪から小学生、職員、作業員、寮母ら、55人が疎開してきました。もう、なんだか、わけがわからない状態でした。毎日毎日大勢の暮らしです。その中で母は、寮母としても働いて、こどもたちのお世話をしていました。
寺の仕事は祖母と生家(等通寺)の祖父と母でやり繰りしていましたが、母は昭和18年11月、京都へ教師の資格を受けに行きました。毎日毎日つめこみの勉強であったそうです。
そのころは、女性住職は許されておらず、代務者としての教師資格でした。
その後は、葬儀に導師を勤め、本格的に寺役まわりを始めました。母が24歳の頃からだと思います。
自転車もなく、歩くばかりの日々、一日に二人も亡くなられた時には、体がだるく、足の裏が膿んで歩けくなりました。それでも、下駄を履いてがんばっていました。
20年8月、無理を重ね、母はついに肋膜炎を患ってしまいました。幼い私に病気をうつしてはいけないと、祖父母の計らいで、私を残し、生家に帰り養生していました。
8月15日、敗戦。その8日後、8月23日、父はパラオ島で餓死しました。病床で、母は夫の死を知りました。戦争は、母の幸せも、なにもかも、奪いました。
境内にあったまわりが4尺5寸もあった20本の杉の木、水橋から五百石までこんな立派な杉はないといわれた杉を供出。梵鐘も供出。住職二人も戦死。疎開児童も帰りました。その後は、毎年毎年、本堂や庫裏の修理の連続でした。そのために、毎日、毎日、お世話方が来られ、お金の相談。その後は酒。寺は荒れ放題。叔母(上市の称慶寺へ嫁ぎ三十九歳で死亡)が結婚することがまとまった時、お世話方の中に、笑いながら、一体だれが結婚するのかと尋ねる人がいました。その時の悔しさを、今でも忘れることができません。母は若く、まだ34歳の時でした。
寺は私と母と二人だけになり、お世話方が夜遅くまでの宴会、暴言。恐ろしさで隣の家まで、裸足で飛び出したことが幾度もありました。
母はやっと購入した自転車に乗って、黒いマントを着、雪の中も雨の中も走りました。いつも、帰ってくる頃は、日が暮れていました。つぎのあたった足袋と濡れたマントが、こたつのやぐらに掛けられていました。
それでも、暖かく迎えて下さったご門徒の皆様に支えられ、耐えてきたのだと思います。私は学校に行くようになり、近所のおばあちゃんたちが留守に来てくれていました。
高校を終え、上の学校を望みましたが、「片羽根しかない私をどこまでこうさせるの。無理したら、もう片方の羽根も折れてしまう」といった母に、返す言葉もありませんでした。
私は19歳になったとき、結婚。母は「まじめにたてなさい。」と繰り返し教えてくれました。今も耳の底に残ります。
母は40歳になったころから、県の未亡人会、教区の坊守会、村の婦人会等、いろんなお世話をして、とっても強くなっていました。父が戦死したフィリッピンまで一人で出かけ、私も誘ってくれましたが、男の子3人持った私は、子育てに忙しく、母を思いやることができませんでした。「あんたがいたからがんばってきたのだ」といった母の言葉に押しつぶされる思いでいました。
60歳になってから、役をいっさい止め、今度はあなたが出なさいと坊守会に出ることをすすめてくれました。その後、心臓を悪くし、昭和58年1月1日、心筋梗塞で、63歳にて、浄土へ帰っていきました。
亡くなる日の午前、救命救急センターのベッドの上でポツリと言いました。「死ぬって淋しいね」私は思わず応えました。「お母さん、彼の国(弥陀の浄土)へ生まれるのだと先生が教えて下さった、淋しくないよ」「あっ、そうなの。彼の国だね。こうして寝ていて自分の一生を振り返ると、私は本当にしあわせものでした」それが最期に交わした言葉でした。ちょうど私が歎異抄の9章を学んでいたときでした。いつも愚痴ばかりこぼしていたけれど、強い母だったのに。私は母に背を向け、涙がひとりでに流れました。その夜に急変し、母は亡くなりました。
母の一生は自分の幸福より、寺院護持の一生でした。みなさんに見守られ、私自身の信心が問われる日々です。「まじめにたてなさい」今なお、母の声が聞こえます。早いもので今年は17回忌です。終戦より、半世紀経た今年も、東京より、疎開児童であった方々が、お参りに来てくださいます。
|
[このページのトップに戻る]
[HOME]]
(c)copyright 2004 ゆうなみ
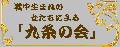 写真の無断転載はご遠慮下さい
up date:2004/8/15
byゆうなみ
写真の無断転載はご遠慮下さい
up date:2004/8/15
byゆうなみ
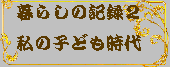


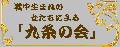 写真の無断転載はご遠慮下さい
写真の無断転載はご遠慮下さい