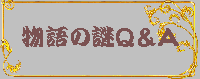
仏仏仏撉傔偽撉傓傎偳丄偝傑偞傑側撲偑傢偒偍偙傞乽尮巵暔岅乿丄 夛堳偑偄偩偄偨栤偄偺悢乆偲丄偦偺撉傒夝偒曽傪徯夘偟傑偡仏仏仏
傑偢偼乽嬎氣乿偺姫偐傜丅暔岅偺庡栶偨偪偺塣柦傪憖傞撲偼偡傋偰偙偺姫偵傂偦傫偱偄傞両
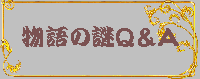
 侾丆屻尒栶偺晝戝擺尵偑巰嫀偟偰偄傞偺偵丄嬎氣峏堖偼側偤擖撪偟偨偺偐丠丂 侾丆屻尒栶偺晝戝擺尵偑巰嫀偟偰偄傞偺偵丄嬎氣峏堖偼側偤擖撪偟偨偺偐丠丂
|
| 亙杮暥偐傜亜
丂乽嬎氣乿偺姫朻摢偱丄掗偺偙偺峏堖偵懳偡傞搙傪夁偓偨挒垽傇傝偲廃埻偺偦偟傝傪婰弎偟偨偦偺捈屻偱丄 岅傝庤偼丄乽晝偺戝擺尵偼朣偔側傝偰乿偲丄岅傝弌偟偨丅乽峏堖乿偲偡傞偲忋埵偺曽偩偲偄偆偙偲偼丄偡偱偵暘偐偭偰偄傞偐傜丄 戝擺尵壠偺昉偩偲偄偆偙偲偼挳偒庤偺梊憐捠傝偱偁傞偑丄偦偺晝偑婛偵屘恖偩偲偄偆忣曬偼丄嬃偒傪傕偭偰暦偐傟偨偙偲偩傠偆丅 丂宱嵪椡偑側偔抝偺屻尒栶偺偄側偄昉偑擖撪偡傞偙偲偼忢幆偵斀偟偰偄傞丅偦偺屻尒偼媽壠弌恎偺曣杒偺曽偑丄恎偵偮偗偨嫵梴傪憤摦堳偟偰 懳張偟偰偄傞偲偄偆丅偱傕丄奿幃偁傞媀幃偺愜傝偵偼丄偳偆偵傕懳張偟偒傟側偄偱丄曣柡偲傕崲偭偰偄傞丅 丂偦傟偼暘偐傝愗偭偨偙偲丅側傜偽側偤丄偦偙傑偱偟偰擖撪偝偣偨偺偐丅 丂偦傟偼丄杮暥拞偱偼丄峏堖偺巰屻丄挗栤偵棃偨柙晧偺柦晈偵岦偐偭偰岅傞曣杒偺曽偵傛偭偰柧偐偝傟傞丅 乽惗傑傟偟帪傛傝巚傆怱偁傝偟恖偵偰丄屘戝擺尵丄偄傑偼偲側傞傑偱丄亀偨偩偙偺恖偺媨偯偐傊偺杮堄昁偢偲偘偝偣曭傟丅 傢傟側偔側傝偸偲偰丄偔偪傪偟偆巚傂偔偯傎傞側亁偲偐傊偡偑傊偡偄偝傔抲偐傟帢傝偟偐偽乿偲尵偆丅屻尒側偒媨巇偊偺嬯楯偼暘偐偭偰偄偨偑丄 晝戝擺尵偺堚尵備偊偺弌巇偩偭偨偲偄偆丅偦傟偑掗偺恎偵梋傞挒垽傪捀偄偨偽偐傝偵丄廃埻偐傜偺偹偨傒偦偹傒偺偁傟偙傟傪庴偗丄 柡偼乽傛偙偞傑側傞傗偆側乿巰傪寎偊偨偺偩偲丅曣偼柡傪乽墶巰乿偝偣偨尨場傪嶌偭偨掗偺挒垽傇傝傪崷傓尵梩偝偊丄晅偗壛偊傞丅 丂柡偺擖撪傪朷傫偩偺偼曣偱偼側偄丅偁偔傑偱屘戝擺尵偩偭偨偺偩丅偦傟偱偼側偤丄晝戝擺尵偼柡抋惗帪偐傜丄偙偺柡傪擖撪偝偣傛偆偲偄偆 嫮偄堄巙傪帩偭偨偺偐丠杮暥偱偼岅傜傟側偄丅 丂 |
| 亙撉傒夝偒亜
丂乽戝擺尵壠乿偺昉偼擖撪偟偰丄挒垽傪庴偗偨偲偊抝巕傪弌惗偟偰傕丄彈屼偲偼奿偑堘偄丄杮恖偑拞媨偵棫岪偡傞偙偲偼弌棃側偄偟丄 偦偺巕偑搶媨偵棫偮壜擻惈偼敄偄丅偩偐傜丄偦偺壠偺庴偗傞塰壺偲偄偆傕偺偼丄柡偑掗偺挒垽傪庴偗偰偄傞帪偩偗偺傕偺偱偁偭偰丄 師婜揤峜偺戙偺奜慶晝偲偟偰偺惌帯揑幚尃傪朷傓偙偲偼偱偒側偄丅 丂偦傟側偺偵側偤丄戝擺尵偼帺暘偑巰偸帪偵傑偱丄柡偺擖撪偵偙偩傢傞偺偐丅傗偼傝撲偱偁傞丅 丂戝擺尵偼傕偟丄巰側側偗傟偽丄師偼塃戝恇偵側傞埵抲偵偄傞丅偙偺恖偼塃戝恇偺億僗僩傪椺偺峅婮揳偺彈屼偺晝偲憟偭偰攋傟偨偺偐傕抦傟側偄丅 幐堄偺僂僠偵丄戝擺尵偺傑傑偱惱嫀偟偨偲峫偊傜傟傞丅媽壠弌恎偺杒偺曽傪寎偊偰偄傞強偐傜丄偙偺戝擺尵傕桼弿嵼傞弌恎偩偲巚傢傟傞丅 堦曽偺塃戝恇壠偼偦偺傛偆側婥攝偼偳偙偵傕側偔丄柡彈屼偺幚柋壠傇傝偐傜悇嶡偟偰傕丄偨偨偒忋偘偺弌悽傪偟偰偒偨抝偱偁傠偆丅 怴嫽惃椡偺塃戝恇壠偵懳偟偰丄偙偺戝擺尵偼旤杄偺柡傪摼偨抜奒偐傜丄偙偺柡傪巊偭偰偺柤栧夞暅偺擮婅偑偁偭偨傕偺偲巚傢傟傞丅 丂屘戝擺尵偺堄巚偼偄偮幚尰偡傞偺偐丠懛乽岝尮巵乿偵戸偝傟偨偺偐丠 丂偠偮偼丄暔岅偱偼丄恊偺嫮偄堄巙傪扴偭偰丄杮棃偺恎暘傪挻偊偨崶堶傪幚尰偡傞彈惈偑傕偆堦恖偄傞丅屻偵搊応偡傞柧愇偺孨偱偁傞丅 偦偟偰丄柧愇偺孨偺晝柧愇偺擖摴偺晝偼丄偙偺嬎氣偺峏堖偺晝戝擺尵偲孼掜偱偁偭偨戝恇偲偄偆偙偲偑柧傜偐偵偝傟傞丅乮乽恵杹乿偺姫乯 丂偦偺晝戝恇偼幐媟偟偨堊丄帺暘偺弌悽傕朷傔偢丄嬤塹拞彨偲偄偆抧埵傪幪偰丄攄杹偺庣偲偄偆抧曽姱偵惉傝壓偑傝丄 壥偰偼偦偺抧埵傕幪偰丄搚拝偺摴傪慖傫偩曄傢傝幰偲偟偰搊応偡傞丅傂偨偡傜嵿椡傪拁偊丄 柡傪崅婱側恖偺嵢偵偲朷傓擖摴偺栰朷偑尮巵傪寎偊擖傟傞揥奐偵側偭偰偄偔丅 丂晝戝擺尵偑柡偺峏堖偵戸偟偨擮婅偼丄夢傝傑傢偭偰丄墮偺柧愇偺擖摴偺丄柡傪尮巵偵壟偡偲偄偆擮婅偲側偭偰嵞惗偝傟偰偄偔丅 丂丂 |
 俀丆嬎氣掗偑廃埻偺斸敾傕屭傒側偄偱丄偁傟傎偳嬎氣峏堖傪挒垽偟偨偺偼側偤丠 俀丆嬎氣掗偑廃埻偺斸敾傕屭傒側偄偱丄偁傟傎偳嬎氣峏堖傪挒垽偟偨偺偼側偤丠 丂 |
| 亙杮暥偐傜亜
丂暔岅偼丄乽掗偑偙偺曽傪奿暿挒垽偟偰偄傞乿偲偄偆婛惉帠幚偐傜岅傜傟弌偡丅側偤挒垽偡傞傛偆偵側偭偨偐偼丄堦尵傕傆傟傜傟偰偄側偄丅 丂偱偼丄偙偺曽偑懠偺恖傛傝傕彑偭偰摿暿偵旤偟偄偐偲偄偆偲丄偦傟傕岅傜傟側偄丅擇恖偺娫偵抋惗偟偨峜巕偼乽悽偵側偔惔傜側傞嬍偺乿偲傕偆偙傟埲忋偵側偄偲偄偭偨宍梕岅傪楢偹偰丄嵟崅偺旤偱岅傜傟偰偄傞偵傕偐偐傢傜偢偩丅 峏堖朣偒屻偺掗偺捛壇偺拞偱丄乽怱偙偲側傞壒傪偐偒柭傜偟丄偼偐側偔暦偙偊弌偯傞尵偺梩傕丄恖傛傝偼堎側傝偟偗偼傂偐偨偪偺乿偲岅傜傟傞偩偗偱偁傞丅 旤杄偵偼堘偄側偄偑丄乽愨悽偺旤彈乿偲偄偆庯偼側偄丅 丂偱偼丄惈幙偑奿暿椙偐偭偨偺偐丅偨偟偐偵丄峅婮揳彈屼偺丄乽偄偲偍偟偨偪偐偳偐偳偟偒強傕偺偟媼傆屼偐偨偵偰乿偲偄偆惈奿宍惉偼丄偙偺掗偱側偔偰傕丄 宧墦偟偨偄強偱偁傠偆偑丄懠偵戝惃偺彈屼丒峏堖偑偄傞側偐偱丄偙偺峏堖偺傒偺摿怓偁傞恖暱偲偄偊偽丄忋昳偱偁傞偙偲偲丄壐傗偐偱慇嵶側恄宱偺帩偪庡偲偄偆偲偙傠偱偁傠偆丅 丂抝彈偺拠偺堦栚崨傟偲偄偆偺偼丄棟桼側偳側偄丅偩偐傜偙偺擇恖偺拞偑奿暿側偺偼丄慜悽偐傜偺廻墢側偺偩傠偆丄偲岅傝庤偼挳偒庤偺堄傪媯傫偱尵偆丅 壥偨偟偰偦傟偩偗偐丠丂丂丂丂丂丂丂丂 |
| 亙撉傒夝偒亜丂丂
丂堦栚崨傟傕偁傠偆丄峏堖偺惈奿偺傛偝傕偁傠偆丅偦偟偰廃埻偐傜偄偠傔傜傟傟偽偄偠傔傜傟傞掱垽偟偝偑曞傞偲偄偆偺傕偁傞偩傠偆丅 偟偐偟丄偦傟偩偗偱偼丄掗偺偁偺挒垽傇傝偼愢柧偟偵偔偄丅 丂摿偵丄峜巕偑抋惗偟偰偐傜偺堦尒丄巚椂怺偄峴摦傪庢傞傛偆偵側偭偨掗偑丄 屻椓揳偵偄偨懠偺峏堖傪傛偦偵堏偟偰丄偙偺恖偵忋嬊傪梌偊傞偲偄偆傗傝曽偵偼丄扨側傞揗垽偱偼側偔丄峏堖傪忋嬊傪傕偮彈屼懸嬾偵偟偰丄 廃埻偺偄偠傔傪嫋偝側偄偲偄偆嫮偄堄巙偑巉偊傞丅 丂偙偙傑偱掗偑乭偙偺恖乭偲怱偵寛傔傞壗偐偑偁傞偲偟偨傜丄偦傟偼側偵偐丅偦傟偼丄偙偺恖偩偗偑帩偮忦審偱懠偺傂偲偺側偄傕偺偩丅 偙偙偱撉傒庤偵晜偐傃忋偑傞偺偼丄偙偺恖偺擖撪偺堎椺偝偩丅偙偺恖偩偗偑屻尒栶偺晝傗孼傪帩偨側偄丅 丂懠偺彈惈偼偡傋偰丄偦偺攚屻偵晝孼偺惌帯揑側嫮偄婜懸偑偁傞丅偙偺恖偵偼丄撲侾丆偱夝愢偟偨傛偆偵丄晝偺堚尵偑偁傞偑丄偟偐偟丄偦傟偼尰幚揑偵偼側傫傜掗傪峉懇偟側偄丅 偙偺帠幚偼埬奜巚偄堄枴傪帩偮偺偱偼側偄偐丅 丂峏堖朣偒屻丄懠偺偳傫側彈惈偵傕堅傑側偐偭偨掗偑桞堦堅傔傜傟偰偄偔偺偼丄摗氣丅偙偺恖傕晝傕曣傕偄側偄恖丅 丂偙偺揰偵丄嬎氣掗偺丄愛娭壠偺惃椡傪攔彍偟偰丄墹尃偺妋棫傪朷傓堄巙傪撉傒偲傠偆偲偡傞偺偑丄娾攇怴彂嵟怴姧偺亀尮巵暔岅偺悽奅亁偺挊幰擔岦堦夒巵丅 乽尮巵暔岅乿傪墹尃偲惌帯偺暔岅偲偟偰撉傒偲傠偆偲偡傞庡挘偩丅 丂嬎氣掗偼丄堦偺峜巕傪傗傓側偔搶媨偵偼偡傞偑丄奜愂偺塃戝恇惃椡傪嬌椡攔彍偟偨偄堄巙偼柧敀偱丄偦傟備偊丄尮巵傪恇愋崀壓屻丄嵍戝恇偺昉偲寢崶偝偣傞偙偲偵側傞丅 塃戝恇傪墴偝偊傞嵍戝恇傪枴曽偵偟偨偐偨偪偩丅 丂乽尮巵暔岅乿傪墹尃偲惌帯偺暔岅偲撉傓庡挘偵偼慡柺揑偵偼巀惉偟偑偨偄偑丄嶌幰巼幃晹偑丄嬎氣掗傪乽揤峜恊惌乿傪幚尰偡傞掗偲昤偄偨偺偼帠幚偩丅 偦傟備偊丄暔岅偺晳戜傪帪戙揑偵丄彂偐傟偨摉帪傛傝傕侾侽侽擭掱慿傞戠岉揤峜偺屼戙偺僀儊乕僕偱撉傑偣傞岺晇傪偟偰偄傞丅 丂嬎氣掗偑側偤丄嬎氣峏堖傪偁傟傎偳傑偱偵挒垽偟偨偺偐丠塃戝恇傜奜愂偺尃椡傪傕偨側偄偨偩堦恖偺彈惈偲偟偰垽偡傞偙偲偑偱偒偨偐傜丄偲峫偊傞偙偲偑壜擻偩傠偆丅 丂丂丂丂 |
 俁丆嬎氣掗偑揤峜偱偁傝側偑傜丄峏堖偵懳偡傞屻媨偺偄偠傔傪嬛巭偱偒側偐偭偨偺偼側偤偐丠 俁丆嬎氣掗偑揤峜偱偁傝側偑傜丄峏堖偵懳偡傞屻媨偺偄偠傔傪嬛巭偱偒側偐偭偨偺偼側偤偐丠 丂 |
| 亙杮暥偐傜亜
丂暔岅偱偼丄屻媨偺崷傒偹偨傒傪偆偗偰乽偄偲偁偮偟偔側傝備偒丄傕偺怱傏偦偘偵棦偑偪側傞傪丄偄傛偄傛偁偐偢偁傢傟側傞傕偺偵巚傎偟偰丄 恖偺偦偟傝傪傕偊偼偽偐傜偣媼偼偢丄乿堦憌挒垽偑傑偝傞偲彂偔丅 丂傑偨丄屼巕抋惗屻偺傑偡傑偡寖偟偔側傞偄偠傔偵懳偟偰傕丄乽偄偲偳偁偼傟偲屼棗偠偰丄屻椓揳偵傕偲傛傝偝傇傜傂媼傆峏堖偺憘巌傪丄傎偐偵堏偝偣媼傂偰乿偲偁傞偩偗偱丄 掗偼屻媨偺彈惈払偵捈愙偺柦椷傪敪偟偰偄側偄丅偨偩峏堖偵懳偡傞帺暘偺垽忣傪憹偡偙偲偲丄嵟壓埵偺偺峏堖偺晹壆傪堏摦偡傞帠偩偗丅 丂揤峜偲偄偆嵟崅偺抧埵偵偁傞恖偵丄屻媨偺巟攝椡偑尒傜傟側偄偺偼側偤偐丠 |
| 亙撉傒夝偒亜丂丂
丂棟桼偼婔偮偐峫偊傜傟傞丅傑偢丄屻媨偺拋彉偲偄偆傕偺偼丄掗偺湏堄偱摦偐偣傞傕偺偱偼側偔丄 屻媨偵柡傪憲傝弌偟偰偄傞婱懓幮夛偺椡娭學偵巟攝偝傟偰偄傞傕偺偱丄嬎氣掗偺屻媨偵偍偄偰偼丄堦偺峜巕偺彈屼傪捀揰偲偟偰彉楍偑寛傑偭偰偄傞丅 丂偦傟傪棎偟偰偄傞偺偑丄峏堖傪挒垽偡傞掗偺懁偱偁傝丄掗偺柦椷偲偄偆傕偺傕掕傑偭偨拋彉傪庣傜偣傞傕偺偱側偔偰偼敪偣傜傟側偄偱偁傠偆丅 掗偲偼拋彉偺捀揰偵埵抲偯偗傜傟偨懚嵼偱偁偭偰丄姶忣偵帺桼偵廬偊傞屄恖偱偼側偄丄偲偄偆偙偲丅 丂戞擇偵丄偙偺抜奒偱偺嬎氣掗偼丄懄埵屻娫傕側偔偱丄傑偩擭庒偔丄帺暘偺椡偲偄偆傕偺傪敪婗偱偒傞傑偱偵帄偭偰偄側偄丅 斵偺屻尒栶偼丄柡傪堦偺彈屼偲偟偰嵎偟弌偟偨塃戝恇偑壥偨偟偨偄偲偙傠偱偁傞偑丄掗偺峏堖偵懳偡傞挒垽偼丄偙偺塃戝恇偺惃椡傪寵偭偰偺偙偲偲偄偆堄枴崌偄偑尒偰庢傟傞丅 丂偮傑傝丄傑偩擭庒偄嬎氣掗偼丄帺暘撈帺偺椡傪敪婗偟偨偄偲婅偭偰偄側偑傜丄傑偩偦偺椡傪帩偪摼側偄帪婜偱偁傞偲尒傜傟傞丅 屻媨偺拋彉傪弬偵偟偨峅婮揳彈屼偺偄偝傔偵懳偟偰偼丄偦傟傪柍帇偱偒側偄掗偑昤偐傟偰偄偨丅 嬎氣峏堖傪彆偗傞椡偺傑偩柍偄掗偺傕偲偱丄峏堖偼徚偊偰備偔傎偐側偄丅掗偵岝傞孨傪僾儗僛儞僩偟偰丅 丂嬎氣掗偑椡傪敪婗偡傞堊偵偼丄峅婮揳彈屼傪埑搢偡傞抧埵傪帩偮彈惈傪摼傞偙偲丄塃戝恇傪埑搢偡傞尃椡傪帩偮恇壓傪僶僢僋偵傕偮偙偲偑昁梫偱偁傞偺偩丅 偦傟偑摗氣偱偁傝丄岝傞孨偺屻尒偲偟偰偺嵍戝恇偱偁傞丅摗氣擖撪偺偲偒丄掗偼懄埵屻侾侽擭傎偳宱夁丅斵偺揤峜偲偟偰偺椡検偑恇壓偵傕怹摟偟偰偄傞偙傠偱偁傞丅 丂斵偑丄揤峜埵偵俀侽擭傎偳偄傞偁偄偩偵丄恇壓傪梷偊丄屻媨偵懳偟偰傕埑搢揑側椡傪帩偮傛偆偵側偭偰偄偭偨條巕偼丄 摗氣傪峜岪偵偟偨帪偵徹柧偝傟傞丅 丂搶媨偺曣彈屼偱偁傝丄偦偺巕偑懄埵偡傞帠懺偵側偭偨偵傕偐偐傢傜偢丄峅婮揳彈屼傪棫岪偝偣偢丄 摗氣傪峜岪偵偟丄偦偺巕乮幚偼尮巵偺巕丄屻偺椻愹掗乯傪師婜搶媨偵偡傞丅偙傟偼偐側傝堎椺偺偙偲偱偁傝丄峅婮揳偺晄枮偼摉慠偱偁傞丅 丂偦傟偵懳偟偰丄乽偁側偨偼揤峜偺曣偲偟偰亀峜懢岪亁偲偄偆徧崋傪偊傞偺偩偐傜丄偦傟偩偗偱偄偄偩傠偆乿偲愢摼偡傞丅擺摼偣偞傞傪摼側偄峅婮揳彈屼偱偁偭偨丅 丂戅埵偟偨嬎氣掗偼丄庨悵掗懄埵屻傕堾偲偟偰幚尃傪埇傝丄塃戝恇曽傪梷偊偮偯偗丄岝傞孨偑屻尒傪偡傞搶媨偺抧埵偑埨懽偡傞傛偆偵恾偭偰偄傞丅 偦偺嬎氣掗偑戅埵屻傢偢偐侾擭偱巰嫀偟偨偙偲偐傜丄摗氣丒岝傞孨曽偺崲擄偑巒傑傞丅丂 丂丂 |
 係丆嬎氣掗偵嵟弶偵擖撪偟偨彈屼偼塃戝恇壠偺昉偱偁偭偨丅偱偼嵍戝恇壠偼偳偆偟偰偄傞偺丠 係丆嬎氣掗偵嵟弶偵擖撪偟偨彈屼偼塃戝恇壠偺昉偱偁偭偨丅偱偼嵍戝恇壠偼偳偆偟偰偄傞偺丠 丂 |
| 亙杮暥偐傜亜
丂掗偲峏堖偲偺娫偵乽嬍偺傪偺偙屼巕乿偑抋惗偟偨偲岅傞暥偵偡偖懕偄偰丄乽堦偺傒偙偼塃戝恇偺彈屼偺屼暊偵偰乿偲丄搊応偡傞彈屼丅偙偺恖偑偙偺屻丄 偢偭偲岝尮巵偺揋栶偲偟偰棫偪偼偩偐傞恖丅塃戝恇壠偺昉偑嬎氣掗偺嵟弶偵擖撪偟偨彈屼偩偭偨丅偍偦傜偔掗偑搶媨偱偁偭偨偲偒偵偦偺斳偲偟偰擖撪偟偨偺偱偁傠偆丅 偦偟偰偙偺曽偵偼丄偡偱偵峜彈傕傆偨傝偄傞丅 丂揔楊偺柡傪傕偭偨忋払晹偼偒偦偭偰柡傪擖撪偝偣傛偆偲偡傞丅偦偺嵺丄堦斣栚偵擖撪偡傞乭尃棙乭傪帩偮偺偼丄堦斣偺惃椡壠丅 丂偱偼丄塃戝恇傛傝忋埵偺戝恇偱偁傞嵍戝恇壠偼偳偆偟偰偄傞偺偐丠挳偒庤偺娭怱偵偼側偐側偐摎偊側偄岅傝庤偼丄嬎氣偺姫嵟屻偺応柺偱傗偭偲嵍戝恇傪搊応偝偣傞丅 尮巵侾俀嵨偱偺尦暈偵嵺偟丄乽堷偒擖傟偺偍偲偳乿偲偟偰搊応偟偨偺偩丅偦偟偰丄偦偺杒偺曽偱偁傞媨暊偺屼傓偡傔傪尮巵偺乽揧傂傇偟乿偲偟偰嵎偟弌偡偺偩丅 丂偦偺傓偡傔偵偼丄搶媨偺曽偐傜乽屼婥怓偁傞乿偮傑傝搶媨斳偲偟偰擖撪偟側偄偐偲梫惪偑偁偭偨偺偵丄椙偄曉帠傪偟偰偄側偐偭偨偺偩偑丄偦傟偵偼 偙偺孨偵柡傪偲偄偆峫偊偑偁偭偨偐傜偲岅傞丅掗偐傜傕乽屼婥怓偨傑偼傞乿偲偁傝丄嵍戝恇丒掗偺崌堄偺忋偺寢崶榖偱偁傞丅 丂乽偝傜偽丄偙偺愜傝偺屻尒側偐傔傞傪乿偲偄偆掗偺尵梩偐傜丄恇壓偵崀傝丄惉恖偟偨尮巵傪偄傛偄傛恊偺斴岇偐傜曻偨側偗傟偽側傜側偄掗偑丄 偦偺屻尒傪嵍戝恇偵戸偟偨偙偲偑暘偐傞応柺偱偁傞丅 丂嵍戝恇偼掗偺怣擟偑岤偔丄杒偺曽偼掗偲摨偠峜岪傪曣偲偡傞撪恊墹偩偭偨恖丅偦偺壠偑尮巵傪寎偊偰丄堦憌壺傗偐偵側傝丄 搶媨偺奜慶晝塃戝恇壠傪埑搢偟偰偄傞偲偄偆丅 |
| 亙撉傒夝偒亜
丂嬎氣掗偺屻媨偵嵍戝恇壠偺彈屼偑搊応偟側偐偭偨棟桼偼丄揔楊婜偺柡偑偄側偐偭偨偐傜偩丅偝傜偵偦偙偐傜晜偐傃忋偑傞撲丅 忋埵偺嵍戝恇偼塃戝恇傛傝傕偢偭偲擭偑庒偄偺偐丠 丂偦偆偄偆偙偲偩傠偆丅嵍戝恇偼嬎氣掗偲摨悽戙丅塃戝恇傛傝辍偐偵庒偄傛偆偩丅 偦傟偑忋埵偺嵍戝恇偺埵偵偄傞偲偄偆偙偲偼丄偙偺恖偺壠暱偑塃戝恇傛傝傕偢偭偲崅偄偲偄偆偙偲偩傠偆丅搶媨偲摨暊偺峜彈傪惓嵢偵寎偊傞偲偄偆偺傕 晝掗偺偍傏偊偑崅偐偭偨偐傜丅懠偲嫞傢側偔偰傕丄庒偔偟偰嵟崅埵偵忋傞壠暱丅 丂偱偼丄巵偼丠嵍戝恇偺挿抝乽摢拞彨乿偑丄撪戝恇偺崰丄偦偺巕懅偺堦恖偲偟偰乽摗帢廬乿偑偱偰偔傞乮乽忢壞乿乯丅 傑偨丄懢惌戝恇偺崰偵傕乽摗嵣憡乿偲屇偽傟傞懅巕偑搊応偡傞丅偙傟偐傜敾抐偟偰丄乮摉慠偺帠偩偑乯嵍戝恇偼摗尨巵偱偁傞丅 偲偡傞偲丄嵍戝恇偼摗尨巵拕棳偺壠暱偐丅 丂偦傟偵懳偟偰塃戝恇偼朤宯偺壠暱偱丄帺暘屄恖偺惌帯椡偵傛傝偼偄忋偑偭偰偒偨壠宯偐丅 塃戝恇偺挿彈峅婮揳彈屼偑敪尵椡傪帩偭偰偄偰丄巕偳傕偺庨悵掗偵傕椡傪婗偆條側偳偐傜尒傞偲丄摗尨寭壠偑嵨庢偭偰偐傜傗偭偲 挿彈慒巕偺惗傫偩堦忦掗偺悽偵幚尃傪摼偨椺偑巚偄晜偐傇丅 丂嵍戝恇偼惌帯椡側偳側偝偦偆偱丄惗傑傟偺椙偝偑偦偺傑傑戦梘側恖暱偲側偭偰偄傞姶偠偱丄嵢戝媨嫟乆丄傂偨偡傜柟偑偹偲偟偰寎偊偨尮巵傪偐傢偄偑傞丅 |
 俆丆偨偭偨堦廡娫偱悐庛巰偡傞嬎氣峏堖偺巰場偼側偵偐丠 俆丆偨偭偨堦廡娫偱悐庛巰偡傞嬎氣峏堖偺巰場偼側偵偐丠 丂 |
| 亙杮暥偐傜亜
丂嬎氣峏堖偺懱挷偺埆偝偼丄嵟弶偺徯夘帪偐傜岅傜傟偰偄偨丅 丂乽偁偝備傆偺媨巇傊偵偮偗偰傕丄恖偺怱傪偺傒摦偐偟丄崷傒傪晧傆偮傕傝偵傗偁傝偗傓丄偄偲偁偮偟偔側傝備偒丄傕偺怱傏偦偘偵棦偑偪側傞乿偲丅 恖乆偺崷傒傪攦偆偙偲傪婥偵昦傫偱偺怱楯偐傜偺懱挷偺埆偝偲峫偊傜傟偰偄傞丅 丂屼巕偑惗傑傟偰偐傜屻丄峏偵寖偟偔側傞偄偠傔偺拞偱丄乽傢偑恎偼偐傛傢偔丄傕偺偼偐側偒偁傝偝傑偵偰乿偲偄偆忬懺偑偮偯偔丅 丂屼巕俁嵨偺屟拝傪廔偊偨屻偺壞丄 乽傒傗偡強偼偐側偒怱抧偵傢偯傜傂偰丄傑偐偱側傓偲偟媼傆乿偺偵丄掗偑偄偲傑傪梌偊偢偵偄傞娫偵丄傢偢偐俆丆俇擔偱 堦婥偵悐庛偡傞丅 丂傗偭偲掗偑偄偲傑傪弌偟丄戅弌偟傛偆偲偄偆帪偵偼丄傕偆婋撃忬懺偱丄懅傕愨偊愨偊偱丄傢偢偐偵暿傟偺壧傪偄偆偺偑傗偭偲丅 尵偄巆偟偨偄偙偲偑偁傝偦偆偱偁偭偨偑丄傕偆岥偵弌偡婥椡偑側偐偭偨丅峏堖偑戅弌偟偰偡偖丄掗偑弌偟偨巊偄偑棦偵摓拝偟偨帪偵偼丄偡偱偵懅愨偊偰偄偨偁偲偩偭偨丅 丂丂丂丂 |
| 丂亙撉傒夝偒亜
丂峏堖偺嬶崌偺埆偝偼丄乽偼偐側偒偁傝偝傑偵偰乿乽偼偐側偒怱抧偵傢偢傜傂偰乿偲偄偆尵梩偱岅傜傟傞偩偗偱丄擬偑偁傞偲偐丄嫻偑捝傓乮巼忋偺応崌偼偙傟乯偲偐偄偆嬶懱揑側恎懱忋偺婰弎偑側偄偺偑摿挜偱偁傞丅 惛恄揑側庛偝丄怱楯偲偄偆尨場偟偐峫偊傜傟側偄傛偆偩丅 丂屼巕抋惗屻偼傢偢偐俀擭偵枮偨側偄擭寧偱堦婥偵庛偭偰巰偵帄傞丅 偦偺斵彈傪惗偐偟偰偄偨偺偼丄屼巕偺柍帠側惉挿傪尒撏偗偨偄偲偄偆巚偄偩偗偩偭偨偺偩傠偆丅 俁嵨偺屟拝乮崱偺幍屲嶰偵偁偨傞丄巕偺柍帠側惉挿傪偄傢偆嵟弶偺峴帠乯傪尒撏偗傞偲傕偆丄婥椡偑恠偒偰偟傑偭偨傛偆偩丅 丂偦偟偰丄恎懱偵姮偊傞偺偼嫗搒偺壞偺婥岓丅杶抧摿桳偺忲偟弸偝偼丄椻朳憰抲偺側偄屆戙偱偼搤偺姦偝傛傝傕傕偭偲恎懱偵姮偊傞傕偺偱偁傞偺偼丄 乽搆慠憪乿偺寭岲偑丄乽壠嫃偺偮偒偯偒偟偒偼壞傪傓偹偲偡丅搤偼偄偐傗偆偵傕廧傑傞丅乿偲尵偭偰偄傞偙偲偐傜傕暘偐傞丅 彈嶰媨偺崀壟偱怱楯偺廳側偭偨巼忋偑懅傪堷偒庢傞偺偼廐偩偑丄挿擭偺懱挷偺埆偝偑媫寖偵埆偔側傞偺偑傗偼傝壞偱偁傞丅 丂峏堖偺巰場偼丄尦棃偺庛偄懱幙偲惛恄揑側庛偝偺忋偵壛偊傜傟偨廃埻偺偄偠傔偵傛傞怱楯偲偄偆傎偐側偄偩傠偆丅 傢偢偐屲丆榋擔偱媫寖偵埆壔偲偄偆偺傕丄恎懱偵姮偊傞壞偺婥岓偐傜偲尒傞傎偐側偝偦偆偩丅 丂偙偺媫寖側埆壔偲尵偆偙偲偐傜丄庺偄傪偐偗傜傟偨偲偐丄撆傪惙傜傟偨偲偐峫偊傞偺偼丄昁梫側偄偲巚偆丅 曣杒偺曽偺乽墶偞傑側傞巰乿偲偄偆尵偄曽傕丄峏堖偵岦偗傜傟偨悢擭娫偵傢偨傞偄偠傔偲偄偆偙偲偱廫暘偦偺堄枴偑弌偰偄傞偲巚偆丅 丂傑偨丄峏堖峌寕偺愭摢偵棫偮峅婮揳彈屼懁偼丄偁偊偰庺偄傪偐偗側偗傟偽側傜側偄傎偳丄棫応偑庛偔側偄丅 峅婮揳彈屼懁偐傜傒傟偽丄峏堖偼恎暘晄憡墳偺忬懺傪嶌傝忋偘偰丄帺暘偱帺暘偺柦傪弅傔偰偄偭偨偺偩丅 峏堖偺巰屻丄廐偺栭傪娗尫偺梀傃偱妝偟傓彈屼懁偵偼丄僗僢偲偟偨偲偄偆婥帩偪偼偁偭偰傕丄巰傫偩峏堖偐傜偺偨偨傝傪堌傟傞婥攝偼側偄丅 丂挳偒庤偼丄峏堖偺巰傪弮悎偵搲傒偮偮丄峏堖偑帺傜偺柦偲偐偊偰丄掗偵戸偟偰偄偭偨屼巕偺彨棃傪峏堖偲偲傕偵婩傞婥帩偪偵側傞丅 丂丂丂丂丂丂 |
 俇丆乽墶偞傑側傞巰乿傪傓偐偊偨峏堖偼側偤巰楈偲側傜側偄偺偐丠 俇丆乽墶偞傑側傞巰乿傪傓偐偊偨峏堖偼側偤巰楈偲側傜側偄偺偐丠 丂 |
| 亙杮暥偐傜亜
丂乽梉婄乿偺姫偺乽朸堾乮側偵偑偟偺偄傫乯乿偵弌尰偡傞乽暔偺夦乿埲崀丄乽尮巵暔岅乿偵偨傃偨傃弌偰棃傞乽惗偒楈乿乽巰楈乿偺偐偢偐偢偩偑丄 暔岅偺拞偱堦斣斶嶴側巰偵曽傪偟偨乽嬎氣峏堖乿偑丄乽巰楈乿偲側偭偰弌偰棃傞偙偲偼堦搙傕側偄丅 丂丂 |
| 丂亙撉傒夝偒亜丂丂
丂側偤峏堖偼乽巰楈乿偲側偭偰搊応偟側偄偐丅暔岅偺拞偵偦偺昁慠惈傪扵偭偰傒傞偲丄峏堖偺嵃偼捔傔傜傟偰偄傞偙偲偑嫇偘傜傟傞丅 丂傑偢丄曣杒偺曽偑挗栤偵朘傟偨柙晧偺柦晈偵尵偭偨乽墶偞傑側傞巰乿偲偄偆尵梩丅偙傟偼挳偒庤偲偡傞偲彮乆嬃偐偝傟偨尵梩偱偁偭偨偲巚偆丅 偢偄傇傫偲偼偭偒傝偄偭偨傕偺偩偲丅偙偺尵梩偑敪偣傜傟偨偙偲偱丄峏堖偺丄屻媨偱偠偭偲懴偊偰偄偨嫻偺撪偑柧傜偐偵偝傟丄 峏堖偺巰偺柍擮偝偼丄岅傝庤挳偒庤傕娷傫偩嫟桳偺巚偄偲側偭偰庴偗巭傔傜傟偨偙偲偵側傞丅 丂偙偺偲偒偺丄曣偲柦晈偑偟傔傗偐偵岅傝柧偐偡応柺偺惷偐側帪偺棳傟偼丄峏堖偺嵃傪捔傔傞摿暿偺帪娫偲偟偰丄岅傝庤偑怱傪崬傔偰岅偭偰偄傞丅乽嬎氣乿偺姫偺側偐偺桞堦偺柤暥偱偁傞丅 丂傑偨丄柦晈偐傜偺尵忋傪怮偢偵懸偭偰偄偨掗偺巔傪丄尯廆峜掗偲梜婱斳偺帠椺偵側傜偄偮偮丄挿崷壧偵岅傜傟偨埲忋偵桙偝傟側偄斶偟傒偱丄 峏堖偺巰傪搲傒懕偗傞偲偟偰偄傞丅偙偺掗偺恞忢偱側偄搲傒偺偙偙傠偑丄偁偺悽偺峏堖偺嵃傪捔傔傞偱偁傠偆丅 丂偝傜偵偼丄乽巰楈乿乽惗偒楈乿偼偳偺傛偆側恖暔偑偳偺傛偆側恖偺慜偵尰傟弌傞偐丄偦偺忦審傪扵偭偰傒傞傋偒偩偑丄 偦傟偼丄崱屻偺暔岅偺嬶懱揑側搊応応柺偱扵偭偰偄偔偙偲偵偡傞丅 丂乽嬎氣峏堖乿偼乽嬎氣乿偺姫偺側偐偱惷偐偵搊応偟丄惷偐偵嫀偭偰偄偭偨恖暔偱偁傞偑丄 偟偐偟丄斵彈偺偙偺悽偵巆偟偨堦斣戝偒側傕偺偼丄曣偺婄偡傜婰壇偵側偄懅巕乽岝尮巵乿偵崗傑傟偨乽曣恊傊偺巚曠乿偲偄偆怺憌怱棟偱偁傠偆丅 斵偺惗奤偺彈惈曊楌偼丄曣傪媮傔傞怱偑巟攝偟偰偄傞偲偄偊傞丅 丂丂丂丂 |
 俈丆堦偺峜巕偑俈嵨偱搶媨偲側偭偰偄傞丅偱偼偦傟傑偱搶媨埵偼偳偆側偭偰偄偨偺偐丠 俈丆堦偺峜巕偑俈嵨偱搶媨偲側偭偰偄傞丅偱偼偦傟傑偱搶媨埵偼偳偆側偭偰偄偨偺偐丠 |
| 亙杮暥偐傜亜
丂堦偺峜巕偼搊応偺嵟弶偐傜丄乽媈偄側偒栕偗偺孨乿偲偟偰悽偺怣朷偑岤偄丅偟偐偟丄岝傞孨偑抋惗偟丄掗偺摿暿偺垽忣偑孹偗傜傟傞偲丄 堦偺峜巕偺曣彈屼偼丄乽朧偵傕傛偆偣偢偼丄偙偺屼巕偺嫃偨傑傆傋偒側傔傝乿偲媈偄偩偟偨丅 搶媨傪寛傔傞帪婜偵偼傑偩帄偭偰偄偢丄師婜搶媨埵偑晄埨掕偱丄媈怱埫婼偑惗偠偰偄傞偺偩丅 懅巕偺搶媨埵丄傂偄偰偼揤峜埵傪搎偟偰偺嬎氣偺峏堖偵懳偡傞偄偠傔偑慻怐壔偝傟偰偄偭偨偺偩偭偨丅 偙偺搶媨埵憟偄偑寛拝傪寎偊傞偺偼丄嬎氣峏堖朣偒屻丄棦偵偄偨岝傞孨偑嶲撪偟偨梻擭偱偁傞丅 乽偁偔傞擭偺弔丄朧偝偩傑傝偨傑傆偵傕丄偄偲傂偒偙偝傑傎偟偆偍傏偣偳丄屼偆偟傠傒偡傋偒恖傕側偔丄傑偨悽偺偆偗傂偔傑偠偒偙偲側傝偗傟偽乿偲偁傞丅 掗偼搶媨朧傪寛掕偡傞偵摉偨偭偰丄撪怱偼偙偺岝傞孨傪棫偰偨偄偺偩偑丄屻尒恖傕偄側偄偟丄悽娫偑彸抦偡傞偼偢傕側偄偺偱丄偍偔傃偵傕弌偝偢偵丄堦偺峜巕傪搶媨偵偟偨偺偱偁偭偨偲尵偆丅 偙偺偲偒搶媨俈嵨丄岝傞孨係嵨乮嵟彮偺悢偊曽偱乯丅 丂尰戙偺揤峜壠偱偼丄堦晇堦晈惂偺抝宯庡媊偱丄堦斣嵟弶偵惗傑傟偨抝巕偑晝偑揤峜偵懄埵偟偨帪偵丄帺摦揑偵搶媨偲側偭偰偄傞丅 偟偐偟丄偙偺堦偺峜巕偼扤傕偑巚偭偰偄傞搶媨岓曗偱偼偁偭偰傕丄偦傟偼寛掕偡傞傑偱偼晄暘柧偩偭偨偺偩丅偱偼丄搶媨埵偲偼偄偮偳偺傛偆側帪揰偱寛掕偡傞偺偐丠 |
| 亙撉傒夝偒亜
丂搶媨偲偼壗偐丠師婜揤峜埵偵廇偔恖偱偁傞丅偦傟偱偼搶媨偼偄偮寛傔傞偐丠怴揤峜偺懄埵偺偲偒偱偁傞丅 偮傑傝丄揤峜偑乭偄偭偨傫偙偲偁偭偨帪乭偼丄嬻敀婜娫柍偔懄埵偱偒傞傛偆偵慜傕偭偰弨旛乮愝偗丒栕偗乯偝傟偰偄傞恖偺偙偲丅 丂偩偐傜丄偙偺乽嬎氣乿偺姫偱偼丄幚偼丄嬎氣掗偺懄埵帪偱側偔丄拞搑偱搶媨偑掕傑傞偲偄偆偺偼堎椺偺偙偲側偺偩丅 壗偐偁偭偨偺偩丅 丂偮傑傝丄嬎氣掗懄埵帪偵偼暿偺恖偑搶媨偲偟偰偄偨偼偢偩丅偦傟偙偦丄乽埁乿偺姫偱搊応偡傞榋忦屼懅強偺晇丄乽愭朧乿偱偁傞丅 偦偺搶媨偑搶媨埵偺傑傑庒巰偵偟偰偟傑偭偨偺偩丅堦偺彈屼偲偟偰戝恇偺柡偑擖撪偟丄偦偺娫偵峜彈傕抋惗偟偰偄偨偺偵丅 丂晇偑寬嵼側傜丄師婜揤峜斳丒峜岪偲偟偰嵟崅偺抧埵偵廇偔偼偢偩偭偨偺偵丄庒偔偟偰乽枹朣恖乿偲側偭偰丄 悽娫偐傜恎傪堷偐偞傞傪摼側偐偭偨屩傝崅偄彈惈偑丄偙偺峅婮揳彈屼偺埨揼偺攚屻偵塀傟愽傫偱偄傞偺偩丅 丂偙偺愭朧偼丄屻偵嬎氣掗偑尮巵傪偄偝傔偰尵偆尵梩偵傛傝丄掗偺掜偱偁偭偨偙偲偑傢偐傞丅 丂偝傜偵峫偊偰傒傛偆丅師婜搶媨傪寛傔傞偺偼偩傟偐丠廳恇払偺怰媍偵傛偭偰寛傔傞偲偄偆寶慜偼偁傞傜偟偄偑丄 幚幙揑偵偼戅埵偡傞揤峜懁偵偁偭偨傛偆偩丅帺暘偑戅埵偟丄搶媨偵揤峜埵傪忳搉偡傞偵摉偨偭偰丄師婜搶媨傪寛傔傞偺偩丅 丂摉慠丄帺暘偵搒崌偺椙偄寣嬝傪慖傇傢偗偱丄帺暘偺巕傪慖掕偟偰偄偔丅偩偐傜柺敀偄偙偲偵揤峜宯恾傪尒偰偄偔偲 揤峜弴偑丄俙宯偲俛宯偲岎屳偵庴偗宲偑傟偰偄偭偰偄傞偺偑傢偐傞丅 丂偙偺暔岅偱偺嬎氣掗慜屻偺峜埵宲彸偼偳偆側偭偰偄傞偐丠偲傝偁偊偢丄摗氣擖撪傪峫偊傞乽俉丆乿偱峫嶡偟傛偆丅 |
 俉丆摗氣偺晝偱偁傞愭掗偲嬎氣掗偼孼掜偐丠 俉丆摗氣偺晝偱偁傞愭掗偲嬎氣掗偼孼掜偐丠 丂 |
| 亙杮暥偐傜亜
丂摗氣偼乽愭掗乿偺乽巐媨乿偱丄曣偼岪偱偁傞丅嬎氣掗偺晝偼乽堦堾乮偄偪偺偄傫乯乿傑偨偼乽庨悵堾乿偲偟偰搊応丅尮巵偼侾俋嵨偺帪丄晝嬎氣掗偺庨悵堾峴岾偵嫙曭偟偰偄傞丅偦偺帪偺帋妝偱晳偭偨乽惵奀攇乿偺旤偟偝偑恞忢偱側偄偲岅傜傟偰偄偨丅 丂摗氣偺晝乽愭掗乿偼婛偵屘恖偲偟偰榖戣偵搊応偟偰偄傞丅偙偺恖偼忳埵偟偰乽堾乿偲側傞偙偲側偔丄嵼埵拞偵巰嫀偟偨恖偲巚傢傟傞丅 丂 |
| 亙撉傒夝偒亜
丂偙偺掗偑朣偔側偭偰丄嬎氣掗偑懄埵偡傞偵摉偨偭偰丄怴搶媨傪寛傔傞嵺偵丄偙偺揤峜曽偺峜巕偑棫懢巕偟偰偄側偄偱丄嬎氣掗偺掜偑棫偭偨偺偩丅 偙偺恖偑乽榋忦屼懅強乿偺晇偱偁傞搶媨偩丅 丂峫偊傞偵丄乽愭掗乿偵偼乽搶媨岓曗乿偲偟偰傆偝傢偟偄峜巕偑偄側偐偭偨偺偩丅偁傞偄偼峜巕傪悇偡嫮椡側屻尒栶偑偄側偐偭偨偺偩丅 摗氣偺孼乽暫晹嫧偺媨乿偑偄傞偑丄偙偺恖偑搶媨偲側傞僠儍儞僗偼柍偐偭偨傛偆偩丅 丂乽暫晹嫧偺媨乿偺擭楊傪悇掕偡傞偵丄 枀摗氣偑擖撪偟偨帪丄斵彈偼尮巵傛傝俆嵟擭挿偺侾俇嵨偔傜偄丅嬎氣掗偲偼丄侾俆嵨偐傜俀侽嵨偔傜偄偺嵎偑偁傞丅 孼偼俀丆俁嵨擭忋偩偲偟偰丄嬎氣掗懄埵帪偵偼傑偩尦暈慜丅偦傟偱傕丄乽愭掗乿偑傒偢偐傜戅埵偡傞偺偱偁傟偽丄 偙偺峜巕傪搶媨偲偟偰悇偟偨偼偢偩偑丄媫巰偟偰偦偺婡夛偑側偐偭偨偺偩傠偆丅 丂偦偙偱丄愭偺掗偱偁傞嬎氣掗偺晝乽堦堾乿偺堄岦偱丄嬎氣掗偺掜峜巕偑搶媨偲側偭偨偲峫偊傜傟傞丅 丂嬎氣掗偲乽愭掗乿偲偼丄乽孼掜乿偲偄偆嬤偟偄娭學偱偼側偔丄偐偊偭偰丄峜埵傪憟偄崌偭偰偄傞擇偮偺峜摑偲峫偊傞偙偲偑弌棃偦偆偩丅 偦傟偑丄乽愭掗乿偺巰嫀偵傛傝丄峜埵偑乽堦堾乿亅乽嬎氣掗乿乕乽掜偺搶媨乿傊偲堦偮偺宯摑偵廂澥偟偰偒偨偲峫偊傜傟傞丅 偙偙偵丄嫮椡側墹尃曐帩幰偲偟偰偺乽嬎氣掗乿偺埵抲偑妋棫偝傟偰偄偭偨偲尒傞偙偲偑弌棃傞偺偱偼側偄偐丅 丂偺偪偵嬎氣掗偑戅埵偡傞偄偒偝偮傪尒傞偲丄掗偼搶媨偱偁傞堦偺峜巕偵埵傪忳傞偵嵺偟丄峅婮揳彈屼傪梷偊丄屻偐傜擖偭偨摗氣傪峜岪偲偟丄 偦偺惗傫偩峜巕傪搶媨偵棫偰丄偦偺屻尒栶偵尮巵傪擟偠傞偲偄偆棧傟嬈傪幚峴偡傞丅偙偙偵偼墹幰偲偟偰偺嬎氣掗偺堄巙偑嫮椡偵摥偄偰偄傞丅 丂乽嬎氣峏堖乿偺巕乽岝尮巵乿傪峜埵偵棫偰傞偙偲傪抐擮偟偨嬎氣掗偼丄乽愭掗偺巐媨乿偲偄偆乽恎暘乿傪帩偮摗氣傪庢傝崬傓偙偲偱丄 塃戝恇曽傪梷偊傞庤偩偰傪摼偨丅 丂丂丂 |
 俋丆崅楉偺憡恖偺梊尵偼壗傪堄枴偡傞偺偐丠 俋丆崅楉偺憡恖偺梊尵偼壗傪堄枴偡傞偺偐丠 丂 |
| 亙杮暥偐傜亜
丂乽嬍偺屼巕乿傪搶媨偵棫偰傞偙偲傪抐擮偣偞傞傪摼側偐偭偨掗偼丄偙偺屼巕偺彨棃傪偳偆偡傞偐丄巚椂偡傞丅傑偢俈嵨偵側傞偲塸嵥嫵堢傪巤偡丅偙偺屼巕偺憦偝偵嬃偒丄 惌帯偵昁梫側娍妛偼傕偲傛傝丄乽嬚乿乽揓乿側偳偺娗尫妝婍傕妛偽偣傞偑丄偙偺屼巕偼揤嵥揑側壒怓傪敪偡傞丅偙偺偁偲丄岝尮巵偼乽嬚偺嬚乮偒傫偺偙偲乯乿偺柤庤偲偟偰暔岅偺嵟屻傑偱岅傝宲偑傟傞丅 丂柍擻側巕側傜偦傟憡摉偺張嬾偱偡傓偑丄偙偺嬃偔傋偒擻椡傪傕偮屼巕偺彨棃傪偳偆偡傞偐丅峫偊偁偖偹偨掗偼偍傝偐傜棃擔拞偺乽崅楉乿偺乽憡恖乮偦偆偵傫乯乿偵愯傢偣傞偙偲偵偡傞丅 恎暘偼嫵堢學偩偭偨塃戝曎偺幚巕偲偄偮傢偭偰丅 丂憡恖偺愯偄偺尵梩丅乽崙偺恊偲側傝偰丄掗墹偺忋側偒埵偵徃傞傋偒憡偍偼偟傑偡恖偺丄偦側偨偵偰尒傟偽丄棎傟桱傆傞偙偲傕傗偁傜傓丅偍傎傗偗偺屌傔偲側傝偰丄揤壓傪曘乮偨偡乯偔傞偐偨偵偰尒傟偽丄 枓偦偺憡偨偑傆傋偟丅乿偮傑傝掗墹偵側傞憡偺帩偪庡偩偑丄傕偟偦偆側偭偨傜揤壓偑棎傟傞偩傠偆丄挬掛偺嫮椡側恇偲偟偰崙偺惌帯傪曗嵅偡傞栶偲偟偰尒傞偲丄偦傟偵傕摉偰偼傑傜側偄憡偩偲偄偆偺偩丅 揤峜偺憡傪傕偮偑丄揤峜偱傕側偔丄恇壓偲偟偰偺乽堦偺恖乿偵傕擺傑傝偒傜側偄恖丅 丂偙偺尵梩傪暦偄偰丄晝掗偼丄偙偺屼巕傪尮巵偵壓偡偙偲偵偡傞丅偮傑傝丄恊墹偺傑傑偱峜埵宲彸偺壜擻惈傪巆偡偙偲傪傗傔偨偺偩丅 偦偺応崌偼悽偺棎傟偑惗偠傞丄偮傑傝丄偙偺巕偑惌憟偵姫偒崬傑傟傞偙偲偑柧敀側偺偩丅傑偨丄屻尒偺側偄恊墹傎偳丄懚嵼偺敄偄幰偼側偄偺偩丅 丂晝偼丄偙偺巕偺嵥擻偵婜懸偟偰丄恇壓偲偟偰丄帺椡偱摴傪愗傝奐偗傞壜擻惈傪慖傫偩丅傕偪傠傫丄怲廳偵屻尒栶傪偝偩傔偰丅 乽岝傞孨乿偲偄偆屇徧偼偙偺乽崅楉乿偺乽憡恖乿偑偮偗偨傕偺偲傕岅傜傟傞丅 |
| 亙撉傒夝偒亜
丂偙偙偱側偤丄乽崅楉乿偺乽憡恖乿偑搊応偡傞偺偐丅 丂妏愳暥屔乽尮巵暔岅乿偺拹偱嬍忋戶栱偼乽崅楉恖乿傪乽偙傑偆偳乿偲傛傒丄幚嵺偵偼乽熭奀崙恖乿偺偙偲偲偟偰偄傞丅 丂楌巎傪偝偐偺傏傞偲丄俋俀侽擭偵熭奀崙偺巊偄偑擖嫗偟丄惓嶰埵傪庼偗傜傟偰偄傞丅偦偺擭丄戠岉揤峜偼峜巕崅柧偵尮巵惄傪梌偊丄恇壓偵壓偟偰偄傞丅 丂偙偺崅柧偙偦丄堦悽尮巵偲偟偰嵍戝恇偺抧埵傑偱徃偭偨偑丄埨榓偺曄偵傛傝幐媟偟丄懢嵣晎偵棳偝傟傞恖偱偁傞丅岝尮巵偺儌僨儖偵媅偣傜傟偰偄傞丅 丂偙偺乽熭奀乿崙偺巊幰棃挬傪傆傑偊偨榖偩偲偟偰丄側偤丄乽崅楉乿崙偺巊幰偲偡傞偺偐丅 丂暔岅偺幏昅帪挬慛敿搰偱偼怴梾偑柵傃丄乽崅楉乮偐偆傜偄丒偙偆傜偄乯乿偑敿搰傪摑堦偟偰偄偨丅 傑偨丄挬慛敿搰偺偙偲傪傂傠偔乽偙傑乿偲屇傇尵偄曽偑偝傟偰偒偨偙偲偐傜丄挳偒庤偵栚丒帹姷傟偨乽崅楉乮偙傑乯乿偵偟偨偺偐傕抦傟側偄丅 丂偟偐偟丄乽偙傑乿偲屇傃姷傢偡乽崅楉乿偼杮棃乽崅嬪楉乿偺偙偲丅 乽怴梾乿乽昐嵪乿乽崅嬪楉乿偲嶰崙暲傫偱丄擔杮偺屆暛帪戙偐傜俇俇俉擭偵搨偵柵傏偝傟傞傑偱丄挬慛敿搰偱椡傪帩偭偨崙偺偙偲丅 丂擔杮彂婭偵傛傞偲丄崅楉偐傜搉偭偰偒偨憁偑丄擔杮偺偁傞恖傪宧偄堌晐偟丄偦偺恖偵柤傪憽偭偨榖偑嵹傞丅惞摽懢巕偱偁傞丅 丂崅楉偺憁宒帨偼屘崙偱懢巕偺巰傪揱偊暦偒丄懢巕傪乽尯乮偼傞偐乯側傞惞偺摽傪埲偰丄擔杮偺崙偵惗乮偁乯傟傑偣傝乿偲偨偨偊丄忩搚偱懢巕偵夛偄丄 嫟偵廜惗嵪搙傪偟偨偄偲師偺擭偺懢巕偺柦擔偵巰傪惥偄丄壥偨偡偲偟偰偄傞丅憁宒帨偼懢巕偺俀侽戙偺帪丄擔杮偵搉傝丄懢巕偺巘偲偟偰栺俀侽擭娫嫵偊摫偄偨恖偱偁傞丅 惞摽懢巕偺屇徧偼偙偺巘偵傛傝晅偗傜傟偨偺偩丅 丂乽尮巵暔岅乿偺嶌幰偼丄偙偺惞摽懢巕揱愢傪偙偺屼巕偵偐偝偹偰丄乽崅楉乿偺乽憡恖乿偺梊尵偺嫮椡側偙偲傪撉傒庤偵報徾偯偗偰偄傞偺偱偁傞丅 丂偝偰丄偙偺乽崅楉乿偺乽憡恖乿偺愯偄偑幚尰偡傞夁掱偑丄乽尮巵暔岅乿戞堦晹偺摴嬝偱偁傝丄恵杹戅嫀偺恏巁傪側傔偨偁偲丄 搒偵曉傝嶇偄偨尮巵偑丄巐廫偺夑傪傑偊偵丄懢惌戝恇傪挻偊偰丄恇壓偱偁傝側偑傜丄堷戅偟偨揤峜偵旵揋偡傞弨懢忋揤峜偲偟偰丄 乽堾乿偺徧崋傪偊傞偲偄偆慜恖枹摜偺嫬抧偵帄傞寢枛偑梡堄偝傟偨丅 丂丂 |
 侾侽丆嵍戝恇偼側偤柡偺埁傪搶媨斳偵偟側偄偺偐丠 侾侽丆嵍戝恇偼側偤柡偺埁傪搶媨斳偵偟側偄偺偐丠 丂 |
| 亙杮暥偐傜亜
丂尮巵侾俀嵨偺尦暈偵嵺偟丄乽堷偒擖傟乿偺戝恇偲偟偰弶傔偰搊応偟偨嵍戝恇偱偁偭偨偑丄尦暈偺媀幃偑懾傝側偔嵪傫偱偄偔柾條傪岅傞暥偺拞偵丄 偙偺戝恇偺傓偡傔偺榖戣偑嵎偟偼偝傑傟偰偔傞丅 丂乽堷偒擖傟偺偍偲偳偺傒偙偽傜偵丄偨偩堦恖偐偟偯偒媼傆屼傓偡傔丄搶媨傛傝傕屼婥怓偁傞傪丄偍傏偟傢偯傜傆帠偁傝偗傞丄偙偺孨偵曭傜傓偺屼怱側傝丅乿 丂堷偒擖傟偺戝恇偺峜彈暊乮峜彈偱偁傞嵢偺偍嶻傒偵側偭偨巕乯偵丄偨偩傂偲傝戝愗偵偍堢偰側偝偭偰偄傞昉孨丄偦偺曽偵偼搶媨偐傜傕斳偲偟偰偺偛強朷偑偁偭偨偑丄 晝偺戝恇偼偍曉帠傪廰偭偰偄傜偭偟傖偭偨偑丄偙偺孨偵嵎偟忋偘傛偆偲偺偍峫偊偩偭偨偺偩丄偲岅傝庤偼愢柧偡傞丅 |
| 亙撉傒夝偒亜
丂係丆偺栤偄偱偺撉傒夝偒偱婛偵怗傟偨偑丄嵍戝恇偼帺暘偺強偺堦斣偺庤嬵偱偁傞丄媨暊偺傓偡傔傪嵟弶偐傜丄岝尮巵偵嵎偟弌偟偨偄偲峫偊偰偄偨偲偄偆丅 搶媨偺尦暈偵嵺偟丄愭曽偐傜強朷偝傟偨擖撪傪偁偊偰抐偭偰偄偨丅 丂師婜揤峜斳偲偟偰丄峜巕傪惗傔偽偦偺巕偼傗偑偰揤峜埵偵偮偔偐傕偟傟側偄丄傓偡傔偼峜岪偵傕側傞偱偁傠偆丄偦偺壜擻惈傪偡偰偰丄恇壓偵壓偭偨乽岝尮巵乿傪乽柟乿偵丄偲偼偳偺傛偆側峫偊側偺偐丅 丂堦斣偵峫偊傜傟傞偺偼丄嬎氣掗偺堄岦偱偁傞丅尮巵偺尦暈帪偵丄嵍戝恇偵屻尒栶傪埶棅偟偨偺偼掗偱偁傝丄嵍戝恇偲偺憡屳偺椆夝偑偁偭偨丅 掗偼塃戝恇偺椡傪梷偊傞堊偵丄嵍戝恇偺椡傪帺暘偺懁偵庢傝崬傓昁梫偑偁傞丅 丂嵍戝恇偲偟偰偼丄柡傪搶媨偺彈屼偲偟偰弌偡偙偲偼丄塃戝恇壠偵柡傪嵎偟弌偡偙偲偵側傝丄帺暘偑偦偺壓偵埵抲偡傞偙偲偵側傞丅 丂嵍戝恇偼偍側偠摗尨巵偱偁傞偑丄塃戝恇偲偼壠宯偑堘偆柤栧偱丄 撪恊墹傪嵢偲偟偰寎偊傞偙偲偑偱偒傞壠偱偁傞丅怴嫽惃椡偱偁傝丄奜愂偲偟偰尃椡傪埇傝偨偄塃戝恇傪梷偊傞堊偵丄掗偲嵍戝恇偲偺嫟摨愴慄偑偼傜傟偨丅丂 |
 侾侾丆乽岝傞孨丄恇愋崀壓丄尮巵偲側傞乿偲偼偳偆偄偆偙偲偐丠 侾侾丆乽岝傞孨丄恇愋崀壓丄尮巵偲側傞乿偲偼偳偆偄偆偙偲偐丠 丂 |
| 亙杮暥偐傜亜
丂掗偼堦偺峜巕傪搶媨埵偵偮偗偨屻傕丄偙偺屼巕偺庢傝埖偄偼寛傔偐偹偰偄偨丅乽崅楉乿偺乽憡恖乿偵屼巕傪愯傢偣偨偩偗偱側偔丄帺恎傕屼巕偺憡傪愯偄摨偠寢壥傪摼偰偄偨丅偝傜偵 懡偔偺愯偄傪嬈偲偡傞恖偵傕尒偣偰偄傞丅 丂掗偼偍偍偄偵擸傫偱偄偨偺偩丅偟偐偟丄偳偺愯偄偵傛偭偰傕屼巕傪偙偺傑傑恊墹偵偡傞偙偲傪惀偲偟偰偄側偄丅 丂乽恊墹偲側傝媼傂側偽丄悽偺媈傂晧傂媼傂偸傋偔傕偺偟媼傊偽丄廻梛偺尗偒摴偺恖偵偐傫偑傊偝偣媼傆偵傕丄摨偠偝傑偵怽偣偽丄 尮巵偵側偟曭傞傋偔丄偍傏偟偍偒偰偨傝丅乿 傑偩丄恀堄偼扤偵傕崘偘側偄偑丄怱拞偱偼寛傔偰偄偨丅 丂傗偑偰丄偙偺屼巕傪恇壓偵壓偟乽尮乿巵傪梌偊傞偙偲偼幚峴偵堏偝傟偨傜偟偄丅壗嵨偐偼暘偐傜側偄偑丄 摗氣擖撪偺榖偺偁偲丄偙偺屼巕偼乽尮巵偺孨偼乿偲徧偝傟偰偄傞丅 丂 |
| 亙撉傒夝偒亜
丂偙偙偱偝傑偞傑側栤偄傪棫偰傞偙偲偑偱偒傞丅 丂嘆丂乽峜巕傪恇壓偵壓偡乿偁傞偄偼乽尮巵傪帓傆乿偲偼偳偆偄偆偙偲偐丠 丂嘇丂傑偨丄掗偼側偤丄屼巕傪恊墹偲偣偢丄峜懓偺恎暘傛傝辍偐偵壓偲側傞恇壓偵偡傞偺偐丅 丂嘊丂偝傜偵丄偙偺暔岅偵偍偄偰丄庡恖岞偑揤峜偺巕偲偟偰偺嵟崅偺恎暘偱搊応偟側偑傜丄恇壓偵壓傞偙偲偱暔岅偲偟偰偺偳偺傛偆側敪揥偑壜擻偵側傞偺偐丠 丂嘆丂乽巵乿偼忋戙偵崑懓偑帺傜偺宯摑傪帵偟丄懠偲嬫暿偟偨柤徧丅乽惄乮敧怓偺惄傗偔偝偺偐偽偹乯乿偼揤晲揤峜 偑榋敧巐擭偵丄奺巵偺壠奿傪惍棟摑堦偡傞偨傔偵惂掕偟偨敧摍媺偺惄丅恀恖丒挬恇丒廻擧側偳丅丂 丂峜懓偼巵惄偑側偄丅偩偐傜揤峜偺巕偑恇壓偵崀傝傞帪偼丄巵傪梌偊傜傟傞丅偦傟偑乽尮乿傗乽暯乿傗乽嵼尨乿偱偁傞丅 丂嘇丂嬎氣掗偑岝傞孨偺彨棃傪偄傠偄傠峫偊偰丄恇壓偵偍傠偟偨偺偼丄堦偮偵偼丄恊墹偱偁傟偽峜埵偵棫偮壜擻惈偑偁傝丄偦偺応崌偺揤壓偺棎傟傪偝偗傞堊丅 傑偨丄偨偩偺乽恊墹乿偱堦惗傪廔偊傞偲偟偨傜丄偦傟偼屼巕偵偲偭偰偐傢偄偦偆側偙偲偲峫偊偨偺偱偁傠偆丅 丂乽尮巵暔岅乿偺搊応偡傞懡偔偺乽恊墹乿偑丄偡傞偙偲偺側偄偮傑傜側偄惗妶傪憲偭偰偄傞偟丄拞偵偼乽敧偺媨乿偺傛偆偵悽偺拞偐傜朰傟傜傟偨懚嵼偵側偭偰偟傑偆丅 揤峜偺巕偲偟偰惗傑傟偨側傜丄揤峜偵側傞埲奜偵偼偐偊偭偰椡傪敪婗偡傞僠儍儞僗偼幐傢傟傞偺偩丅 丂乽岝傞孨乿偼妛寍偵偨偖偄傑傟側嵥傪帵偟偰偄傞丅偙偺屼巕偺擻椡傪怣偠偰偦偺椡偱帺暘偺悽奅傪峀偘偝偣傞壜擻惈偵掗偼搎偗偨偺偩丅 偦偺偨傔偺屻尒栶偲偟偰丄恇壓偺堦偺恖乽嵍戝恇乿傪攝偟偨丅 丂嘊丂乽恊墹乿偵偼峜懓偲偟偰偺恎暘暱丄帺桼偑側偄丅岝傞孨偼恇壓偵崀傝偰帺桼傪妉摼偡傞偲摨帪偵丄偨偩偺恇壓偱側偔丄 掗偺挒垽偡傞屼巕偲偟偰偺丄懜偝傪帩偪懕偗傞偙偲偱丄偝傑偞傑側峴摦偑嫋偝傟傞偲偄偆帺桼傪傕帩偮丅 暔岅偺庡恖岞偲偟偰丄帺桼傪妉摼偡傞丅 丂 丂丂 |
 侾俀丆摗氣擖撪偵傛傝掗偺嬎氣峏堖偺巰偺斶偟傒偑偆偡傟偨偺偼側偤偐丅丠 侾俀丆摗氣擖撪偵傛傝掗偺嬎氣峏堖偺巰偺斶偟傒偑偆偡傟偨偺偼側偤偐丅丠 丂 |
| 亙杮暥偐傜亜
丂摗氣偑擖撪偡傞偲丄掗偺怱偼師戞偵摗氣偵堏偭偰偄偭偨偲偄偆丅 丂杮暥偱偼乽偍傏偟傑偓傞傞偲偼側偗傟偳丄偍偺偯偐傜屼怱偆偮傠傂偰丄偙傛側偆偍傏偟堅傓傗偆側傞傕丄偁偼傟側傞傢偞側傝偗傝丅乿偲旝柇側昞尰傪偡傞丅 丂峏堖傪幐偭偨斶偟傒偼暣傟傞偲偄偆偙偲偼側偄偺偩丅偟偐偟丄帺慠偲摗氣偵懳偡傞挒垽偺婥帩偪偑怱拞傪愯傔偰丄斶偟傒偺怱偼攚屻偵堏摦偟偰備偔丅 掗偺擔忢傪忢偵巟攝偡傞姶忣偱偼側偔側偭偰備偔偺偩丅偦傟傪岅傝庤偼丄乽偁偼傟側傞傢偞側傝偗傝乿偲尵偆丅 丂杮暥偱偼摗氣偲峏堖傪斾妑偟偰俀崁栚嫇偘偰偄傞丅 丂嘆嫟捠揰乽乮傆偠偮傏偼乯偘偵屼偐偨偪偁傝偝傑丄偁傗偟偒傑偱偧偍傏偊媼傊傞丅乿擇恖偺婄棫偪丄偐傜偩偮偒偑晄巚媍側掱帡捠偭偰偄傞丅 丂嘇憡堘揰乽偙傟偼丄恖偺屼偒偼傑偝傝偰丄巚偄側偟傔偱偨偔丄恖傕偊偍偲偟傔暦偊媼偼偹偽丄偆偗偽傝偰偁偐偸帠側偟丅乿 偦傟偵懳偟偰丄乽偐傟偼丄恖偺嫋偟暦偊偞傝偟偵丄屼偙偙傠偞偟偁傗偵偔側傝偟偧偐偟丅乿 摗氣偼恎暘偑崅偔丄恖乆偺昡敾偼偡偽傜偟偔扤傕傕嫒傔傞偙偲偑偍弌棃偵側傜側偄偺偱丄杮恖傕摪乆偲偟偰偄偰側偵晄懌傕側偄丅 偦傟偵懳偟偰丄峏堖偼恖乆偑擣傔側偐偭偨偺偵丄掗偺挒垽偑偁偄偵偔怺偡偓偨偺偩丅 丂嘆偲嘇偑掗偺怱偑堅傔傜傟丄摗氣偵怱偑堏偭偰偄偭偨棟桼偲偟偰偁偘傜傟偰偄傞丅 |
| 亙撉傒夝偒亜
揟帢偺慐傔偼乽峏堖偵偆傝傆偨偮乿偲偄偆忦審偩偭偨偑丄嘆偲嘇偲傪椻惷偵撉傒斾傋偰傒傞偲丄嘇偺堘偄偺曽偑嵺偩偭偰偄傞偙偲偑傢偐傞丅 婄偐偨偪偺椶帡傛傝傕丄惈奿傗怳傞晳偄偺堘偄偺曽偑戝偒偄偺偩丅 丂恖娫偺僀儊乕僕偼丄弶懳柺偲丄偟偽傜偔偮偒偁偭偰偦偺恖暔偺恖暱傪抦偭偨屻偱偼丄 屻幰偑嫮偔側傞偺偼丄擔忢偺宱尡偑偟傜偣傞偲偙傠丅 丂偮傑傝丄峏堖偲摗氣偲偼暿恖側偺偩丅 丂偦傟偑丄掗偺婥帩偪偑堅傔傜傟傞攚宨偵偁傞偲偟偨傜丄掗偑摗氣偵枮懌偟偨棟桼偼丄偳偙偵偁傞偐丅 傕偪傠傫丄峏堖偺柺塭偵帡傞偲尵偆揰偼偼偢偣側偄偩傠偆偑丄偦偺傎偐偵丄 嘆丂屻媨偱嵟崅埵偺摗氣傪偩傟溳傞偙偲側偔挒垽偱偒傞揰丅嘇丂偦偺摗氣偵偼丄僶僢僋偲側傞尃椡幰偑偄側偄揰丅 偲偔偵丄嘇偺揰偑掗偵偲偭偰偼堄枴偑偁傞偺偱偼側偄偐丅 丂奜愂偲偟偰偺尃椡攃埇傪業崪偵婅偆塃戝恇偲偦偺柡峅婮揳彈屼偺堄傪偦偖偵偨傞懚嵼偲偟偰丄摗氣偼掗偺婅偭偰傕側偄彈惈偲偟偰尰傟偨偺偩丅 |
 侾俁丆岝傞孨偺憗偡偓傞尦暈偼側偤峴傢傟偨偺偐丠 侾俁丆岝傞孨偺憗偡偓傞尦暈偼側偤峴傢傟偨偺偐丠 丂 |
| 亙杮暥偐傜亜
丂摗氣偲尮巵偲擇恖暲傃棫偪丄悽偺恖偐傜乽岝傞孨乿乽偐偑傗偔傂偺媨乿偲徧偝傟傞偙偲傪弎傋偰丄 岅傝庤偼師偺榖戣丄岝尮巵偺尦暈傊偲恑傓丅 乽偙偺孨偺屼傢傜偼偡偑偨丄偄偲偐傊傑偆偔偍傏偣偳丄廫擇偵偰屼尦暈偟媼傆丅乿 丂愭擭丄堦偺峜巕偺尦暈偑偁偭偨偲偄偆丅偦偺尦暈偼搶媨偲偟偰偺尦暈偱偁偭偨偐傜丄枩帠岞偺掕傔偵懃偭偨傕偺偱偁偭偨丅 搶媨偺尦暈偼巼泜揳偱峴傢傟丄偡傋偰岞偺嵿偱傑偐側傢傟傞丅 丂偝偡偑偵偙偺屼巕偺尦暈傪偦偙偱峴偆傢偗偵偼偄偐側偄丅惔椓揳偺掗偺屼嵗強偱峴偆偑丄 偦傟埲奜偼偡傋偰丄搶媨偺帪偲摨偠丄偄傗偦傟埲忋偵崑壺偵丄岞偺嵿傪傕曻弌偝偣偰峴偆丅偙傟偵偼懡彮偺旕擄偑弌偨傜偟偄丅 丂屻尒栶偵摉偨傞乽堷偒擖傟乿偺偍偲偳栶偼慜弎偺嵍戝恇偑峴偭偨丅 乮搶媨偺帪偺乽堷偒擖傟乿偑偩傟偐偼岅傜傟側偄偑丄懡暘丄塃戝恇偩偭偨傠偆丅乯 丂摉擔丄屼巕偼嵟弶偵摱巕巔偺傒偯傜傪寢偭偰搊応丅偦偺敮傪愗偭偰丄傕偲偳傝傪寢偄丄偦傟傪姤偺嬓巕乮偙偠乯偺拞偵擖傟偰丄 姤傪偙偆偑偄偱偲傔傞丄偦偺栶傪嵍戝恇偑偡傞偺偩丅乽尦暈乿傪乽弶姤乮偆傂偐偆傇傝乯乿偲傕尵偆偺偼偙偺偨傔偩丅 丂掗偼敮傪愗傞変偑巕傪偠偭偲尒偮傔偰偄傞偆偪偵丄偙偺巔傪側偒峏堖偑傕偟尒傞偙偲偑弌棃偨側傜偲巚偆偲丄椳偑弌偦偆偵側傞偺傪偠偭偲偙傜偊偰偄傞丅 媣偟傇傝偵峏堖傪巚偄弌偡掗偱偁傞丅 丂摱巕巔偺旤偟偝偵尒側傟偰偄傞恖乆偼丄乽偝傑曄傊媼偼傓偙偲惿偟偘側傝乿偱偁偭偨丅 丂乽偐偆偒傃偼側傞掱偼丄偁偘偍偲傝傗丄偲媈偼偟偔偍傏偝傟偮傞傪乿偲偁傝丄屼巕偼乽偒傃偼乿偩偲岅傜傟傞丅乽偒傃偼側傝乿偲偼 乽梒偔偰庛乆偟偄條乿傪偄偆丅廫擇嵨偺屼巕偼擭傛傝傕戝恖傃偰偄傞偺偱偼側偔丄偐偊偭偰丄梒側偍偝側偟偨姶偠側偺偩丅 掗傕偦傟傪傛偔彸抦偟偰偄傞丅 |
| 亙撉傒夝偒亜
偦傟側傜偽丄側偤丄掗偼岝傞孨偺尦暈傪媫偖偺偐丠 丂恇壓偵壓偡偙偲偵偟偨乽岝傞孨乿偵偼丄晝偲偟偰偺帺暘埲奜偵斴岇幰偼偄側偄丅偟偐偟丄帺暘偼乽掗乿偲偟偰偺岞揑懚嵼偱偁傝丄 惛恄揑偵偼巟偊傞偙偲偼弌棃偰傕丄幚惗妶偱偼壗傕偟偰傗傟側偄丅 丂偙偺巕偵偼丄偼傗偔恇壓偺屻尒恖偑昁梫側偺偩丅偦傟偵偼丄帺暘偺枀傪嵢偲偟偰寎偊偰偄傞婥帩偪偺捠偠偨嵍戝恇偟偐偄側偄丅 丂偦偺嵍戝恇偺柡偼侾俇嵨丄寢崶揔楊婜偱搶媨懁偐傜傕強朷偝傟偰偄傞丅 丂偙偙偼彮偟憗偄偑丄岝傞孨傪尦暈偝偣偰丄嵍戝恇壠偺柟偲偟偰偺埵抲傪妋曐偟偰偍偙偆丅晝掗偲嵍戝恇偺斴岇傪庴偗偨偙偺巕偼丄嵟崅偺摴傪曕傓偙偲偑壜擻偩傠偆丅 丂偙偺攝椂偑丄憗偡偓傞尦暈丒憗偡偓傞曣巕乮摗氣偲岝傞孨乯暘棧傪傕偨傜偟丄岝尮巵偺堄幆偺掙怺偔摗氣巚曠偺怱傪崗傒偮偗傞寢壥偲側偭偨傢偗偩偑丄晝掗偼嶡抦偟偰偄偨偐偳偆偐丅 |
 侾係丆岝尮巵偑摗氣傪巚曠偡傞昁慠惈偼丠 侾係丆岝尮巵偑摗氣傪巚曠偡傞昁慠惈偼丠 |
| 亙杮暥偐傜亜
丂尦暈偺栭丄嵍戝恇偺昉偲寢崶偟丄嵍戝恇揁偱柟偑偹偲偟偰挌廳偵寎偊傜傟偨偺偱偁偭偨偑丄側偐側偐嵍戝恇揁偵偼懌偑岦偐偢丄偲偐偔媨拞偵偄傞偙偲偺懡偄尮巵偱偁傞丅 丂昞岦偒偼丄掗偑憡曄傢傜偢棧偟偨偑傜側偄偐傜偩偑丄偠偮偼丄尮巵偺撪怱偵偼丄摗氣傪棟憐偺彈惈偲偟偰偟偨偆怱偑惗偠偰偟傑偭偨偺偱偁偭偨丅 丂乽偨偩摗氣偺屼偁傝偝傑傪丄偨偖傂側偟偲巚傂暦偙偊偰丄亀偝傗偆側傜傓恖傪偙偦尒傔亁乿偲巚偄丄嵍戝恇偺昉傪乽傪偐偟偘偵偐偟偯偐傟偨傞恖偲偼尒備傟偳丄怱偵傕偮偐偢乿 偲巚偆偺偱偁偭偨丅 丂偦偺捈屻偵丄尦暈偲偼偳偆偄偆帠懺偵側傞偙偲偐傪岅傝庤偼尵偄弌偡丅乽偍偲側偵側傝媼傂偰偺偪偼丄偁傝偟傗偆偵丄傒偡偺偆偪偵傕擖傟媼偼偢乿偲側傞偺偩丅 丂帺暘偺堄巙偱側偔丄廫擇嵨偱尦暈偟偨偲巚偭偨傜丄廧傑偄偼媨拞偐傜弌偰嵍戝恇揁偱丄媨拞偵偄偮傕峴偒棃偡傞偵偟傠丄 帺桼側応強偼帺幒偲偟偰摿暿嫋偝傟偨嬎氣偺傒丅掗偵屇偽傟偰偄偭偰傕丄偄偮傕偺傛偆偵堦弿偵屼楘偺拞偵偼彽偠擖傟偰傕傜偊側偄丅 帺暘偼屼楘偺奜丄馀巕偵嵗傜偣傜傟傞偺偩丅 丂屼楘偺拞偐傜傢偢偐偵塳傟暦偙偊傞摗氣偺惡傪暦偔偩偗偟偐偱偒側偄丄偁傟傎偳曣戙傢傝偵側偠傒曠偭偰偄偨恖偲丄偨偭偨侾擔傪嫬偵偟偰妘偰傜傟偰偟傑偭偨丅 乽尦暈乿亖乽偍偲側乿偩偐傜偲偄偆棟桼偱丅 丂摉帪偺寢崶偼抝偑彈偺強偵捠偆宍偱丄姰慡側摨嫃偱側偄偐傜丄尮巵帺恎偺壠偑昁梫偩丅偦偙偱掗偼曣峏堖偺棦揁傪戝廋棟偟偰旤偟偔嶌傝捈偟偰尮巵偺揁戭偲偡傞丅 擇忦堾偱偁傞丅尮巵偼乽偐偐傞強偵丄巚傆傗偆側傜傓恖傪偡傦偰廧傑偽傗偲偺傒丄扱偐偟偆偍傏偟傢偨傞丅乿 丂偙偺擇忦堾偵悩偊偨偄恖丄偦傟偼摗氣側偺偩丅 |
| 亙撉傒夝偒亜
丂杮暥偱傎傫偺悢僙儞僥儞僗偱岅傜傟偰偟傑偆乽摗氣巚曠乿偺怱棟偩偑丄偙傟偑柍棟側偔挳偒庤偵庴偗庢傜傟傞偺偼丄 攚屻偵偁傞乽嬎氣峏堖乿偺懚嵼偩傠偆丅朣偒曣傪曠偆乽巕偺怱乿偺晛曊惈偑丄曣戙傢傝偺摗氣傪曠傢偣傞丅 丂偦傟偑丄偁傞擔撍慠丄晄忦棟偵堷偒楐偐傟偨偙偲偱丄妷嬄偺懳徾偵揮壔偡傞丅 丂偟偐傕丄尰幚偱埁偺忋偲偺寢崶偲偄偆宍偱 堦婥偵乽堦恖慜偺戝恖乿偲側傟偲梫媮偟偰偒偨悽偺拞側偺偩丅乽戝恖偺抝乿偼丄嵢埲奜偺乽戝恖偺彈乿偲夛偭偰偼側傜側偄偲偟偨傜丄 帺暘偺夛偄偨偄彈惈傪嵢偵偟偨偄偲巚偆偺偼摉慠側偺偩丅 丂偙偺尮巵偺怺憌怱棟偑丄僼儘僀僪偺暘愅偟偨抝惈偺惉挿夁掱偵偁傞僄僨傿僾僗丒僐儞僾儗僢僋僗偲摨幙偱偁傞偙偲偼丄偩傟偵傕偡偖巚偄晜偐傇偙偲偱偁傠偆丅 丂偙偺屻偺暔岅偺揥奐偺側偐偱偼丄尮巵偺昞憌堄幆偼乽摗氣巚曠乿偵偺傒尷掕偝傟偰偄偔偑丄偦偺怺憌偵乽曣巚曠乿偑偁傞偙偲偼朰傟偰偼側傜側偄偩傠偆丅 丂偦偺曣偑寣偑偮側偑傜側偄偙偲偱丄傛傝愭塻偵丄乽堎惈偲偟偰偺摗氣巚曠乿偵側傝丄偦偺彈惈傪撈傝愯傔偵偟偰偄傞掗亖晝偵懳偟偰嫞憟怱傪擱傗偡丅 帺暘傪斴岇偡傞偐偗偑偊偺側偄懚嵼偱偁傝側偑傜丄帺暘偑嵟傕忔傝墇偊偨偄懚嵼丅 丂掗偺岪偱偁傞偦偺摗氣傪斊偡偙偲偱丄乽執戝側晝乿嶦偟傪壥偨偡惵擭尮巵偑抋惗偡傞丅 丂丂 |
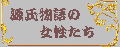 幨恀偺柍抐揮嵹偼偛墦椂壓偝偄
幨恀偺柍抐揮嵹偼偛墦椂壓偝偄