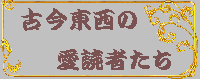
***源氏物語を愛した人たちのことば***
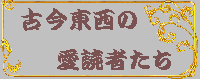
| ∽ ∽ 菅 原 孝 標 の 女 の こ と ば ∽ ∽ |
 菅原孝標女1005ころ-1060ころ 日本の小説家、日記作家 菅原孝標女1005ころ-1060ころ 日本の小説家、日記作家 |
| 「更級日記」
あづま路の道のはてよりも、なほ奥つかたに生ひ出でたる人、いかばかりかはあやしかりけむ を、いかに思ひ始めけることにか、 世の中に物語といふもののあんなるを、いかで見ばやと思ひつつ、つれづれなるひるま、宵居などに、姉・継母などやうの人々の、 その物語、かの物語、光源氏のあるやうなど、ところどころ語るを聞くに、いとどゆかしさまされど、わが思ふままに、そらに いかでかおぼえ語らむ。 いみじく心もとなきままに、等身に薬師仏を造りて、手洗ひなどして、人 まにみそかに入りつつ、「京にとく上げたまひて、 物語の多くさぶらふなる、あるかぎり見せたまへ 」と、身を捨てて、額をつき祈り申すほどに、 十三になる年、上らむとて、九月三日門出して、い またちといふところに移る。 |
主人公の文学少女ぶりをいかんなく発揮した、あの有名な「更級日記」の冒頭の一節。 「あづま路の道のはてよりも、なほ奥つかたに生ひ出でたる人」とあり、自分がいかに田舎娘であるかを強調しているが、この「あづま路の道のはてよりも、なほ奥つかた」とは、現在の千葉県市原市あたりのこと。千葉県生まれ、千葉県育ちの人間にとってはちと顔赤らむ表現である。 菅原氏は菅原道真に始まる学者の家柄であるが、藤原氏全盛の父孝標の時代には一介の受領階級にすぎない。母は藤原倫寧の女、「蜻蛉日記」作者道綱母とは姉妹である。つまり「更級日記」作者は「蜻蛉日記」作者と姪・伯母の関係。紫式部とも母方の血縁関係にある。 彼女が「更級日記」を書いたのは1059(康平2)年ころ。50歳過ぎであった。 日記の書き出しは13歳で上京するところから始まる。逆算すると彼女は紫式部よりも30歳くらい年下だ。彼女が田舎で源氏物語に憧れていた頃、(おそい方の死亡説をとると)紫式部は都で亡くなっている 彼女が書き終えた「源氏物語」は現在の54帖の形で人々の手に伝わっていたことが、「更級日記」の記述で分かる。 都に上った主人公はやがて叔母から「源氏物語」全巻を箱入りでもらいうけて、驚喜することになる。 しかし「源氏物語」を手にした喜びも束の間、文学少女は現実の壁にぶつかり、生活の為の宮仕え、おそい結婚、夫との不仲など人生の波風をつぶさに経験し、最晩年は阿弥陀浄土を渇仰する心境に至る。 その生涯の一人居の時間に、やがて自らも物語作者として「夜半の寝覚め」「浜松中納言物語」を書いたと見られている。 |
| ∽ ∽ ヴ ァ ー ジ ニ ア ・ ウ ル フ の こ と ば ∽ ∽ |
 ヴァージニア・ウルフ1882-1941イギリスの小説家、批評家 ヴァージニア・ウルフ1882-1941イギリスの小説家、批評家 |
いまさらこの国の読者の注意をうながす要はほとんどないであろうが、あのウルフリックが『説教集』を書いたのは九九一年の頃のこと、 旧約と新約の聖書について書いたのはその少し後のことであり、それらの著述からさらに年が経て、定かには知られぬが深刻な騒乱が起り、 デンマークのスウェーゲンが英蘭土の王位に登った。 私たちの先祖たちは、絶間なく人間や猪と戦い、また森林や沼沢と戦っていたのだから、 彼等がペンを取って、筆写し翻訳し記録したり、未熟な歌心の発作に荒っぽくぎこちなく身を任せたりした時、 その握拳は労働に腫れあがり、心は危難に痙攣し、眼は煙にいたみ、足は床に敷く燈心草の中に冷却していた。 だから、 夏が来た 夏が来た 郭公鳥やかましく鳴く というように、彼等の衝動の叫びは粗野だった。 ところでちょうどその折り、地球の向側では、紫式部は花園を眺めながら、「葉かげの白い花の半ば開いた花びらは、 自らの想にひとり微笑む人の唇に似ている」と感じていたのだ。 アルフリックやアルフレッドたちがこの英蘭土で嗄れ声で咳き立てていた時に、この宮廷婦人は (訳者ウェイリ氏は、その六巻が出つくすまではわざと彼女の一切のことを秘匿されるらしいので、 私たちは彼女について何もしらないのだが)絹の長衣と袴とをつけて坐し、絵画をながめ耳は詩の韻律の流れを追い、 庭園には花が咲き樹間には鶯が啼き、ひねもす語らい夜もすがら舞踊しーーそのような1000年の頃、 坐して、源氏君の生涯と冒険とを物語ろうとしていた。 だが、紫式部はいかなる意味でも記録作者でなかったということを、急いでここに書きとめておこう。 その本は音読されたのだから、聴き手が存在したと思われるが、彼女に耳を傾けたのは、鋭敏で微妙で複雑な心情を持つ男女だったのにちがいない。 彼等は大人だったから、格闘の場面で注意を引きつけたり、惨劇で驚愕させたりする必要はなかった。 そのようなことではなく、彼等は人というものの性に息を凝らして熟(ママ)したのだーー彼は拒まれたものをいかに熱情的に追い求めるか、 あわれ深い親愛の生活への願望がいかに裏切られつづけるか、奇異幻妖の趣は単純明確のものよりもいかに強く心を奪うか、 散りかかる雪はいかに美しく、またそれを眺める時、その孤りの歓喜をわかち合う相手をいかにいやましに求めるか。 たしかに紫式部は芸術家にとって、ことに女性のそれにとって幸せな世に生きた。人生の緊急時は戦争ではなく、 人々の関心は政治に集注されておらなかった。その二者の力の暴圧から逃れて、人生は主として微細な行状のはしばしに呈示されていた、 ーー男たちは何をいったか、女たちは何を仄めかしたかということに、白銀の鰭で沈黙の水面を破る詩歌に、舞踊と絵画とに、 人々が十分に安全だと思う時にのみ持ちうるところの、荒涼の自然への愛、などに。 このような時代に紫式部は生き、大言壮語を忌み、諧謔と良識にみち、人生の矛盾と奇異さとにはげしく惹かれ、 また荒草のなかに崩れて行く古い館や、風や、さびしい自然や、瀑布の音や、打球の遊びや、雁の群や、姫君の赤い鼻などを愛で、 それからいう迄もなく美を、ことに美をさらに美とするところの撞着を愛で、それらすべての彼女の力を自然に生き生きと揮うのだった。 そういう世の中であったからこそ(それが日本でどのようにして育成されたか、またどのようにして破壊されて行ったかは、 ウェイリ氏が教えてくれるのを待つほかはないが)作家がありふれた事物を美しく描き出したことも当然であり、 公衆に向かってあからさまに「世の常のものこそ感嘆に値します。誇張や強調に押し流され、また珍奇なものや一時の強い印象に誘われたならば、 ほんとうに深い歓を知ること出来ません」ということもできたのだった。 つまり紫式部によれば二種類の匠人があり、ひとつは、ひと時の気分に任せて他愛のないものをつくり、他は「人々が実際に使用するものに真の美を吹き込み、 伝統が定めたところの完形を与えようと努める」また彼女はいうのであるが、人々の眼をうばい驚かせること、「嵐に乗って怒り狂う海の怪物を描いたり」することは、 まったくやさしく、ーーやんやと褒めそやされることだろうが、それならばそこいらの玩具職人にでもできることだ。 「しかし、世にありふれた山や川の姿や、常に見なれた家の姿などももつすべての美と調和とをーー優雅に如実に描き、または人里から遠く離れて住む人のひそやかな籬の内にあるものや、 なだらかな山の木々の茂みなどを、それに相応しい構図均整を心にこめ描くというようなことーーそれは最高の名匠の技のかぎりを要求するのであり、 世の常の匠人ならば数かぎりない錯誤に陥ってしまうであろう」 彼女の魅力は、私たちにとっては、何ほどかは偶然から来ると思われる。というのは、実際のところ私たちは、彼女が「常に見なれた家」というのを聞くとき、 ただちにこのロンドンのサービトンやアルバート記念館から何千哩はなれた彼女に、鶴や菊花にかざられたところの優美で幻めく何ものかを心に浮かび上がらせるのだ。 私たちは今日のイギリスでは求め得ぬものと諦めたところの背景環境を彼女に付与するという贅に耽るのである。 しかしそのような誘惑に任せることによって、彼女の作品を脆美なものと感じたり感傷で包もうとするならば、 これは重大な罪をおかすことになる。それは微妙でありながら一点の頽廃もない芸術品であり、感受性にみちながら溌剌として少年のごとく、 老廃した文明のもつ過剰性や物懶さには少しも汚されておらぬ。彼女のもつ魅力の本質は鶴や菊花にはない。 それは、彼女がまったく素朴に信じたことーーその信念は皇帝や侍女たちによっても、また彼女が呼吸する空気や彼女が見る花によっても支えられたいたと思われるのだが、 ーー「人々が実際に使用するものに真の美を吹き込み、伝統が定めたところの完形を与えようと努力する」ものが正しい芸術家である、 という信念にこそあるのだ。 だから彼女は、ためらいも自意識めくものもなく、力作感も煩悶もなく、ぐんぐんと筆を進めて魅惑にみちた一少年について物語る。 ーーその皇子が『青海波』を優美に踊るとき諸王や大貴顕たちは声に発して感泣する。彼は求め得られぬ人々を恋する、 彼の放逸は最も完全な礼節によって整調されている、彼は子供たちと愛にみちて喜戯し、またその女友達が知っていたように、詩歌は終句をきかぬうちにやめられることを好む、 彼の心のさまざまの面を証明するために、紫式部は女だったから、他の女たちの心情を媒介したというのは自然のことであった。 葵、槿、藤壺、紫、夕顔、末摘花など、艶美なもの、赤鼻のもの、冷たいもの、激情的なものーーつぎつぎに立ちあらわれて、その中心に立つ好色の若者に向かって。 透徹した光や気まぐれな光を投げかける時、彼は飛び走り、追いかけ、笑い、悲しみ、そして常に躍動と喜悦と歓笑にあふれているのであった。 紫式部の筆からは、急ぐこともなく、立ちもとむることもなく、衰えを知らぬ豊饒さをもって、物語が溢れ出て打ちつづく。 このような発明力の天才の作品でなかったとすれば、『源氏物語』は六巻が終わらぬうちに干からびてしまうだろう、 と私たちは危惧したかも知れぬことである。もちろん、この才華の場合、その恐れは無用だ。私たちはここの観測点に立ち、 ウェイリ氏の美しい望遠鏡を通して、いま新しい星がゆるぎない自信をもって昇り、やがて大きく静謐に輝がやかになりまさるのを見つめるだろう ーーしかしさもあらばあれ、それは第一等の巨星ではなかろう。たしかに、紫式部はトルストイやセルヴァンテスその他の西方世界の大物語作者の仲間内として自己を呈示しようとしているのではない。 その連中の先祖たちといえば、彼女が格子窓から「自らの想に微笑む人の唇に似て」開く花に眺め入っていた時に、 格闘したり小舎にうずくまったりしていたのではないか。 彼女の東方世界では、ある種の恐怖、惨劇、鄙俗性など、何かは人生体験の根源物が取り除かれていたのだから、 野性は相手にされず粗暴は問題にならなかったのだが、それと共にある種の活力、豊澹さ、人間精神の成熟などが逃げ出してしまったのであり、そこで、 黄金は白銀の色にうつろい、酒には水が交じった。、紫と西方の大作家との比較は、結局は彼女の完璧性と彼等の力強さとを目立たせることになるほかはない。 しかし何にしても美しい世界である。育ちよく洞察力と機知に富むこの静かな女性は、完全な芸術家だった。これから何年かの間私たちは彼女の森林をさまよい、 彼女の月の出や降雪を眺め、彼女の雁の啼声や笛と琴と篳篥の鳴り音に耳をかたむけ、その時、皇子は人生のあらゆる珍らかさを味わい験し、 絶妙に踊って人々を泣かせ、しかし決して典雅の掟を踏みこえることはなく、また常に、より奇異な何ものか、より精美な何ものか、 彼に拒まれている何ものかを追求することをやめようとはしないだろう。(阿部知二訳・1952・1『婦人公論』) |
|
「ダロウェイ夫人」や「オーランドー」などの特異な内面的心理描写を中心とした作品で知られたヴァージニア・ウルフ。ブルームズベリーにあった彼女の家のサロンには、
文学者だった父の代から多くの学者・文学者が集まって、ブルームズベリー・グループと呼ばれていた。著名な経済学者ジョン・メイナード・ケインズもグループの一員だった。
メンバーのひとり、アーサー・ウェイリーが、日本の古典作品「源氏物語」を辞書だけで英訳して、グループに発表した。
彼等グループは、ちょうどマルセル・プルーストやジェイムズ・ジョイスの作品を評価し世に出していたところだった 。意識の流れの「自動記述」法で人間心理をとらえる新しい文学をはじめて自分たちが生み出したときに、東洋で千年も前に一人の女性が人間の内面の苦悩と闇をみつめ、 それを記述する文体を発明していたということは全く驚異だった。 ウルフは、AD1000年の頃のイギリスと眺め比べ、その同じ時、東洋の片隅で戦さや争いのない平和に恵まれた一時期に、すぐれた一人の天才が生み出した作品を 時代や文化の差をこえて、深く味わっている。紫式部とヴァージニア・ウルフとが、「言葉によって人の心をつかみとる」という共通の志によって手をつないだ瞬間だ。 この文章を書いた時、ウルフはまだ、全巻を読み終わっていない。ここに登場しているのは、夕顔、紫、末摘花など。ウェイリー氏の訳は、パート6までで完了。 ここではパート1の「桐壺」から「葵」までの英訳を読んだだけであろう。まだ、女三宮は登場せず、「宇治十帖」はまだ先だ。 ウルフの作品解釈が「光源氏」中心に成っているのも仕方がないが、第3部までを読み終わった後の彼女の感想をぜひ聞いてみたかったものだ。 ヴァージニア・ウルフは長く神経を病み、1941年3月、第二次大戦中に入水自殺した。 |
| ∽ ∽ 瀬 戸 内 寂 聴 の こ と ば ∽ ∽ |
 瀬戸内寂聴1922- 日本の作家・俗名晴美、73年出家 瀬戸内寂聴1922- 日本の作家・俗名晴美、73年出家 |
| 「痛快!寂聴源氏塾」
「煩悩の火を鎮め、慈悲の心を得るために人は出家する」 仏教にとっての出家とは、辛いことばかりの俗世から離れ、親兄弟や恋人と縁を切るというだけのものではありません。 煩悩の火を鎮め、渇愛ではなく仏の慈悲の心を持つように修行をしていくためにこそ出家はあるのです。 古来、出家とは「生きながらにして死ぬこと」とも言われてきました。出家して髪を剪るというのは単なる形式ではありません。 煩悩の炎に焼かれてきた、それまでの苦に満ちた人生にピリオドを打ち、新しい人間となって生まれ変わる。 荘厳なる得度式は、古い自分を弔うための葬式でもあると言えるのです。 こうして出家の意味が分かってくると、なぜ源氏物語の女性たちが出家とともに心の丈がすっくと伸び、 源氏を高みから見下ろすようになるのかも理解されてくるのではないでしょうか。 これは私の想像でしかありませんが、源氏物語の作者紫式部は非常に理知的な人ですから、こうした仏教の教えの意味を 理解していたのだと思います。 そして、男性上位の社会で女性が嫌というほど味わう苦悩や不条理から救われるのは出家しかないのだと、彼女は自分自身の経験からも 骨身に染みて感じていたのではないでしょうか。 彼女もまた、源氏物語のヒロインたちと同じような恋愛や結婚の辛さ、苦しみを味わってきたのです。それだけに、女性が人生の苦しみから逃れるには 出家という最終手段を選択するしかないのだという結論を持ち、それを物語として綴ったのではないかと思うのです。 「はたして紫の上は幸福だったのか」 そして、そう考えてみると源氏物語の主要なヒロインでありながら、なぜ紫の上だけが出家を果たせなかったかという意味もよく分かってきます。(略) 紫の上の晩年を見ていくと、「はたして紫の上は幸福だったのだろうか」と思わないではいられません。 彼女は最も源氏の愛に包まれた女性であったのは事実ですが、それは同時に、終生、その愛情の網から逃れることができなかったということでもあります。 彼女自身はそんな自分の姿をよく知っていたからこそ、出家をしたいと願ったのですが、その夢は叶えられることはありませんでした。 最も幸福に見える人が、実は最も不幸なのだ・・・紫式部は、紫の上の生涯を描くことでメッセージを私たちに伝えようとしたのではないでしょうか。 |
|
自らも激しい愛の遍歴のすえ、出家した瀬戸内晴美ー寂聴。50歳で奥州平泉中尊寺で得度下というニュースは衝撃的だった。 しかし、剃り上げた坊主頭の寂聴はそれ以前よりとても美しくなっていた。 それ以後の寂聴の活躍は、めざましい。 京都嵯峨野に寂庵をむすび、岩手の無人の寺を再興して住職となり、月一回の講話を精力的にこなし・・・。そして文学者としても 深みのある視点を得て、歌人西行の出家に至る道筋をたどり「白道」を書き上げた。「女人源氏」で、女性の視点で読み解く源氏物語を呈示。 そして彼女の畢生の業績となる「源氏物語全訳」にすすむ。 上記の文章の出典「痛快!寂聴源氏塾」は、集英社の「痛快!」シリーズの一冊。このシリーズは政治・経済の分野など幅広い内容で展開される入門シリーズ。 大判で写真が豊富で装幀も美しい。 この本で、寂聴は、世界中の人に読まれているこの物語を、現代の日本の若者たちに自分たちのお話として楽しんでもらいたいのだ。 「今」の人たちが読むことでこの物語は永遠につたわる作品になるのだから。。 物語の解説は読みやすい語り口で、資料や写真も豊富。さらに編集者が頼み込んで掲載許可をもらったという「あさきゆめみし」の挿絵。 私は一目で気に入った。 さて、寂聴さんにとって、自らの出家体験から見えてくるのは、女主人公が皆出家していく姿。出家する事で彼女たちが得ようとしたのはなにか。 そして、死の間際まで出家を望みながら果たせず死んでいった「紫の上」の特異さが浮かび上がってくる。彼女を最も不幸な存在とする寂聴の視点は、私もまた共有する。 この視点は、女三宮降嫁以降を主人公に心理に感情移入しながら読むならば、皆が得られる視点のはずであったが、 男中心の学者たちには読み解けないものであった。 「男の愛される」ことなどでは、女は自由になり得ない。 自分がどこまで「一人の人間」として、おのれの存在価値を保てるか。それはこの世で可能なことなのか。 世の敬意を一身に集め、現世の最高の男「光源氏」にもっとも愛されたはずの「紫の上」が担ったこの不幸を、 宇治十帖では、「浮舟」という、身分も敬意も「光源氏」ももたない一人の女性に託して、さらにシリアスに描き出していく。 |
| ∽ ∽ の こ と ば ∽ ∽ |
 |
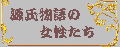 写真の無断転載はご遠慮下さい
写真の無断転載はご遠慮下さい