御文(おふみ)と蓮如上人
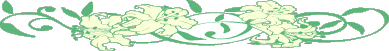
■御文(おふみ)
ご家庭での仏事やお寺での法要、お通夜などで、読経が終わった後、法語が拝読されます。これを「御文」(おふみ)と呼びます。語尾下がりの特徴のある節回しや、最後の「あなかしこーあなかしこー」の言葉など多くの方に親しまれています。「聖人、一流の御勧化のおもむきは・・」や、お通夜でよく拝読される 「夫、人間の浮生なる相をつらつら観ずるに」で始まる「白骨の御文」などはとても有名です。
御文は、宗祖親鸞聖人から数えて八代目の蓮如上人が、その布教手段として全国の門徒へ消息(手紙)として発信された仮名書きによる法語です。蓮如上人が入滅された後、孫である円如上人が、二百数十通の中から八十通を選び五帖に編集されました。
■蓮如(れんにょ)上人
蓮如上人は一一四五年に本願寺第七世存如上人のご長男として京都にお生まれになりました。「御文」などによる独自の布教活動を精力的に展開され、浄土真宗の中興の祖と言われています。
お勤めのやり方を全面的に変えられ、当時ご門徒で頻繁に唱えられていた親鸞聖人作の『三帖和讃』を取り入れ、朝夕に『正信偈』と『三帖和讃』を唱える方式に制定されました。ご門徒に広く受け入れられるようになり、今日まで引き継がれています。

浄土真宗本願寺第八世 蓮如上人