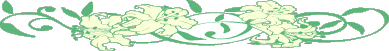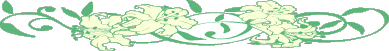「知恵・智慧」 (ちえ)
私たちは日ごろどのような意味で、「知恵」という言葉を使っているでしょうか。「知恵比べ」「知恵者」「知恵袋」「知恵の輪」「知恵熱」などさまざまな使い方ががありますが、知恵という言葉の意味はそれほど明確ではないようです。学校教育の問題で、最近「知識の詰めこみだけでは駄目だ。生きる知恵を教えることが大切だ」といわれたりするように、知恵は単に「知識」ということでもなく、また、頭の回転の早い「利口・利発」ということでもないようです。
従って、知恵は科学的知識のように具体的なものでもなく、功利的目的に必要な利口さのように現実的なものでもないようです。その人の人格から滲みでる言葉や発想が、人々の人生の指針となるような作用を持つ、そのようなものが知恵ということのようです。要するに、正体不明であって、しかもそれに出遇ってはじめて了解できるのが知恵なのでしょう。
さて、知恵という言葉の出所である仏教において、それはどうなっているのでしょうか。
仏教では知恵といえば、般若(はんにゃ)。原語はprajnaです。特に大乗仏教では、般若波羅蜜多(はんにゃはらみた)を意味しています。般若波羅蜜多とは「知恵の至高性・完成された知恵」という意味です。
それでは般若・知恵とは何かと言えば、仏教の基本思想によって一切の存在の本質を見通すはたらきです。他の宗教では説いていない仏教の基本思想とは、「すべての存在は、縁によって起こっているもの(縁起)であり、相互に関係しあって存在しているのであるから、関係性を抜きにして独自に存在しえないもの(無我)である」ということです。私たちは、自分は「私」という確かな存在であると、私たちは思いこんでいますが、確かな「私」などはなく、すべての存在は独自には存在しえない(一切は空である)と見通すのが知恵なのです。 この様に仏教では知恵の意味は明確なのです。
|
|