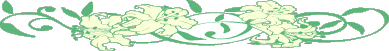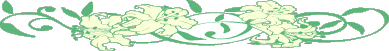「人心地」 (ひとごこち)
物事が一段落して落ち着いたときに「人心地ついた」と使われます。快適な場合は「心地よい」と言われ、大きな恐怖を感じた際には「生きた心地がしなかった」と言います。「心地」は、その時その時の人の心の在(あ)り処(か)をよく表わす言葉です。 仕事に追われあくせくしていると、つい周囲のことが見えなくなってしまうことがあります。結果や業績を残すことだけに執(とら)われると、周り全部が敵か邪魔者であるかのように感ずることにもなります。人心地がつくとは、人としての心を取り戻した瞬間を言うのではないでしょうか。
親鸞聖人が着目している一つの物語があります。
『大般涅槃経』という経典に説かれる阿闍世(あじゃせ)の物語です。目先の感情に流されて、実の父である王を殺してしまう王子の物語です。今から二五〇〇年ほど前、お釈迦様が実際におられた古代インドのマカダ国での出来事です。阿闍世は憎き父を餓死させるのですが、かえって後悔の思いに強く迫られます。眠ることもできずに、熱病にかかり、身体中の毛穴から膿が噴出してきます。そんな中で阿闍世は、父を殺した私は、地獄に堕ちるに違いないと思い悩むのです。
その阿闍世に対して、阿闍世につかえる大臣の一人で、医者でもあった耆婆(ぎば)が言います。人間を苦しみから救うのは慙愧(ざんぎ)の心だと。慙愧とは申し訳ないことをした、人として慙(は)ずべきことをしたという心のことです。耆婆は、もし慙愧の心がないならば、それは人とは言えない、畜生であると言うのです。ここで「畜生」と言われているのは、決して動物たちのことではありません。また、死んだ後に来世に畜生道に落ちるという話でもありません。慙愧の心がなければ、たとえ姿形は人であっても、とうてい人とは言えないという意味です。
さて、人心地がついたという場合、ホッと一息ついたことには違いないでしょう。しかし、その上で、本当に人としての心を取り戻したと言えるかを顧みることが大事です。貪りや怒りの心に振り回されて畜生のようになってはいないか。日ごろの生き方をふり返ってみる必要があるのではないでしょうか。
|
|