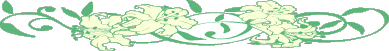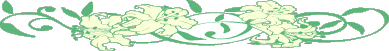「奈落」 (ならく)
「奈落の苦しみ」とか「奈落の底に突き墜とされた」と使われる「奈落」という言葉は、古代インドの言語であるサンスクリット語の〈naraka〉の音写です。辞書には「地獄、また地獄へ堕ちること」とあります。
その地獄を、源信僧都は、自らの著書である『往生要集』で、大きく八つに分けて説明しています。それは、等活地獄、黒縄(こくじょう)地獄、衆合(しゅごう)地獄、叫喚地獄、大叫喚地獄、焦熱(しょうねつ)地獄、大焦熱地獄、阿鼻地獄です。罪を犯した者が受ける苦しみの世界として説かれ、下に行くほど犯した罪が重く、受ける苦しみもきびしいのです。『往生要集』には、それらの苦しみがどのようなものであるのかが、リアルに語られています。そのことは、私たちがどれほど罪の重い者であるかを教えようとしてのことであると言っていいのでしょう。
ところで、「地獄」というような言葉を聞くと、現代という科学技術の発達した時代社会に生きる私たちと無関係な言葉のように感じてしまうのですが、自分の苦しみを実感的に表そうとする時、案外意識せずに使っているようです。たとえば、重い病から治療を終えて無事復帰した時、その苦しみを「きつかった。無間(むけん)地獄から帰ってきた気分」と語ったりします。
無間地獄とは、阿鼻地獄のことですが、苦しみの一番きびしい地獄です。その苦しみは、「我、今帰する所なく、孤独にして同伴なし」という言葉で表されています。関係が壊れてしまい、まったく孤独なひとりぼっちになった世界です。そのことが人間には一番つらいのです。そして、その世界には、「仏法を謗(そし)った者」が墜ちるとされているように、誰もが順わなければならない真実に順わず、自分中心に振る舞う者が出会う世界なのです。つまり、地獄とは、自分自身が作り出す世界なのです。
この「奈落」という言葉は、自分の思い通りになることが、人間の幸せであると考え、ひたすら自分中心に生きる私たち現代人が、どれほど深い孤独の中にあるのかを教える言葉ではないでしょうか。
|
|