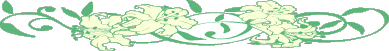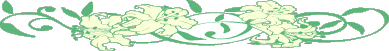「言語道断」 (ごんごどうだん)
この言葉は一般的には、「あの件で某氏のとった態度は、言語道断である」といった使い方で、「もってのほか」「不当な」といった意味です。
しかし、実はこの言葉は、仏教の悟りの境涯を表す言葉です。仏教の悟りは、言葉や心のはたらきを越え、個人の体験から直観されるもので、言語の道が断たれた世界です。それを空性(くうしょう)ともいいます。言も語も同じく断つ、と読めば「言語道断」も同じ内容となります。
赤道直下の、南極の本当の暑さ寒さは、いくら多くの言葉を費やしても伝えられませんので、現地に行って自ら知るしかないわけです。それでも、真理を伝えるには、その表現能力の限界を認めつつも言葉に依らざるを得ません。そこに真理を伝える苦労が生まれるのです。
言語活動を断つことがなぜ悟りに通じるのかといえば、言葉は厄介なことに、迷いをもたらす根源でもあるからである。言葉は、本来、それに対応する実体をもつものではありません。
しかし、我々は言葉に様々な思いを寄せ、イメージを膨らませ、価値判断を付加します。それによって言葉が一人歩きを始めるのです。たとえば、「東京大学」。「『東京大学』は、この世で幸せな人生を送るためには是非入学せねばならぬ大学である。そのためにはどこの幼稚園に入園すべきか、中高一貫教育のどこを選ぶべきか」などと、正に言語道断ともいえる社会現象をひきおこします。これが、仏教でいう、煩悩、業(行為)の迷いの世界です。したがって、煩悩にともなう業が滅すれば、迷いの世界から解放されることになります。その煩悩、業の根源は、われわれに種々な価値判断(分別)をひきおこす言語なのです。
インドで2、3世紀頃に在世したといわれる龍樹大師(ナーガールジュナ)は、このような迷、悟の構造を、主著『中論』の中で次のような詩頌でのべています。
「業と煩悩が尽きることから解脱(げだつ)はある。業と煩悩は分別(価値判断)から起こる。それら価値判断は、多様性をもつ言語から起こる。しかし、多様性をもつ言語は、空性において滅せられる。」と。 |
|